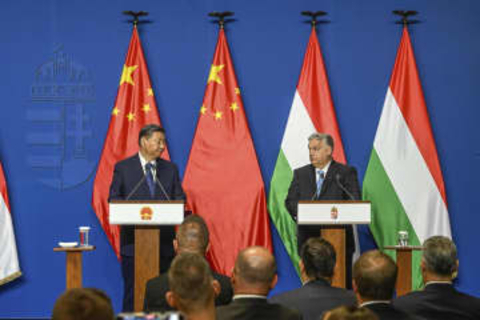もしかしてパズルの映画?
だとしたら見ないわけにはいかない。ジグソーパズル検定1級の腕前を持つ、このわたしは。
舞台は南米アルゼンチンの首都、ブエノスアイレス。主婦マリアは、堅物だけれど真面目でやさしい夫と、そろそろ家を巣立とうとしている二人の息子たちと、幸せに暮らしていた。
マリアの50歳の誕生日。大勢の親戚や友人たちがホームパーティーに集まり、にぎやかに祝ってくれた。あわただしく料理を運んでいたマリアは、うっかり皿を落として割ってしまう。彼女はバラバラにくだけた皿を拾い集め、台所で破片を並べ替え、皿の復元を試みる。見事な手際で。
この時点では、マリアは自分のなかに眠る才能に気づいていない。
家族が寝静まった夜。誕生日プレゼントにジグソーパズルがあるのを見つけたマリアは、そっと箱を開け、テーブルの上にピースをひろげてみる。形の合いそうなものを探し出しては、組み合わせていく。
ジグソーパズルというものがあるのは知っていたけれど、自分でやるのは初めてのマリアだったが、皿を復元したときと同様に、見事な手際でパズルを組みあげてゆく。これまでは家族を支えることだけに夢中で、趣味らしい趣味を持ったことがない彼女は、一瞬にしてこの快感の虜となった。
数日後、マリアはプレゼントをくれた叔母からパズルを買った店を聞き出すと、次なるたのしみを買い出しにいく。そうしてたどりついたパズル専門店の片隅で、マリアは“運命的なもの”と出会ってしまう。ジグソーパズル世界選手権の出場パートナー募集の告知だ。パートナーを募集していたのは独身で大富豪の男性ロベルト。
マリアは「伯母の見舞いに」と家族には嘘をつき、ロベルトの豪邸に入り浸り、パズルの練習にのめり込んでいくのだった──。
この後、マリアがどうするか。それは見てからのおたのしみだが、なんとも軽やかで、解放的な場所に着地する。その晴れ晴れしい気分は、ジグソーパズルが完成した瞬間にも似ている。意地をはらずに観にいってよかった。
マリアはジグソーパズルの才能がある、という設定なのだが、その見せ方がうまい。
とくに注目するべきは、マリアを演ずるマリア・オネットが見せるふたつの仕草だ。パズルのピースをつまむ指先と、散らばったピースを追うときの目。この無言の演技は見事と言うしかない。
いい映画にはセリフが少ないもので、言葉で多くを語らないかわりに、絵で見せる。音で表現する。
劇中、マリアとロベルトが新しいジグソーパズルに取り掛かる場面が何度も登場する。シャカシャカしたビニール袋をパリリと破り、中に詰まったピースをテーブルの上にぶちまける。ジグソーパズルは圧縮したボール紙で出来ているので、ひとつひとつのピースは硬く、テーブルに落とすとパキパキと小気味のいい音を立てる。二人はそれを手で選り分け、あれこれと組み合わせを試しながら、ひとつずつ確認していく。パズルのピースを押さえたマリアの人差し指がクローズアップになる。それをススス……と滑らして別のピースのところへ持っていく。はめ込むときはパキッ! ……というほど軽快な音はしない。プスッというか、フカッというか、とにかく静かに、でも、しっかり凸と凹が連結したことが伝わる音が鳴る。ジグソーパズルを愛好しているひとには、聞き慣れた音だ。
映画の中の重要なモチーフがジグソーパズルだから、パズルの場面で記述してみたが、この映画はあらゆる場面でクローズアップと、繊細な音の表現が多用される。細かいディテールを積み上げて映画を構築している。
それはまるで、映画を作ること自体がジグソーパズルを組み立てるかのようだ。同様の問いに対して、監督自身もこう答えている。
「ただし、百万ピースのパズルですね。ひとつのジグソーを完成するためには、全ての小さなピースをよく知る必要があります。それぞれの形、色、特殊性を掴んで初めて、全てがどう繋がるのか見え始めるのです」
(とみさわ昭仁)