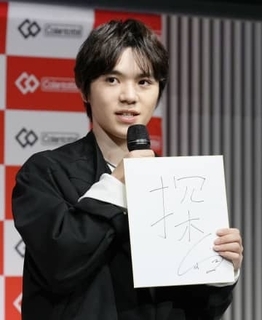「臨床犯罪学者 火村英生の推理」第4話「ダリの繭」を見ながら思わずつぶやいていた。
いや、大泉滉はもう鬼籍に入っていて、この世の人ではないのだった。
調べたら1998年に亡くなっていたことがわかり、一気に時の流れを感じてしまった。
日本版ダリを岩城滉一が演じたということにも隔世の感がある(あ、滉の字が同じだ)。

初の都会派ミステリー
今回の原作『ダリの繭』は1993年12月に角川文庫から刊行された。最初の本が文庫というのは現在では珍しくないが、当時は目新しい趣向に感じたことを覚えている。実はこれ、〈角川ミステリーコンペティション〉という企画の一環をなす作品なのである。本書の著者・有栖川有栖のほか、姉小路祐、阿部智、井上淳、岩崎正吾、折原一、香納諒一、黒崎緑、鳥羽亮、新津きよみ、乃南アサ、服部まゆみ、吉村達也(五十音順)といった面々が参加し、刊行作品の中から読者投票で一位を決めるという趣向の試みだった。
エッセイ集『有栖の乱読』の記述によれば「フロートカプセルの中で見つかる死体」というイメージから出発した作品であるという。
──私の長編小説は、都会の人間が辺鄙なところに出掛けていって恐怖に遭遇する、というパターンになりがちなので、今回は都会的なものばかりを素材に書いてみることにした。
犠牲者は今様サルバドール・ダリを気取る宝飾品チェーンの社長、美貌の秘書を巡る恋の鞘当てがあり、容疑者も会社の関係者にほぼ絞られる。キャラクター配置や小道具などが、確かにすべて都会的な印象のものに統一されている。殺人現場となった社長の別宅の所在地も原作では六甲山中、神戸市の100万ドルの夜景を見下ろす場所に設定されているのである。
初めて明かされるアリスの過去
火村&アリスチームの2冊目の作品ということもあり原作では、第1作『46番目の密室』で登場させた2人にもう少し肉付けを施そうという作者の意図も見てとれる。
近作では警察から依頼を受けて動くことが当たり前になりつつある火村英生だが、本書のころはまだそんなに立場も強くなかった(「『きてもいいぞ』と言われるだけさ。以前は頭を下げてお願いして回ってたから、それに比べると研究もやりやすくなった」)。また、アリスの過去についての言及が多いことにも気づかされる。
──印刷会社の営業をしていたサラリーマン時代なら、こうして唸っている間にも退社時間が近づいていたわけだが、脱サラをして専業作家となってからはそういうわけにもいかない。
おお、アリス。君、元は営業だったのか。
本書のタイトルにある「繭」とは、殺人事件の被害者が中から発見されたフロートカプセルのことを指しているのだが、同時に登場人物のそれぞれが自身を守るために形成した鎧であり巣であるものの比喩でもある。事件関係者ではなく、火村とアリスについてもそれぞれ何が繭であったかの言及がある。本篇がドラマ化の原作に選ばれたのも、そうした要素があるからだろう。ちなみにアリスが作家を目指すことになったエピソード(内田理央演じる鷺尾優子にアリスの初恋の女性を重ね合わせるという演出はドラマ独自のものだ)は、有栖川有栖によれば著者の実体験ではなく、まったくのフィクションであるという(前出『有栖の乱読』)。
新婚ごっこ
ドラマではアリスの部屋に泊まった火村が、2人分の朝食をこしらえる場面があった。原作にもあったいい場面で、食卓についたアリスと火村は「まるで新婚家庭の朝の食卓やな」「新妻になったような気がした」と言い交し合う。ドラマではカットされていたが、この会話に続く台詞はこうだ。
「それにしても、君が自炊に関してはマメなのは知ってたけど、ここまでしてくれるとは思ってなかった」
「これぐらいおやすいご用さ。明け方まで書いてたんだろ? 仕事の遅い作家は大変だな」
まるで世話女房である。
本篇の人物配置は鷺尾優子を巡る男たちという形式になっており、ガラ・エリュアールを我が女神と崇めたダリ、という構図がそこに重ねられている。それを眺めながら、火村は言うのだ。
「困りものなのは男どもだよ。どいつもこいつも女神がいなけりゃ生きていけないんだから」
「おお、女嫌いがぼやいてる」
作家アリスシリーズには火村とアリスの関係の緊密さゆえ、異性が間に入る余地がない印象がある。そうしたイメージがつき始めたのは、この『ダリの繭』あたりからなのではないか。ドラマでは言及されないが、冒頭で2人がレストランで食事をしていたのも、火村の誕生日とアリスの新作脱稿を記念してのお祝いなのである。本当に仲がいいなあ。
長篇のエッセンスを凝縮
第4話にして初の長篇原作だった。
これまでの回同様、人間関係には若干の省略があり、原作では大きなミスリードをすることになった登場人物がドラマには出てこない。この部分の迂回路のつけ方には芸があるので、ぜひ原作を読んで確認してもらいたい。
ところで、原作『ダリの繭』で試みられているのは、物証と証言を元に筋道を作っていく演繹的推理よりも、「可能性をすべて潰していけば、最後に残ったものがどんなにありそうに見えなくても真実だ」というシャーロック・ホームズ式の推理に近い。火村英生は1つの手法にこだわらない探偵で、作品ごとに違うアプローチを採用しているようにも見えるのだ。その多様性が火村&アリスチーム登場作品の魅力にもなっている。
今回『ダリの繭』原作を再読して、作者はかなり早期の段階からシリーズに幅を持たせるような書き方をしていたことに気づかされた。ドラマでは印象が拡散することを防ぐためか、あえて画一的な探偵像に火村を嵌めこむような演出がされているが(最後に関係者を一度に集めて謎解きを行うなど)、それは許容範囲の改変だろう。オリジナルの決め台詞「この犯罪は美しくない」を言わせるタイミングなど、パターンもできてきた。ドラマならではの逸脱や遊びがこの先あるのか否かという点にも着目したい。
第5話の原作は『怪しい店』所収の短篇「ショーウィンドウを砕く」である。今夜の放送もお見逃しなく。