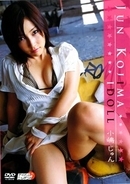『マジンガーZ』『キューティーハニー』など、TVアニメのジャンルでも数々の傑作を残してきた天才漫画家・永井豪。欧州での人気も高いとウワサには聞いていたが、これほどだったとは!? イタリアで大ヒットした実写映画『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』は、1970年代にイタリアでもテレビ放映された永井豪原作アニメ『鋼鉄ジーグ』(英題『Jeeg Robot』)がきっかけで、ローマで暮らすケチなチンピラ男が正義のヒーローへと目覚めていくというユニークなアクションドラマ。
──イタリアで日本産TVアニメの放映が始まったのは1978年から。中でも永井豪原作の『UFOロボ グレンダイザー』(英題『Goldrake』)は凄まじい人気を呼び、翌年には『鋼鉄ジーグ』が放映されることになったそうですね。1976年生まれのガブリエーレ監督は当時まだ3歳だったわけですが……。
ガブリエーレ・マイネッティ イタリアでも「君の年齢で『鋼鉄ジーグ』を知っているのか?」と驚かれることがあります(笑)。
──永井豪作品の中では『鋼鉄ジーグ』は、それほど評価の高い作品ではありません。ガブリエーレ監督は『鋼鉄ジーグ』のどこに魅了されたんですか?
ガブリエーレ 永井豪の作品はどれも魅力的です! バイオレンスに満ちあふれていて、しかも道徳的ではありません。
──処女作には監督のすべてが込められていると言われますが、長編デビュー作に『鋼鉄ジーグ』をモチーフにすることは最初から考えていた?
ガブリエーレ 最初はそうではありませんでした。イタリアでいちばん人気のある『グレンダイザー』をモチーフにできないかと考えていたんです(笑)。でも、ストーリーを考えていくうちに、自分のことしか考えないダメな主人公が内面的に徐々に変化していくという映画の内容に相応しいのは、『鋼鉄ジーグ』しかないと思うようになっていったんです。
■明るいイタリア人の知られざる国民性とは……?
──主人公のエンツォ(クラウディオ・サンタマリア)はローマの下町で暮らすゴロツキ野郎。置き引きなどのケチな犯罪でお金を稼ぎ、後は自宅のアパートでエロDVDを観ているという最下流人生を送っている。
ガブリエーレ 警察に追われたエンツォが飛び込むのは、テヴェレ川です。ローマ市を二分する川で、しかもローマ神話ではローマの街の始まりとなったとされているエリアでもあるんです。そんな神話の言い伝えられる川で、エンツォは洗礼を受けて生まれ変わるわけです。実際問題として、イタリアの水質汚染や土壌汚染は大変な事態になっています。
──主人公エンツォはイタリア市民の怒りを具現化した存在でもあるんですね。イタリアではこれまで国産のスーパーヒーローが存在しなかったと聞いています。スーパーヒーローが過剰気味の日本から見ると不思議に思えるんですが、ガブリエーレ監督はその理由をどう考えていますか?
ガブリエーレ スーパーヒーローものをどうすれば現代のイタリア社会で成立させることができるかを本作の脚本を書く際に熟考したのですが、素晴しいスーパーパワーが手に入った場合、すぐに社会正義をなすだろうかということがいちばんの疑問でした。実際にそんな能力が使えたら、他人のためじゃなくて自分のために使うんだろうなと(笑)。イタリア人をひとつに括ることはできませんが、イタリア人の傾向としてエゴイストな性質があると思うんです。自分や自分の身内さえよければいいと。社会問題が起きると、何かスケープゴートになるものを見つけて、それを叩くことで満足してしまう。もちろん、政治の世界などではカリスマ性のある指導者は過去に存在したと思うけれど、現代のイタリアにはスーパーヒーローと呼べる存在はいません。それなら映像文化と共に育ってきた自分たちの世代が自分たちに相応しいスーパーヒーロー像を考えてみよう、ということで生まれたのが本作。スーパーパワーを手に入れたエンツォは最初はATMを丸ごと盗むなどの犯罪行為を重ねますが、ヒロインと出逢うことで徐々に内面的に変わっていく。そして、そのヒロインが熱狂的に愛するアニメが『鋼鉄ジーグ』だったという内容になったんです。
──付き合う女によって男が変わっていく──というドラマ展開のほうがイタリア人にはリアルだったんですね。怪力自慢の自己チュー男と頭の弱いヒロインという組み合わせはイタリア映画界の名匠フェデリコ・フェリーニの『道』(54)を彷彿させ、ホロッときます。
ガブリエーレ 確かにそうですね。イタリア人にとってはフェリーニ監督の『道』はとても特別な作品です。でも、今回の作品は『道』を意識したわけではありません。どちらかというとリュック・ベッソン監督の『レオン』(94)に近い。本作の主人公エンツォは自分のお気に入りの甘いヨーグルトばかり食べているけど、『レオン』の大男ジャン・レノが子どもみたいにミルクを飲んでいるみたいなもの。あのときのナタリー・ポートマンは少女だったけど、大人の女性のような魅力を持っていた。本作のヒロインであるアレッシア(イレニア・パストレッリ)は身体は大人の女性なんだけど、頭の中は無垢な少女のまま。『レオン』のヒロインとは対称的な設定になっているんです。
■欲望に忠実な永井豪ワールドの住人たち
──イタリアでは永井豪原作の巨大ロボットものが大人気だったようですが、日本では『デビルマン』や『キューティーハニー』は時代を越えて今も愛され続けています。他の永井豪作品はどうですか?
ガブリエーレ 『キューティーハニー』は変身中に洋服が破けちゃうシーンが忘れられません(笑)。『キューティーハニー』は残念ながら、イタリアでは地上波では放映されませんでしたね。永井豪作品にはポルノチックな要素もあり、もちろんそこも大きな魅力です。『デビルマン』に関しては時間がどれだけあっても語り足りないくらい、僕は大好きです。アニメ版もコミック版もどちらの『デビルマン』も大好き。スーパーヒーローが正義のために戦うのはすっごくストレスを感じることだと思うけど、でもデビルマンは怒りのパワーが悪と戦うための原動力になっている。永井豪作品を観る度に「お前は正しい。お前はお前のままでいいんだ」と自分を肯定してもらっているように思えてくるんです。僕が映像表現の世界に進んだのは、子どもの頃に観たそういった日本のアニメーションに感動したからなんです。
──2012年にガブリエーレ監督が撮った短編映画『Tiger Boy』は覆面を被ったプロレスラーに憧れる少年の成長ドラマでした。「強い人間になりたい」という変身願望がガブリエーレ監督作品のテーマとなっているようですね。
ガブリエーレ 『Tiger Boy』は『タイガーマスク』をモチーフにしたものです(笑)。“変身”というテーマは自分では意識していませんでしたが、そうかもしれません。僕自身は恐がりなので、強い人間になりたいという気持ちから映画を撮っている部分があるようです。スーパーヒーローのような強い人間は僕らに勇気を与えてくれますが、でもその勇気を本当に自分のものにするためには、自分自身が変わることが必要です。ようやく新作の脚本を書き終えたところで、新作は日本のアニメーションをモチーフにはしていませんが、やはり主人公に勇気を与えてくれる人物が登場します。僕が描く作品の主人公たちは変身するきっかけを探し求めているのかもしれませんね。日本は『鋼鉄ジーグ』が生まれた、僕にとっては特別な国です。日本のみなさんにも、日本のアニメで育った僕の作品に関心を持っていただけると嬉しいです。
(取材・文=長野辰次)
『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』
監督・音楽・製作/ガブリエーレ・マイネッティ
出演/クラウディオ・サンタマリア、ルカ・マリネッリ、イレニア・パストレッリ、ステファノ・アンブロジ
配給/ザジフィルムズ 5月20日(土)よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほかロードショー
http://www.zaziefilms.com/jeegmovie
●ガブリエーレ・マイネッティ
1976年ローマ生まれ。ニューヨークのティッシュ・スクール・オブ・アートで演出・脚本・撮影などを学ぶ。舞台、映画、テレビなどで俳優としてのキャリアを築く一方、2011年に製作会社「Goon Films」を設立。第一弾作品として短編映画『Tiger Boy』を監督し、ブレスト・ヨーロピアン映画祭など各国の映画祭の短編部門で映画賞を受賞。長編デビュー作となった『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』はイタリアのアカデミー賞と呼ばれる「ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞」で最多16部門にノミネートされ、新人監督賞をはじめ最多7部門での受賞を遂げた。