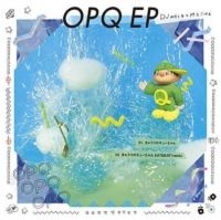7月21日、阿佐ヶ谷ロフトAで「思考ツールとしてのタロット」が開催された。主催者はゲームデザイナー、立命館大学教授、そしてエキレビ!ライターでもある米光一成さん。
タロットを、物事を新しい視点で捉える思考ツールとして使っちゃおう! というイベントだ。
「え〜、タロット? 呪術的っぽーい、こわーい、しんようできなーい」と言う人もいるかもしれない。
いやいや、たしかにタロットと言ったら占いのイメージは強いけど、水晶玉で未来を見たり、ろうそくの炎ユラ〜ってしたりとかはしないんですよ。
おれは、タロットというと「ドラクエ4」とか「ジョジョ3部」とか「ペルソナ」に出てきたくらいでしか知らない。そういえば、米光さんがつくったゲーム「バロック」には、異形というタロットの大アルカナを対応した敵キャラクターが出てくる(カトーという異形もいる)。
はじめに書いたように、誰かに占って「当てて」もらうんじゃなくて、自分で「思い当たる」のが、思考ツールとしてのタロット。
わかりやすい例として、「なぜ相談は失敗するのか」があげられてた。
正しい助言をしても、理屈があっているほど、否定されている気になってしまうから。
自分でも本当の悩みに気づいていないことは多いし、「○○だから△△なんじゃない?」と正しいアドバイスをしても、「でも、□□って問題もあるし」とどんどん新しい事実が出てくる。
つまり、相談された側は当事者じゃないから、どうしたって悩みごとは共有できない。最終的には「あなた、何様なのよ!」ってケンカになっちゃう。あるある。
客席からも「たしかに〜」「あ〜、わかる」などの声が漏れていたよ。
で、結局どうすればいいのか。悩みはどうやって解決すればいいのか。
ここで、タロットの登場。
もし、神様が助言をしてくれたら、「神様が言うんだったら仕方ない」って思っちゃうでしょう。それをタロットに任せちゃうのですよ。
会場で行われた方法は、二人一組になり、相談者とタロット使いにわかれる。タロット使いがしていいのは、相談内容を理解するための質問だけ(助言しない!)。
話を聞いたら、相談者に、タロットを3枚引かせ、並べる。
引いたカードの説明をし、タロットは左から、過去、現在、未来を示している。
相談者はここで、なにかに「思い当たる」。
自分で、思考して、気付くのが大事。
世界をたった22枚のカードに分類したものがタロット。この世のあらゆる事柄は、22枚のカードのいずれかに当てはめることができるのだ。
実際にやってみよう。
おれの相談事は「3月9日に出版した『プリキュア シンドローム!』を、この先、どうやって売っていけばいいか」だ。
3枚引いてみる。過去に皇帝、現在に愚者、未来に恋人。
皇帝が暗示しているのは、父性・土地・明示ルール。
愚者が暗示しているのは、冒険・自由・無軌道。
恋人が暗示しているのは、恋のドキドキ・関係・選択。
考えてみよう。
えーと、過去は版元、組織って考えることもできるな。
強引な解釈かもしれないけど、つまりはこういうことだ。
米光さんによると、「相談するときは、すでに自分のなかで答えが出ていることが多いから、カードによって顕在化してあげる。悩んでいる人は視野が狭くなっちゃっていることに気づいていない」とのこと。
まさにそのとおりだなと実感した例がひとつある。
以前、ライターとは別にずっと続けていた仕事がどうもきつくなり、米光さんに相談したことがあった。
「おれ、これからどうすればいいんですかね?「それじゃ未来のことをタロットに聞いてみればいいんじゃない〜」と、引いたのが戦車のカード。
「戦車ってのは、まっすぐに突き進むカードだから、泣き言なんて言ってないでやればいい……」という米光さんの声をさえぎって、「わかりました! これからはライター1本でやっていくことにします!」とこたえた。
米光さんの解釈を最後まで聞くこともなく、自分で結論を出してしまった。
最初から、自分のなかで答えは決まってたのだ。
ここで米光さんがタロットを使わずに「そんなにいやならライターだけでやれば?」とアドバイスをしてくれても、「そうはいいますけど〜」とか言って解決はしていなかったと思う。
間にタロットを挟むことで、自分の考えが浮き彫りにされた。
たしかに、「思い当たる」。
タロットと聞くと、魔術とか呪術的なもので、霊感とかがある人じゃないとできないのかと思っていたけど、これなら誰にでもできる。悩んだらまずタロットに相談だ。
(加藤レイズナ)