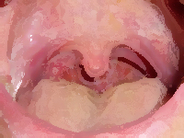僕らの知らない戦争のリアリティー
8月に入ると広島、長崎の原爆の日、そして終戦記念日と、戦争について考えさせられる日が続く。戦争なんて遠い世界のことだと思う人もいれば、緊迫した世界情勢を受けて対岸の火事とは思えないという人もいるかもしれない。いずれにせよ、戦争を知らない僕らが今一度そのリアリティーについて考えてみることときちっと向き合うことも必要だろう。
その絶好の機会を与えてくれる映画『STAR SAND ─星砂物語─』が8月4日(金)から公開される。
沖縄の戦火から離れた島を舞台にしたこの映画を撮ったのはロジャー・パルバース監督。オーストラリア人であるパルバースが、なぜ太平洋戦争の映画を撮ったのだろうか?
事実は小説より奇なりとよく言われるが、本作の公開にまで至るパルバースの半生は凡百の映画よりも奇なるものだった。

CIAにスパイ容疑をかけられ新聞の1面に
1957年10月4日、人類初の人工衛星がソ連によって打ち上げられ、アメリカを始めとする西側諸国がショックとパニックに陥っている中、パルバース少年はロサンゼルスの街から上空数百キロで周回を続けるその衛星にロマンを抱いていた。
少年の宇宙に対するロマンはそれを打ち上げた国へも向かった。青年となりUCLAを卒業するとハーバードの大学院へ行きロシア語とソビエト近代史を学び、ソ連を訪れるようになった。
当時のアメリカ人としては珍しいソ連のスペシャリストとなりつつあったパルバースは、ポスドク(非常勤の研究員)のために渡ったポーランドでとんでもない事件に巻き込まれる。
「CIAから濡れ衣を着せられ、スパイの嫌疑をかけられLAタイムズの1面に大々的に報じられたのです」(パルバース)
ベトナム戦争を避け、日本へ
パルバース青年は冷戦という圧倒的な現実に飲み込まれる。スパイの嫌疑をかけられもはやポーランドにいられなくなったものの、祖国アメリカに帰れば当時戦火が激化していたベトナム戦争にすぐにでも徴兵されかねない状況だった。
見も知らぬ罪のないベトナム人を殺さなければいけないというのは、最もロマンティックでない行為だった。
行き場を失ったパルバースは気づけば縁もゆかりもない極東の地に降り立っていた。言葉もまったくわからぬその地に降り立ったその日、パルバースは不思議な感覚に襲われたという。
「1967年の9月に羽田空港に降り立って、目黒にあるホテルに向かうタクシーの窓から見る黄昏の東京の景色を見ながら、『僕はこの国に一生住むんだ』と独り言ちたんです」
その予感は的中し、以後パルバースは今日に至るまで日本を主要な活動の拠点とする。

伝説の名作『戦場のメリークリスマス』の助監督に抜擢
1967年に日本にたどり着き、宮沢賢治作品との出会いを経たパルバースのロマンチシズムは創作活動に向かうようになった。唐十郎、寺山修司など伝説の演劇人や大島渚、井上ひさし、山田洋次、筒井康隆など多くの文化人と親交を深めながら、日本の文化シーンの中心人物の一人となっていった。
日本の大学で教鞭を取っていたパルバースは、創作活動に没頭しようとオーストラリアに渡り、劇作家として成功し、そこで祖国アメリカの国籍を捨てオーストラリアに帰化する。
以後、日本とオーストラリアを行ったり来たりしながら行うパルバースの活動はいつしか半世紀近くにも渡り、青年も気づけば老成の域に達したといわれる年齢になっていた。
72歳。
隠居していてもおかしくないその年齢でパルバースは映画監督として初めてメガホンをとることを決意する。それが『STAR SAND ─星砂物語─』なのだ。
原作小説を井上ひさしが絶賛
『STAR SAND ─星砂物語─』はパルバース自身の小説『星砂物語』の映画化したものだ。構想自体は1977年に沖縄の鳩間島を訪れて以来温めていたが、2003年にGWブッシュ政権がイラク戦争を開戦したのを機に、パルバースの中の何かに火が付いた。大義なき侵攻は、まさにベトナム戦争そのものだった。そんな戦争を正当化させてはいけないという思いから、2008年に同書の執筆にとりかかる。2009年に完成すると、パルバースは友人であり、尊敬する小説家・劇作家である井上ひさしに恐る恐る原稿を送る。
「素晴らしい! これは絶対に出版すべきだ」
井上の絶賛に勇気を得て世に出ることになった小説は高い評価を経て、ついに映画という形で公開されることになったのだ。
「脱走兵」は監督自身の分身

本作ではアメリカ軍と日本軍の二人の脱走兵と、それを見守る一人の少女の物語が、2016年と1945年の二つの視点からミステリー交じりに描かれている。脱走兵とは、まさにベトナム戦争を直前に戦うことから逃げたパルバースの分身だ。
象徴としての無垢をも汚す戦争のおぞましさ、そして損なわれた無垢の回復と継承という繊細かつ難しいテーマを、織田梨沙、満島真之介、吉岡里帆などの若手俳優が好演し、石橋蓮司、緑魔子、寺島しのぶら実力派のベテランがしっかりと脇を固める。
「俳優たちは皆パーフェクトでした。織田梨沙は経験もあまりないのに素晴らしく深い演技をしますし、海外の人に見せると吉岡里帆の演技も凄いと言われます。本当に素晴らしい俳優たちに恵まれました」(パルバース)
あらゆる暴力は絶対肯定されてはいけない
しかし「戦争」と大上段に構えると、かえって見えなくなることもある。戦争の是非を問う前に、そもそも暴力自体が許されてはいけないものだとパルバースは強調する。
「本作のテーマは反戦平和というよりは非暴力です。戦争、幼児虐待、DV、ありとあらゆる暴力は絶対に正当化されてはいけません」
国際情勢がきな臭さを増す中、反動でマチズモを振りかざすものもでてきている。しかし、そのような時代だからこそ、もう一度立ち止まって暴力をかざすことの意味や、圧倒的な暴力を強いられる戦争について考えてみる必要があるのではないだろうか。
本作は、そうしたことをゆっくり考えるいい機会を与えてくれる。(文中敬称略)
(鶴賀太郎)