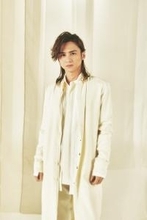第17週「支えたい!」第98回 7月24日(火)放送より。
脚本:北川悦吏子 演出:深川貴志
98話はこんな話
「あの日からどれだけ経ったろう」
原作ものを脚本化すると誓ってから2年、2002年初夏、涼次(間宮祥太朗)はついに「名前のない鳥」の脚本を完成させた。
ベストセラー作家・佐野弓子(若村麻由美)は自作の映像化を拒否してきたがその脚本が気に入って・・・。
2年間の倹約生活
涼次の打っている原稿を見ると、「名前のない鳥」の主人公はレナとダイゴというらしい。
レナ「歩幅が・・・同じ・・・」
出た、三点リーダーが三文字分。映像界の人はとかくこう書く人が多い。 出版界の決まりだと三点リーダーは一文字分に凝縮したものにしたうえ、ふたつ並べる(「……」)のが規則だ。ネット業界でも、それだと読みづらいということで「・・・」になる。
世界が違うとルールも違うものなのだ。
いろんなルールがあるということで・・・。
この2年間、鈴愛は、喫茶店で水しか飲まず、ペットボトルで風呂の水増し、鳥の胸肉しか食べない、スーパーで変装して何回も並んで特売品を買うなど、独自のルールで生活してきた。説明はユーコ(清野菜名)。
喫茶店では必ずひとり一品は注文する、おひとりさま何個と決まったものはそのとおりに、という世間一般のルールは無用である。生きるためには。
ヒロインは鈴愛似
そして、ようやく涼次は原稿を完成させた。
涼次は原稿ができたことを顔に書いて鈴愛に知らせる。
だが、長らく健気に働いて支えてくれた鈴愛よりも先に元住吉に見せたいという気持ちを鈴愛は察する。
でも、はねっかえりはそのままらしく、脚本のヒロイン(レナ)は鈴愛がモデルになっていて、はねっかえりで早口だと涼次は言う。
鈴愛は「はねっかえり」という言葉は聞こえてないらしく「早口なんか〜」しか言わない。都合の悪いことは無視する、そこは昔と変わらない。
それにしても原作がのもともと鈴愛に似ているヒロインだったと解釈して良いだろうか。
そうでないと、勝手に鈴愛に似たヒロインに寄せてしまうなんて、原作者も熱狂的な読者も許さないであろう。
若村麻由美、登場
できた脚本を、佐野先生に読んでもらったら、いたく気に入った様子。
売れっ子佐野先生は、なんだかエキセントリックな人だった。
それを軽やかに演じる若村麻由美。
自作が売れていることを「いいんじゃない数字は」というところでは、北川悦吏子がネットで視聴率のことを「もう数字はいいんじゃないか」と発言して話題になったことを思い出す。ちょうどこの回の脚本を書いているときに、ツイートしたんじゃなかろうか。
佐野先生のサバサバしたお姫様気質な台詞回しとふるまいは、ロンバケの南に似ているように見える。おそらく、北川悦吏子の好む台詞回しを的確に読んで再現すると、同じ口調や振る舞いが浮かび上がってくるのだろう。これがやってみるとなかなか難しく、さばさばしていて、エキセントリックでありながら、可愛げは残さないといけないという、俳優の才能が試されると想像する。
ポイントは語尾を少し伸ばして甘さを出すこと。山口智子、若村真由美に限らず、キムラ緑子もちょっと大げさなくらいにやっている。
そうしないと語尾がただキツく聞こえてしまうのだろう。永野芽郁は先輩たちの芝居を参考するといいと思う。
若村麻由美は、Praraviで配信中の堤幸彦監督「SICK‘S」で、ピンクハウスもどきのワンピを着て大活躍。ここでも難しい役をみごとに演じている。
俺が監督しちゃだめでしょうか
原作者がクールフラットにやって来たとき、なぜか、その場に涼次は呼ばれていなくて、斑目プロデューサー(矢島健一)と元住吉だけ。
「すごい この人才能あるよ」と佐野が言うと、元住吉は「俺が監督しちゃだめでしょうか」と言い出す。
元住吉は「追憶のかたつむり2」が大コケして以降、映画が撮れなくなっていて、芸術性の欠片もないCMなどで糊口をしのいでいた。
CMを依頼してきた人物が、「アンナチュラル」にも出ていた飯尾和樹。
と、ここで思うのは、デジャビュである。
98話で鈴愛が麦(麻生祐未)に「岐阜の山猿」と言われて「デジャビュ」と言う。
元住吉が、人の書いたものを自分で撮りたいと言い出すことにも、漫画家編で、ボクテ(志尊淳)が鈴愛のネタを漫画にしたいと言い出したエピソード66話を思い出した。
さらに、鈴愛のネタを原案にして師匠・秋風(豊川悦司)が「月が屋根に隠れる」を描いた79話も、彼女を助けるためではあったが、元住吉と涼次の関係性と重なる。
ここで、同じパターンじゃないかというのは簡単だが、ここには意図があるような気がするのだ。
人生、同じようなことが繰り返されるものというのは自明の理だし、実際、「リフレイン」を演出の手法としている作家もいるのだ。
マームとジプシーの藤田貴大は劇中、何度も何度も同じ台詞や場面を繰り返す作品で有名だ。彼はそれをリピートではなくリフレインと呼ぶ。何度も何度もあるシーンや台詞が繰り返され積み重なる演出は、演者にも観客にも同じことにもかかわらずなんだか違う感情や身体感覚をもたらす。
“僕の舞台作品で取り扱われるシーンの反復は、リピートではなくて、“シーンが助長されていくリフレイン”なのだと気づいたのも、それくらいの時期で、それからは反復されるシーンのことを、僕らはリピートではなく、リフレインと呼んでいます。
取り扱う事柄を、より多面的に描くのにも有効でしたし、多くの登場人物の心情風景に濃淡をつけるのにも、さらに言えば、ある街を描くうえでも、一番の武器になったように思います。“(パフォーミングアーツ ア~ティストインタビューより 聞き手:扇田昭彦 2011年11月18日配信)
98話は2002年の FIFAワールドカップとNHKの放送のテーマソングになったポルノグラフィティ「Mugen」で視聴者を沸かせたが、ここはあえてユーミンの「リフレインが叫んでる」を思い出したい。
このレビューで前にも紹介したが、北川悦吏子は「リフレインが叫んでる」をモチーフに脚本を書いている。

「リフレインが叫んでる」が収録されたアルバム
ふたりの男性の間で揺れ動くヒロインのお話で、ふたりのうちのひとりと付き合ったものの彼女の心は定まらない。この作品の場合の「リフレイン」は「どうしてどうして」と後悔や未練の繰り返しである。
「半分、青い。」に表出する「リフレイン」はどこに向かっているのだろうか。
(木俣冬)