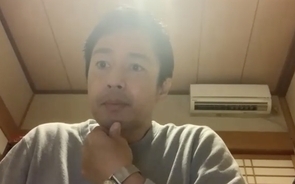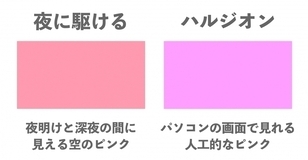柳原陽一郎/ニューアルバム『小唄三昧』をリリース
平成が始まった頃に音楽シーンに登場し、“たま現象”と呼ばれる社会現象まで引き起こした人気バンド“たま”に在籍、代表曲「さよなら人類」の作者でもある柳原陽一郎が、平成の最後にまたもや怪作にして快作の『小唄三昧』をリリースした。この人の手にかかると、日本の小唄もカントリーもフォークロックもブギウギも……、ラブソングもプロテストソングも……、すべて仲よく収まるところに収まっていく。
あんまり力づけない、大袈裟でもない、他愛もない歌なんですけど、こんな歌はどうですか?
──5年ぶりとなるオリジナルアルバム『小唄三昧』ですが、まずタイトルとジャケットが衝撃でした。……小唄? お座敷? 伝統芸能? でもテンガロンハットの骸骨……みたいな。
柳原:“小唄”と聞いて、みなさんがピンとくるのは芸者さんが歌うものだと思うんだけど。なんとなく自分にとっては立派なことを歌っていない歌、ためにならない歌、そういう意味での“小唄”だったりするんです。最近は偉そうなことを歌う歌が多いでしょ、明日を信じようって力づける歌とか。そうじゃなくて、あんまり力づけない、大袈裟でもない、他愛もない歌なんですけど、こんな歌はどうですかっていう意味を込めました、タイトルには。
──けれども歌の内容はとても「他愛もない」とは思えない、プロテストソングもかなりあるように思いましたが。
柳原:そうかもしれない。なんか日本のポップソングって、自分を大事にしてほしい、自分は寂しい、でも明るい未来に向かって頑張ろう、みたいな歌が多いなぁと思うことがあって。
──そういう歌は以前から聴いていたのですか。
柳原:聴くことはありました。古い話だと、“たま”を気に入ってくれていた評論家の竹中労さんからも「こういうの聴け」ってカセットテープを何10本ももらったし。だけど、その頃はピンとこなかった。でも勝手なもので、音楽は時代や状況によって聴こえ方も感じ方も変わるから。たしか5~6年前くらいからじゃないかな、田端義夫の「ズンドコ節」とか、小唄や端唄に影響を受けたデビューした頃の美空ひばりの歌を聴いて、いいもんだなって思うようになったのは。またちょうど同じ頃に『三文オペラ』もやって、それの影響もあると思う。
──『三文オペラ』はウイットに富んだ反骨精神がテーマとも言える音楽劇ですよね。
柳原:そうそう。あれを訳したり歌ったりしながら、今の日本には「俺たち困ってんだぞ、なんとかしてくれよ」とか「俺は飲んだくれのダメ人間だ」とか「あなたが好きすぎて殺したいんです」みたいな歌はあんまりないよな、と思ってね。なんか歌のバリエーションが狭くなっちゃったよね。ドイツで『三文オペラ』を歌ったときにも思った、もしここで日本の歌を歌うことになったら何を歌うんだろうって。『三文オペラ』という、お上に楯突くような際どい歌を歌った人間が『さくら』を歌う? 『君が代』を歌う?『よこはまたそがれ』を歌う? それでいいの?って。でも残念ながら今の日本の歌に『三文オペラ』に通じるような歌はないから、タイムマシンに乗って時を遡るしかなかったんだよね。
──それで添田唖蝉坊や田端義夫や昔の小唄に行きついた。
柳原:そう。昔の日本には庶民の反抗精神を歌った歌がいっぱいあるから。
──そうは言うものの、以前から、そういうタイプの歌を歌っていませんか? 例えば「えらくなりたい」(2003年リリース『ONE TAKE OK!』収録)などは俗物な偉い人を揶揄ってる歌のように思いましたけれど。
柳原:はいはいはい。あの歌でも偉くなるためには感動のストーリーをでっちあげろって歌ってるもんね(笑)。たしかにそう。そういうところは昔からあったと思う。ただ、ここまでハッキリとやってはいなかったと思いますね。

──それには、何かきっかけがあったのでしょうか。
柳原:なんだろうなぁ……。「頑張ろうよ、お互い肩を組もうよ」っていうことは前作の『「ほんとうの話」』で歌ったから、今度は権力への攻撃に回ろうと思ったのかな。責任を取らずに全部なかったことにしようとする連中、金で解決しようとする連中、そういう偉い連中に対して、それでいいの?って思ったんじゃないかな。平たく言うなら、今回はそういう感じの歌なんだと思う。
──たしかに『「ほんとうの話」』と『小唄三昧』は全く感じの違う作品で。正直なところかなり驚きました。
柳原:そもそも『「ほんとうの話」』は2011年の地震や原発事故のために、どうしようもなくなってしまった人の悲しみを歌いたいっていうところから始まったアルバムなので。その悲しみとか怒りを「農夫に力を」という曲で歌ったり、そういうなかでもなんとか生きていってほしいと思って「再生ジンタ」みたいな曲を作ったりして。そのあと25周年の企画でセレクションアルバム『もっけの幸い』(2015年)を出して、ライブ音源集の『らぶ あんど へいと』(2016年、ライブ音源によるミニアルバムのシリーズ第1作目)を出したんですけど。その『らぶ あんど へいと』が『「ほんとうの話」』と『小唄三昧』をつなぐ作品だったような気もしますね。
──『らぶ あんど へいと』には切ないくらいやさしい「また明日」や深い悲しみが歌われた「4B」がある半面、強い怒りを感じる「ハラショー!戦争」も収められていましたね。
柳原:この時期は次のテーマを探してたんじゃないかな。ちょうど端境期というか。だから「あなたがいなくて私はとっても悲しい」っていう「4B」みたいな曲と、「こんな世界に誰がした」っていう「ハラショー!戦争」みたいな曲が共存しているんだろうし、もっというと「ハラショー!戦争」でファックユー系の曲の火蓋を切っちゃったんだろうね。だけど「ハラショー!戦争」は怖いでしょ?
──怖いというか、本当にシリアスな歌ですよね。
柳原:そうでしょ。
──『三文オペラ』と『らぶ あんど へいと』を経て、世の中の毒を茶化して歌いたいと思うようになったわけですか。
柳原:特に『三文オペラ』は大きかった。そこで音楽は明るくなきゃダメと思ったからね、楽しくなきゃダメだなって。『三文オペラ』にはラテン、クラシック、ジャズとか音楽的にいろんな要素があるから。そういう一つのジャンルに縛られない豊かな音楽の世界に実際に触れて、自分でも何かできないだろうかと思ったから。
──すると『三文オペラ』がなかったら、『小唄三昧』もちょっと違うものになったと思いますか。
柳原:違うと思う。ここまで踏ん切れてないかもしれないし、もうちょっとパーソナルなものになっていたかもしれない。でもパーソナルなことは『「ほんとうの話」』で突き詰めたから。ただシリアスなことをテーマに歌うのはいいけど、自分はシリアスなことをシリアスなまま歌う歌手じゃないなとも思った。やっぱり偉くない、元気づけでもない、明るくチャラチャラと毒のあることをやるのが自分らしいかなって。
──でも「生きなっせ」に力づけられる方は多いと聞きましたが。
柳原:あの歌はちょっとヤケクソ的なとこもあって、実はパロディーというか。だって“80歳で己を知る”“100歳で満開”って、どう見てもバカバカしい感じでしょ(笑)。むしろ本当に歌いたかったのは「なさぬ人」のほうだから。何もしなくたっていいんだよ、なんで偉くならなきゃいけないの? なんでお金をたくさん稼がなくちゃいけないの?とか。

──そういうことをちょっと茶化して歌っているところがいいですね。「生きなっせ」もそうですけれど。
柳原:立派な考えをひけらかす歌や飼い慣らされた羊の歌ばかりじゃつまらないでしょ。お上に楯突いて「やってらんないよ」って言いながら、それを笑えるような歌もないと。世を憂えて悲しんだり怒ったりするだけじゃなく、「みんなで笑っちゃおうよ、あのバカな奴らを」みたいな歌がないと。大統領とか首相とか偉い人がいて、そうじゃない全然偉くない人がいて、そっちのほうから世の中を見た歌を作りたいって、ずっと思っていたんですよね。
――【柳原陽一郎】インタビュー後編へ