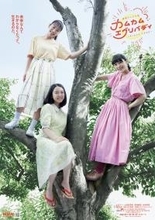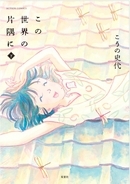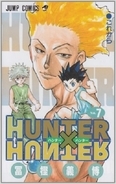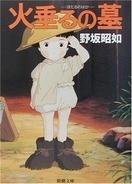「250万乙女」が夢中だった作家11名
80年代後半から90年代前半の読者は、本誌の中で「250万乙女」と呼ばれた。今回展示対象となったのは、「250万乙女」のころに活躍した作家がほとんどだ。「一番読者が多かったころの作品」ということなのだろう。

1955年の創刊から64年の歴史がある『りぼん』だが、今回の展示はこの時代の作品が中心だ。主に現在30代後半(もしくはその前後)の世代にとって馴染みのある作品が多い。
会場には、原画120点や当時のふろく150点が並び、先生によるこだわりや裏話のコメントを読みつつ閲覧できる。

読者が初めて見る岡田あ〜みんの生原稿
作家11名のうち、過去に開催された展覧会で一度も登場したことがなかったのは岡田あ〜みんの原画だけだ。

「ルナティック雑技団」の読み切り数作は、長年単行本に収録されないままだったので、多くの読者は読むことができなかった。
絶版本の復刊を目指すサイト「復刊ドットコム」で十年以上ぶっちぎり一位でありつつ、ずっと何の音沙汰もなかったが、2015年に発売された新装版にようやく収録され、その原稿が展示されたのだ。
ファンにしてみたら「作者も引退してしまっているし、もう新しい動きなんてないと思ってた」のに、「あのずっと読むことすらできなかった原稿が、生で目の前で現れた」のだ。
グッズのTシャツが初日に売り切れになったことからも、根強い人気が分かる。

アラフォーが持ちやすいグッズ展開
展覧会に合わせて発売されるグッズは種類も豊富で、作品の世界観と合ったものが多い。開発担当の方に少しお話を聞いた。
──グッズはどういったこだわりで開発されたんでしょうか?
担当者:私はまさにこの頃の『りぼん』を読んでた世代なので、当時のふろくの絵柄やイラストを使って懐かしさを感じるもの、そして自分と同じアラフォーぐらいの女性が持っててもおかしくないようなアイテムを考えてみました。
──私も同世代ですが、使いやすそうなグッズがたくさんあって嬉しいです。
担当者:どのグッズを気に入ってもらえましたか?
──ノートは特に、当時のふろくそのまんまなのが嬉しいです。懐かしい思いを持ちつつ、普段から使えそうなのがいいですね。
担当者:人前で出さなくても、個人でたまに開いて「フフッ」となるような感じがありますよね。ノート以外には、スチームクリームやポーチもカバンの中に忍ばせておいて、自分だけが見て「フフッ」と笑えるような、そんなグッズを目指しました。


やはり使う側と近い立場の人が作ったからこそ、物販も盛況なのだろう。
展示を見るだけじゃなく、写真を撮ったり、買い物をする楽しみもある「特別展 りぼん」は7月28日まで続き、秋以降は京都・長野・佐賀への巡回もある。
(さくらいみか)