■グループ企業3社で発覚した認証不正問題
日本の衰退を多くの人が懸念する昨今、世界の企業に伍している希少企業のひとつ、トヨタのグループ企業に不祥事がつづいている。
2022年3月、日野自動車がエンジンの性能試験で不正を働いていたことが発覚し、国内で全車種の出荷が一時止まった。
昨年3月には、トヨタの源流企業である豊田自動織機で、フォークリフト用エンジンの性能試験で不正があったことがわかった。
昨年4月は、ダイハツ工業の海外向け4車種で、安全性を確認する衝突試験で不正が発覚した。
また昨年5月に、鋼材メーカーの愛知製鋼で、顧客と契約した規格から外れた鋼材を出荷していたことが明らかになった。規格外の製品は、重量換算で全体の約3%だったという。
いずれもグループ会社の不正問題で、トヨタ本体の不祥事ではない。しかしトヨタ本体が無関係とは言えない。
■豊田会長がグループ企業の改革に取り組む
「トヨタの強さ」とはそもそも何か。これからも世界の優良企業に引けを取らずに発展しつづけるのか。ここでは、トヨタがもつ強さの本質について考察したい。
ダイハツ問題が発覚した昨年4月、トヨタの豊田会長と佐藤恒治社長は、自社サイトの「トヨタイムズニュース」で53分の動画を緊急生配信し、認証不正の経緯や背景を説明した。
また、豊田会長は今年1月の記者会見で、相次ぐ不正問題について謝罪したうえで、不正を起こした3社の変革は、自分が責任者だと語った。
2月には佐藤社長がダイハツとともに記者会見を開き、ダイハツのトップ交代を発表。また、不正問題の背景として、海外事業でダイハツへの負荷が高まっていたことを語り、グループ内の役割分担を見直す考えを示している。
トヨタ経営陣のメッセージが与えた印象は、他社が謝罪会見等で発するものと大きな違いがあった。トヨタが世界トップの自動車メーカーとなった理由、成功の土台となった経営姿勢が読み取れるのだ。
■トヨタの経営思想は、問題との向き合い方に表れる
2月13日に開かれた佐藤社長の記者会見を例にとろう。企業不祥事の会見は、たいていトップが謝罪の作法に則ってタテマエを述べるに留まるのに対して、佐藤社長は不正が起きた経緯と背景を具体的に説明した。
2016年に子会社化して以降、トヨタはダイハツの経営に関与してきた。ただし、問題を起こした小型車については、ダイハツの強みであることから、リスペクトもあって現場にはタッチしなかった。
佐藤社長の認識では、小型車の現場を放任していたのは経営の責任である。再発防止策としては、今後は小型車の現場もしっかり管理していくと説明していた。タテマエや抽象論でなく、責任の所在を明確にし、経営の具体的な行動を示している。このあたりに違いが見える。
佐藤社長の説明に垣間見えたのは、「常に問題を見える化し、根治治療に取り組むことで組織は進化する」という企業観、経営観だ。どんな企業にも問題と呼べるものはある。問題から目をそむけ、問題を隠そうとする経営者とは異なり、佐藤社長はじめトヨタの経営陣は正面から問題に向き合い、常に根治治療を目指す。会社、組織の本質をどう捉えるかの問題である。
■豊田章男流のガバナンスとは
豊田会長が1月30日に不正問題について語ったときも同様の印象を受けた。再発防止策を問われ、「今回不正を起こした会社は、やってはいけないことをやりました。
豊田会長は、各社のトップや現場リーダーに「私がトヨタという会社の主権を現場に戻した、商品に戻したということを一度ご自身でお考えください」と話したという。会社の主権を現場に戻し、立場や出身にかかわりなく、経営に参画できる体制にしたのが、豊田章男流のガバナンスだという説明もあった。
聞く人によっては「不遜な態度」と感じるほど、自らの信念に基づき、トップの責任を果たす姿勢がうかがえる謝罪の言葉だった。
■経営者、マネジャー層は必見のYouTube動画
トヨタが日本を代表する企業といえるのは、売上や組織の規模だけでなく、卓越した経営思想によるところが大きい。87年の歴史で培われ、受け継がれてきた経営思想だ。
業種や規模を問わず、企業経営者が参考にし得る点がたくさんあると私は思う。
もともとトヨタは「現場が発する挑戦文化」と「スタッフ陣が先頭に立つグループを重視した安定志向の調整文化」の絶妙なバランスによって成長してきた会社だ。したがって、グループ内には古い体質の会社も見られ、一部の販売会社には家父長制的な経営姿勢やグループ偏重の姿勢も残る。
豊田会長にとって14年間の社長時代は、トヨタグループの古い調整文化と闘い、現場発の挑戦文化を醸成する期間でもあっただろう。特に情報公開の姿勢は、見違えるほど変化した。社内の細部まで見える労使協議会や労使交渉の全容をYouTubeで公開するなど、かつてのトヨタでは考えられないことだ。過去のものから視聴していくと、どの会社にもあるような話し合いの中身が、年を経るごとに質的に変化してレベルアップしていく様がよくわかる。どんな経営書よりも学びが多く、経営者やマネジャー層は必見の動画なのだ。
■意思決定のスピードを上げる
ただし、トヨタの10年先を考えると懸念はある。動画で発信するメッセージのなかに、豊田会長を絶対化するような発言が時折見られるからだ。成功のすべては、当時の豊田社長がひとりで成し遂げたかのように聞こえる。しかしトヨタに成功をもたらした数々の施策が、豊田会長ひとりの知恵であったはずはない。
トヨタにはそもそも非常に優秀な人材がそろっている。優秀なスタッフたちの仮説がぶつかればぶつかるほど、意思決定は混迷を極める。豊田会長の果たしてきた役割は、大きな方向性を提示すること、トヨタ哲学の確認、そして最終的な意思決定だったはずだ。
私が専門とする風土改革の最前線では、意思決定スピードが速い欧米企業に負けないために、多数の合意に頼らず意思決定を速めるしくみを働かせる。「衆知を集め、リーダーの役割を担うひとりの人間が決め、全員で推進する」というルールを共有する。ひとりのカリスマに頼っていては人材が育たない。意思決定の役割を果たし、試行錯誤を重ね、数多くの失敗を経験して人材は育つ。意思決定の速い人材が育つ組織風土を築けるか否かで勝負は決まる。
■「主権を現場に」はどこまで浸透するか
豊田会長がいう「会社の主権を現場に戻す」は、トヨタを進化させた力の源泉であり、最も大きな役割を果たしたのはお家芸であるカイゼンだろう。トヨタの改善活動が独特なのは、取り組むテーマを選ぶ際に「できるか」「できないか」を判断基準にしない点だ。重視するのは「必要か」「意味があるか」である。
大企業は真面目な従業員が多く、指示されたことをうまく捌く力で仕事をまわしている。上司から指示を受けたらまず「どうやるか」「どう達成するか」を考える。私に言わせれば、思考停止の状態だ。
トヨタにも「どうやるか」と考えてしまう従業員はいる。しかし他社と大きく違うのは「必要か」「意味があるか」と、自分の頭で考える従業員が、間違いなくそれなりの割合で存在することだ。自分の頭で考える従業員を増やし、チーム力を高めていくことが、豊田会長がいう「主権を現場に」の真意だろうと私は理解している。
■“現場との対話”は簡単ではない
不正問題を起こした3社では、今後「主権を現場に」を進めて、自分の頭で考える従業員を増やしていくはずだ。万が一、上司から不正な行為を指示されても、「どうやるか」と考えるのでなく、「必要か」「意味があるか」と考えるようになれば、問題が起こることはない。トヨタの現場リーダーがダイハツに入って、風土改革を支援していくことも考えられる。
経営陣が、現場からの情報を待つのではなく、自ら現場に出向いて直接対話することの必要性をトヨタ会長は説く。“現場との対話”を徹底する経営が求められていることは確かだ。
しかし、経営者と無数にある現場が直接コミュニケーションをとる組織運営は実際には難しい。現場第一と言っても、忙しい経営者が足を運べるのは、ごく一部の現場にすぎない。経営者と現場の間にはいくつもの階層があり、さまざまな会議体が情報伝達の役割を担っている。懸念されるのは、会議体によっては短時間で効率よく情報を伝達することが目的化され、重要な生の情報が伝わらない可能性があることだ。
■心理的安全性の高さが会議を「拓く場」にする
効率を重視する会議は、あらかじめシナリオが用意され、予定調和型に陥りやすい。結論を想定せず、シナリオを用意せず、本気で議論すれば、効率は圧倒的に悪くなる。白熱した議論のコーディネートは、スキルと経験が必要であるから簡単にできないのだ。
風土改革の最前線では、シナリオ通りの会議を「閉じる場」と呼び、活発な議論が起こる会議を「拓く場」と呼んでいる。「閉じる場」では、何ごとも「できるか」「できないか」を基準に検討される。スキルと経験を積み重ねることで、「拓く場」になる「必要か」「意味があるか」という思考が醸成される。
トヨタの労使協議会でも、現場リーダーの工長が上司である課長にものが言いにくいという問題が取り上げられていた。トヨタでさえ、会議はまだまだ「閉じる場」が残るのだろう。誰もが安心してすべての情報を伝えられる会議、つまり心理的安全性が高い会議ではないということだ。
ダイハツはじめ不正問題を起こした3社で、どれだけ「主権を現場に」が浸透していくか、今後に注目したい。
----------
柴田 昌治(しばた・まさはる)
プロセスデザイナー代表、創業者
1979年、東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。86年、日本企業の風土・体質改革を専門に行なうスコラ・コンサルトを設立。30有余年にわたる改革の現場経験の中から、タテマエ優先の“調整文化”を象徴する〈閉じる場〉が培養する、社員の思考と行動の縛りを〈拓く場〉を経験することで緩和し、変化・成長する人の創造性によって揺らぎながら組織を進化させる方法論〈プロセスデザイン〉を結実させてきた。『なぜ会社は変われないのか』『トヨタ式最強の経営(共著)』『なぜ社員はやる気をなくしているのか』『どうやって社員が会社を変えたのか(共著)』『なぜ、それでも会社は変われないのか』(いずれも日本経済新聞出版)、『成果を出す会社はどう考えどう動くのか』(日経BP社)、『日本企業の組織風土改革』(PHPビジネス新書)、『日本的「勤勉」のワナ まじめに働いてもなぜ報われないのか』(朝日新書)など著書多数。
----------
(プロセスデザイナー代表、創業者 柴田 昌治 構成=伊原直司)


















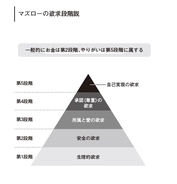

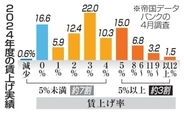








![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)

![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)








