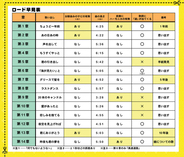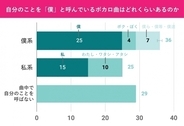ブルース・スプリングスティーン風のロックンロール、80年代ポップ、そして現代的なシンセポップまでをひとまとめにしたような音楽性は2021年の前作『Take The Sadness Out of Saturday Night』を踏襲したもの。だが今回は、本人の言葉を借りれば「一皮剥けた」ように生き生きとして開かれたサウンドになっている。
詳しくは以下の対話に譲るが、これまでのブリーチャーズはアントノフが18歳のときに妹を亡くしたことの喪失感や悲しみと向き合い続けてきた。しかし今の彼はその消えない悲しみを抱えたまま、悲しみ以外の様々な感情のスペクトラムも表現できるように成長した。音楽的にも精神的にも「一皮剥けた」のである。
この変化を後押ししたのが、一昨年結婚した俳優のマーガレット・クアリーとの出会いやアントノフのアーティスト仲間たちとの絆。だからこそ、このアルバムにクアリーをはじめ、ラナ・デル・レイ、The 1975のマシュー・ヒーリー、セイント・ヴィンセントなど、「アントノフ・ファミリー」が多数参加しているのは感動的だ。
先日、ブリーチャーズはサマーソニックの第1弾ラインナップとして発表された。バンドとしてキャリア史上最高の充実期を迎えつつある彼らの姿を、この夏、ぜひ目撃してもらいたい。
―まずはグラミーの最優秀プロデューサー賞の受賞、おめでとうございます。3年連続での受賞は90年代のベイビーフェイス以来の快挙ですが、あなたは自分がプロデューサーとしてこのような華々しいキャリアを歩むようになることをどの程度想像していましたか?
アントノフ:まさかこの域にまで達するとは夢にも思っていなかったよ。
―いまではプロデューサーとして大活躍しているわけですが、ブリーチャーズの活動とのバランスを取るのが難しかったりしませんか?
アントノフ:それが不思議なくらい難しいことではないんだ。いつ何時も、自分が惹かれる、「やらずにはいられない」と思うことしかやらないから。作品作りにおいて、大事なのはそこだと思う。曲作りにしてもプロデュースにしても、自分の中から衝動のようなものを感じない限り、やるべきではないんだ。
―本当にやりたいことだけをやっていれば、多忙でも大変じゃないと。
アントノフ:朝起きてスタジオに来た時に、自分の作品用の曲を書きたいと思う時もあれば、他の誰かの作品用の曲を書きたいと思うことだってある。前もって決めて取り組むことは少なくて、なんとなくやっている感じなんだ。その日の気分で、「スタジオに来て、何か一緒に作らない?」って誰かに連絡して、その人の作品を一緒に作業することもあるし、自分向けの曲を作りたいと思ったらそうする。実際はそれだけのことなんだよ。

Photo by Alex Lockett
―プロデューサーとしてだけではなく、ブリーチャーズというバンドとしても好調であることは、ニューアルバムの『Bleachers』からも伝わってきます。特に前半はこれまでよりもアップテンポで開かれた曲が多いですね。
アントノフ:今回は、音楽を作るようになってから初めて、悲しみ以外についての曲が書けると感じたんだ。18歳の時に妹の他界を経験してから、これまで書いてきた曲のほとんどはその経験にまつわるものだったんだけど。
―ええ、これまでのブリーチャーズのアルバムは、どれも13歳で病死した妹の死の悲しみを背負っていました。
アントノフ:ただそれも、決して過去に生きていたというわけじゃないんだよ。その経験について書き続けていただけで、年齢を重ねるごとに、違う視点で書いたり、悲しみと時間の経過の関係について書いたりしてきたから。でも今回は何か違ってね。
―今回のアルバムでも妹の死には向き合っていますが、以前と較べると違うテーマの曲が増え、前を向いて今を楽しむというニュアンスが強くなっているように感じました。
アントノフ:そうだね。
―だからこそ、あなたは妹の死の悲しみに向き合った曲を書き続けてきた。
アントノフ:やっぱり僕の中でその悲しみ自体が小さくなることはないんだけど、何年も時が経つと、他の感情もそこには存在していることに気づくんだ。その(悲しみ以外の)空間が大きくなる感じっていうか。
―なるほど。
アントノフ:例えるなら、自分の心が一つの街で、そこに少しずつ建物を建てているような感覚かな。自分がかつて凄く落ち込んだ時だったり、不安でいっぱいだった時に居た建物に立ち帰ることもできるし、他にも誰かをひたすら恋しいと思うことについての建物や、心を痛めたことについての建物、死についての建物もあるっていう。で、この1年は新しい建物も建てて、そこで時間を過ごすこともあったんだ。このアルバムでは、僕の中にあるその街をあっちこっち行き来している感じだね。悲しみはまだあるけど、美しくもあって、それ(自分の心の街にいろんな感情の建物があるということ)を知る唯一の手立ては時間なんだよ。
―先ほど自分の変化に影響を与えたもののひとつとして、一昨年結婚したマーガレット・クアリーとの出会いを挙げていましたが、「Me Before You」の歌詞を聴くと、彼女との出会いがあなたの考え方に与えた影響は本当に大きいのだなと感じます。
アントノフ:もちろん。彼女と出会ったという経験がきっかけで、まさに今話した、自分の心の中にまだ知らない100の建物があるんだってことに気付かされたんだ。自分の人生をわかったつもりでいたけど、そうじゃなくて、予想だにしなかったことが起こるんだ、と気付かされる経験というのが良くも悪くもあるよね。恋に落ちるといった素晴らしいことで、新しい世界が開けたんだったら幸せだ。でも逆に、悲劇的なことがきっかけで視野が広がることだって、悲しいけどある。
―あなたはまさにその両方を経験してきました。
アントノフ:僕たち人間というのは、変化が怖いから、知っている世界の中にとどまってしまう傾向がある。それでも、好むと好まざると、変化は起きる。だから、アーティストは一つのやり方に囚われることなく、変化を受け入れるのが大事だと思っているよ。例えば、アーティストは世界中を巡ってライヴをするなんて尋常じゃないことをやるわけだけど、それでも慣れれば、それが当たり前になって行く。飛行機移動やホテルに泊まることも、慣れればどうってことないんだよ。それなのに、僕たちは未知のものを恐れてしまうんだよね。
「人間らしさ」と「ブリーチャーズらしさ」
―曲作りの変化という点で言うと、「Self Respect」や「Jesus Is Dead」のような、世の中の事象に言及した社会観察的な歌詞が新鮮に感じました。また、「Modern Girl」にはそれをひっくり返したような、つまり社会から観察された自分=ジャック・アントノフのパブリックイメージに皮肉っぽく言及したようなフレーズも挿入されていますね。
アントノフ:僕は社会的発言に命をかけているタイプの人間ではないけど、これまで僕が大事だと思う話をしたり、自分の夢や希望を書いたりしていた手段(SNSのこと)は、自分がカルチャーの動向、ひいては人々が僕についてどんなことを言っているのかを目にする手段と同じであることに気づかされたんだ。自分が何て言われているか、気にしているわけじゃない。何を言われようと別に構わないんだけど、僕が感じたのは、いつの間にかその二つが混在してしまったな、ということ。携帯に歌詞を書き留めていたり、何かのミックスを確認のため聴いていた流れで、たまたまTwitterを開いてみたら、くだらないものを目にしちゃうってことがよくあるなって(笑)。
―わかります(笑)。
アントノフ:個人の社会的発言、カルチャー、人とのコミュニケーションの取り方、それら全てが、携帯のおかげで僕たちの日常生活の中で密接に絡まってるんだという気付き――それについての歌を書くつもりはなかったけど、僕自身の経験をありのまま書こうとは思った。つまり、自分の中で境界線が曖昧になってきているっていうこと。沸々と湧く激しい感情だったり、私的な思いだったりがある一方で、9秒後にはネット上でどうでもいいくだらない何かを目にしてしまうっていう。その全部が同じ場所で起きているんだ。だから、僕の中でいかに早く脳が切り替えを強いられているかを聴き手に伝えたかったんだ。それが一番色濃く出ているのが、君が取り上げた「Jesus is Dead」と「Self Respect」だね。歌詞の1行の中で、僕にとって一番私的な思いとポップカルチャーで今起きていることを綴っている。僕の頭の中では、それくらいのペースで情報や感情の処理が行なわれているっていうことだよ。
―「Jesus is Dead」ではいろんなことが歌われていますが、ゼロ年代初頭に盛り上がったニューヨークのインディシーンがすっかり変わってしまったことを嘆いているくだりが印象的でした。
アントノフ:インディは今も変わらず人気があると僕は思っているけど、今の新しいNYシーンは、これまでと違って、音楽よりもヴィジュアル重視になってしまった。そのことに苦言を呈した感じだね。
―「Modern Girl」は、ブリーチャーズというバンドをやることの喜びやライヴのエナジーを余すところなくキャプチャーしたような最高のロックンロールソングです。いま改めて、ブリーチャーズというバンドをセレブレートするような曲を作ろうと思った理由を教えてください。
アントノフ:どこからともなく出てきた曲だったんだ。きっかけは、僕が気に入っていた断片がいくつかあったのと、僕的に、ブリーチャーズのテーマ曲があったらいいのに、と思いついたこと(笑)。だから、曲の中でバンドについてだったり、ポップカルチャーにおけるバンドの立ち位置を自虐的に茶化したりしている一方で、バンドの演奏はえげつ無いくらい勢いがあるっていう。そういう、ちょっと変わった、このバンドの今の立ち位置を象徴するテーマ曲になっているんだ。
―この「Modern Girl」を聴いても、やはりブルース・スプリングスティーンの影響は本当に大きいんだなと感じます。あなたにとってスプリングスティーンとはどのような意味を持つ存在なのでしょうか?
アントノフ:今ではもっとも親しい友人の一人だよ。自分が音楽をやる上で自信と勇気をくれる素晴らしい人で、僕の人生において大事な存在だね。
―スプリングスティーンは小さい頃から聴いていたんですか?
アントノフ:ニュージャージー出身だから彼のことはもちろん知っていたけど、彼の音楽にどっぷり浸かって聴くようになったのは20代初めの頃からだね。
―特に惹かれたポイントは?
アントノフ:挙げたらキリがないんだけど、どの作品にも共通して言えるのは、「人間であることがどういうことなのかが伝わってくる」っていうところ。つまり、全然違う感情から感情へと常に揺れ動いているっていうこと。生まれ育った街から逃げ出して人生を棒に振るっていう話をしてたと思ったら、次の瞬間、誰かにプロポーズをしていて。かと思ったら、鬱になり過ぎて家から出られない。で、次の瞬間にはパーティーにいたりする。誰もが頭の中では、いろんな感情の間を絶え間なく行き来しているよね。曲というのは1つの感情だったり、モードを表しているものだけど、ブルースの音楽の魅力というのは、生きていて経験するあらゆる体験だったり、生きている証というのをどの曲からも感じられるところなんだと思う。

Photo by Alex Lockett
―このアルバムで特徴的なのは、ほとんどの曲でサキソフォンが使われていることです。どのような意図で今回サックスを多用したのでしょうか?
アントノフ:サックスという楽器が大好きだっていうのと、最近使っている人があまりいないと感じていたから。何をやるにしても、人と違うことがしたいと僕は思っていて。誰もがその人にしかない個性をもっているんだから、音楽もそうであってほしいと僕は思っているんだ。あまり耳にしないサウンドはどんなものでも大好きだよ。だから、「Modern Girl」を最初のトラックにしようと思ったんだ。アルバムで最初に耳にするのが、激しいサックスの音色で、それは現代の音楽ではあまり耳にしない。そうやって、あまり頻繁に使われていないサウンドを取り入れるのが好きなんだ。
―本作におけるサックスの使い方で意識したことは?
アントノフ:シンセでメロディーを弾く、あるいはギターがフレーズを弾くような箇所に、あえてサックスをもってくるという発想でやっているんだ。メロディーを奏でられて、独特のサウンドを出す楽器の一つだから、その特徴のある音色に惹きつけられながらメロディーを味わってもらいたいね。それと、幅広い表現ができる楽器でもあると思っている。耳をつん裂く大きな音を出すこともできるし、優しく美しい音色を奏でることもできる。管楽器ならではの風を感じる音も出せるし、歪んだギターのような音色を出すこともできるんだよ。
―では、どのような観点からでも構いませんが、あなたが考える本作のキートラックは何でしょうか?
アントノフ:「Were Gonna Know Each Other Forever」だね。(サウンドやリリックなど)全てにおいてそうだと言える。大人になって、この世界で自分の味方になってくれる人たちと出会うことの奇跡について歌っているんだ。僕の音楽を聴いてくれるオーディエンスについての曲だね。彼らとの絆は永遠に続くものだと思っているよ。
テイラー、The 1975、ラナとの絆
―本作にはあなたと関わりが深いアーティストが多数参加していて、ジャック・アントノフの音楽的ファミリーが集結したような印象です。最近では珍しく、トラックリストにフィーチャリングアーティストとしてゲストの名前が載っていないことにもこだわりを感じました。ストリーミングの再生回数を稼ぐためにゲストを呼んだというよりも、純粋に友人たちと一緒に楽しくアルバムを作ったということを強調する意図なのでしょうか?
アントノフ:前面に打ち出す形での参加であれば、当然フィーチャリングアーティストと表記するし、これまでもそういう形の客演をしてもらったことはあるけど、今回のアルバムに関しては、友達がバッキングコーラスや、ちょっとしたパートを弾いてもらっている程度だから、再生回数を稼ぐためだけに名前を出すようなことはしたくなかったんだ。アルバムという貴いものを作る中で、ビジネスを優先させるようなことはしたくない。聴いた人たちがライナーノーツを読んだ時に、知ってる名前を見つける喜びのほうが大事なんだよ。
―本作はDirty Hit移籍後、初のアルバムです。Dirty Hitはアジアを含む様々な地域の新しいインディポップをフックアップする現代的で面白いレーベルですが、あなたのDirty Hitに対する印象を教えてください。
アントノフ:彼らがやっていることや、出している音楽は大好きだよ。大企業化したメジャーレーベルがやらないことをやっているところが好きだね。
―Dirty Hitと契約に至ったのは、The 1975のアルバムをプロデュースしたことも大きかったと思います。あなたがThe 1975のようなギターバンドをアルバム一枚丸ごとプロデュースするのは意外と珍しいことですが、彼らとの仕事は他と何か違いはありましたか?
アントノフ:正直、みんなそれぞれ違うんだけど、アルバムを作る上で目指すもの――つまり、可能な限り最高の作品を作るという目標は、どんな場合においても変わらないよ。みんな同じだね。それを達成するための手段や使う楽器は作品によって全く異なるけど、突き詰めれば、数人の人間が集まって、頭の中で鳴っているものを具現化する、ということだから。彼らとやって一番印象的だったのは、大きな円形のスタジオに全員がいて、楽器を全部セッティングした状態で、バンド全員で演奏しながらレコーディングを行ったことだね。僕はその演奏を録音しておいて、その中から特別と思える瞬間をとっておいたんだ。凄く充実したやり方だったよ。
ジャック・アントノフのプロデュースワークをまとめたプレイリスト
―あなたは『1989』のときからテイラー・スウィフトのアルバム制作に携わってきました。彼女のクリエイションを傍でずっとサポートしているあなたから見て、彼女が常にトップに立ち続けている理由はどこにあると思いますか?
アントノフ:卓越したソングライティングだね。
―もう少し具体的に言うと?
アントノフ:いや、全てだよ。音楽も歌詞も。彼女の、自分の体験をあれほどまで深く、そして完璧な形で、不必要な要素を取り除いて曲やアルバムにする能力は、ただただ凄いんだ。
―様々なメディアの年間ベストソングで1位を取ったラナ・デル・レイの「A&W」は、昨年を代表する曲のひとつと言っていいと思います。かなり実験的な構成を持った曲でもありますが、この曲はどのように生まれたのでしょうか? また、曲が出来たときに、何か特別なものを作れたという手ごたえはありましたか?
アントノフ:間違いなくあったね。とにかく大好きな曲なんだ。自分が思い描いていた形になったと思える瞬間というのは、自分の中で「この曲がどう受け止められようと関係ない。この世に存在してくれるだけで十分だ」って思える。「A&W」の曲の構成が決まった時、かなり早くにできたんだけど、その時は純粋に「この曲ができて神に感謝しかない。自分達がその時感じた何かがこの曲を導いてくれて本当によかった。この曲が好きでたまらない」と思った。それに今は、これまでと比較にならないくらい幅広い曲が人気を集めるようになったよね。
―つまり今は「A&W」のような実験的な曲でも受け入れられる土壌があると。幅広い音楽が人気を集めているということで言うと、昨今は世界各地の様々なポップミュージックが人気を博すようになったのも大きな変化です。そのような動きにあなたがインスパイアされることはありますか?
アントノフ:もちろん。初めて聴く新しいものには常に刺激をもらっている。これだけ多種多様なものが聴ける時代に生きているのは本当にワクワクさせられるよ。ただ、インスパイアされるのは、どの地域の音楽かよりも、曲に込められたフィーリングだけどね。
―では、今あなたが特に注目しているアーティストや音楽は?
アントノフ:最近だとカントリーミュージックが気に入っている。レイニー・ウィルソンが好きなんだ。今、僕が真実だと感じるサウンドだね。
―昨年はアメリカのメインストリームにおけるラップの人気にやや陰りが出てきたとも言われています。また、オリヴィア・ロドリゴのようにロックサウンドを打ち出す新世代も増えてきました。第一線を走るプロデューサーとして、こうしたメインストリームの光景の変化は意識していますか?
アントノフ:ジャンルは常に移行し変化を繰り返していて、もはや意味を持たないんだ。大事なのは、人の心に訴えることができるかどうかであって、その装い、つまりジャンルというのは、装いに過ぎない。だから、あるジャンルだけがどうこう、ってことはないと思う。どのジャンルも常に存在して、時には新しいものが生まれたり、その時々で人気のあるものが入れ替わることもある。どんなものでも波のように押し引きがあるからね。でも僕としては、あまり気にしていない。僕にとって大事なのは、自分が何をその時々で感じているかであって、どんなジャンルかではないんだ。
―もう時間が無いので、最後の質問です。ブリーチャーズのアルバムはあなたとパトリック・バーガーでプロデュースしていますが、もし歴史上の偉大なプロデューサーが誰でも引き受けてくれるとしたら、誰にブリーチャーズのプロデュースを頼みたいですか?
アントノフ:(即答で)ジェフ・リン。
―おお。ジェフ・リンが手がけた作品で一番好きなものは?
アントノフ:一枚だけ選ぶなんて不可能だよ!
2022年のライブ映像

ブリーチャーズ
『Bleachers』
発売中
配信・購入リンク:https://lnkfi.re/240ifSNJ
SUMMER SONIC 2024
2024年8⽉17⽇(⼟)18⽇(⽇)
東京会場:ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
⼤阪会場:万博記念公園
公式サイト:https://www.summersonic.com/