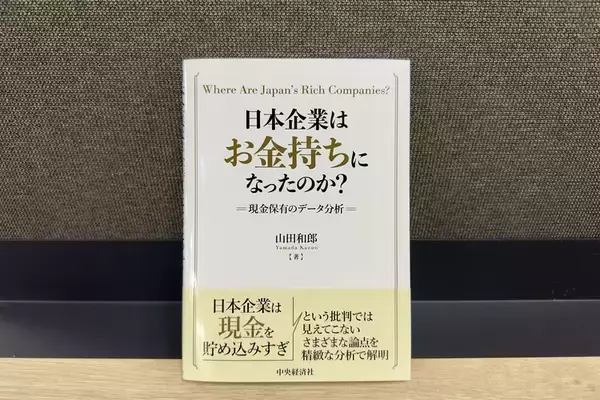
数あるビジネス書や経済小説の中から、M&A Onlineがおすすめの1冊をピックアップ。M&Aに関するものはもちろん、日々の仕事術や経済ニュースを読み解く知識として役立つ本を紹介する。
・・・・・
日本企業はお金持ちになったのか?―現金保有のデータ分析 山田和郎著、中央経済社、定価2860円
なぜ、日本企業は現金を抱え込むのか?
「正義は逆転する」NHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」の冒頭のセリフだが、企業財務も同様だ。かつて企業にとって「美徳」だったキャッシュリッチも、「内部留保を優先し、現預金を有効に活用せず、新たな投資や事業展開が停滞している」と見なされ、株主や従業員への還元に消極的だと批判されるようになっている。
日本企業はなぜ現金を貯め込むのか。バブル崩壊後から続く企業の「現金余剰」への批判は根強い。一方で、経営環境の不確実性や株主還元圧力の高まりなどを踏まえれば、単純に「ため込みすぎ」と断じるのは早計だ。本書では現金保有に関する学術研究や統計データを整理し、その実像を探っている。
企業が現金を保有する意義は、経営者、株主、債権者など立場によって異なる。株主にとっては将来の配当原資となり、銀行にとっては返済余力の裏付けになる。一方で従業員にとっては雇用の安定を保証する「安全弁」の意味合いもある。
経済学ではケインズ以来、現金保有の動機は「取引動機」「リスク対応」「資金調達リスク回避」などで説明されてきた。特にリスク動機については研究が蓄積され、金融危機やパンデミックのような不確実性が企業の現金需要を高める要因とされる。
イメージと違うキャッシュリッチ企業の実像
一方、現金の持ちすぎは「経営者が自由に使える資源を増やし、効率を下げる」といったエージェンシー問題*を招くと指摘されている。現金保有は、こうしたメリットとデメリットのせめぎ合いの上に成り立つという。
*エージェント(代理人)が依頼人の利益ではなく、自己の利益を優先する行動を取り、依頼人に不利益を与える利害対立問題。
「現金の持ちすぎ」に対する世間の印象は、「バブル崩壊を受けた保守的な大企業が、リスクを恐れて内部留保を積み上げている」だろう。確かに、法人企業統計によれば、日本企業の現金保有総額は長期的に増加している。企業規模で割った現金比率も上昇傾向にある。
ただ、1990年代以前の方が内部留保の比率は高かった。2000年以降の伸びは主に中小企業に集中しており、大企業は横ばいに近い。さらにソフトウエアや研究開発に依存する産業ほど現金比率が高く、この20年でさらに上昇している。内部留保を積み増しているのは中小企業とIT、研究開発型企業という意外な実態が浮かび上がる。
「企業間格差」が現金の抱え込みを生んだ?
統計からは、企業ごとの現金保有には大きなばらつきがあることが分かる。債務超過企業ほど現金比率が高い傾向がみられ、「規模が小さい」「利益率が高い」「赤字幅が大きい」といった特徴を持つ企業が「余分な」現金をため込む傾向がある。
これは財務面から見れば、当然の行動だろう。小規模で赤字幅が大きい企業は倒産につながる資金ショートを防ぐために現金を手元に置くだろうし、利益率が高い企業は何もしなくてもキャッシュが積み上がるからだ。
1980年代と比べると現金比率の分散は2020年代に入って大きくなっているが、これは日本企業の行動が変わったというよりも、企業間格差が拡大していることを示唆する。
「現金の積み上げは投資や株主への還元を抑制しているのではないか」との批判は根強い。しかし、調査データからは、過大投資企業も過少投資企業も共通して超過的な現金を保有している実態が浮かぶ。株主還元比率が高い企業ほど現金比率も高い傾向があり、「投資か還元か」の二者択一ではないという。
企業の現金保有は「ため込み」か「備え」か。答えは一律ではなく、産業特性や企業規模、成長期待によって大きく異なる。企業統治(コーポレートガバナンス)の強化や市場環境の変化に伴い、企業における現金のあり方は今後も考え続けなければならない問題なのだ。本書は、その一助となるだろう。
文・写真:糸永正行編集委員
【M&A Online 無料会員登録のご案内】
M&A速報、コラムを日々配信!
X(旧Twitter)で情報を受け取るにはここをクリック
【M&A Online 無料会員登録のご案内】
6000本超のM&A関連コラム読み放題!! M&Aデータベースが使い放題!!
登録無料、会員登録はここをクリック




















![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)
![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)







![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)
