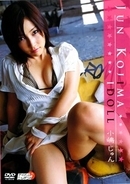恥ずかしい時、悔しい時、モヤモヤする時……思わずネガティブな気持ちになったときこそ、読書で心をやすらげてみませんか? あの人・この人に聞いてみた、落ち込んだ時のためのブックガイド・エッセイです。
気がついたら、“二(ふた)時代前の人”になっていた……。
私は昭和の真んなか辺よりも少し平成寄りの生まれだが、祖父母世代は普通に明治・大正だった。私が大人になったころは、さすがに明治生まれは珍しくなっていたものの、大正生まれはまだまだ現役だった。生年月日の元号記入欄が「M、T、S」から「T、S、H」になっても、そこを気にしたことはなかった。
ところが、先日、気がついてしまった。令和生まれにとって、自分が“二時代前の人”になってしまっていたことに。「M、T、S」の表記のころならば、「M」の部分の人になっていたことに。
え? 私? え? いつの間に? とあわあわしてしまった。落ち着いて考えたら、いつの間にじゃねえよ! という話なのだけど。
迂闊だった。“二時代前の人”になる心の準備ができていなかった。あぁ、昭和はあっという間に遠くなりにけり。
そんな昭和世代の私の心の支えというか、心張り棒が、幸田文『月の塵』と白洲正子『白洲正子自伝』である。
『月の塵』でとりわけ好きなのは「個人教授」と題された一編だ。ある家の取込事を手伝い、その手際の良さを家の主人から褒められた作者は、けれど、褒められなかった娘さんたちの母親からあてこすりを言われる。悔しくて腹がたった作者は、父親にそのことを話すのだが、この時の露伴の答えが実に、実にいいのだ。
「水の流れるように、さからわず、そしてひたひたと相手の中にひろがっていけば、カッと抵抗してたかぶるみじめさからだけは、少なくものがれることはできた筈だと教えてくれ、それを教えておかなかったのは、親の手落ちですまないことをした、といった。
これ、めちゃくちゃ深い言葉じゃないですか? そして、めちゃくちゃかっこいい。
『白洲正子自伝』は、由緒正しい超お嬢様にもかかわらず、「韋駄天お正」という伝法な二つ名を持つに至った作者の、その真っ直ぐで正直な生き様に、胸が空(す)く。
幸田文と白洲正子。こんな素敵な女性がいたことを、平成生まれにも令和生まれにも、覚えていて欲しい。