
維新が大阪府を中心に進めてきた「私立高校の無償化」は2024年度からは東京都でも実施されるなど全国的に広がりを見せている。一見すると経済格差を是正するための優しい政策だが、そうではない。
『崩壊する日本の公教育』の著者でもある鈴木大裕氏はこれまでセーフティネットの役割を果たしてきた学校が淘汰されることに警鐘を鳴らしている。
私立高校無償化の問題点とは
――現在進行形で、日本の公教育にはさまざまな動きが起こっています。気になっているトピックがあれば、教えていただけますか?
私立高校の無償化です。一見、経済格差を是正するための良い政策に映るんですが、これを手放しで歓迎することはできません。
私学の存在意義は、公立では抱えきれない様々なニーズを持つ子どもたちの受け皿として、教育の多様性を保障することにあります。
私学には超進学校もあれば、部活を最大の売りにする学校もあり、中にはキリスト教系の学校や、学力的に厳しい子や不登校を経験した子達が多く集まる優しい学校もあります。
あくまでも一部の特別なニーズを抱える子どもたちのオルタナティブとして私立高校を無償化すれば、家庭の経済環境に関係なく、子どもたちがそれぞれの適正に合った高校を選択することが出来るようになる。これが本来の学校選択制の姿です。
しかし、この政策案の旗振り役である日本維新の会がモデルとしているのは、大阪維新の会が大阪府で進めてきた私立高校の無償化政策であり、弱肉強食の厳しい競争の中、各学校が自らの生き残りをかけて生徒を奪い合う、「市場型」学校選択制です。
財政効率化を図りたい財務省の思惑とは
――多くの学校が廃校になっていると聞きます。
危険なのは、私立高校の無償化が、公立高校の熾烈な統廃合とセットで行われてきたことです。
実際、大阪府の公立高校は過去20年余りでおよそ40校が廃校となり、2025年4月時点では21校の新たな廃校が決定しています。今後の統廃合の検討対象となっている高校も多く、さらに多くの公立高校が廃校となる見通しです。
そして、危険なのは、このような維新モデルが、少子化を理由に学校統廃合を進め、財政効率化を図りたい財務省の思惑と一致するということです。
大阪府では、大規模な公立高校の統廃合と同時に、学区の撤廃ならびに公立と私立の募集定数比率の撤廃も行われました。つまり、生徒は大阪府内であればどこの学校でも選ぶことができ、3年連続定員割れの公立高校は容赦なく廃校にされ、公立高校と私立高校の生徒数の比率が逆転する可能性もあるのです。
そんな中で私立高校を無償化すれば、学費の面で私立と公立の境界が溶け、一つのきれいな「市場」が出来上がります。
大阪大学の髙田一宏教授は、2010年に橋下府知事(当時)が発したメッセージ「「教育」への私の思い」に注目しています 。
橋下氏は、私立高校の授業料無償化措置について次のように述べています。
「この制度の導入によって、いよいよ、公私が切磋琢磨するための同一の土俵ができあがる。これからは、公立も私立も、誰が設置者かではなく、学校そのものが生徒や保護者から選択される存在でなければ生き残れない。もはや、「公私7・3枠」で生徒が入学してくるという状況は保障されない。大阪の学校勢力図は大きく塗り替わる。」
実際、制度導入後には公私の比率が6対4と変わっており、髙田教授は、近い未来に公私の入学者比率の逆転もあり得る、と指摘しています。
また、どれだけ多くの生徒を確保できるかが全てとなるわけですから、私立高校も無償化するのであれば、公立も私立も関係なく、同じ土俵の上で競争し、勝ち残らなければなりません。
そうなれば、今日の厳しい格差社会の縮図のように、「勝ち組」「負け組」の厳しい生存競争となり、私学はしだいに個性を失っていくでしょう。
セーフティーネットの役割を担う高校が消えてゆく
――どのような学校が淘汰されていくのでしょうか。
もちろん、底辺からです。先述の髙田教授は、超進学校が高倍率を維持する一方、中学校までの学習内容の学び直しに重点を置く高校や、外国籍で日本語の指導を要する子たちの受け皿となるはずの高校など、「セーフティーネットの役割を担う高校」と位置付けられた学校の存続が危ぶまれていると指摘し、子どもたちの「進路保障の危機」であると言います。
子どもたちの「選択肢」を増やすために、彼らが高校で学ぶ「権利」が犠牲になるならば、それは本末転倒と言わざるを得ません。
また、地域唯一の府立高校が廃校になるケースも多く見受けられます。もちろんそうなれば、交通費や通学時間の増加により、高校に通えない子たちが出てきます。
私が住む、土佐町(高知県)のような中山間地域に住んでいると、私立高校の無償化が実現すれば、郡部の高校はどんどん淘汰されていくという現実が見えてきます。
地域で唯一の高校がつぶれると、学齢期の子どもは都市部の学校に通うことになります。親にとってみれば、子ども2人を都市部の高校に通学させるくらいなら、引っ越したほうが安上がりになります。
そうなると、まずは子どもがいなくなる。子育て世代がいなくなる。そして移住の候補地としても人気が無くなり、やがて地域そのものが無くなるでしょう。
そうかといって、私立高校の無償化が全てダメというわけではありません。愛知県私立学校教職員組合連合のように、高校の統廃合や経営陣による授業料の値上げに反対し、公立と私立の募集定数比率をしっかりと守った上で、私学助成の拡充を独自で勝ち取ってきたケースもあります。
他の先進国並みに教育予算を拡充し、少子化を逆手に取って少人数学級制を進め、純粋な「学校選択制」を進める。私立高校無償化に関する議論が、そんな方向に向かったら良いと思います。
参考文献
髙田一宏 『新自由主義と教育改革:大阪から問う』岩波新書、2024年。
写真/shutterstock
崩壊する日本の公教育
鈴木大裕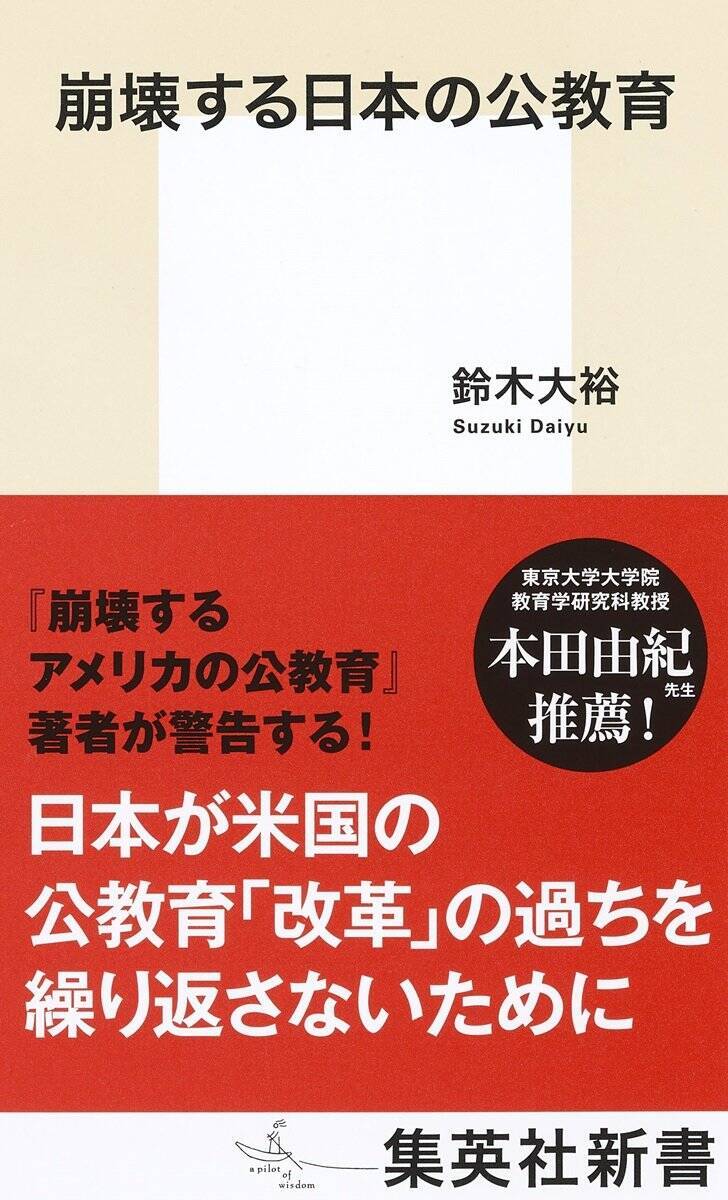
その結果、教育現場は萎縮し、教育のマニュアル化と公教育の市場化が進んだ。
学校はサービス業化、教員は「使い捨て労働者」と化し、コロナ禍で公教育の民営化も加速した。
日本の教育はこの先どうなってしまうのか? その答えは、米国の歴史にある。
『崩壊するアメリカの公教育』で新自由主義に侵された米国の教育教育「改革」の惨状を告発した著者が、米国に追随する日本の教育政策の誤りを指摘し、あるべき改革の道を提示する!

































![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


