
世界最大のスパイス生産国、インドに多くの日本企業が参入している。日本とはまったく異なる食習慣を持つインドで受け入れるられるために日本企業はどんな勝負をしているのか。
朝日新聞の特派員記者が現地で見たその実態について『『インドの野心』人口・経済・外交――急成長する「大国」の実像』より一部抜粋・再構成してお届けする。
カレーハウスCoCo壱番屋の挑戦
日本人が愛する食事でも、インド人とのズレは垣間見える。
「日本食って、味がないから苦手なんです」
あるとき、取材先でたまたま出会ったインド西部プネに住む10代の少年に、こんなことを言われてしまった。日本のアニメが好きで日本語の勉強をしているという彼だが、どうにも食事は合わないというのだ。必死に日本食のすばらしさを説明したが、どこまで理解してもらえたか心もとない。
そんな私も、インドに赴任後は、現地の人々が毎日食べる料理やお菓子、紅茶も「マサラ(混合香辛料)風味」になる食文化に驚かされてきた。クミン、クローブ、カルダモン……。首都の旧市街の一角にある「スパイスマーケット」を訪れると、食欲をそそる香りが漂ってくる。
スパイス店の4代目店主、シバン・グプタさん(18)に、「スパイスとはどんな存在?」と聞いてみると、「スパイスなしで、インド人は生きていけないよ」と笑った。各家庭の台所には、複数のスパイスを保管しておく「マサラボックス」があり、結婚式では、身を清めるために新郎・新婦が黄色のターメリックを顔や体に塗る儀式も欠かせない。
「スパイスジェット」という香ばしい名前の格安航空会社もある。
歴史をひもとけば、大航海時代にインドに到達したバスコ・ダ・ガマは、コショウなどのスパイスを求めて海へこぎ出したと言われる。政府の商工省内にあるスパイス委員会は「インドは世界最大のスパイス生産国だ」とうたう。
そんな「スパイス大国」に、スパイス料理の代表格、カレーで挑む日本企業がある。
国内外で1400店舗以上を展開し、「世界最大のカレーチェーン店」としてギネス世界記録に認定されたカレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ)だ。運営する壱番屋(本社・愛知県一宮市)の浜島俊哉前会長は「カレーの本場インドで挑戦しないまま、世界一と胸を張れるのか?」と社員に檄を飛ばした。
2019年、三井物産との合弁で進出を果たすと、翌年8月に首都近郊の新興ビジネス街グルガオンにインド1号店を開店した。当時は、世界中を襲ったコロナ禍のまっただ中。それでも、日本で人気のチキンカツや野菜カレーといった定番を持ち込み、さらに、インド製カッテージチーズの「パニール」や、ギョーザに似た「モモ」入りカレーなど、現地の人に愛される独自メニューを次々に開発した。
カギを握るベジタリアンメニュー
進出から5年たった24年秋時点で、北部にあるグルガオンと首都ニューデリーに店舗を展開。当初、6対4で日本人が多かった客層は今や8割以上がインド人に。カレーうどんやラーメンなどの麺類も健闘している。スパイスを利かせたナポリタンを食べていた会社員のビドゥ・ヤンシュさん(24)は、「同僚に評判を聞いて初めて来た。ピリ辛でおいしいね」と笑った。
カレーのルーは、海外用に開発した動物由来の原料を使わないものを日本から輸入する。インドでは、肉や魚を食べないベジタリアンが5億人以上に上るとの推計があり、ベジタリアンメニューの注文が全体の約4割を占めている。
意外なインド人の好みも見えてきた。エリアマネジャーのマーシュ・マックスウェルさん(39)らによると、お客さんが選ぶカレーの辛さのレベルは、オリジナル味か「1辛」が多く、辛くしても「3辛」までがほとんどだという。
23年7月にインドに赴任した同社の長谷川克彦さんは、「インド北部にはバターチキンなど、そこまで辛くないカレーも多い。スパイスの強い食事を好む南部に行けば、もう少し辛い味が選ばれると思う」と語った。
日本の8.7倍もの面積があるインドは、地域によって食文化や言語が異なる。飲酒が禁止されている州もあれば、日本酒やウイスキーを愛飲する人もいる。一言でくくりにくい多様性が、インドでビジネスをする難しさであり、商機にもなりうる。
牛肉を提供できない米国のファストフードチェーンなども、現地の住民が好きな風味を採り入れながら10年、20年とかけて定着していったと言われる。
長谷川さんは「そこまで年月はかけられない」としたうえで続けた。「日本食のチェーン店がなかなか進出できていないこの国で、何とかして結果を出したい」
さらに詳しく現地の状況を知るため、インドの食事情や日本企業の進出状況に詳しいジャーナリストのビル・サンビ氏(68)にも会いに行った。
日本の飲食企業はインドで成功するのか? 彼にそんな質問をすると、「純粋な日本食だと、インドでの(ビジネス)チャンスは限られるだろう。日本食は食材そのものの食感や、繊細な風味まで大事にする。
確かに、街の飲食店で食事をすると、肉がパサパサしていたり、野菜が傷んでいたりすることはある。ただ、最近は都市部の若者を中心に、すしや天ぷら、ウイスキーを好む人も増えるなど、好みの変化も少しずつ起きていると言う。
「米国でカリフォルニアロールといった巻きずしが受け入れられたように、インド流に適応させた味や提供方法を考えていく必要がある」
スパイス大国に挑む日本企業
実際に、インド人の味覚に合わせた商品を開発し、売り込んでいる日本企業も出ている。日清食品ホールディングスの現地子会社が発売するカップヌードルの多くは、「マサラ」「スパイシー」「ホット」と、辛さを売りにする。インドに多いベジタリアン向けの商品も豊富にそろえる。
スープは現地の食文化に合わせて日本より少量。私が日本でよく食べていたシーフードヌードルは、インドでは「リッチシーフードカレー味」に。何度か試してみたが、一口食べると刺激が広がり、水が欲しくなる。
インドでは、スープ入りの麺を食べる習慣は一般的ではない。それでも、世界ラーメン協会の推計によると、インドの即席麺の総需要は年々増えており、2023年は86億8000万食に。麺を食べる文化が定着しているベトナムや日本などを上回り、中国・香港、インドネシアに次ぐ世界3位につけた。
色が濃いしょうゆ「ダークソイソース」が使われていた「インド中華」というジャンルに目を付けたのが、キッコーマンだ。20年9月に子会社を設立し、翌年から本格的に営業を開始した。都市部を中心に店舗が増えていたインド中華料理店などで商品をアピールしている。
ただ、インド事業を担当する田島圭さん(44)は、「現地のシェフたちに『日本のしょうゆってすしに使うものでしょう?』と、何度も言われた」という。誤解を解こうと、唐辛子やガーリックを漬け込んだピリ辛しょうゆを持参し、味見をしてもらった。
インド中華の歴史をたどると、中華系の人々が数百年前にインド東部コルカタに移住して中華街を設け、そこからインド風にアレンジされて広まっていったようだ。ピリ辛の中華風焼きそばは想像できるが、スパイスと絡めたカリフラワーを揚げた「ゴビ・マンチュリアン」など、独自の発展を遂げたインドならではのメニューも少なくない。
大豆や小麦、塩といった原料しか使わないしょうゆは、ベジタリアンでも問題はない。販路を広げるため、ベジタリアン向けのオイスターソースやインド中華で好まれるダークソイソースも展開する。
販売実績を着実に積み上げながら、数十年先の将来も見据える。国連の推計では、インドの人口は60年代前半まで増え、17億人近くに達すると予測されている。さらに、世界各国に移住するインド系住民も3500万人以上に上る。
田島さんはこう指摘する。「人口が増えることは、胃袋も増えるということ。世界中に出て行くインドの人たちがキッコーマンを知っていることが、次の市場開拓につながる可能性もある」
文/石原孝 伊藤弘毅
『インドの野心』人口・経済・外交――急成長する「大国」の実像(朝日新聞出版)
石原孝 伊藤弘毅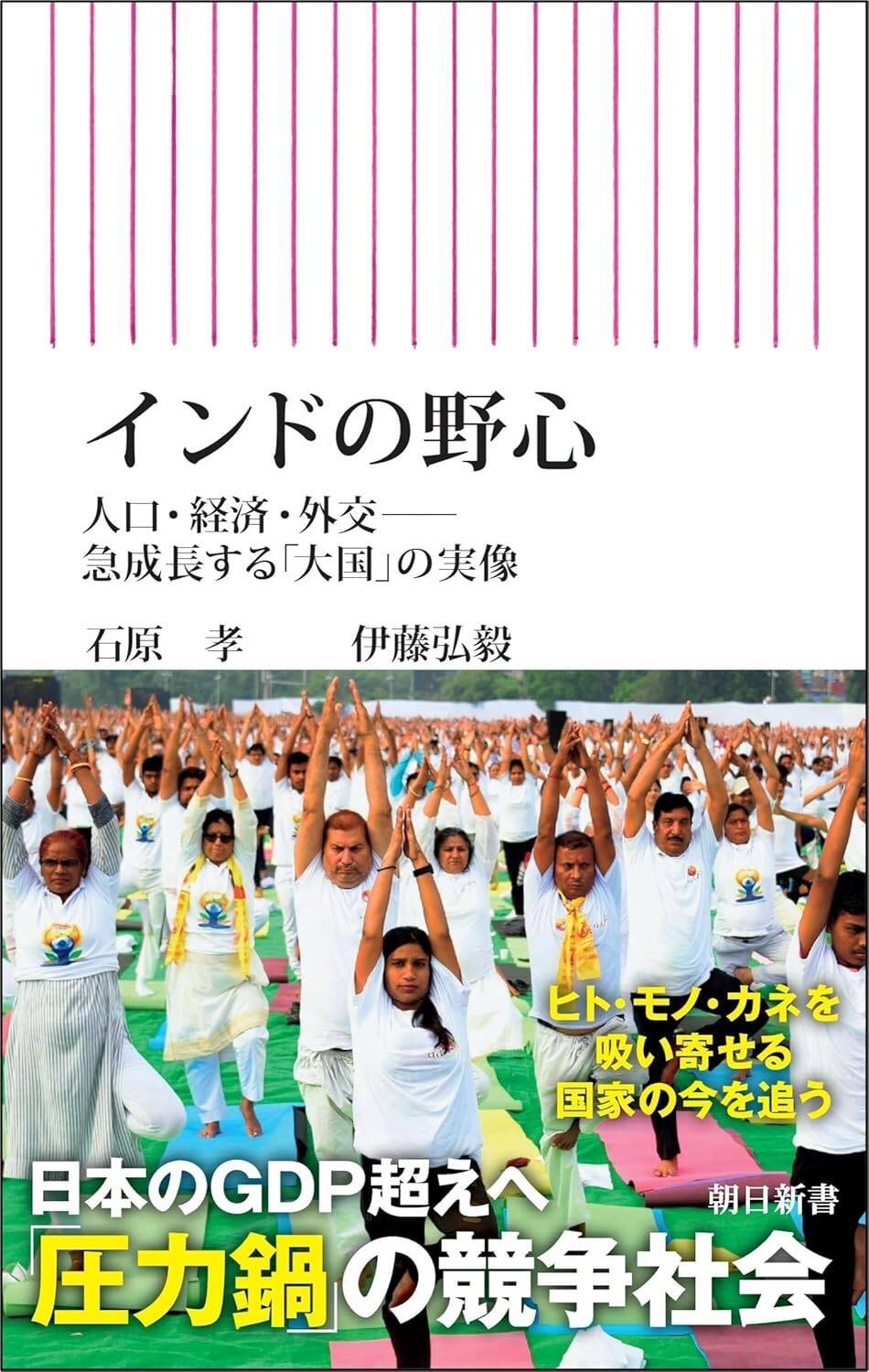
マイクロソフトやグーグルなど、世界の名だたる企業のトップに名を連ね、
20年代後半にはGDPで、米中に次ぐ世界3位になると予測される。
上昇志向と加熱する受験、米政財界への浸透、「モテ期」の到来と中国・パキスタンとの衝突……
教育・外交・経済・文化的側面から、注目を集める国の『今』に迫る。


























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


