
年功序列型の長期雇用制「メンバーシップ型」の雇用が主流であった日本だが、現在、あらかじめ仕事内容を明確に決める「ジョブ型」の雇用導入が広がっている。しかし、そこには思わぬ死角があるという……。
『世界経済の死角』(幻冬舎新書)より一部抜粋・再構成して、トップエコノミストふたりの明晰な分析をお届けする。
「ジョブ型雇用」で賃金が上がるわけではない
唐鎌大輔(以下、唐鎌) 近年、日本企業の中には、長年続いてきたピラミッド型の長期雇用制度、いわゆる「メンバーシップ型」の働き方を見直し、あらかじめ仕事内容を明確に決める「ジョブ型」を導入しようとする動きが散見され始めています。これはこれで功罪あるとは思いますが、変化があること自体、私は肯定的に見ています。
しかし、その議論の中で、メンバーシップ型が「悪」で、ジョブ型が「善」であるかのように単純化されている印象もあって、これには危うさを覚えています。このジョブ型の導入について、河野さんはどうお考えですか。
河野龍太郎(以下、河野) まず、念のために説明しておくと、日本の大企業を中心とする年功序列型の長期雇用制を「メンバーシップ型」と呼びます。一方で、日本の多くの中小企業や非正社員、あるいは諸外国で企業規模や雇用形態を問わず、広く採用されている雇用制が「ジョブ型」です。海外の雇用制は、ジョブ型と言って差し支えないと思います。
私自身は、日本の長期雇用制にガタがきているのは認めますが、メンバーシップ型がすべて悪いとは考えていません。イノベーションを起こすには人的資本が非常に大事であり、長期間、同じ会社で働いて、現場や顧客についてよくわかっている人たちを重用しているからこそ、イノベーションが可能になる部分があります。
ただ、メンバーシップ型雇用に問題がないわけではありません。というのも、メンバーシップ型の長期雇用制においては、優秀な人材の幹部への選抜があまりにも遅すぎるからです。
たとえば1990年頃の大企業では、入社後、課長になるのに15年、部長には20年かかると言われていました。
1990年代後半以降、テクノロジーの進歩が加速し、技術の陳腐化も早まっているため、本来なら幹部への選抜のタイミングは早めるべきでした。しかし、現実には真逆のことが起きていたわけです。
人材の選抜をより早い段階で行うことは、企業にとっても働く個人にとっても、よいことではないかと思います。ただ、日本企業が導入している早期選抜は、メンバーシップ型を前提にしているので、海外のジョブ型とはまったく異なる仕組みです。それでも最近では、こうした早期選抜のことを「日本版ジョブ型」と呼んでいるようですね。
唐鎌 私も、旧来のメンバーシップ型の雇用がすべて悪いとは思いません。会社の繁閑に応じて、新規に人を採用するのではなく、既存人員の残業や配置転換で乗り切るというのは、日本企業の強みでもあったと思います。
しかし、そのような働き方が現役世代に負担を強いるのは間違いなく、労働者の稀少価値が上がっている今の時代にはそぐわなくなっていると感じます。
最近の議論で特に違和感を覚えるのは「ジョブ型を導入すれば、賃金停滞も解決できる」という風潮です。「働き方」を変えれば、「賃金水準」が一気に変わるかのような議論は危険と言わざるを得ないと思います。
ジョブ型かメンバーシップ型かという議論は、あくまで「働き方」の問題であって、「賃金水準」を引き上げる妙手ではないと思います。この2つを混同したまま議論するのは、適切ではないはずです。
その上で、「メンバーシップ型の仕組みに馴染めなかった人たちのためにジョブ型を導入し、それぞれの能力を十分に発揮できる環境を整える」という考え方には合理性があると思います。
事実、私は日本企業で長く働いていますが、メンバーシップ型の仕組みの中にいるわけではなく、典型的なジョブ型の仕組みの中に身を置いています。組織内で双方が適切に運用されればよいのであって、どちらがベターという話ではないと考えています。
メンバーシップ型雇用の「負」の側面
河野 かつての「成果主義」と同様で、ジョブ型と称した新しい制度の導入によって、賃金が上がるどころか、むしろ多くの人の賃金水準を押し下げる心配もありますよね。
唐鎌 おっしゃる通りです。ジョブ型というのは、働き手の視点から言えば、自分の仕事に値札を付けて、労働市場に飛び込むということです。
たとえば、新卒で日本の大企業に入って働き続けている40代の人に、「あなたの仕事に値札を付けて、転職活動をしてみてください」と言って会社の外に出てもらった場合、多くの人は転職先を見つけられたとしても、残念ながら転職前よりも年収が下がるケースが多いのではないかと思います。
日本企業の働き方が、定期的な配置転換(異動)を前提とするジョブローテーションを基本としている以上、一定の専門性を蓄積し、それが評価されるような人材は構造的に出現しにくいはずです。
あくまでメンバーシップ型の仕組みは「会社の中で幅広い知識を持つゼネラリストを育て上げる」という目的があると思いますし、そこにも大きな意味があると思います。
極端な話、私のような人間ばかりで大企業が回るはずがありません。ゼネラリストは企業「内」労働市場では大いに価値のある人材に違いないですし、必要不可欠な存在だと考えます。
しかし、ゼネラリストというのは、意地悪な言い方をすれば、特定分野に関しては素人にとどまります。よって、企業「外」労働市場で明確な値札が付くような人材にはなりにくいと思います。
それが悪いという話ではなく、メンバーシップ型が向いている人もいれば、ジョブ型が向いている人もいるという話だと思います。私は後者だったというだけで、前者だったという人も私はたくさん知っています。
重要なことは、これまでメンバーシップ型でやってきた人をいきなりジョブ型に移行させても、今まで以上の高値が付く、つまり賃金が上昇するということは論理的に起こり得ないということです。
河野 たしかに、ある特定の企業に長く勤めているからこそ、その人の能力が発揮され、年収1200万円という報酬を与えられているのであって、急にその組織を飛び出して、業種や規模が異なる会社に行って「私、部長ができます」と手を挙げても、同じ金額の賃金を期待することは難しいでしょうね。
唐鎌 こうした現実を無視して、ジョブ型雇用へのシフトが賃金上昇のための処方箋であるかのように語るのは、筋違いだと思います。
頻繁な配置転換や退職金、年金支給額など、各種インセンティブ設計を工夫することで、従業員を長く組織内にとどまらせる現象を「エントラップメント(囲い込み)効果」と呼ぶそうです。
実際、定期的に担当職務が変われば、専門性の蓄積は難しくなり、労働市場でのアピールも困難になるでしょう。企業「内」労働市場での価値は保全されても、企業「外」労働市場での価値は失われる。だから転職が難しくなる。
しかも、長く在籍したほうが退職金も年金もたくさんもらえるとなれば、余計に転職への意欲は薄れるでしょう。
たとえば、とある有名企業にお勤めの方から聞いた話では「35歳以上にならないと海外留学できない」という制度があるそうです。これは帰国後に40歳近くになっていれば、転職できないだろうという算段だそうです。エントラップメントを企図した仕組みと感じます。
もちろん、「安定した雇用を求めるなら、ある程度の不自由さは受け入れるべき」という考え方も理解できます。しかし、そのバランスをどこで取るかが重要だと思います。
ちなみに余談ですが、昨今「若年世代が手を挙げれば、必ず留学はできるようにしている」という会社も珍しくないようです。それほど若手は稀少な人材になっているという証左ですが、超氷河期世代の私からすると、隔世の感を覚えます。
日本の組織風土とジョブ型は“食べ合わせ”が悪い
河野 日本社会は「ジョブ型」導入の効果に期待しすぎじゃないか、という唐鎌さんの指摘は重要です。ここで私が言っているのは、あくまでもカッコ付きの日本型ジョブ型のことですが、世界的に見れば、ジョブ型は決して最先端の働き方というわけではありません。
唐鎌 むしろ海外では、ジョブ型など特別な働き方ではなく、ごくありふれた働き方の一つだと思いますね。
河野 ジョブ型は、18世紀後半に産業革命が起こった頃から、欧米で広がっていきました。
欧米ではジョブ型雇用が引き起こす様々な問題がすでに明るみに出ていて、その解決策をずっと模索し続けているようにも見えます。
また、ヨーロッパのライン川流域にあるオランダ、ドイツ、フランスといった国では、ホワイトカラーは、もともと日本の長期雇用制に近いような雇用形態がとられてきました。こうした特徴などから、これらの国々の制度は「ライン型資本主義」といった名前で呼ばれたりします。
外資系金融機関に四半世紀にわたり身を置いてきた私の印象からすると、今の日本の組織風土とアメリカのジョブ型は、非常に相性が悪いように思えます。仮に、アメリカのジョブ型をそのまま日本の会社に導入したら、一発屋とゴマスリ屋のような人たちが跋扈する事態になってしまいます(笑)。
唐鎌 一発屋とゴマスリ屋ですか(笑)。
河野 言葉は悪いですが、これは真面目な話です。そもそも人の能力というものは周囲の環境がたぶんに影響するので、今うまくいっているのが本当にその人の力量のおかげなのか、疑問に思うこともあります。
実際には、一緒に働いている人との相性が大きく影響しているのではないでしょうか。仕事は運・不運も大きく影響するので、その人が優秀かどうか、直属の上司であっても、短い時間で見極めることはまず不可能です。
長期雇用制の利点は、何人かの上司の目で一人ひとりをチェックして、誰が本当に優秀で、幹部に登用すべきか、かなり長い時間をかけて見定められるところにあります。
一発屋のような人を突然、幹部に加えたら、下手すれば経営が不安定化しかねませんよね。
長期雇用制にガタがきているのは事実だと言いましたが、それなりのメリットもあるわけです。先ほど触れたように選抜の遅さなど改善したほうがよい部分もあるので、その改善に貢献する形で日本版のジョブ型を導入することができるのなら、まるきり無意味でもないとは思います。
唐鎌 ちなみに今、日本企業でジョブ型と呼ばれている制度の多くは、実際には旧来のメンバーシップ型とさほど変わらないように見受けられます。
本来のジョブ型は、「ポストに適した人材を配置する仕組み」だと思います。「ポスト」が大前提として存在していて、そこに「人材」をはめ込む、という手順です。
しかし、多くの日本企業では、「人材」が大前提として存在していて、それに「ポスト」を与える、という手順になっているように見えます。
本来のジョブ型では「ポスト」がなくなれば、はめ込まれていた「人材」も不要、つまり解雇になります。しかし、おそらく今、日本企業の多くで取り入れられているジョブ型では「ポスト」がなくなった場合、「人材」は解雇されずに別の部署へ異動させられて「こちらが新しいポストです」と、違うジョブが与えられると思います。
結果として、日本のジョブ型は、従来のメンバーシップ型の枠組みをほぼ維持したまま、表面的に名称を変えたものにすぎないという印象を抱きます。その善し悪しはさておき、本来のジョブ型とは似て非なる代物だという理解は持ちたいところです。
河野 私も日本で「ジョブ型」といっているものは、基本的にメンバーシップ型の“変種”だと思っています。
文/河野龍太郎、唐鎌大輔 サムネイル/Shutterstock
『世界経済の死角』 (幻冬舎新書)
河野龍太郎 (著), 唐鎌大輔 (著)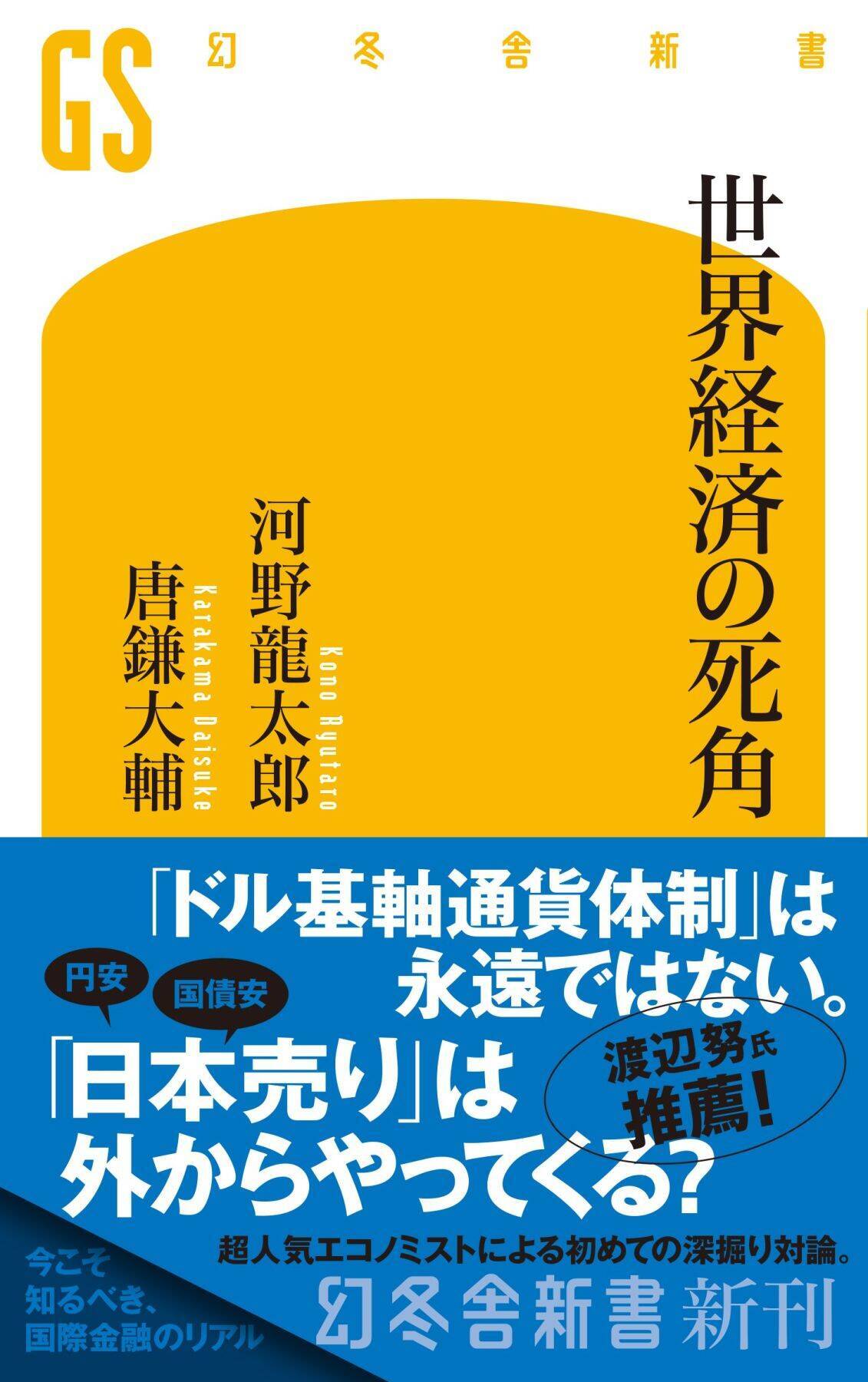
渡辺努氏推薦!(経済学者、『世界インフレの謎』の著者)
多くの人が抱く疑問に2人のトップエコノミストが果敢に挑戦。
日本経済と世界経済の先を見通す”直観力”を養うのに絶好の書。
超人気エコノミストによる初めての深堀り対論。
今こそ知るべき、国際金融のリアル。
〈内容紹介〉新NISAの導入をきっかけに海外の金融資産を保有する日本人が増加するなど、日本経済はかつてないほど世界経済への依存度を高めつつある。
そうした中、トランプ大統領による相互関税措置を受け、国際金融市場は大きく揺れ動いている。
しかし、そもそも世界経済には、日本人が見落としがちな「死角」がいくつも存在する。それらを押さえずして先の見通しを立てることはできない。
そこで本書では超人気エコノミストの2人が世界経済と金融の“盲点”について、あらゆる角度から徹底的に対論する。
先の見えない時代を生き抜くための最強の経済・金融論。





















![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


