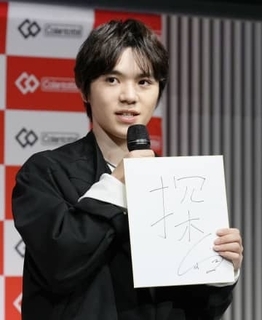『アイネクライネナハトムジーク』伊坂幸太郎(幻冬舎)
伊坂の本屋大賞ノミネートはこれが7回目。第1回目から第6回までは連続で候補に上がっており、第5回に『ゴールデンスランバー』でついに受賞を果たした。伊坂は同作と次年度の候補作『モダンタイムス』を並行して執筆していた頃までを〈第1期〉、『ゴールデンスランバー』を上梓した2007年以降を自身の〈第2期〉だとしており、より前衛的な技巧を用いた作品を書くようになった。結果だけ見れば本屋大賞はその〈第2期〉を支持しなかったことになるが、今回6年ぶりに候補作として選出された(しかも2作同時)。
『アイネクライネナハトムジーク』は短篇よりも長篇を得意とし、かつ恋愛小説に関心がないと公言する伊坂が初めて発表した連作短編形式の恋愛小説だ。冒頭の「アイネクライネ」は男女の出会いの場面だけを切り取ってきた作品で、偶然の要素の使い方が見事だ。
収録作のうち「ライトヘビー」はミュージシャン・斉藤和義のCDの初回特典として収録されていたという変り種で、今回初めて単行本で読めることになった。電話だけでつながっている男女を描いた話で、これがいちばん恋愛小説らしいプロットである。
『怒り』吉田修一(中央公論新社)
吉田作品が候補に上がるのはこれが3回目だ。吉田修一は犯罪小説の優れた書き手でもあり、事件という非日常の出来事が日常生活に空けた穴を効果的に作中で用いる技巧に長けている。
作者は3つの物語を同時に書き進めていく。最初の舞台は房総の漁港だ。家出した娘を連れ戻した槙洋平は、その愛子が、田代哲也というアルバイトと親しくなったことを知る。次の舞台は、東京の新宿のどこかにあるハッテン場だ。
ミステリー読みであれば、この3つの話のどこかに山神一也が潜んでいるのだろう、とまず予想するはずだ。それぞれの話に候補者がいて、同程度に疑わしい。この並立関係が強烈なサスペンスを産むのだ。これがミステリーとしての美点だ。
『億男』川村元気(マガジンハウス)
一昨年の『世界から猫が消えたなら』に続き、候補作になるのは2回目の作者だ。『世界から猫が消えたなら』が発表されるまで私はこの作家を知らなかったのだが、有名な映画プロデューサーであるという。他に絵本やインタビュー集などの著書がある。
『億男』は小細工なく、単純なプロットで勝負した作品だ。主人公の一男は、失踪した弟の肩代わりをして3千万円の借金を背負ってしまった。仕方なく彼は、昼は図書館司書として、また夜はパン工場のラインに立って働き、その金を返そうとする(借金があるなら、もう少し割りのいい仕事をしたほうがいいような気がするのだが)。そのため妻との関係は冷え込み、別居するようになって1年半が経った。その彼の身に一大転機が訪れる。宝くじで1千万円が当たったのだ。持ちつけない大金を手にして困惑した一男は、大学時代の友人・九十九を訪ねる。九十九は一男の入った落語研究会で抜群の巧さを誇った男だったが、今はSNS系のベンチャービジネスを起こし、今は巨万の富を手にしているのである。彼は一男に「金の正体」を教えるため、破天荒な行動に出る。
一男が九十九との出会いである事件に巻き込まれ、そのために旧友とつながりのある人々を訪ね歩いていくというのが基本だ。小説の中でインタビューの部分の比重は非常に大きく、それらの人々の声を小説の形で読者に聞かせることが目的の作品と見たほうがいい。物語の構造が単純なのも当然で、「金」にまつわるあれこれを主人公に聞かせ、読者にメッセージを送ることを目的としているのである。小説としての膨らみに乏しく、構想のノートをそのまま渡されたようで味気なさを私は感じたが、好む人もいるだろう。
少し気になったのは、小説内部のリアリティーが確立されていないように見える点で、日々の仕事に追われている(しかも借金のためかなり余裕がない)はずの一男が自由に人を訪ね歩いているように見える点は変なのではないか、1億円握った男がなぜすぐに借金を返さないのか、などと疑問に感じることが多すぎた。
『キャプテンサンダーボルト』阿部和重・伊坂幸太郎
それまでは一面識もなかったという2人が初対面で意気投合し、あっというまに合作小説の企画が走り出した、という経緯はあちこちで語られているので有名だろう。純文学とエンターテインメントの垣根を越えた合体というのもおもしろいが、執筆の過程においては一方が相手の文章に手を入れて直す場面まであったというのが興味深い。リレー形式ではなく、そこまでやったという点に意味がある。創作の場で分業が成立する場面というのを読者が目にすることは少なく、この2人の試みは新たな可能性を示すものかもしれない。
題名からマイクル・チミノ監督の映画「サンダーボルト」を思い出す読者は多いはずだが、阿部・伊坂共に念頭にあった作家は小説の執筆中に急逝したトニー・スコット監督である。「エネミー・オブ・アメリカ」「スパイ・ゲーム」などの諸作を併せて観ると、2人がこの監督から多くのものを吸収しているであろうことが判る。いわゆる「相棒もの」に属する作品で、出自や性格の異なる2人が即席のコンビを組み、迫り来る危難を協力して切り抜けていく、という作品だ。工夫があるのは、相葉と井ノ原という主人公たちに共通の過去がある点で、小学校時代には野球チームの名コンビと見なされていた2人が、思春期のある事件が元で疎遠になってしまっていた。その過去に向き合うことが、2人の未来を開拓することにつながるのである。少年時代の肯定という「男の子」魂を燃やす物語の図式が、戦隊ヒーローなどのギミックで楽しく装飾されている。2人の主人公の年代記が容易に読者の意識に入ってくるようなキャラクター設定は阿部の手柄だろう。
山形出身の阿部と仙台在住の伊坂の中間地点・蔵王が物語の秘密が隠された場所になる。そういう意味では「東北」ものでもあり、2011年3月11日の東日本大震災直後に執筆が開始されたという事情を知らなくても、現在の少しおかしな方向に行ってしまっている日本の戯画としても読める。伊坂が近作『火星に住むつもりかい?』などで展開している、世界と対立した個人が平和を求めて奮闘する物語でもある。実に読みどころの多い作品だ。
『サラバ!』西加奈子(小学館)
西加奈子も『さくら』『ふくわらい』に続いて3回目の候補となる。直木賞受賞作にもなった本作は、間違いなく2014年を代表する話題作の1つであった。これまで芥川・直木賞受賞作が本屋大賞を同時受賞した例はないが、西が初めてジンクスを破るかもしれない。
主人公の歩は1977年5月、イラン・テヘランに生まれた。このプロフィールは作者自身とまったく同じである。違うのは主人公が男性で作者が女性であるという性別だけといってもいい。日本企業の海外駐在員であった父に従い、一家はイランからエジプトへと居を移していく。『サラバ!』というタイトルは、エジプトの首都カイロにおいて歩が、現地人の友達と交わした会話から採られている。幸福な幼年期が彼の記憶の基層にはあるのだが、歩は次第にそこから離れていかざるを得なくなる。第一の理由は両親が離婚し、彼の名字が圷から母の旧姓である今橋に戻るからだ。そして父を除く一家は帰国し、歩と4歳上の姉の貴子は日本で思春期を過すことになる。
帰国子女としての明暗は姉弟ではっきりと別れ、歩は持ち前の美貌もあって周囲に溶け込めたものの、姉は失敗し、周囲の人間に対して心を閉ざすようになる。時として奇矯な言動に出る貴子は、歩むにとって重荷になってしまうのである。家族が機能不全に陥っている、というコンプレックスを意図的に無視することにより、歩は小市民的な幸せを得ることに成功する。しかし、完璧に見えた幸せは見かけどおりのものではなかった。
性別を逆転させた分身を用い、自身の個人史をすべて投入することによって、西は圷−今橋家という一族の年代記を豊かに書き上げた。作中でも言及があるが、変人揃いのベリー家の年代記『ホテル・ニューハンプシャー』(ジョン・アーヴィング著)が先行作品としてかなり意識されているので、ぜひ併読していただきたい(圷貴子のモデルは傷つきやすい魂の持ち主・フランク・ベリーだろう)。昭和末期から平成への時代の移り変わりを描いた、優れた風俗小説としても記憶されるべき作品だ。
(杉江松恋)
第12回本屋大賞候補作全作レビュー2へ