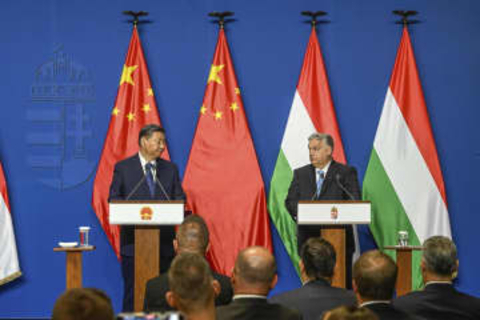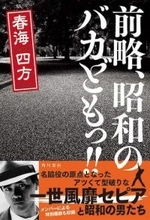オレは左手がどっちかわからない
──まずは、御著書の『サはサイエンスのサ』が星雲賞ノンフィクション部門を受賞されまして、おめでとうございます。
鹿野 ありがとうございます。
──いきなりシロウト丸出しでお聞きしますけど、星雲賞ってなんなんですか?
鹿野 ああ……正確なところはググってもらったほうがいいんでないのと思いますけど、SF大会を運営している「日本SFファングループ連合会議」っていう組織があって、そこが毎年、前年度に発表されたSF作品の中から選ぶ賞ですね。
──ということは、星雲賞は偉い人によって与えられるのではなく、SFファンの手で選ばれる、というのがポイントなんですね。
鹿野 もしなんか賞がもらえるなら、それがいちばんうれしいとは思ってたかなあ。ぼんやりと。ただ、そもそもオレなんて、賞なるものをもらえたりする発想自体がなかったんで、ホント、望外のよろこびというか、ちょううれしいの。
──下世話なことをお聞きしますが、賞金は……?
鹿野 ありません(笑)。賞状と、なんかシャレの効いた副賞があると思うけど。SF大会の開催地にちなんだ何かかな。
──地味ですね。あ、でも『サはサイエンスのサ』が増刷されるでしょ?
鹿野 されません(笑)。でも、次の本を出すことはいちおうゆるしてもらえました(笑)。
──おっ、『サはサイエンスのサ』の第2弾ですか。
鹿野 元々あれは「SFマガジン」にずっと連載していて、その一部をまとめたり、書き下ろしを追加したりして本にしたんだけど、まあ、同じようなスタイルの本になるでしょう。
──それは楽しみです。
鹿野 ……なりゆきじゃないですかね。
──えーと、子供の頃から虫とか生物が好きで、理科が好きで、そこから科学少年になって……みたいなストーリーを勝手に想像してきたんですけど。
鹿野 いや、理科はもちろん好きでしたよ。ただ、あんまり子供の頃のことは覚えてないんだなあ。
──ご出身は名古屋でしたね。
鹿野 そう。一浪して、19歳のときに日大の文理学部に補欠で受かってこっちに来たのね。元々勉強が好きじゃないので、というか好きなことしかやらないので。大学は理系の学部以外行くつもりはなかったんだけど、理系しかない大学はヤだったのね。理学部と文学部と全部あるところがいいなあと思ってて、オレみたいに勉強のできないやつが行ける理系と文系のくっついた大学っていうのは、日大文理しかなかったの。
──科学が好きになったきっかけはなんですか?
鹿野 それは……物心がつく前からじゃないですか。
──自信があるんじゃなくて、自信がない?
鹿野 うん。それはね、非常に根本的なところで自信がないかんじ。たとえば、オレは左手がどっちかわからないのね。
──はい?
鹿野 右手はすぐわかる。でも左手は右手の反対って覚えているから、とっさに左手のことを意識しようとすると、右手を意識するときより遅いんですよ。それはたぶん、物心がつくよりもっと前の時点での“記憶の仕方”と関わっていて、覚える量をできるだけ少なくしようとしてるわけ。
──なるほど、「右」と「左」を覚えるのではなく、「右の反対が左」というように相対的にとらえれば「右」だけを覚えておけば済む、と。
鹿野 うん。丸暗記するのはホントに嫌だから、そういう関連で覚えようとしてるわけ。トランプの神経衰弱とか嫌いだったし、人生最初で最大の危機だと思ったのは「九九」を覚えることだったからね(笑)。こんなにたくさん暗記できねえ! って。
──わたしも九九は苦手でした。
鹿野 あれ1の段は覚えなくていいし、斜め半分だけ憶えればいいなって、まず、なるべく憶える量を減らそうと思ったなあ。で、少しでも何かの関連で覚えようとしていると、たぶん知識全体がネットワーク的に身についていくと思うんだよね。それがオレが感じる理系的なセンスのある人。逆に、そういう理系センスとはちがうタイプの、生まれつき記憶力がよくて博覧強記な人っていうのは、ものすごくいろんなことを知ってるんだけど、矛盾する知識が共存してるのね。Aのことがわかってるのに、なぜAと矛盾しているBのことも受け入れてるの? って、文系的なセンスの持ち主にはそういう人が多いように感じる。でも、同時にそこがおもしろくて、意外なもの同士の類似性とか新しい発見もあったりね。
──これまで「数学の得意な人」が理系で、「国語の得意な人」が文系ぐらいに思っていたんですけど、そうではない?
鹿野 そうではないとまではいわないけど。理系・文系は、大学の学部分けにすぎないからね。オレが言いたいのは、人によって知識を蓄えていくセンスのちがい、みたいなのがあるってこと。だから、いわゆる文系の人にもオレの感じる理系的センスを感じる人はいくらでもいるし、逆もある。オレ自身は、数学はそんな得意じゃないしね。
──数学ダメなんですか!
鹿野 ダメじゃねえよ!(笑) いや、ダメでした(笑)。まあ、プロの学者になるなら、ある時期、関連公式みたいなのをたくさん暗記しないといけない部分があるんだよね。そういうのダメだったから。でも、何かの現象の性質はこんな風っていうような、ざっくりした感じは式を見ればわかるし、知りたいものの性質がわかってれば、そんなに難しいことやらなくても、足し算引き算くらいでもけっこう色々確かめられるしね。
──それでも、鹿野さんは科学のことをとても深く理解している……少なくともわたしにはそのように見えます。
鹿野 π=3ってするの「ゆとりだ」とかわるく言われてたでしょ。でも、あれは正しいんだよね。だいたい合ってる。あれはホントは、完全な円じゃない丸太の断面積を求めるって話で、そんなとき3.14とか細かいこと気にしてもしょうがないのね。そのものの性質がわかっていれば、そういうざっくりしたやりかたでいいし、簡単で早く必要なことが判る。これは物理やると学部一年で習うと思うけど、オーダー・エスティメーションっていって、ある現象のだいたいの感じをつかむのが大事なんだよね。それができると、この現象は絶対これより大くならないとか、これより小さくならないとかわかって、そこから極端に外れたデータや情報があっても、ああ、これは関係ないねってわかる。細かいところは、必要があれば、そのざっくりの範囲で詰めればいいしね。オレの場合、そういう、ものごとをざっくり把握することが、まあまあ得意だからじゃないかな。
どこかちょっと頭がおかしくないとダメ
──最初に読んだSF小説ってなんですか?
鹿野 小学校2年生のときにね、担任の先生から本を2冊おすすめされて、「どっちかをあげる」って言われたことがあるの。1冊は『宇宙怪獣ゾーン』(「宇宙線ビーグル号の冒険」のジュヴナイル版)で、もう1冊は『タイムマシン』(ウェルズ)。そのときにぼくは「宇宙怪獣ゾーン」を選んだんだけど、そうしたら先生に「鹿野くんはこっちを選ぶと思ったよ」って言われたのね。先生はぼくが「ウルトラQ」とか「ウルトラマン」が好きなのを知っていたから。でも、本当はそうじゃなくて、すでに『タイムマシン』は読んじゃってたの(笑)。
──SF的に早熟な子供だったんですね。
鹿野 昔は少年少女文学全集とかに『タイムマシン』や『海底二万マイル』なんかが普通に入ってたじゃない? だから、そういうのはもうあらかた読んでいたわけ。でも、男の子はだいたいみんなそういうの好きでしょ。
──ご自分では書こうと思ったことはないですか?
鹿野 ないですね。小説を書こうって発想はなかったな。
──では、そこからサイエンスライターという職業になっていった過程をお聞きしたいんですが。
鹿野 なっていったりはしません。突然なりました。
──えー(笑)。
鹿野 大学に入ってから、いくつかSFファンの会合に顔を出したりしてたのね。なかでもぼくがいちばん好きだった集まりに「フ科会」っていうのがあって、正式には「SFファン科学勉強会」っていうんだけど、非常におもしろいところで、毎月1回、7~10数人が何かおもしろい話を持ち寄って発表する集まりなのね。当時のオレからすると、それは非常に偉大な教養人の集まりみたいな場所だったんですよ。科学にも詳しいけれど、文化的なことにも詳しいという人たちがたくさんいて、論理的な話からオカルト的な話まで、なんでも話題に出来る場所だったの。で、そうした会合に顔を出しているうちに「今度、徳間書店から新しい雑誌が出るんで、誰かライターをやりませんか?」って言われて、「じゃあやります」って何の根拠もなくライターになったのがはじまり。
──徳間書店の新雑誌というのは『SFアドベンチャー』ですか?
鹿野 そうそう。あ、でもね、その前に柴野さんが別の雑誌でやっていたSF書評の下読みとか、下原稿を書くとか、そういうお手伝いはしてた。とにかく、どうしてもライターになりたかったわけじゃなくて、たまたま自分のいた場所にライターという仕事の口があって、じゃあやりますって言っただけのことでね。
──たまたま……。
鹿野 でも、人生ってそんなもんでしょ。若い頃はとくにそう感じたけど、プロでやってたとしても自分なんかよりよっぽどすごい素人って世の中にいっぱいいるんだよね。いろんな人と話をしてても、すんごい詳しい人とか、賢い人とかいっぱいいてさ、その時点でのオレなんかまったく歯が立たないような人がいくらでもいるわけ。でも、そういう人は頭が正常なので、こんなバカなことはしない。
──バカなことっていうのは、鹿野さん的な人生の選択を、ですか?
鹿野 冷静に考えれば、フリーのライターなんかになったら明日のごはんは食べられないかもって思うでしょ。そういう先行きの不透明さを心配するような人は、最初からフリーライターなんかにならないですよ。で、大学卒業してから、物書き家業で色々調べたりするとホントおもしろくてさ。学生の頃よりはるかに勉強するのが好きになって、それをいまでは30年以上もやってるんで、そこそこの実力はついたとは思うけどね。
──その結果が今回の星雲賞に(おっ、うまく話がつながった!)。
鹿野 だからね、どこかちょっと頭がおかしくないとダメなんですよ。
──そんなミもフタもないことを。
鹿野 でも、フリーでやっていくっていうのは、そういうことだと思うよ。
(とみさわ昭仁)
part2はコチラ