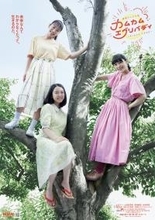鈴鹿のモデルが沢口だと考える根拠にはもう一つ、劇中劇のなかで鈴鹿が月探査の宇宙飛行士の役を演じていたことがあげられる。鈴鹿のモデルが沢口だとするなら、これって、彼女が主演した「竹取物語」(市川崑監督)へのオマージュとはいえまいか。いや、まあ、深読みということは重々承知しておりますが……。
おりしも、同じく『竹取物語』を原作とした高畑勲監督のアニメ映画「かぐや姫の物語」が公開されている。そのパンフレットに高畑が寄せた文章によれば、これだけ日本人にはなじみの深い古典作品でありながら、これを忠実に映画化した作品はいままでほとんどなかったらしい。沢口主演の「竹取物語」は、そのなかにあって唯一の例外であった。とすれば、いまこそ同作は顧みられるべきではないだろうか。
この映画が公開された1987年といえば、バブルの真っ只中だ。景気のいい時代だけあって20億円もの製作費を投入し、鳴り物入りで公開されたことを、当時小学生だった私もぼんやり覚えている。公開時のポスターには、十二単を着た沢口靖子とともに、大きな宇宙船が描かれていたのを思い出す。
日本映画界の巨匠と呼ばれた監督で、市川崑ほどさまざまな表現手法、ジャンルに挑戦し続けた人もいない。何しろ、出発点はアニメーションであり、劇場映画を手がける一方でCMやテレビドラマ「木枯し紋次郎」も監督したし、映画「火の鳥」では、実写にアニメを重ねるという試みも行なった。また、1964年の東京オリンピックの記録映画も手がけ、内容としても興行的にも大成功を収めたことも特筆される。
ただし、「竹取物語」の映画化は、もともと日本映画における特殊撮影のパイオニアで1970年に亡くなった円谷英二が生前に切望したものであったという。市川はその遺志を受け継ぐ形で、脚本の共同執筆者の一人・石上三登志(CMディレクター・評論家)の提案もあり、SF仕立てにすると決めたようだ。だとしても、当時すでに70歳を越えていたにもかかわらず、新たな手法に取り組んだ市川の柔軟さには感服してしまう。
かぐや姫を育てる、老夫婦(竹取の造と田吉女)はそれぞれ三船敏郎と若尾文子という日本を代表する名優2人が演じている。劇中、夫婦は5歳の娘を亡くしたばかりで、竹林で造が見つけ連れ帰った女の赤ん坊を、娘の生まれ変わりと思い育て始めるのだった。ただ、三船と若尾の年齢でつい最近まで5歳の娘がいたというのはちょっと無理があるんじゃ……いや、映画公開当時、三船の実の娘の三船美佳もちょうど5歳だったはずだから、まったく無問題!
映画では、冒頭から宇宙船らしき物体が山に墜落するシーンが出てきたり、幼少期のかぐや姫の目が青く光っていたりと、SFテイストがふんだんに盛りこまれている。原作との相違はそれにとどまらず、たとえば、かぐや姫に対し、石作皇子・車持皇子・阿部右大臣・大伴大納言・石上中納言の5人の貴人が求婚するが、映画ではこれが車持皇子(春風亭小朝)と阿部右大臣(竹田高利)、それから中井貴一演じる大伴大納言の3人だけとなる。しかも、大納言に対しかぐや姫が恋に落ちるという、なかなか大胆な改変がなされている。
この映画でひときわユニークな存在は、かぐや姫たちの屋敷の近所で、小間使いとして働いている明野(あけの)という盲目の少女(小高恵美)だ。もともと学者の家に生まれながら、父の死にともない身寄りを失った彼女だが、学問に秀で、かぐや姫にも色々と教えてくれる。かぐや姫が3人の貴人たちに「蓬莱の玉の枝」「火鼠の皮衣」「龍の頸(くび)の玉」を所望して結婚をあきらめさせようとしたのも、元はといえば明野が入れ知恵したものだった。
物語の展開上、ヒロインと親友やライバルを対置させるということは、80年代のアイドルや若手女優の出演するドラマや映画によく見られたものだ(たとえば、映画「Wの悲劇」における薬師丸ひろ子と高木美保しかり、大映ドラマ「少女に何が起ったか」における小泉今日子と賀来千香子しかり)。かぐや姫と明野の関係はそれを踏襲したものといえる。もともと高い地位にありながらいまは零落した身の明野と、貧しい老夫婦の子に育てながらも裕福な生活を得たかぐや姫は好対照であり、両者の関係は物語に奥行きをもたらしている。
いまひとつ目を引くのは、もともと役人でありながら、いまは朝廷の密偵として身をひそめながら生きている理世(中村嘉葎雄)という中年男の存在だ。理世の友人である藤原の大國(加藤武)は着々と出世しており、ことあるごとに理世に役人に戻るよう忠告するのだが、彼は密偵をやめようとしない。むしろ密偵の仕事で手柄をあげることで出世をたくらんでいる。かぐや姫に求婚した貴人たちにしてもそうだが、市川崑版の「竹取物語」には、野心をたぎらせる男たちのドラマという一面もある。
このように、かぐや姫のまわりには、魅力的な人物たちが配置されている。しかし、物語の中心となるかぐや姫と大納言のラブストーリーが、私には何か物足りなく感じられた。
その点、高畑勲の「かぐや姫の物語」は、前半、かぐや姫が幼少期に捨丸という少年とともにすごす様子を描いておくことで、のちに彼女が貴人たちからの求婚を断り、さらには月へ帰ることまでも拒もうとするという展開に説得力を与えている。
もっとも原作の『竹取物語』は、すべての展開に納得のいくような理由づけがなされているわけではない。そもそも『竹取物語』は心に響く面白い物語なのかどうか、それについて高畑は疑問を呈している。
《古典だからといって、人々があまり面白いとは思わない物語をそのままにして、いくら細部で目新しい工夫をしてみたところで、いい映画にはなりようがない。誰もが知っている誕生や昇天の場面を、たとえあっと息をのむような見事な映像表現で見せたとしても、(中略)それだけで映画が面白くなるわけではないのは当然である》(映画パンフレット所収の「企画 『かぐや姫の物語』」)
これははからずも、市川版「竹取物語」への批評にもなっているように思う。この映画のクライマックスでは、冒頭でも触れたとおり巨大な宇宙船に乗った月からの使者がかぐや姫を迎えにやって来る。宇宙船は、蓮の花をかたどった、巨大ながらもこまやかな美しいデザインを持つ。CGなどなかった時代だから、当然これは実際に模型をつくって撮影したものだ。東宝が長年培ってきたこうした特撮技術には敬意を抱くし、じつは宇宙船の墜落事故の生き残りだったかぐや姫を連れ帰すため使者が訪れるという展開も、話として辻褄は合っている。
だが、そこに登場するのがあのような巨大な宇宙船でよかったのか、私にはどこか釈然としないのだ。それは、宇宙船のデザインが、細部はともかく、全体からするとスティーブン・スピルバーグ監督の「未知との遭遇」(1977年)のマザーシップのモノマネに見えてしまうせいもあるのかもしれない。市川版「竹取物語」は、作品を構成する一つひとつの要素は完成度が高いものの、残念ながら、それらが物語のうえで説得力を持つには、やや中途半端になってしまった感がある。
それでも市川崑という巨匠の果敢な挑戦として、この映画はいまでも鑑賞する価値は十分ある。あれだけの金を注ぎ込んで、日本最古の物語を実写映画化するなんてことはもはや難しいだろうし、原作の『竹取物語』が「物語の出で来はじめの祖(おや)」と呼ばれるように、市川版の映画も「竹取物語の映画の出で来はじめの祖」であることに間違いはない。「かぐや姫の物語」も同作あってこそ、のはずだ。
(近藤正高)