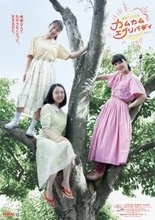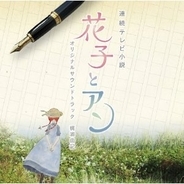新番組といえば4月から、というイメージを覆し、ひと足早い3月31日(が月曜日だから仕方ないんだけど)からはじまったところに、このドラマは、きっとスペシャルなドラマになるに違いない、そんな予感がしています。
なにしろ、主題歌「にじいろ」(絢香)で「これからはじまるあなたの物語」と歌われるので、「想像の翼」(美輪さまのナレーションより)を広げて生きていくヒロインの物語が、まるで自分の物語のような錯覚を起こして、既に胸いっぱいです。
4月の第1週は何かと忙しく、見逃してしまったよー という方々に、第1週6回分をおさらいしてみましょう。
「花子とアン」第1週(3月31日〜4月5日)「花子と呼んでくりょう!」(演出・柳川強)
昭和20年4月15日、東京大空襲から、ドラマははじまります。
翻訳家の村岡花子(吉高由里子)が空襲の中「赤毛のアン」の原本をもって逃げます。
もし、この時、原書をもって逃げなかったら、「赤毛のアン」は日本でこんなににもメジャーにならなかったであろうという示唆です。
花子は、爆撃の炎の恐怖を、「花火」と想像することで回避。
彼女のこの想像力は、幼い頃から彼女の生きる原動力になっていました。
ということで、ドラマは、1900年(明治33年)の山梨県甲府へ。
第1週は、まだ安東はな(山田望叶)だった村岡花子の、7歳から10歳までを描きます。
貧しい小作の家に生まれ育ったはな(自称はなこ)は、幼いながら家の手伝いをしています。
つらい労働や空腹は、想像の翼を広げることで忘れるようにしているのです。
とはいえ、お昼のお弁当を抜きにして、雲をおにぎりに見立ててしのぐ(第2回)というのはいくらなんでも・・・。
家庭がこんななのに、一番の働き手のはずのお父さん吉平(伊原剛志)は、稼ぎのあまりない行商をやっていて、家にはなかなか帰ってきません。
ただ、彼は、本(おやゆび姫)をお土産にもってきたり、労働者の集会に参加したりするなど進歩的な考えをもっていて、はなを東京の学校に行かせようとします。
父に似て、はなは本が好き。学校でたくさん勉強をしたいと願うものの、貧しい家庭環境はそれをなかなか許してはくれません。
第1週では、はたして、はなは東京の学校に行けるのか? というところまでを、
はなとその家族構成(祖父、父母、兄、妹ふたり)、幼なじみの少年の紹介、時代背景の紹介、甲府特有の言葉「てっ」「こびっと」「ずら」などの紹介を、ぶどう畑や白鳥、富士山などの甲府の美しい自然を交えながら、一気に描きます。
ドラマの中に、「赤毛のアン」らしさがさりげなく盛り込まれていることは、米光一成さんのレビューに詳しいですが、朝ドラファンは「おしん」らしさを感じた方々も多いのではないでしょうか。
貧乏な小作の家庭。幼い子供が重労働をしたり、赤ちゃんを背負って学校に行ったり。
地主が年貢をあげてさらに苦しくなり、子供が奉公に出なくてはならなくなる。
勉強が思うようにできない環境だけど、勉強したい思いが募る。
そんなところは「おしん」を思わせます。時代背景もほぼ同じです。
「おしん」は少女おしんが家族のために重労働している話が延々描かれましたが、「花子とアン」では、ご安心を。
はなの代わりに3年間の奉公に行った長男・吉太郎もあっという間に帰ってきます。
え、もう3年経ったの? と驚くくらいに早く時間が過ぎて、はなは希望に満ちた表情で東京の女学校に行くというのが、土曜日第6回。
この展開の速さは、ほかにもいくつかありまして。
はなと喧嘩した幼なじみの朝市くん(朝ドラの後のニュース番組「あさイチ!」と同じ名前!)との喧嘩の仕方は「赤毛のアン」のアンとギルバート。
とはいえ、彼らが仲直りに4年近く費やしたことに比べて、はなと朝市の仲直りは1回から3回の、わずか3話分(春から秋くらい)。
仲直りした朝市くんとはなが、ちょっとした冒険の末、森の池に落ちてしまうという事件もあっても(第4回)、はなはひとりで家に帰り、奉公に行こうとし、家族も「朝濡れて帰ってきた」というあっさりした様子。
朝市くんは、まだ家に帰っていなくても、それほど騒がれず、いつの間にか帰ってきているのです。
その後、はなが、濡れたせいで高熱を出し、牧師と助手(?)が進撃の巨人みたいに襲ってくる悪夢を見たり、運命を大きく変える辞世の句を詠んだりするにしてもですよ、なんだ、このさっぱり具合は! と思いませんか。
しかし、ドラマは、ツッコまれ対策をしていました。
はなと朝市が池に落ちた3話の最後、美輪さまが「はなと朝市の運命はいかに。
ごきげんよう、さようなら」と優雅な口調でナレーションするので、そんなに大変じゃないんだろうなあと思わせるようになっているのです。
現に、大した話ではありませんでした。
つまり、朝市とはなは、幼なじみどまりということを語っているのでしょうか。
事前にアナウンスされているドラマ紹介で、既に未来の夫は別の人だとわかっているのです。切ない。
冒険の代償に、はなが高熱で苦しんでいるところへ、帰ってきたお父さんが、「医者には見せたのか!」と慌てて、医者のもとへつれていくという場面は、現代の感覚ではとぼけている印象を受けます。
明治の貧しい人たちは、医者にも見せることもなかなかできない状態だったのですね。
第2回では、お父さんが、はなをキリスト教の学校に通わせるため、洗礼させたいと言い出すとき、「(キリスト教の世界では)金持ちも貧乏人も平等だ」と希望を語り、第5回で、牧師は「まだ金持ちと貧乏人がいるのは厳然たる事実です」ときっぱり(ドラマ的にいうと「こぴっと」?)現実をつきつけます。
第2週「エーゴってなんずら?」は、富豪の娘だらけの女学校に入ったはなの日々が描かれるようです。
「花子とアン」は、人は想像力で、空腹や貧しさや苦しみから逃れることができるかという、想像力が命のドラマや小説などの創作に携わる者たち誰しもが考える命題になりそうな気がします。
最後に。
米光レビューにあった、アンの舞台・アヴォンリーのもじりの「阿母尋常小学校」のほか、はなを喜ばせる本がいっぱいの教會は「阿母里基督教會」でアヴォンリーまんま。
さらに、「安東はな」は、名字がすでに「アン」なんですよね。あんどうはな。あんとはな。なんちて。
では「ごきげんよう、さようなら」(美輪さまの声でお読みください)。
(木俣冬)
第2週へ