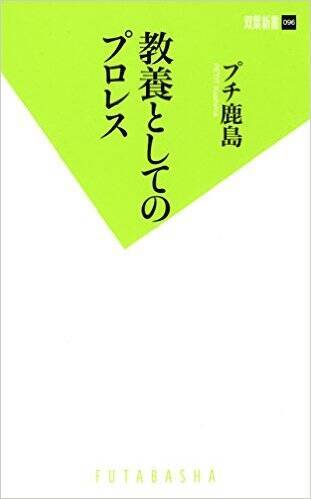
子供の頃から痩せっぽちで、極度の運動音痴でもあったぼくは、スポーツ全般が苦手なまま大きくなった。その延長上で、格闘技──ヒトとヒトとが争うようなものには興味が持てなかった。だから「プロレス」のこともわからない。
いや、それがどんなものかはわかる。海パン一丁の大男たちが、四角いリングの上で取っ組み合いして、相手を叩きのめす。倒れた相手をマットに押さえつけて、レフェリーが3カウント取ったら勝ち。だいたいそれで合ってるよね?
ただ、これはあくまでも興行としてのプロレスを説明したに過ぎない。ぼくがわからなかったのは、プロレス好きな文化人たちが時として使う「これはプロレスだ!」と言う、その「プロレス」という言葉の微妙なニュアンスだ。
素人のぼくだって、プロレスがガチンコ勝負ではないことくらい知っている。かといって、なんらかの出来事に対して半可通が「八百長」というニュアンスでプロレスと言うのが間違っていることも、感覚的にはわかる。
じゃあ、正確にはどういう意味なのか? そう問われると、途端に答えに窮してしまう。やはり何もわかっていないのだ。……そこで、ぼくはこんな本を手に取ってみた。プチ鹿島の『教養としてのプロレス』だ。2014年に新書として刊行されたものに、巻末の対談(博多大吉、森達也)を加え、このほど文庫化された。
プチ鹿島といえば、芸能界でも有数のプロレスファンだ。本書は、そんな彼の手による社会評論集である。採り上げられるテーマは宗教、アイドル、政治、SNSなど多岐にわたる。それらの諸問題に対して、鹿島はプロレスを軸にして縦横無尽に語り倒す。本業であるお笑い芸人なればこその、歯切れのいい文体にぐいぐい引き込まれ、気がつけば3カウント取られている。
しかし、宗教をプロレスで語る? 政治をプロレスで語る? そんなことが可能なのだろうか。
可能なのである。
宗教だって、アイドルだって、政治だって、プロレス的なモノの見方をしてみることで、新たな側面が見えてくる。そのことを知って、ぼくはようやく腑に落ちた。プロレスはリングの上にだけあるのではない。プロレスはどこにだってある。いや、言い換えよう。プロレスはどこにでもあるわけではない。森羅万象を見つめる「ぼくらの中」にあるのだ。
鹿島は本書の中で「無駄なものを愛す」と告白している。普通の人は、コップ一杯の水を運ぶとき7分目まで入れてゆっくり運ぶが、プロレスラーはタプタプまで入れて全力で運ぼうとする人種だという。その無駄を愛おしむ。
「私はプロレスを見てきたからこそ、社会からグレーゾーンがなくなっていくことを実感する。
そのとおりだと思う。社会は多様性でできている。ある者にとって価値のないものが、別のある者にはこのうえない価値をもつ。社会を見渡せば、そんな例はいくらでもある。つい先頃、特定の人々を社会にとって無駄な存在だと断じて、一方的に殺害を試みるおぞましい事件があった。彼らを無駄だなどと、誰が決められよう。
そんな悲しく息苦しい社会を少しでも生きやすくするためにも、プロレス的視線は持っているようにしたい。
(とみさわ昭仁)






























