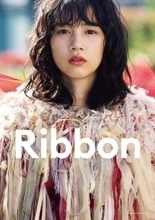マラソンの場面はまさかの実況中継スタイル
時は1911(明治44)年11月19日。翌年に迫ったストックホルムオリンピックに日本代表として出場する選手を決めるべく、東京郊外・羽田運動場にて予選大会が開催された。このときのマラソンの模様はすでに第1話で、日本のオリンピック参加を決めた嘉納治五郎(役所広司)の視点から描かれているが、今回は、金栗四三(中村勘九郎)らランナーの側からあらためて描かれた。そこでとられたのはまさかの実況中継スタイル。ドラマの語り手を務める若き日の古今亭志ん生=美濃部孝蔵(森山未來)は、レースが始まると実況アナウンサーに早変わり(これがまた流暢で驚いた)、画面には現実のマラソン中継と同様、中継地点や暫定順位などが随時テロップで入るという凝りようだった。
歴史ドラマにおいてこうした手法が用いられることは、わりと古くからある。NHKラジオでは1957年以降、「架空実況放送」と銘打って、関ヶ原の戦いなどの歴史上の大事件がたびたび実況スタイルでドラマ化されている。より最近の例としては、フェイクドキュメンタリー仕立ての歴史番組「タイムスクープハンター」(NHK総合)が思い出される。市井の人々をハンディカメラで追いかけるなど、同番組の臨場感あふれる演出は今回の「いだてん」にも通じる。
このように手法的には目新しいものではないとはいえ、それを天下の大河ドラマでやったことはやはり画期的だ。「いだてん」ではこれ以前から、三島家の女中シマ(杉咲花)の心の声がテロップで表示されたり、あるいは古今亭志ん生(ビートたけし)の弟子・五りん(神木隆之介)のガールフレンドである知恵(川栄李奈)がその場にいない彼の話をしているときに、五りんの顔がワイプで抜かれたりと、バラエティの手法が持ち込まれることがたびたびあった。そこへ来て今回の実況中継仕立ての演出に、オーソドックスな大河ドラマを期待する視聴者は眉をひそめたかもしれない。
しかし、こうした革新的な手法が繰り返されてきたという歴史も大河ドラマにはある。
話を劇中のオリンピック予選会に戻せば、マラソンは大雨のなか実施された。時間が経つにつれ落伍者があいつぐなか、四三と同じ東京高等師範学校の野口源三郎(永山絢斗)が空腹にたまりかね、沿道の店に飛びこむとパンをつかんで店番のおばあさんに叱られる。さらにレース終盤、先頭を走っていた小樽水産の佐々木政清が急に立ち止まって振り返ったかと思うと、後ろから追いかけてきた四三をにらみつけるというエピソードが出てきた。これらはいずれも実話である。また、マラソンの前に行なわれた短距離の各レースに、当日審判員を務めていた三島弥彦(生田斗真)が飛び入り参加し、ことごとく1位になったというのも史実に基づいている。
マラソンの場面では、孝蔵青年の実況だけでなく、1960(昭和35)年の志ん生も寄席でレースの模様を語って聞かせ、四三に時空を超えて並走した。四三が当時の世界記録を更新する2時間32分45秒でゴールしたあと、水を飲もうとしてやめるところでは、志ん生が「また夢になるといけねえ」と人情噺「芝浜」の有名なサゲをかぶせ、またしても意表を突かれた。そうか、宮藤官九郎がタイトルに「オリムピック噺」とつけたのは、こういうことをやりたかったからなのか! と思わず膝を打った。
予選で優勝してもさらに高みを目指す四三
とまあ、振り返るにつけ、今回の演出には驚かされることばかりで、「いだてん」は第5話にして一気にアクセルをかけてきた感がある。まだ序盤のこの時点でこれだけ盛大にやってしまって大丈夫だろうかとちょっと心配にもなったが、第5話の後半の展開を見て考えを改めた。
四三は幼いころに嘉納に抱っこしてもらうはずが叶わなかったことが、ずっと心に引っかかっていた。それがオリンピック予選で1位でゴールインし、嘉納に抱きしめられることで、思いがけず実現する。そもそも四三が東京高師に入ったのも、嘉納が校長だったからだ。ある意味、この時点で目的は達せられたともいえる。
しかし彼はそれで終わりとしなかった。優勝して学校のみんなから祝われたあと、寮の部屋でノートを取り出すと、表紙に「勝つために」と記し、徹夜で今回の反省点を書き出す。さらに翌日には、レース中に足袋が破れて最後は裸足で走らざるをえなかったため、改善してもらうべく足袋職人の黒坂辛作(ピエール瀧)に注文をつける。辛作には機嫌を損ねて追い返されてしまったが、しかしそれもこれも、日本のマラソンの向上、そしてオリンピックという世界を相手にしての新たな目標のためであった。
四三が予選で優勝しても慢心せず、新たな高みを目指す姿に、私はこのドラマのつくり手の決意表明みたいなものを読み取った。第5話にしてさまざま冒険的な演出に挑んだ「いだてん」スタッフ陣が、今度は本番となるストックホルムオリンピックをどんなふうに見せてくれるのか、ますます楽しみになる。
孝蔵がついに円喬に弟子入り
第5話ではまた、志ん生がなぜ「オリムピック噺」を思いついたのか、その理由もあきらかにされた。じつは、孝蔵青年が落語家の橘家円喬(松尾スズキ)に弟子入りしたのには、オリンピック予選会がかかわっていたのだ。
孝蔵の浅草の仲間である車夫(人力車引き)の清さん(峯田和伸)がオリンピック予選会に出場するので(ただし出場資格はないためモグリでの出場だったが)、孝蔵がその日にかぎって彼の仕事を請け負う。
じつは落語家になる前の志ん生については、落語家になる経緯も含めて謎が多い。本人は終生、円喬の弟子を自称していたが、実際には別の落語家の門下だったという説が有力である。ともあれ、謎が多い分、このドラマでは若き日の志ん生が思い切り想像を膨らませて描かれている。彼が「オリムピック噺」をつくったのは、予選会に出場した清さんから話を聞いていたからという理由も、ちゃんと脈絡がついて無理がない。
志ん生については一方で、その著書などを踏まえたエピソードも見られる。たとえば、円喬が俥に乗りながら落語「鰍沢」の稽古をしていると、孝蔵はふと雨の気配を感じて幌をかけようとした。しかし実際には雨は降っていない。

たけしが志ん生を演じる必然性とは?
志ん生といえば、第5話では、高座で「オリムピック噺」を演じながら、出演前に飲んだ酒のせいで、途中で居眠りしてしまう一幕もあった。現実の志ん生も、酔っぱらって高座中に寝てしまったという話がつとに知られる。
結城昌治『志ん生一代』(小学館)には、戦時中に渡った満州から終戦後もしばらく帰れなかった志ん生が1947(昭和22)年にようやく引き揚げてきた直後、酒をしこたま飲んで寄席に出演し、大喜利中に寝てしまったというエピソードが出てくる。このとき共演していた桂文楽(先代)が、「志ん生は満州の疲れがとれておりません。なにとぞご勘弁のほどを」とあわてて頭を下げると、客席からは「ゆっくり寝かしてやれよ」という声がいくつもかかったという。
その後も酒に酔って高座で寝てしまうということはたびたびあったらしい。そんな志ん生をよく知る客たちは、寄席に彼が出るたび《「きょうは、やるか、やらないか」混沌とした気持をいだきながら待っていた》という。「やらない」とは半分投げやりで高座を勤めるということだが、志ん生の場合、《ときとしては、「やらない」ときのほうが、面白いという点ではふだん以上などということもあるので、油断ならない落語家であった》と、演芸評論家の矢野誠一は書いている(『志ん生のいる風景』文春文庫)。
ハプニング込みでファンに期待させるという点では、このドラマで志ん生を演じるビートたけしにも当てはまる。
そんなふうに考えると、孝蔵青年が円喬に弟子入りを申し出るシーンが、どうも、浅草フランス座のエレベーターボーイだった北野武青年が、喜劇役者の深見千三郎に弟子入りを志願する姿(実際に見たわけではないけれど)と重なってしかたがなかった。
(近藤正高)
※「いだてん」はNHKオンデマンドで配信中
作:宮藤官九郎
音楽:大友良英
題字:横尾忠則
噺・古今亭志ん生:ビートたけし
タイトルバック画:山口晃
タイトルバック製作:上田大樹
制作統括:訓覇圭、清水拓哉
演出:井上剛