「賢人論。」今回のゲストは、株式会社土屋の代表取締役兼CEO高浜敏之氏。高浜氏は、2020年8月に株式会社土屋を起業。
初めての介護現場で障がい者運動の活動家に
―― 高浜さんは、既成概念にとらわれない方法で、異例の実績を残されています。もともと、どのような経緯で介護にかかわるようになったのでしょうか?
高浜 介護業界に入ったのは30歳になったときのこと。参議院議員の木村英子さんが運営する重度訪問介護サービスの事業所「自立ステーションつばさ」で働き始めたのがきっかけです。
木村さんは車椅子に乗った脳性麻痺当事者で、障がい者運動のパイオニア的な団体である全国公的介護保障要求者組合の事務局の運営もしていました。
私は、介護の仕事をしながら、週の半分ぐらいは業界団体の事務局としてデモンストレーションに参加していました。そして、厚生労働省や都道府県の担当部局と話し合って、国の制度に当事者の声を盛り込んでいました。
障害福祉分野は、サービスを受ける当事者の方々が国や行政などに訴えたことで制度ができた歴史があります。
―― 介護業界に入った頃から、珍しい取り組みをされていたのですね。
高浜 そうですね。30代前半は、障がい者運動を出発点として、難民の方、ホームレスの方、非正規労働者の方などの権利回復のための活動をしていました。
―― その後、どのようにして経営者の道が開けていったのですか?
高浜 経営者になるまでにはいろいろとありまして……。
35歳のとき、アルコール依存症における離脱症状で倒れたんです。破滅的なところがあったので、お酒の度が過ぎていたようです。その後、35歳から38歳までは生活保護を受けながらリハビリをしていました。
症状が回復した頃、今度は高齢福祉の勉強をしようと思い、認知症対応型のグループホームでアルバイトを始めました。アルバイトはリハビリの一環だったのですが、経営者に認められ38歳で正社員になりました。
その後しばらくして、そこで出会った方が新しく会社を設立することになったのです。そのとき「デイサービスをつくりたいから、そこの管理者になってくれないか」というオファーをいただきました。勤めていたグループホームはNPO法人だったのですが、声を掛けてもらったのは、介護系ベンチャー企業。そのベンチャー企業に創業メンバーとして参加したのが39歳のときです。

―― 高齢者介護から重度訪問介護に戻られたのは、どのような経緯からなのでしょうか。
高浜 2014年、重度訪問介護の歴史をつくってきたパイオニアの方が亡くなったんです。その弔いとして重度訪問介護事業を、社内で立ち上げることにしました。
センチメンタルな理由から始めた事業でしたが、ニーズがたくさんあったし、経営資源もありました。特に、医療依存度が高いALSや進行性筋ジストロフィーの方の支援が足りていない現状を知り、そこにアプローチしたいという思いが強かったです。
最初は、東京都内だけで事業を行っていたのですが、あれよあれよという間に広がっていきました。
―― その後の事業拡大のスピードは速かったですね。
高浜 2019年には40都道府県で事業を展開するようになりました。当時は東京に住んでいたので、東京から北海道、沖縄……と全国飛び回る日々を送っていました。そんななか、娘が生まれたんです。そこで、妻の実家がある岡山に移住することにしました。
ただ、当時は介護ベンチャー企業のCOO(最高執行責任者)でしたが、代表の方との意見の相違があり、残念ながらたもとを分かつことになりました。そして、2020年、それまで担当していた地域の一部を引き継ぐとともに、岡山の地で起業しました。
お風呂がない部屋で育ち、力をつけたかった幼少期
―― ご著書で心に残ったのが、高浜さんが、他人の痛みを自分ごとのように受け止めて行動しておられたことでした。幼い頃からそのような性格だったのですか?
高浜 今はイカツイ感じになっちゃったけど、幼い頃は、弱さを抱えた子どもだったんです。友達に何か言われたり、ボコンと叩かれたりすると、すぐに“えーん”と泣くような。今でも、感じやすさや敏感さとして、その弱さは残っているのかもしれません。それに、おふくろが病気がちだったので、ケアを自分の役割のように思っていた面はありました。

―― 今でいうヤングケアラーのような感じですか?
高浜 そのような面もありました。でも、叔母が手伝ってくれていたので、看病に追われて勉強や遊びができないということは一切なかったのですが。
―― ご著書に、一時期、ボクサーを目指していたとありました。お父さまの影響でしょうか。
高浜 そうですね。親父は不動産会社を経営していたのですが、元ボクサーで、柄の悪いヤンキーのような人でした。父も母も中卒の家庭だったので、勉強しなくても何も言われないのですが「ケンカには負けるな」と言われましてね。泣かされて帰ってくると「やり返してこい」と言って、家から閉め出されることもあったくらい(笑)。親の期待と自分の性格とのギャップに悩んだ末、父の背中を追ってボクシングに打ち込みました。
中学生ぐらいには、私もヤンキーのようになっちゃいましてね。たくさんの人を傷つけたし、傷つけらました。中学時代にはすべての前歯がなくなっちゃったりもしました。

―― 高浜さんは、上智大学と慶応義塾大学に入学されていますよね?その状況からどうやって学力をつけていったのですか?
高浜 勉強は比較的できる方でしたが、「リッチになってお風呂付きの部屋に住みたい」という思いだけでやっていましたね。
うちの家は相対的に貧困な家庭でした。アパートは6畳と4畳半の部屋があるだけの2Kで、お風呂もなかったんです。隣の部屋には、スナックで働くシングルマザーが暮らしていました。
当時、お風呂のない家に住んでいたのはクラスで私だけ。だから、友達に“貧乏人”とバカにされて、ずいぶん悔しい思いをしました。
ある日、「リッチになるにはどうしたらいいんだ」って父に聞いたんです。すると「勉強して、いい大学に入って資格を取ることだ。そしたら、リッチになって風呂がついてる家に住めるぞ」と言われました。「何としてもお風呂付きの家に住みたい」と思っていた私は、「じゃあ勉強しよう」という気になりましたね。
―― 「やり始めたら極めるまでやるぞ」というタイプだったのですか?
高浜 そうでもないですね(笑)。今の事業で、初めて物事を全うできるようになりましたけど、それまでは何をやっても中途半端でした。ボクシングが最たるものです。親に「勉強しろ」と言われたことは一度もないけど、勉強は地味にやり続けていたんです。
―― 地道に続けたのが結果につながりましたね。
高浜 そうですね。中学3年生ぐらいまでは勉強を頑張って、そこそこ偏差値の高い高校に行きましたので。でも、いざ入学したらやる気がなくなってしまい、進学はせずにボクシングにのめりこみました。その後、紆余曲折を経てプロボクサーへの道を断念。慶応義塾大学の文学部で哲学を学ぶことにしました。
―― 哲学に興味を持ったきっかけについてもお聞きしたいです。
高浜 文学や哲学には、幼い頃から興味がありました。これも父の影響です。
父は中卒のアウトサイダーだったのですが、文学好きでもありました。酒に酔うと「集まれ」と言って小さな部屋に家族を呼び集め、自分が好きな文学作品を朗読し始めるんです。椎名麟三の『深夜の酒宴・美しい女』とかを読まれても、当時はさっぱり分からなかったのですが……。そんな環境だったので、10代で文学作品を読む習慣がありました。外国モノだとアルベール・カミュやジャン=ポール・サルトルやドストエフスキー、日本だと椎名麟三や坂口安吾などをよく読んでいました。
20代になり、ボクシングの挫折で苦しんだとき、根っこの部分から考え直したいという思いになったんです。そして、慶応義塾大学に入り直して文学・哲学を学びました。
ボクシングでの挫折から哲学の道へ
―― ボクシングで挫折したときは、どのような思いだったのでしょうか。
高浜 何をやっても中途半端に終わるんだと思いましたね。
高校卒業後、2年遅れで上智大学に入学したのですが、2年で退学してボクシングに戻ったんです。そのボクシングの道も断念することになりました。名門のボクシングジムでプロテストの手前ぐらいまでいって、プロとのスパークリングとかもやっていたんです。でも、プロの世界に入ることにためらいがでてきたんですよね。
何にたじろいでいたかと言えば、後遺症なんです。ボクシングジムには、ケガの後遺症が残っている人が少なからずいました。だから一度プロになってから、やめて戻ってきたときには、人生の選択肢が限られると思いまして。

ボクサーだった父も、プロになることは大反対でした。「ボクサーは、引退年齢の35歳ぐらいまでは充実してるけど、引退したあとは人生がきつくなるから」って。
悩んだ末、プロボクサーの道を断念しました。そして、悶々とした思いのなか「原点に戻りたい」と考え、哲学を学び直すことを決めました。
哲学はイノベーションを生み出す
―― ご著書を読んでいると、いろいろな場面で哲学的な考え方をされていることを感じます。経営上の問題も、哲学から解決のヒントを得られるのでしょうか。
高浜 役に立っているとは感じますね。
哲学は「汝自身を知れ」というソクラテスの言葉から始まったと言います。それってある意味自己客観視だと思うんです。哲学は、「なぜ人は生きるのか」「なぜ1+1=2なのか」というように、「そんなの当たり前でしょう」というようなことを、あえて問い直す。当然だと思うことを捉え直すと、見えてくることがあるんです。
例えば、経営で何か問題が起こったら、自分たちが置かれた現状を外から見直す。それは冷静になる方法でもあるし、物事の全体像が見えてくる方法でもあります。それに、物事を違う角度から見る癖をつけることは、イノベーションにつながるのではないでしょうか。
―― 経営においては、柔軟な思考によるアイディアが力を発揮するということですね。
高浜 そうですね。哲学科出身の経営者って割といると思うんです。堀江貴文さんがそうです。哲学ではないですが、ジョブスは禅に親しんでいましたし。一見、何の役にも立たないことばかりやっているようですが、その思考方法が事業のヒントになっていると思います。
アルコール依存症回復プログラムが経営に役立っている
―― 他の取材記事では、アルコール依存症から回復するためのセラピーが経営に役立ったと語られていました。どのように活用されたのでしょうか?
高浜 私は、アルコホーリクス・アノニマス(AA)というアルコール依存症の方のグループでリハビリをしていました。そこでは、円になって座り、それぞれが自分の体験談を話す取り組みが行われています。誰かが話しているとき、周りの人は、ただ話を聞くんです。
最初は失敗談を話すのが恥ずかしいという思いがありますが、ほかの人が話していると、自分も話そうと思えてきます。そして、自分の話を周りが受け止めてくれることで、だんだん癒され、回復していくんです。TOKIOの元メンバーである山口達也さんもここのセラピーを受けています。
AAでは、ミーティングの最後に、あるポエムを朗読するんです。それはアメリカの神学者ラインホールド・ニーバーという牧師が書いた「ニーバーの祈り」という詩です。「神様、私にお与えください。自分に変えられないものを受け入れる落ち着きと、変えられるものを変えていく勇気を。そして二つのものを見分ける賢さを」。
それを毎日読んでいると自己洗脳が起きてくるんですよ(笑)。物事を判断するときには、常にそのポエムを実践できているかを意識するようになりましたね。

でも、このポエムで表現される落ち着きと勇気と賢さは、経営の場面でも非常に役に立ちます。うまくいかない人は、変えられもしないものを変えようとしたり、変えられるものをあえて放っておいてそのままにしたりしますから。
その二つの判断は単純なものではなく、そのときの状況によっても変わります。 今、これは変えられるけど、前は変えられなかったなとか。逆もまたしかりということはあります。
ビジネスだから変えられること
―― 社会活動家時代、社会の巨大な力への無力感を感じた体験があったともご著書に書かれていました。そのときに解決したかったことが、ビジネスだから変えられている面もあるのではないでしょうか。
高浜 私が社会運動をやっていた頃「理不尽なものは何でも変えるべきだ」と思っていました。そして、変えられなかったら頭に来て酒を飲むというような悪循環に入っていましたね。
当時、アル中という自覚はなかったですし、このフレーズとも出会っていなかった。だから、「ニーバーの祈り」の視点は持ち合わせていませんでした。
もともとは私、ビジネスにものすごい嫌悪感があったんです。戦争も環境破壊も貧富の格差もすべてビジネスによる搾取の結果だと思っていました。
そんななか40代でソーシャルビジネスというコンセプトと出会いました。同じテーマに対して、社会運動とは違うアプローチで解決できるという点は、実感があるところです。
逆に、ビジネスでは解決できなくてもNGOなら解決できることもあります。どっちが正、どっちが悪ということはありません。それでも、ビジネスでしか変えられないことがあるので、今はこの方法を選んでいます。
ケアの質を問う前にケアを生み出せるかどうか
―― 実際、どんな場面で「ビジネスだから可能になるケアがある」と感じますか?
高浜 ケアの質の良し悪しの差には圧倒的な違いが出ます。しかし、ケアの質を問う前に、ケアできる仕組みを生み出せるかどうかの問題です。
ケアを存在させるためには、ケアを担う事業者がいなければいけない。ケアを担う人がいなければいけない。ケアを担う人たちを採用し、育成しなければいけない。そしてケアを担う人を育成できたら、その人たちのマネジメント的な役割をする人が必要になります。
いろいろな経営資源が必要になるので、ビジネスにおいては投資活動が求められます。マイケル・ポーターは「資本を自ら生み出すことができるのはビジネスだけだ」と言っています。1万円しか持っていない人が1億円のM&Aをすることはできません。経営資源を持ってる人だけが投資できるわけです。

NGOやNPOなどの非営利組織は、資本は外部に依存します。寄付による補助を受け、その資本に基づいて動きます。一方、ビジネスは資本を自己増殖していきます。
毎月・毎年、利益が生まれれば、そこから税金が引かれます。そして、その税金を引いた基準利益が貸借対照表の純資産に乗っかってくるというプロセス。これが資本の自己増殖だと思うのです。
私たちの会社も、ビジネスとして社会課題に関わるからこそ、ケアを生み出すことができています。そして、高速に環境をつくっていけたのは、ビジネスだったからだと思っています。
介護事業の経営は規模が大きい方がいい
―― 「福祉は清貧でなければいけない」という思い込みに縛られている人も少なくないのではと思います。ビジネスの力を生かしてより良いケアをしていくにはどうすればよいでしょうか?
高浜 3つのルートがあると思っています。ひとつは内部留保によって組織の体力を強化すること。ふたつめは、新規事業や採用などでさまざまな投資をしていくこと。最後は、従業員の給料を良くする待遇改善。これも投資のひとつかもしれません。
この3つをバランス良く配分するのが経営者の仕事だと思っています。例えば、ビジネスとしてケアをする場合、業績によっては、従業員の待遇改善に費用をかけられます。
もし内部留保が溜まりやすいのであれば、従業員の給料を上げればいい。内部留保が溜まりにくければ再分配しにくいので不利です。ですが、規模が大きければ、それにもかかわらず、優位性が確立されています。なぜかと言えば、スケールメリット(規模の経済)が働くからです。
地域密着で留まれば、経営が厳しくても小さい規模のなかでやりくりしていく必要があります。規模が大きくなっていけば、キャリアアップの構造ができ、効率性が上がっていきます。すると、会社の利回りが良くなる。結果的に、規模を大きくする方が、従業員に多くのお給料を払えます。それがビジネスによる強みですね。
会社経営をしたら分かりますが、利益を上げたら税金以外のお金が内部留保に詰め上がっていく。それが純資産になって事業が発展していきます。総資産に対する純資産の割合が30%以上ないと経営不安定と言われ、金融機関から融資を受けられなくなるわけですよね。
ビジネスが悪に傾くかどうかは経営者の志に委ねられる
―― ケアをビジネスにする過程で、賞賛だけではなく批判もあったのではないでしょうか。
高浜 かつての私のように、決めつけでの批判というのはありました。
私は以前、マルクス主義的思考で利益イコール搾取であり、悪だと思っていました。しかし、利益そのものが悪なのではなく、生み出された利益をどう配分していくかが大事なのです。
従業員への再分配事業に対する投資、内部留保。このバランスを極端に間違えた場合は悪になりうるでしょう。例えば内部留保にばかり力を入れてスタッフへの還元がまったくないなら、搾取と言われてもしかたないと思います。
どこにどう分配するかの裁量は経営者の倫理に委ねられています。処遇改善加算という縛りはありますが、法律があるわけではない。所有権を持っている人たちの志に依存しているところが危うさのひとつでしょう。

従業員の給料がやたら低いのに利益率がやたら高くて内部留保が多い企業もあります。精査してみたら、社長が会社のお金でレクサスを買ったり、ハワイ旅行に行ったりしていたということがあります。M&Aをしていると、1週間に2回ぐらいは、そのような理由で会社が倒産した状況を知ることになります。
高齢者介護でも年収1,000万円は可能
―― 株式会社土屋では、年収1,000万円の社員も少なくないと聞きました。障がい者福祉の領域だから高収入が可能になったということはありますか?
高浜 ないと思います。実際、高齢者福祉の事業でも同様の取り組みを始めています。理想の利益率を確保し、従業員がキャリアアップを果たして高待遇を実現する方法は、すでに設計済みです。それに、収支差率を見ても、重度障がい者福祉が高齢分野に比べて極端に高いところはないです。
大切なのは、内部留保している資金を従業員への再分配に回したいと思えるかどうかですね。私たちの会社は、従業員への再分配を重要視しています。それが好待遇の人材を大量生産できている理由です。
ただ、たとえ好待遇になったとしても課題が残ると思っています。報酬が上がったら上がったで「高い給料もらえるから仕方なくやってるんだ」という不満を抱き続けるかもしれません。だから、ハードもソフトも両方、考えていく必要があると思います。
―― お金もらっているから仕方なくやっているという人も出てきますか?
高浜 なかには、ですけどね。ただ、エンゲージメントの高さとその人の待遇は相関性があります。ちょうど昨日、社員を対象に行ったエンゲージメント調査の結果が出てきたんです。やっぱり、給料が高ければ高いほどエンゲージも高い。つまり幸福度も満足度もやる気も高いということはあります。じゃあ、給料が高くなったら、必ずみんなが満足するかと言えば、それほど直線的な関係ではないとも思いますね。
高い給料でモチベーションが上がって、良いケアができて、利用者も満足。そうなればいいと思うのですが、なかなかそうはいかないと気付かされました。もちろん、待遇が上がれば上がっただけの人材が来るようにはなりますが。
経営は「変えられるもの」を見極めるタイミングが重要
―― 高齢者介護の事業所を安定して経営していくためには何が大切だと思いますか?
高浜 先ほども言いましたが、規模を大きくすることですね。介護報酬の額が決まっている状況においては、規模が小さければ小さい範囲内でのことしか物事を考えられません。規模を大きくすると、バックオフィスのDX化など、いろいろな面で効率化が進みます。効率性が上がると利益率も上がります。
―― 現在、経営が厳しい事業所は、どのように規模を大きくしていくべきでしょうか。
高浜 本来は、国の制度で報酬単価アップを実現できれば、それが良いと思うのです。ただ、高齢人口が増えていくなかで医療費の予算はどんどん膨らんでいきます。なので「変えられること」とすれば、私たちの側が規模を追求することだと思うのです。経営状況が厳しいのは、小さな規模のところが多いのではと思います。
「規模は追求しないけど、低賃金問題を解決したい」というのは、ダダをこねているようなもの。現実を見ずに反対運動をしても何も解決しません。
だから、経営を続けたかったら規模を大きくするか、どこかのグループに入るかだと思います。できないのに無理して経営を続けたら、ボロボロになります。そのまま債務超過や3期連続赤字になると、廃業せざるを得なくなります。

私たちの会社では救済型M&Aに取り組んでいます。そこで出会う方のなかには「1年前に相談に来たら受け入れることできたのに」と思うケースも多くあって。経営が厳しい会社は、今後の身の振り方を判断するタイミングがとても重要になります。
それから、経営効率を直視すべきです。そのような話をすると、往々にして「僕らは金儲けのためじゃなく利用者さんのことを思ってやってるから」と言われます。しかし、経営が悪化して会社が潰れてしまったら、利用者さんがサービス受けれなくなる。本当に利用者さんのことを考えてるんですか?という話ですよね。
私もビジネスを毛嫌いしていたから、お気持ちはよく分かります。でも「理想だけじゃなく現実も見てバランスを考えた方がいいですよ」と、かつての私に言いたいですね。そのようなやり方で経営している会社がどんどん潰れかけているので、何とか存続させられたら……と思うのです。
ケアの面白さはワインの違いを知ることに似ている
―― アルバイトとして高齢者介護の現場も経験されていますが、介護の大変さは感じましたか?
私は、高齢者介護の分野は、楽しくて奥行きがあると感じました。哲学的な話ですが、認知症の方は、同じものを見てもいろいろな読解の仕方をします。その変化を見つけることに喜びを感じていました。でも「面白い」という感想は、あまり周囲と共有できませんでした。温度感のギャップを感じたことが記憶に残っていますね。

―― 高浜さんのように介護職に楽しさを感じることが難しい人も中にはいると思います。何かアドバイスをいただけますか?
高浜 山口周さんではないですが、リベラルアーツに対する知見が深まると、面白さを感じるようになるかもしれませんね。
例えば、ワインの味を例に出して考えてみましょう。私は、メルシャンだろうがコート・ダジュールだろうが、飲めれば何でもいいというタイプでした。でもロマネ・コンティとメルシャンの違いが分かる人にとっては「こっちしか飲めない」ということがあるわけじゃないですか。違いが分からないと楽しめないということは、ありますよね。
音楽も同じだと思うんです。モーツアルトとベートーベンの違いが見いだせるようになったら、そこに面白さが見えてきます。文学も然り。
ケアにおいても同じことが言えると思うのです。同じ出来事を目にしたとき、それに感動したり面白いと思えたりするかどうかですね。これは、本人の感受性の問題だけではなく、訓練で身に付くものでもあると思うんですよ。じゃあ、訓練ってどういうことかと言えば、言語化能力だと思うんです。
―― 言語化能力ですか。
高浜 私は20歳のとき、表参道にあったフランス料理屋で働いていたんです。そこでは、残ったワインを飲んで良いことになっていました。そこで、スタッフにテイスティングする機会をあげるために、わざとワインを残すお客さんがいたんです。大抵フランス人の方でした。
しかし、残ったワインを飲んでみても、味の違いが分からない。どうしたら分かるようになるのかを聞いたら「言語化することだ」と言われました。
このワインの味は「百合の花のようだ」、「青空のようだ」、「大地のようだ」などと言語化する習性をつける。するとだんだん違いが分かってくるんです。
それって、日常生活でも同じことが言えるのではないかと思うんです。同じ体験をしていても、ある人にとったら面白いけど、別の人にとっては、そう思えない。その人のリテラシーが影響してる可能性はあるんじゃないでしょうか。
山口周さんは「ビジネスマンはリベラルアーツを身に付けるべきだ」と言っています。私は、ケアワーカーにも同じことが言えると思うのです。文学・哲学・アートに触れて感じたことを、言葉にして共有する……。そんな癖がついた途端、日常で体験していることが、とてもエキサイティングなものに映る可能性があるのではないでしょうか。
認知症の症状のなかで”やり残し”を果たしたおばあちゃん
―― 高浜さん自身、その違いを実感されたエピソードはありますか?
高浜 グループホームで働いていたとき、ある入居者のおばあちゃんと仲良しだったんです。その方にはお子さんがいませんでした。「私、子どもができなかったけど、お父さんとあちこちに旅行に行けたことがすごく楽しかった」と、よく語っていました。公園に行くと、いつも地域の子どもたちと交流していましたね。
そんななか、その方はどんどん認知症が進行して、周辺症状がひどくなっていきました。
私が夜勤をしていたあるとき、自室から下着姿になって出てきたんです。その人は、私を自分の旦那さんだと思い込んでいたので「お父さん、来て来て」と言うんです。汗だくでどうしたのかなと思って居室に行ったら、部屋のなかに物が散乱していました。
そして、お布団がかけてあったバケツを指さして「見て!生まれた。私、頑張ったよ」って言うんです。
言わば、ひとつのシミュレーションですよね。人生でやり残したことを、認知症の症状を通して表現していたのかなと思いました。その数年後、彼女は亡くなりました。
私は、とても大事な場面に立ち合えたことに感動して、この仕事、本当に面白いなと感じました。
でも「なんかわけわかんないこと言って」という解釈で終わったら、何にも面白くない。やっぱり読解力の話だと思うのです。
認知症の方や知的障がいがある方と接する奥深さは、ワインの味の違いが分からなかった自分では、発見できなかったかもしれません。今なら、その違いが感じられない残念さがよく分かります。
赤字になったとしても介護難民をなくしたい
―― 現在のホームケア土屋さんの課題と今後の目標についてお聞きしたいです。
高浜 私たちは47都道府県に事業所をつくりました。しかし、私たちの目標は47都道府県にサービスを広げることではなく、介護難民問題を解決することです。そこから考えると、まだまだサービスを提供できていない人たちがいます。
例えば、北海道の拠点は札幌だけです。札幌から稚内や函館へは遠距離になるため、サービスが届けられません。
和歌山県は和歌山市に拠点があります。しかし、ALSの多発地域である那智勝浦や熊野へは車で3時間かかります。こちらもやはりサービスが届けられません。
だから今、新しいプロジェクトとして、京都府北部の福知山、和歌山の熊野、淡路島などに事業所をつくっています。既存の拠点では届けられていないところまで、サービスを届けるためです。重度障がい者の訪問介護事業に取り組んでいるところが少ないためでもあります。
最初は全部赤字になると思います。でも、問題解決のためには赤字分をつくってでもやるべきことはやる。そのために何が必要かと言えば、経営純利益と自己資本を生み出していくことですね。今後も、さらに経営の効率性を追求して、洗練させていきたいと考えています。

―― ホームページには、障がい者介護と同じぐらい高齢者介護や児童福祉にも力を入れていきたいと書かれていました。高齢者介護の分野では、どんな取り組みを考えていますか?
高浜 高齢者介護の分野では、通所介護と訪問看護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護のセグメントが動いています。一番期待しているのはこの定期巡回・随時対応型訪問介護看護ですね。
今回の介護報酬改定で5%ぐらい単価削減されましたが、5%減ったところでまだ十分事業として成立する見通しがあります。
今までは、このサービスによって、障がいを持った人が在宅で暮らせるための環境づくりを進めてきました。その高齢者バージョンに取り組もうとしています。これを広げていって、高齢者が病院や施設ではなく、ご自宅で最期を迎えられるような環境をつくりたいです。
すでに全国に6つの事業所があり、今期中に10事業所ぐらいになります。この事業所数の中で複数件、看取りもできています。
介護難民の増加は今後の社会課題
―― 現在の介護業界において高浜さんが問題視されていることは何ですか。
高浜 さっき言ったことと矛盾するかもしれませんが、長く地域に根差して経営してきた事業所は、その事業所だけが生み出せる価値を持っていると思うんです。だから、地域の事業者さんが今までの思想やスタイルを維持したまま持続的に経営できる状況は必要だと思うし、そうあってほしいです。
今の介護報酬の設定は大規模事業者と小規模事業者を一緒くたにしたものです。数字を基準に判断していますが、実質は数字が良くても経営が厳しい会社はあります。国は効率性重視なので、そうせざるを得ないと思いますが、数字で計れない小規模事業者の価値をきちんと評価してほしいですね。
介護事業の経営者は現在65歳ぐらいになっている方が多いです。事業が大変なので子どもが継いでくれないし、本人も継がせたくない。M&Aラッシュです。経営状況を見ていくと、本当に良いサービスを提供していて、間違いなく価値があるけど、財務諸表はボコボコという会社は多いです。
事業が廃業してしまった場合は、介護サービスを充実させたいと考える国の方針と逆行してしまいます。だからこそ、業界固有の事業承継に対して、国策としてアプローチした方が良いのではないでしょうか。例えば、事業承継での税制における移行措置をスムーズにするところからでも実現してほしいですね。
―― このままいけば、一層顕在化してくる問題ですね。
高浜 そうですね。救済型M&Aを行っている我々は、小さな事業所などの買い手になります。昨年は、潰れそうな会社を買いすぎて、メインバンクに厳しく怒られました。うちが潰れそうな会社を吸収したところで、大したことはありません。ジャブが鼻かすったぐらいのものです。それでも、債権者である金融機関は「もらったらダメでしょ」って考えるんですね。
我々も金融機関の支援なくして経営が成り立たないので、今、M&Aには慎重になっていますが、依頼は結構来ています。それも仲介会社を通さずに。「そもそも誰も受けないでしょ」というような内容も少なくないので、行く末は見えています。
会社が破産すると、スタッフが失業して、利用者さんがサービスを受けられなくなる。そんなことが、どんどん起きていくと思うんですよね。今後、大きな社会課題になるのではないかと思います。

―― ケアに向き合う心得から、経営面のヒントまで、多岐に渡るお話をありがとうございました。幼少期の環境、ボクサーの道での挫折、アルコール依存症によるリハビリなど、マイナスに思える出来事も含めて、すべての経験が現在の事業につながっているのですね。今後のチャレンジも楽しみにしています。
取材/文:谷口友妃 撮影:熊坂勉














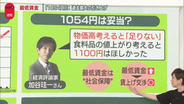














![[医食同源ドットコム] iSDG KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい](https://m.media-amazon.com/images/I/51S5YMnLMNL._SL500_.jpg)

![[アイリスオーヤマ] ディスポーザブル 不織布 プリーツ型マスク ふつうサイズ 120枚](https://m.media-amazon.com/images/I/41jEQGK2thL._SL500_.jpg)








