4月26日、「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」のシェフパティシエ、青木定治さんは、自身が開発したシードルを発売した。なぜ菓子職人が果実酒を手掛けることになったのか。
■世界的パティシエが日本を拠点にしたワケ
菓子の本場・フランスに拠点を置き、パティシエとして長らく世界の第一線で活動している青木定治さん(55)。コロナ禍以降は日本での活動が増えている。その一つの理由が、「国産フルーツ」だ。
国内に数あるフルーツの名産地の中で、青木さんが目を付けたのが長野県だ。もともと長野県産のリンゴを使った商品を手掛けていたが、リンゴ以外のフルーツはそこまで注目していなかった。
21歳でフランスへ修行に行った際には、日本とフランスの大きな“果物格差”に驚いたという。
「日本では見たことない果物が大量にありました。味もさることながら、豊富なフルーツを最適な加工をしてお菓子に仕立て上げていることに衝撃を受けました。『フランスではこんなお菓子を食べているのか。これは今までの舌をリセットしないと戦えないぞ』と思ったほどです」
ところが、数年前のコロナ禍のころに長野を訪れた際、そこで生産者たちと話をしながらアンズやプルーンなどを実際に食べたところ、そのレベルの高さに驚いたという。
「すぐにアンズのコンフィチュール(ジャム)をつくることを思い立ちました。
■即座に軽井沢の物件を抑える
そこからの青木さんの動きは速かった。
「ありがたいことに『熟しきって落ちているものを自分たちで拾うなら、好きに持って行って良いよ』といってくださって、拾うカゴなども貸していただきました。拾ったものを車にたくさん詰め込んで、東京に持ち帰りました」
しかし、拾ったものは全て完熟。東京に持ち帰るまでに、果汁が染み出て、傷んでしまう。そこで、東京まで持ち帰るのではなく、現地で物件を借りて冷凍し、東京へ配送できないかと考えた。
「山の中でもどこでも、冷凍さえできれば東京に送れる。そう考えて場所も見つけたのですが、今度は道が狭くて配送用のトラックが入ってこられず、最終的に『東京に送らず、この場所で加工するのが良いのでは』と思い付きました」
そこから探して見つけたのが、以前はフレンチレストランとして営業していたという国道沿いの物件。現在は、コンフィチュールなどを製造する工場併設の店舗、アトリエ軽井沢店となっている。
■菓子職人が「シードル」を手掛けたワケ
その後、青木さんと長野県との縁はどんどんと深まっていく。2022年には、パティスリー・サダハル・アオキ・パリの運営元である株式会社SAJと長野県で連携協定を締結。地元事業者との協業による商品開発、地域ブランドの育成などを含む内容の協定だ。
直近では、県内産のリンゴを使ったシードル「サダハルアオキ SAYA2023」(2600円)も発売する。企画から発売まで足掛け3年ほどを要した肝いりの新商品だ。
シードルはリンゴを原料にした酒で、日本ではまだそこまで認知度や市場が大きくないものの、フランスでは日常的に親しまれている飲み物で、青木さん自身もよく嗜むという。近年は米国で「ハードサイダー」がブームになっていて、国内の商品も増え始めている。そんな中で、長野県に足を運んだ際にリンゴ生産者が販売しているシードルを飲み、もっと伸びしろがあるのではと考えたのが開発のきっかけだ。
「シードルは甘口と辛口の2つに分けられます。
■洋菓子にも肉料理にもあう味わい
シードルの開発に当たっては、もともとコンフィチュール(ジャム)で使っていたリンゴで試作。しかし、発色や味などが思い描いたものにならず、別のリンゴを探していたところ、長野県で試験生産していた「キルトピンク」という品種に出会った。
キルトピンクを使ってシードルを作ったところ、キレイな発色に。もちろん色だけでなく「僕が手掛けるものであれば、味はいつでも正解にしたい」と語る青木さんも納得の味わいを実現できた。具体的には、パンチがありながらもスッキリとした甘みとほどよい渋みという味を両立したシードルに仕上がっている。
シードルの製造は京都府の丹波ワインに委託している。同社について青木さんは「京都の山の中にあるワイナリーで、OEM製造に対するチャレンジ精神なども持っていらっしゃる」と評価しており、開発工程でもさまざまなオーダーを出しながら、ともにブラッシュアップし、納得のいく完成形までこぎつけた。
■長野県は「まだまだもったいない」
長野県について、青木さんは「土壌も豊かですし、良い立地にもありながら、PRが不足していると感じています」と話す。今回のシードルでは、その長野が誇るリンゴの魅力を発信することを狙う。
シードルそのものだけでなく、地元食材との「マリアージュ」にも期待する。そもそもシードルは、フランスの中でもブルターニュやノルマンディーといった地方で愛されており、ガレットやチーズといった、現地の食べ物と一緒に楽しむことが多いという。
青木さんは今回のシードルも、長野のフルーツや信州牛など、地元の食材と合わせてもらいたいと考えている。
「パリで抹茶を使ったお菓子を広めたことがあります。成功したのは、『和菓子』として勝負したからでも、当時のトレンドに合わせたからでもなく、フランスの人が食べてきた『エクレア』に合わせたからだと思うんです。シードルを長野の食べ物と組み合わせて『こんな楽しみ方があったのか!』という驚きを地元の人に感じてもらいたいと考えています」
■「できるだけ出荷できないリンゴをください」
長野県の魅力をアピールするだけでなく、フードロス問題への寄与も狙っている。シードルに使うリンゴは、生食用としては出荷できないような形の悪いものでも問題ない。そもそも日ごろから青木さんは生産者に対して「できるだけ出荷できないものをください」と伝えている。なぜなら、「そっちのほうが熟していておいしいから」(青木さん)。
「何においても重要なのは『味』です。もちろんブランディングなども重要ですが、私たち職人は、いかに食材をおいしく作れるか、組み合わせられるか。この点を常に考えています」
長野県には、リンゴ以外にも魅力的な食材がいくつもある。その代表例が東御市のクルミ。同市は日本一のクルミ産地で「信濃くるみ」のブランドで知られる。パリの店舗でも信濃クルミを使った商品を販売している。
■日本のフルーツを世界へ
世界の最前線で活動し続けてきたパティシエが太鼓判を押す日本のフルーツ。その一方で、日本人の間では「果物離れ」が進んでいる。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、2019年における国民1人が1日に食べた果物は96.4グラムだった。2009年の113.0グラムから減少しており、特に若年層で落ち込みが激しい。
青木さんは「日本では、フルーツを生でしか食べないからでしょう。それは恵まれたことではあるのですが、もったいない。ひと手間加えることで可能性は無限に広がる」と指摘する。
青木さんはコンフィチュールの原材料として、生では苦みや酸味が強いものをあえて使用することがある。砂糖などで甘みを調節すれば、誰も食べたことがないような味わいを表現できるからだ。
「幸いにも、僕にはヨーロッパを中心に海外に通用するブランドがあります。まず地元の人たちに感動を与えて自信や誇りを持ってもらいながら、世界に日本のフルーツをアピールしていきたいですね」
「生」だけではない国産フルーツの魅力を、世界へ発信する。青木さんの挑戦はまだまだ続く。
----------
鬼頭 勇大(きとう・ゆうだい)
フリーライター・編集者
広島カープの熱狂的ファン。ビジネス系書籍編集、健保組合事務職、ビジネス系ウェブメディア副編集長を経て独立。飲食系から働き方、エンタープライズITまでビジネス全般にわたる幅広い領域の取材経験がある。
----------
(フリーライター・編集者 鬼頭 勇大 インタビュー・構成=鬼頭勇大)
その経緯と今後の展望を、ライターの鬼頭勇大さんが聞いた――。
■世界的パティシエが日本を拠点にしたワケ
菓子の本場・フランスに拠点を置き、パティシエとして長らく世界の第一線で活動している青木定治さん(55)。コロナ禍以降は日本での活動が増えている。その一つの理由が、「国産フルーツ」だ。
国内に数あるフルーツの名産地の中で、青木さんが目を付けたのが長野県だ。もともと長野県産のリンゴを使った商品を手掛けていたが、リンゴ以外のフルーツはそこまで注目していなかった。
21歳でフランスへ修行に行った際には、日本とフランスの大きな“果物格差”に驚いたという。
「日本では見たことない果物が大量にありました。味もさることながら、豊富なフルーツを最適な加工をしてお菓子に仕立て上げていることに衝撃を受けました。『フランスではこんなお菓子を食べているのか。これは今までの舌をリセットしないと戦えないぞ』と思ったほどです」
ところが、数年前のコロナ禍のころに長野を訪れた際、そこで生産者たちと話をしながらアンズやプルーンなどを実際に食べたところ、そのレベルの高さに驚いたという。
「すぐにアンズのコンフィチュール(ジャム)をつくることを思い立ちました。
このレベルの高さなら、きっとおいしい菓子が作れる。いずれ世界と戦えるものが作れるかもしれない」
■即座に軽井沢の物件を抑える
そこからの青木さんの動きは速かった。
「ありがたいことに『熟しきって落ちているものを自分たちで拾うなら、好きに持って行って良いよ』といってくださって、拾うカゴなども貸していただきました。拾ったものを車にたくさん詰め込んで、東京に持ち帰りました」
しかし、拾ったものは全て完熟。東京に持ち帰るまでに、果汁が染み出て、傷んでしまう。そこで、東京まで持ち帰るのではなく、現地で物件を借りて冷凍し、東京へ配送できないかと考えた。
「山の中でもどこでも、冷凍さえできれば東京に送れる。そう考えて場所も見つけたのですが、今度は道が狭くて配送用のトラックが入ってこられず、最終的に『東京に送らず、この場所で加工するのが良いのでは』と思い付きました」
そこから探して見つけたのが、以前はフレンチレストランとして営業していたという国道沿いの物件。現在は、コンフィチュールなどを製造する工場併設の店舗、アトリエ軽井沢店となっている。
■菓子職人が「シードル」を手掛けたワケ
その後、青木さんと長野県との縁はどんどんと深まっていく。2022年には、パティスリー・サダハル・アオキ・パリの運営元である株式会社SAJと長野県で連携協定を締結。地元事業者との協業による商品開発、地域ブランドの育成などを含む内容の協定だ。
直近では、県内産のリンゴを使ったシードル「サダハルアオキ SAYA2023」(2600円)も発売する。企画から発売まで足掛け3年ほどを要した肝いりの新商品だ。
シードルはリンゴを原料にした酒で、日本ではまだそこまで認知度や市場が大きくないものの、フランスでは日常的に親しまれている飲み物で、青木さん自身もよく嗜むという。近年は米国で「ハードサイダー」がブームになっていて、国内の商品も増え始めている。そんな中で、長野県に足を運んだ際にリンゴ生産者が販売しているシードルを飲み、もっと伸びしろがあるのではと考えたのが開発のきっかけだ。
「シードルは甘口と辛口の2つに分けられます。
日本では焼酎や日本酒で辛口を好む人も多く、シードルもドライのものが多い。ただ、私はもっと甘いリンゴを使って、甘口だけれどパンチの効いたものがあってもいいんじゃないかと考えました」
■洋菓子にも肉料理にもあう味わい
シードルの開発に当たっては、もともとコンフィチュール(ジャム)で使っていたリンゴで試作。しかし、発色や味などが思い描いたものにならず、別のリンゴを探していたところ、長野県で試験生産していた「キルトピンク」という品種に出会った。
キルトピンクを使ってシードルを作ったところ、キレイな発色に。もちろん色だけでなく「僕が手掛けるものであれば、味はいつでも正解にしたい」と語る青木さんも納得の味わいを実現できた。具体的には、パンチがありながらもスッキリとした甘みとほどよい渋みという味を両立したシードルに仕上がっている。
シードルの製造は京都府の丹波ワインに委託している。同社について青木さんは「京都の山の中にあるワイナリーで、OEM製造に対するチャレンジ精神なども持っていらっしゃる」と評価しており、開発工程でもさまざまなオーダーを出しながら、ともにブラッシュアップし、納得のいく完成形までこぎつけた。
■長野県は「まだまだもったいない」
長野県について、青木さんは「土壌も豊かですし、良い立地にもありながら、PRが不足していると感じています」と話す。今回のシードルでは、その長野が誇るリンゴの魅力を発信することを狙う。
シードルそのものだけでなく、地元食材との「マリアージュ」にも期待する。そもそもシードルは、フランスの中でもブルターニュやノルマンディーといった地方で愛されており、ガレットやチーズといった、現地の食べ物と一緒に楽しむことが多いという。
青木さんは今回のシードルも、長野のフルーツや信州牛など、地元の食材と合わせてもらいたいと考えている。
「パリで抹茶を使ったお菓子を広めたことがあります。成功したのは、『和菓子』として勝負したからでも、当時のトレンドに合わせたからでもなく、フランスの人が食べてきた『エクレア』に合わせたからだと思うんです。シードルを長野の食べ物と組み合わせて『こんな楽しみ方があったのか!』という驚きを地元の人に感じてもらいたいと考えています」
■「できるだけ出荷できないリンゴをください」
長野県の魅力をアピールするだけでなく、フードロス問題への寄与も狙っている。シードルに使うリンゴは、生食用としては出荷できないような形の悪いものでも問題ない。そもそも日ごろから青木さんは生産者に対して「できるだけ出荷できないものをください」と伝えている。なぜなら、「そっちのほうが熟していておいしいから」(青木さん)。
「何においても重要なのは『味』です。もちろんブランディングなども重要ですが、私たち職人は、いかに食材をおいしく作れるか、組み合わせられるか。この点を常に考えています」
長野県には、リンゴ以外にも魅力的な食材がいくつもある。その代表例が東御市のクルミ。同市は日本一のクルミ産地で「信濃くるみ」のブランドで知られる。パリの店舗でも信濃クルミを使った商品を販売している。
■日本のフルーツを世界へ
世界の最前線で活動し続けてきたパティシエが太鼓判を押す日本のフルーツ。その一方で、日本人の間では「果物離れ」が進んでいる。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、2019年における国民1人が1日に食べた果物は96.4グラムだった。2009年の113.0グラムから減少しており、特に若年層で落ち込みが激しい。
青木さんは「日本では、フルーツを生でしか食べないからでしょう。それは恵まれたことではあるのですが、もったいない。ひと手間加えることで可能性は無限に広がる」と指摘する。
青木さんはコンフィチュールの原材料として、生では苦みや酸味が強いものをあえて使用することがある。砂糖などで甘みを調節すれば、誰も食べたことがないような味わいを表現できるからだ。
「幸いにも、僕にはヨーロッパを中心に海外に通用するブランドがあります。まず地元の人たちに感動を与えて自信や誇りを持ってもらいながら、世界に日本のフルーツをアピールしていきたいですね」
「生」だけではない国産フルーツの魅力を、世界へ発信する。青木さんの挑戦はまだまだ続く。
----------
鬼頭 勇大(きとう・ゆうだい)
フリーライター・編集者
広島カープの熱狂的ファン。ビジネス系書籍編集、健保組合事務職、ビジネス系ウェブメディア副編集長を経て独立。飲食系から働き方、エンタープライズITまでビジネス全般にわたる幅広い領域の取材経験がある。
----------
(フリーライター・編集者 鬼頭 勇大 インタビュー・構成=鬼頭勇大)


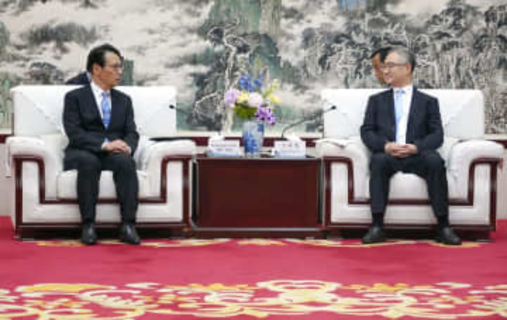














![[医食同源ドットコム] iSDG KUCHIRAKU MASK (クチラクマスク) ホワイト 30枚入 ダイヤモンド型 くちばし型 メイクが付きにくい](https://m.media-amazon.com/images/I/51S5YMnLMNL._SL500_.jpg)
![[医食同源ドットコム] iSDG 立体型スパンレース不織布カラーマスク SPUN MASK 個包装 ホワイト 30枚入](https://m.media-amazon.com/images/I/51m0nKLQ+rL._SL500_.jpg)
![[医食同源ドットコム] iSDG 不織布マスクPREMIUM 50枚入り (個包装) (ふつう)](https://m.media-amazon.com/images/I/51XlQaY1QuL._SL500_.jpg)








