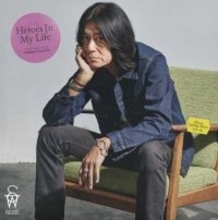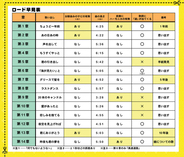初期の歌ものポストロック的な作風から、徐々に歌謡曲的な側面を強めつつ、アンサンブルを磨き上げてきたが、『濡れゆく私小説』では改めて山下達郎や松任谷由実らと向き合い、歌メロを練り、現代的なプロダクションと組み合わせることによって、高次元のポップスへと到達。
―インディゴはメジャーデビュー以降、2015年から5年続けてフルアルバムをリリースしていて、毎回内容を更新し続けているのは凄いなと。特に、前作の『PULSATE』は新旧の曲が入り混じってるという話でしたが、新作『濡れゆく私小説』はバンドがまた新たな領域に踏み込んだような手ごたえを感じました。
川谷:今回も「通り恋」と「砂に紛れて」は昔のテイクがベーシックだったりするんですけど、すごくいいアルバムになったと思います。
長田:できあがったものに対してはもちろんいいと思ってるんですけど、リリースをして、ツアーを回って、手ごたえはそこでわかってくるのかなって。
佐藤:今回も各々が成長した部分を生かして、オーガニックに作れました。バンドの役割って、リーダーが言ったことを反映させつつ、そこに自分らしさもちゃんと出すってことで、地味ではあるんですけど、そこで頭を悩ませて、「いい感じの演奏だね」ってなったので、すごくいい仕事ができたと思ってます。あと、今回ミックスを(井上)うにさんにやってもらったのも、個人的にすごく大きかったです。
後鳥:今回録ってから出すまで結構早かったんで、自分でも新鮮な気持ちで聴けて、楽しいです。「通り恋」と「砂に紛れて」は古い曲だから、仮ミックスは何回も聴いてたんですけど、エンジニアさんが変わったことで、新曲みたいに聴けて、それもよかったですね。
―僕まだ今回のエンジニアさんのクレジットは見れてないんですけど、うにさんがメインで参加されてるんですか?
佐藤:基本的には美濃(隆章)さんなんですけど、「通り恋」「砂に紛れて」と、「Midnight indigo love story」のミックスはうにさんです。川谷さんが別のプロジェクトでうにさんにお会いして、「じゃあ、頼んでみよう」って。自分の中で、ある程度のイメージはあったんですけど、全然それを超えて、メンバーみたいな関わり方をしてくれたんですよね。「Midnight indigo love story」とか、リミックスに近いくらいの感じで、かなり踏み込んできてくれて。
―川谷くんの別のプロジェクトというのは?
川谷:美的計画で一緒にやらせてもらったときに、結構ドープな感じで仕上げてくれて、「めっちゃいいですね」って言ったら、「大丈夫? ここまでやっていい?」って、逆に不安だったみたいで。でも、俺的にはすごく好きな感じで、そのときは打ち込みだったから、インディゴでもやってみたいなって。絶対合うと思ったんで。

川谷絵音(Photo by Masato Moriyama)
―椎名林檎さんであり、あとはやっぱりピープル(People In The Box)をやってる人でもあるから、インディゴとの相性はいいでしょうね。
川谷:そう、うにさんに「僕のことなんで知ってるの? 林檎ちゃん?」って聞かれて、「ピープルの音がすごく好きで」って言ったら、「わかってるね」って言われて(笑)。
佐藤:(ピープルは)新譜も狂ってて、最高でしたね(笑)。
川谷:俺は今まで一緒にやる人を変えるんじゃなくて、自分たちで変えればいいやって思うタイプだったんですよ。プロデューサーを入れたりとかって、「誰かに何か言われたくない」って思ってたし。でも、いろんな人に会ってみると、やっぱり自分にはないものを持ってるんですよね。今回うにさんとやっても、絶対自分じゃ思いつかないようなことをやってくれて、勉強になったし、実際よかったから、もう少しいろんな人とやってみるのもいいかもなって思いました。
「やっぱり、人と一緒に何かをやるのは意味がある」
―川谷くんのワーカホリックっぷりは相変わらずだけど、アウトプットの形がこれまで以上に多岐にわたって、その分出会いも増えてるだろうから、それがバンドにもいい形で還元されるといいですよね。
川谷:この前蔦谷(好位置)さんと話をして、米津(玄師)はまだもっと若い時から蔦谷さんにプロデュースを頼んでて、その後「アイネクライネ」や「orion」なんかを蔦谷さんと一緒にやってるんですけど、蔦谷さんは最初「君は自分でできるんじゃない?」って、一回突っぱねたらしいんですよ。でも、米津はそのときの自分に足りないものをわかってて、蔦谷さんのエッセンスをしっかり奪って帰ったらしくて(笑)。やっぱり、人と一緒に何かをやるのは意味があって、海外もフィーチャリングめちゃめちゃ多いし、今回のうにさんも第5のメンバーみたいな感じでやってくれたから、こういうのも重要だなって。
―ちょうど今日蔦谷さんが「フランシス・アンド・ザ・ライツの新曲に関わってる人たちがすごい」ってツイートしてたのを見たけど、あんなに大勢じゃなくても(笑)、インディゴとプロデューサーの組み合わせも見てみたい気はする。
川谷:次のモードとして、客観的に何か言ってくれる人がいる状態で一曲作ってみても面白いかなって、今は思ってます。「5:5」じゃなくて、できれば「8:2」くらいの割合で、遠くから言ってくれる人がいたらいいんですけど(笑)。
―今回のアルバムの楽曲って、美濃さんがミックスした楽曲も含め、プロダクションはかなり面白いですよね。ここ数年「バンドは過去のものになってきた」とも言われる中にあって、打ち込みのトラックと並列に聴くことのできるプロダクションがバンドに求められるという流れもあるように思いますが、そういった視点はありましたか?
佐藤:打ち込みとか、音楽を作る形態はいろいろあって、やろうと思ったらできるわけじゃないですか? でも、今「新しい手法を取り入れました」とか、「シンセをふんだんに」「ダンス・ミュージックのエッセンスを」みたいに言ってるのは、逆にダサいっていうか。
川谷:栄太郎は、俺が「こういう感じにしたい」って言ったのを、自分の中のライブラリにトレースして、「このドラムの音にしよう」みたいなことを一曲ごとにやったらしくて。

佐藤栄太郎(Photo by Masato Moriyama)
佐藤:「あのドラマーを憑依させよう」みたいな感じですね。各々の担当してる楽器を使うことに無限の可能性があると思うし、録音にしても、マイキングしてる以上関わってくれる人によってもまったく違ってくるわけで、バンドマンはそこに行くべきだと思うんですよ。そういう行為って、「いろんな手法を取り入れました」とかよりも、もっと難しくて、尊い行為だと思うので、今回もそこに挑戦したし、みんなもっとやるべきだと思います。
川谷:具体的に言うと、「花傘」の仮タイトルは「ユーミン(仮)」で、ユーミンさんっぽい音にしようと思って、ギターは俺も長田くんも結構ラインで録ってて、アンプと混ぜたりして。「心の実」は仮タイトル「ヤマタツ(仮)」で、達郎さんみたいなカッティングを意識したり。もともと好きでしたけど、今回はもう一歩踏み込んだというか、サカナクションの(山口)一郎さんも「忘れられないの」を作る前に一回達郎さんをまんまコピーしたって言ってて、僕らコピーはしてないけど、ベースやギターの音も意識的に近づけて。とはいえ人間なんで、手癖とかも入ってきて、ちょっとずれる。それを楽しんだ感じですね。
佐藤:川谷さんがリファレンスの曲を送ってくれても、メンバーそれぞれのイメージするユーミンさんとか達郎さんってちょっとずつ違って、でもそれがギュッとなったときが面白いんですよね。
川谷:あと今回歌メロをほぼ弾き語りで作ったんですよ。自然発生的なものを待つんじゃなくて、納得いくまで考えて作って。
―あ、それはすごくでかいですね。アレンジの面白さ、プロダクションの面白さも十分あった上で、今回歌メロ自体もすごく立ってると思ったので。
川谷:それこそ、ユーミンさんや達郎さんの声を頭の中で再生しながら歌メロを作ったりして、でもやっぱりそのままにはならないんですよ。達郎さんのレコードを集めて、部屋で流して、でも曲は作らずに一回寝る、みたいな(笑)。そうすると、結局全然違うものになって、でもそれが面白かったですね。
「新しいことと、自分が前からやってることの瀬戸際というか、その一番いいところをどう見つけるか」
―後鳥さんも誰かのプレイを憑依させたりしましたか?
後鳥:ヤマタツさんはやっぱりすごく聴いたんですけど、あとたまたまプレシジョンベースを手に入れて、音を作って、それによって出てくるプレイが変わったりもして。最初はスラップのイメージばっかりだったんですけど、音が変わるとフレーズをどう展開させるかも変わってきて、寄せたり、離れたりを繰り返してました。

後鳥亮介(Photo by Masato Moriyama)
―「ほころびごっこ」のミュージック・ビデオでは5弦ベースも弾いてますよね。
後鳥:スピッツの田村(明浩)さんが同じクルーズっていうメーカーのベースを弾いてるんですけど、「使ってみる?」って連絡をいただいて、たまたまその時期に「ほころびごっこ」のレコーディングがあったんで、これも巡り合わせだと思って、使ってみました。ピープルの健太も5弦を使ってて、2人でスタジオに入って遊んだりしてるときに、弾かせてもらって、「かみさま」のコード感とかいいなって思ってたのもあります。
―長田くんはいかがですか? カッティングの話などもありましたが。
長田:カッティングめちゃめちゃ苦手なんですよ(笑)。
―確かに一昔前は単音のイメージでしたけど、ここ数年はカッティングのイメージありますけどね。
長田:必要に迫られてやるようになったんですけど「花傘」や「心の実」はまだライブは不安で、練習せなあかんなって。達郎さんも聴きつつ、the band apartをめっちゃ聴いてたんですけど、でも僕それもリードギターばっかり聴いちゃって(笑)。

長田カーティス(Photo by Masato Moriyama)
―ただ、今回のアルバムにはクリーンのカッティングの曲もあれば、歪んでる曲もあるし、「小粋なバイバイ」とかはそれこそ一昔前の単音弾きっぽかったりと、いろんなバリエーションのプレイが収められてる印象です。
長田:新しいことと、自分が前からやってることの瀬戸際というか、その一番いいところをどう見つけるかっていう、個人的にはそういうテーマで作ったアルバムかなって。カッティングはあんまりやらずに来たんですけど、ギタリストとして次のステップに行くために、そういうものも取り入れないとなって思って、「花傘」と「心の実」は結構ターニングポイントの2曲になったと思います。あと「Midnight indigo love story」は全編アコギの指弾きで、アコギもあんまり得意ではなかったので、結構練習しましたね。
―「ラッパーの涙」はまんまヒップホップというわけではないですけど、スネアの音作りとかはまさに生音ヒップホップですよね。栄太郎くんは自分のライブラリの中から誰を引っ張り出してきたんですか?
佐藤:イメージとしては、サチュレーションがめちゃくちゃ効いてる生ヒップホップで、ザ・ルーツとか、新しい方のディアンジェロ、でも一番はアンダーソン・パクの『Oxnard』のときの、ガチガチにサチュレーションかかってる感じ。最終的な仕上がりがこういう曲になるとは思ってなかったけど、それがいいんですよね。
―川谷くんもここ最近は海外のヒップホップをよく聴いてると思うんですけど、この曲ではラップもしてますね。
川谷:もともとゲスは早口で、インディゴではそれはやらないっていう分け方があったので、インディゴでこんなラップを入れたことは一度もなかったんですけど、この曲は皮肉としてやってるというか、「ラッパーの涙」っていう曲なので、だったらラップ入れた方がいいなって。だから、海外のヒップホップどうこうってわけでもないんですけど、タイラー(ザ・クリエーター)の新譜にはオオッてなって……でも、それがどうということもなく。毎回結構流れで作るので、作って行くと、「もともと何を参照してたんだっけ?」ってなることが多いんですよ。アウトロも「2小節だけジャズにしよう」みたいな感じで……プログレチックな感じは昔からあるけど、ポストロックっぽさは抜いていこうっていうのはありました。開放弦で何となくポストロックっぽくなるやつあるじゃないですか?(笑)
―アルペジオの感じね(笑)。
川谷:あの無機質な感じは安易に聴こえちゃうから、そういうのはどんどんナシにして行って、もっと有機的な歌ものというか、そっちにシフトしてきたっていうのはあって。
「普遍的な、いつの時代に聴いてもいいものにしたい」
―ポストロックは徐々に形式的になっていって、ムーブメントとしては廃れていったけど、その精神性はそれこそ2010年代のジャズ周りにも受け継がれてると思っていて。
川谷:結局時代は回るから、ビリー・アイリッシュみたいなのが出てきて、タイラーも新しいことを始めたり、またちょっと変わってきてると思うんですよね。今海外で竹内まりやさんの曲が流行ってるとかっていうのも、時代が回ってるっていうことだと思うし、そういう中でも取り上げられるような、普遍的な、いつの時代に聴いてもいいものにしたいっていう、それだけは決めてやってるかもしれない。昔のインディゴの曲って、いいんですけど、時代は超えられてなかったかなって。でも『藍色ミュージック』以降は、どのタイミングで聴いても古くないと思うから、そこは一貫してると思います。
―それこそ最初期は歌ものポストロック的なイメージだったけど、『幸せが溢れたら』が転換期の作品になって、『藍色ミュージック』からは歌謡曲的な要素と、海外の同時代的な要素をどちらも踏まえつつ、より普遍的になっていったなって。
川谷:『幸せが溢れたら』も、まだ邦楽ロック感があったというか。
―もちろん、あれはあれですごくいいんだけどね。メロディいい曲多いし。
川谷:まだ演奏面でできることが少なかったから、いろんなメロディを使ってたというか。でも、『藍色ミュージック』以降は演奏面でかっこいい曲が作れるようになって、今回はその演奏ありきで、メロディは弾き語りからしっかり考えて作ったから、すごくいいものになったと思います。
―だからこそ、最初に言ってた「良質なポップス」に、ホントの意味でなってるというか。
川谷:今回の曲って、ライブで一定の乗り方ができると思うんですよ。GREEN ROOMに行って、トム・ミッシュとかやってると、手を上げるとかじゃなくて、カッティングのリズムとかに普通に乗っちゃうじゃないですか? これまでの曲は、「ここで手を上げた方がいいのかな?」みたいになってたかもしれないけど、今回はそうじゃないゾーンに入ってきたというか、クラムボンとかくるりとかもそうじゃないですか?
―ゆったり乗ってもいいし、手を上げたい人は上げるし、自由な空間になってますよね。
川谷:クラムボンって、特に初期の曲とかめっちゃキャッチーだけど、でもフジロックみたいな場所が映えるじゃないですか? 「キャッチーなバンドがこの並びの中にいるのは違和感がある」みたいにならないっていうか。
―それは音楽的な強度がちゃんとあるからでしょうね。
川谷:80年代のポップスが今でも最先端くらいな感じで聴かれてるのも、そういうことかなって。布施明さんとかも今聴いてもめっちゃ新鮮で、「これを今の人がやったらどうなるんだろう?」とか思って、今それをやろうとしてるのが、月9の主題歌の……。
―ああ、折坂悠太くん。
川谷:そう、折坂くんが今ああいう歌謡曲の感じを一番うまくやってるなって。ナイアガラとか、はっぴいえんどが好きな若い人はいっぱいいるけど、でもその多くがアンダーグラウンドで終わってる中、折坂くんがあの感じで月9をやってるっていうのはすごいなって。(星野)源さんや米津とかは、もっと海外のトレンドを意識してると思うけど、これからどうなっていくんだろうなって思ったり。俺が今やりたいのは、大橋純子さんのバンド形態(美乃家セントラル・ステイション)がすごくて、『PAPER MOON』とかめちゃめちゃいいから、次はこれかもなって思ったりもしてるんですよね。
―じゃあ、気が早いけど次の作品はインディゴ版『PAPER MOON』?
川谷:今はそう思ってるんですけど……。
長田:実際作る頃にはまた変わってそう(笑)。

Photo by Masato Moriyama
<INFORMATION>

『濡れゆく私小説』
indigo la End
ワーナーミュージック・ジャパン
発売中
ONEMAN HALL TOUR 2019「心実」
2019年10月26日(土)大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA
2019年10月27日(日)福岡・福岡国際会議場
2019年11月8日(金)群馬・高崎市文化会館
2019年11月10日(日)宮城・日立システムズホール仙台
2019年11月15日(金)神奈川・横浜関内ホール
2019年11月17日(日)北海道・札幌市教育文化会館
2019年11月24日(日)岡山・岡山市立市民文化ホール
2019年11月29日(金)愛知・日本特殊陶業市民会館
2020年1月30日(木)、31日(金)東京・中野サンプラザホール