ライムスター宇多丸がお送りする、カルチャーキュレーション番組、TBSラジオ「アフター6ジャンクション」。月~金曜18時より3時間の生放送。

『アフター6ジャンクション』の看板コーナー「週刊映画時評ムービーウォッチメン」。ライムスター宇多丸が毎週ランダムに決まった映画を自腹で鑑賞し、生放送で評論します。
今週評論した映画は、『82年生まれ、キム・ジヨン』(2020年10月9日公開)です。
宇多丸:
さあ、ここからは私、宇多丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画時評ムービーウォッチメン。今週、扱うのは10月9日に公開されたこの作品、『82年生まれ、キム・ジヨン』。
韓国のみならず日本でも話題を集めたチョ・ナムジュのベストセラー小説を『トガニ 幼き瞳の告発』や『新感染 ファイナル・エクスプレス』のチョン・ユミとコン・ユ主演で映画化。
ということで、この『82年生まれ、キム・ジヨン』をもう見たよ、というリスナーのみなさま、<ウォッチメン>からの監視報告(感想)をメールでいただいております。ありがとうございます。
主な褒める意見は、「見ていてずっとつらかった。だからこそ、見てよかった」「描かれているのは韓国だけの話ではない。
■「とても現実的な映画でした。そこに底知れぬ怖さを感じました。」byリスナー
というところで、代表的なところをご紹介しましょう。
いろいろと書いていただいて……「うっすらと感じていた産後の女性のキャリアプラン、改めて地獄だと感じました。子供をもうける、もうけないが生まれた時から己の性別の価値としてぶら下がっており、その価値を発動すると今まで死ぬ気で築き上げたものが崩れ去る。そんな無理ゲーを働く女性は課されている。それをいろんな立場の女性を通して、いろんな地獄が多角的に描かれており、絶望しました」と。
それでまたこれも、「男性はこの映画見てもピンと来るところが少ないのではないかなとも思います。
あと本当にね、皆さんいろんな立場の方から……たとえば不妊治療をして、今現在お子さんを妊娠中という立場からのメールであるとか。あとは若い男性から、自分の母親に対してどうだったか、みたいなことのメールであったりとか、ありました。あとは、よくなかったというほうのご意見もちょっとご紹介しましょう。ラジオネーム「ヒロヤフェスティバル」さん。
「初めて投稿させていただきます。自分にはあまりよい出来の作品には感じませんでした。映画のほとんどがチョン・ユミの顔。本当にきれいな方なんで、それだけで見ていられます。もちろんコン・ユも素敵。音楽もいいですが、自分にはそれだけの映画でした。というか、少し嫌な気分にもなりました。ステレオタイプな人物描写が多くて、それってこの映画のテーマで言ってることを映画の作り自体がやってしまっているのではないでしょうか?
女性が見れば共感できる部分が多いんだろうと思いますが、それだけに、似たテーマを扱った『ストーリー・オブ・マイライフ』のように、年齢、時代、性別を超えて刺さる作品にはなっておらず、『はちどり』のような男性の描き込みも感じられませんでした」というようなご意見でございます。
■国境を越えて多くの女性たちの共感を呼んだ原作小説。その映画化は一体どうなるのか?
はい。ということで行ってみましょう。私も『82年生まれ、キム・ジヨン』、今回は、初めて渋谷パルコ8階のWHITE CINE QUINTOに行って、2回、見てまいりました。ということで、先ほどから言ってるようにですね、韓国本国で2016年に出て社会現象になった、チョ・ナムジュさんによる大ベストセラー小説。日本でも、2018年末に斎藤真理子さんによる翻訳が出て、やはり異例の大ヒット。この番組でもね、その斎藤真理子さんご自身をお招きして、2019年2月の韓国文学入門であるとか、何度となく取り上げて、話題にしてきました。
ざっくり言えば、ある平凡な女性……普通の女性ですね。先ほどのメールにもあった通り、何か特別なこと、特別なひどいことが起こる、というわけではない。ある平凡な女性が、成長し、就職、結婚、出産と、人生の様々なステージを経験していく中で直面することになる、まあ社会の中に浸透しきってしまっている、性差別の現実。で、それはその、韓国社会のみならず、残念ながら我々が生きているこの日本社会にも、諸々完全に当てはまってしまうようなもので。
だからこそ、国境を越えて、そうした日常化した、習慣化したと言ってもいいかもしれませんが、性差別に傷つき、疲弊していくその主人公キム・ジヨン……「キム・ジヨン」っていうのは、82年に生まれた韓国の女性の中で、最も多かった名前、という。要するに、あなたでもあるし、あなたの話でもあるよ、という名前、キム・ジヨンに、韓国の女性だけではなく日本でも、国境を越えて多くの女性たちの共感を呼んだ。
さらに我々男性は、その自分たちのわかってなさ加減とか、あるいはその冷淡さ、というものを、改めて突き付けられて。特にその「自分はわかってるつもり」という男性でさえ、本質的には……っていう、この小説のラストの切れ味ですね。わかってるつもりで話してるやつでさえ、こうだっていう。本当にですね、もう、うううっ……と、ドキッと、身がすくむような思い(を男性はする小説)でもあり。一部にはね、逆ギレ反応も生んだりなんかもしたというね。
これもね、特に韓国の男性の場合はですね、兵役義務があるということで、それゆえに、フェミニズムに対する独特の歪んだ反発を生みやすい土壌がある、なんていうのも聞くと、ああなるほどな、なんて思ったりしますけど。とにかく、そんなちょっと一種、小説自体が特別な存在ともなっているこの中でですね、その映画化というのが一体どうなるのか?っていうのは、原作ファンとしては当然やきもきするあたりで。
■「小説と映画は全く別の方向に陣を張り、あらゆるタイプの感受性を包囲した上で、『キム・ジヨンを理解せよ』と突きつけてくる」(by山内マリコ)
特に、割とね、そのハートウォーミング風なトーンのメインビジュアル……ポスターなんかも、あったかい感じだし。そんなのを見る限りでは、ひょっとしたらその、原作のメッセージを甘口の人間ドラマでコーティング、覆い隠してしまっているパターンか?っていう危惧がわいてくるのも、これは無理からぬ話で。
そのあたりのこともですね、あの、今回の映画パンフ。劇場で売っているパンフ。デザインも素敵だし、読みごたえのある記事も多いこのパンプにですね、小説家の山内マリコさん……山内マリコさんはこの番組、3月24日に、「若尾文子映画祭特集」にお越しいただきましたけども。山内マリコさんが寄稿されているそのレビューにも、それはしっかりと書かれていて。
これは要するに、こういうちょっと辛口の視点というか、ちょっと違う視点をこの公開劇場で売るパンフに載せる、配給会社のフェアさというか、度量もなかなかなものだな、と思いますけども。で、結論から言えば今回の映画版『82年生まれ、キム・ジヨン』。たしかに原作小説とは、当然のことながらアプローチは異なっていますし、一見ソフトな、甘口な語り口になっている、ようにも見える……これ、映画版だけ見た人は、「えっ、これでソフトなの?」って思うかもしれないけど。小説と比べるとだいぶソフトなんですけども、まあそういう風に見えてもおかしくない作り、ではあるんですが。
しかし、そのパンフの文の中で、その山内マリコさんも見事な表現で言ってますけどね。「小説と映画は全く別の方向に陣を張り、あらゆるタイプの感受性を包囲した上で、『キム・ジヨンを理解せよ』と突きつけてくる」という。これ、見事な表現だと思いますね。つまりその、両面から攻めてくる。両面から挟み撃ち。これが本当の「挟撃戦」!っていうことなんですね。『TENET テネット』の挟撃戦はあんまり意味がよくわかんなかったですけど(笑)、こっちの挟撃戦はよくわかる。
あるいは、原作を翻訳されたその斎藤真理子さんも、パンフとか、あるいはその(月曜パートナー)熊崎風斗さんも寄稿された『LEE』の記事などでですね、こんなことを言っていて。小説は男性の医者がつけているカルテ、というテイを取ってるんですけども、今回の映画は、ひとつの「処方箋」を示している。(原作小説が提示した)カルテに対して、処方箋を示している、という風におっしゃられている。このように、要は原作の物語と問題意識に、また別の角度から光を当てることで、小説とは違う……しかし、それはそれで重要だったり味わい深かったりする要素、というものを浮き上がらせてみせたのが今回の映画、という風に捉えるべきなんじゃないかと、僕も思います。
むしろ、その火曜パートナーの宇垣美里さんが指摘したように、一見ソフトに、甘口にも見えるからこそ、実はより問題の根深さ、その絶望が際立っている、という読み取り方も全然できる作りだったりする。なので、今回の映画から見た人はもちろんぜひ、そのまま原作小説にトライしていただきたい。そうすれば、この物語が伝えようとしていたことのさらに本質であるとか、巨大なその事実の背景、っていうのに触れることができる。
■小説より登場人物たちにはっきりとした「顔」が与えられている
たとえば、その元の小説。先ほど(番組オープニングで)も言いましたけど、元の小説のドライなタッチを際立てている、実際のデータ群ですね。データを示す。社会そのもの、システムそのものが、巨大な矛盾、罠として、女性の人生の目の前にいちいち立ちはだかってくる、という感じ。これは本当に何より小説で味わってほしいですし。一方、その原作小説を先に読んで映画をまだ見てないという方は、劇中の人々に、ひとつひとつのはっきりした「顔」が与えられるわけですね。この映画版で初めて、その心情的に親しみを持って寄り添える人物たち、というのもいくつか現われてくるのではないかと思いますね。
それでですね、特にやっぱり印象的なのは、コン・ユさん演じるジヨンの夫のデヒョンという人と、キム・ミギョンさん演じるジヨンのお母さんのミスクという。これ、要するに小説版と違って、この主人公ジヨンの現在が、現在進行系の話がメインになるので。当然、まあダンナがいる比率が高くなる、っていうのはもちろんありますし。
その、言葉による心情説明というのがいちいちはされないがゆえに、彼女のそばで、「彼女を見ている人」の視線っていうのが、語り部的に重要になってくる。それゆえにこの夫の視点と、そしてジヨンのお母さんの視点、というのが非常に……役柄的な比重、人間味が、小説よりだいぶ増している、ということ。これが今回の映画版の特徴と言えると思うんですけど。
まず、その夫デヒョンですね。このジヨンを演じるチョン・ユミさんとコン・ユさんというのは、先ほども名前を言いましたかね、『トガニ 幼き瞳の告発』。これ私、2012年9月8日に評しました。これ、本当に社会派エンターテイメントの大傑作ですけど。『トガニ 幼き瞳の告発』だとか。あとは、みんな大好きゾンビ映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』など、要はある種、コンビ的な役柄で共演してきたことで知られる2人というか。コンビ感があるっていうか、パートナー感がある2人なので。
で、実際にそのコン・ユさん、『トガニ』でも遺憾なく発揮された、その見るからにいい人感500パーセントの、この「戸惑いながらも状況に向かい合おうとする」っていうその視線とか、たたずまいの説得力、というのがむちゃくちゃあるわけですね。ただ、しかしそれがですね、その『トガニ』とかではその真摯な姿勢、戸惑いながら状況に向かい合おうとするその真摯さっていうのが、非常にプラスなキャラクターとして働いているんだけど。
これが本作ではですね、それだけむちゃくちゃいい人な、わかってくれようとしている夫でさえ、実際のところの理解のレベルはこんなもの……という、まさにその宇垣さんがおっしゃっていたような、むしろその女性側の絶望を深める仕掛けとして、このコン・ユさんというキャスティング、そしてその演技が、割と最後の方まで機能し続けるわけですね。だから、僕とか男性観客は、作品からずっと問われ続けてる感じなんですね。要は、「お前、これなんでダメか、わかる?」「こいつ、なんでダメか、わかる?」「すいません……わかってませんでしたっ……!」みたいなのが続く、というね。非常に居心地が悪い思いを ──これは当然していいんですけど──するような作りになっているという。
■コン・ユの醸し出す「消極的な善意」が表す、社会構造の限界
で、これは作り手としても、はっきり意図的なバランスだったようでございまして。たとえばですね、『FRaU』の、桑畑優香さんによるキム・ドヨン監督のインタビュー。ちなみにこのキム・ドヨン監督 ……ちょっと説明が遅れましたけど、キム・ドヨンさんは、48歳にして本作が長編映画監督デビューとなる、女性ですね。元々俳優をやったりとか、短編の演出なんかもしてたんだけど、子育てでキャリアを断念して、 2017年になって大学院に入り直して映画を学んだ、っていう人なんですよ。すごくないですか?
そのキャリア自体がキム・ジヨンと重なる、というか。だから、本作の映画化にこういう人をキャストする、置くっていうこと自体が、すごいと思うんですよね。で、とにかくそのキム・ドヨン監督への桑畑優香さんによる『FRaU』のインタビューによると、コン・ユさんとの話し合いの中で、「夫デヒョンを悪者にはしていけないという結論になりました。なぜなら、キム・ジヨンが心を患ったのは、周りに悪い人がいたせいではないからです。社会の構造や家父長制的な雰囲気、周りの視線、そういった空気のせいではないだろうか? デヒョンをはじめ、周りの人を悪者にしないほうが、作品のポイントをより正確に描けると思ったのです」というようなことを言っている。
で、コン・ユさんとも事前にすごく話し合った中で、「自分も気付かない雰囲気や価値観から抜け出すことができない夫。彼が優しい人であっても、社会の構造の中では限界が存在するのではないか、という話をコン・ユさんとした」ということを言ってるわけですね。なので、今回のその映画版では、夫側の社会的立場っていうのも、小説よりは同情的にというかね、描かれているわけですね。夫側は夫側で、要するに「お前、育児休暇を取っても、帰ってきた時にはお前の居場所、なくなってるよ?」なんてひどいことを言われるわけですね。
で、やっぱりここがですね、さすが『トガニ』主演のコン・ユさんというか。作品選び、役選びの、意識の高さを物語っていますよね。つまり、明らかに自分が損をしかねない、自分が今までいい人役でちゃんと売ってきたものが、全部ひっくり返りかねない役を……そのいい人演技も嘘っぽく見えかねない役を買って出てるわけですね。「これは大事な作品だから」って。だからコン・ユさん、やっぱりこれは株が上がりますよね。
で、とにかくコン・ユさんの醸す、僕の表現で言う「消極的な善意」とでもいうようなそのムードが、本作ではその過去作と180度違う、非常に鋭い効果をあげている、という風に思います。「手伝うよ」って何だよテメェ? とかさ。あとあの、「君もちょっと休んだ方がいいから」って……あんた、育児が「休み」だと思ってるんですか? とかね。「僕も本とか読めるし……」とか(笑)。テメェナメてんのか? みたいな、あの感じ。結構最後の方までそれが続く、っていうね。
また、キム・ジヨンの母ミスク。原作でも、彼女が男兄弟のために人生のいろいろを諦めざるを得なかったという……時代の関係もあって、それを諦めざるを得なかったこと、それでも常にたくましく一家を支え、時には夫に激しく抗議したり、余裕で言い負かしたりもするすごい人なんだ、っていうのは描かれていたんですけども。この本作、映画版では、「せめて娘には自分と同じ轍は踏んでほしくない」という彼女の思い、自分の好きなように生きてほしいというそのお母さんの思いが、主人公キム・ジヨンの、その「憑依」ですね……いろんなその女性の立場になり代わって話し始めちゃう。そして自分ではそれに気づいていない、という現象が起こってしまうわけですけど、それが単に病気、心の病というよりは、あたかも様々な世代、さまざまな立場の女性の心の声の、代弁のように響く、というのとも、そのお母さんの視点が共鳴して。よりはっきり、エモーショナルに演出されている、ということだと思います。
この、お母さんから娘への、その「せめてお前の世代では……」という思い。そこを娘を見つめる視線に託す、というあたりは、やっぱりあの、7月20日に評したばかりの、『はちどり』とも重なるあたりかなと思いますね。その、家父長制の理不尽な抑圧の中で、お母さんが娘に託す思い、というところ、非常に通じるところはあるかなと思います。あの家族の描き方……お父さんとか弟、男兄弟の描き方、かなり『はちどり』と通じますよね。
■随所に用意された映画的な語り口、演出もしっかりと活きている
ともあれ、その意味で、この夫の視線と母の視線というのが、目の前で「発症」するジヨン、というその1点に注がれ、交わる、後半のあるシーンがあるわけです。これ、映画オリジナルのシーンでもあるこの場面が、本作のその、映画的なハイライトと言ってもいいのかもしれませんね。まあ、ここで描かれているのはやっぱり、その性差別とか家父長制っていうシステムは、結局男側も含めて誰も幸せにしてないじゃないか?っていう。これも『はちどり』でも描かれてましたけど、明らかに誰も幸せになってないシステムとして、それがはっきりと三者の立場で浮かび上がる、という場面。あれ、素晴らしかったですね。映画的な語り口。
映画的な語り口という意味ではですね、基本、時系列順である原作と違って、時制が時折前後するこの映画版の構成、というのがあるわけです。それゆえに、たとえば僕、一番強烈だったのは、あの会社内で、とある事件が判明しますね。これ、ちょっとネタバレしないように一応伏せますが。要はその、性犯罪とポルノの境目がついていないかのような、男性社会のおぞましい目線。これ、残念ながら、現実にめちゃめちゃあるんだよな……やっぱりこれは、最悪だよね。
というそのエピソードからですね、ジヨンが学生時代に経験した、男性のその一方的な性的目線の恐怖……しかも、そこで怒られるのはなぜか自分、って理不尽な出来事。どちらも原作で描かれていることなんですが、それらを繋げて語ることでですね、女性がいかに、常に恐怖と不信を抱えながらこの男性優位社会で生きていかなければならないか、というのを、わかりやすく鋭く突きつけていて……うーん、本当に男性としては、本当に情けなく、申し訳なく。改めてね。
これは……こんな思いをして、トイレひとつ行けない。なんてひどい世界に……っていうのは、頭ではわかっていたつもりだけど、やっぱりこうやって、感情的なレベルでも突きつけられて。これで(男性側が)つらくなるのはいいことなんですが。「おげえ……」となるところでございました。このへんなんかも、映画ならではの語り口が非常に生きてるあたりと言えると思いますね。
あと、そのジヨンが、かつて働いていた頃の記憶に、一気に場面がジャンプする瞬間なんかも、非常に映画的に、鮮やかな場面演出だったんじゃないでしょうか。あとはね、映画っぽい語り口って意味では、美術なんかもすごく印象的で。一番多く舞台となるのはもちろん、そのジヨンの自宅のマンション。キッチンがあって、リビングがあって、その向こうにベランダがある、っていう普通の作りなんだけど。
特に印象的なのは、キッチン側にいても、リビング側にいても、ジヨンはいつも、家事とか育児などに追われていて、どっち側にも……リビング側にいてもキッチン側にいても、何かしら家事とか育児で追われていて、彼女だけが孤立していて。で、その別の部屋にいる家族は、なんか呑気にくつろいでやがる。で、彼女がそことも遮断……家庭と遮断できるのは、そのリビングの向こうのベランダだけ、っていう、そういう造りになってる。家にいても、くつろいでいるようには見えない。
これが、照明なども含めてはっきりそういう風に、彼女の孤立っていうのを、そのマンションの空間の、部屋の中だけで見せる、っていう。これは非常に巧みな……これはキム・ドヨンさん、劇場デビュー作品として、なかなか堂々たる手腕じゃないですかね。こういう風に、あくまで彼女の置かれている状況とか心情を映像的に伝える、映画ならではのヒリヒリとした演出も、しっかりと活きている。
■原作からの改変は「小説が書かれたことがムダではなかった」という思いを込めたかったのではないか
ということで、原作小説にあるさまざまな要素。たとえば「最初の女の客は嫌がられる」っていう、本当にひどい迷信であるとか。算数の問題を解き続ける、本当は学歴がしっかりある主婦の話であるとかを、あちこちに再配分しつつ……本作は、原作ファンからはやはり、ちょっとここは評価が分かれてもおかしくない、大きな改変をしています。
特に終盤、エンディングに向けて、大きな改変が行なわれてます。もちろん、原作ラストの圧倒的なまでの切れ味、絶望というのは、本当にすさまじいし。もちろん、その性差別的な状況が解消されたわけでも何でもないわけですから、「絶望のまま終わるべきだ」って言うのも、これはごもっともだと思うんですけども。ただ、その原作小説だと、ジヨンの心の傷がまさに一線を越えてしまう、その「憑依」的な症例を発してしまう、そのきっかけとして出てくる、韓国のとあるネットスラング……子育て中のお母さんに対する、非常に悪意ある蔑称。
それがこの映画では、逆にジヨンが、もう我慢しない、声を上げる、きっかけとして置かれているわけです。非常に対照的な場所に置かれているわけですね。で、これは僕の読み方、僕の捉え方だと、原作小説が書かれた2016年と、この映画が作られた2019年の違いを、作り手はやっぱり、込めたかったんじゃないか?
つまり、それこそ原作に対する反響であるとか、あるいは世界的なMeToo運動の広がりっていうのを、作り手としてはやっぱり、「2019年であれば、2016年の結末よりは先に進んでいるし、進めたいじゃないの」っていう風に……僕は取りました。
つまり、まずは女性たちが声を上げる……「名前のない女たち」じゃない。あんた、私のこと知っているの? 「お母さん」って一般化して言うけど、私にはちゃんと自分の名前があって、自分の物語がある、という。そこまでのその違和感、その痛み、その怒りを表に出すこと。それがこの『82年生まれ、キム・ジヨン』という作品が示した希望なのだ、という。
だからこそ、まさに『82年生まれ、キム・ジヨン』の物語が吐き出される瞬間で終わる、っていう、ちょっとメタな構造の終わり方になってますよね。要するに、その現実に向けて、もう1回、希望を持って開かれる、というか。そういう終わりにしているのは、たぶんその作り手が、もう1回映画として語りなおす、それは(原作の出版から)3年経っているんだから、その反響があったという……つまりその、小説が書かれたことがムダではなかったということを、映画そのものが示すべきだ、というのを、この改変に込めたのではないか、という風に私は読み解きました。
といったあたりで、もちろん女性の方が見れば、立場を超えて、共感を持って見ることでしょうし……特に俺ら男性はですね、基本何もわかってないこと、自分らの加害性、諸々を、一旦わかる入口に、とば口に立つ意味でも、全員まずはこの、映画版から見るべきではないでしょうか。少子化対策とか言ってる時に、くそトンチンカンなことを言っているような政治家の方とかは、特に見るべきではないでしょうか。原作と合わせてぜひ、ということでございます。ということで、もう1度言います。「これが本当の挟撃作戦!」(笑)。ということで、ぜひぜひ劇場で、原作小説と合わせてウォッチしてください!

(ガチャ回しパート中略 ~ 来週の課題映画は『異端の鳥』です)
以上、「誰が映画を見張るのか?」 週刊映画時評ムービーウォッチメンのコーナーでした。

◆10月16日放送分より 番組名:「アフター6ジャンクション」
◆http://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=20201016180000



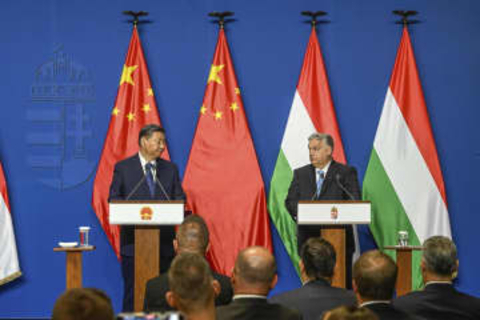



















![『ゴジラ-1.0』 2枚組 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41lU7cnz6-L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】劇場版 ポールプリンセス!! Blu-ray Disc <特装盤>(特典:L判ブロマイド4種セット+缶バッジ ) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51UrfeqtsRL._SL500_.jpg)







![[山善] 32V型 ハイビジョン 液晶テレビ (裏番組録画 外付けHDD録画 対応) QRT-32W2K](https://m.media-amazon.com/images/I/516WFLybmIL._SL500_.jpg)
