《暮しの手帖》1968(昭和43)年8月に出た第96号の1冊をまるまるあてた特集『戦争中の暮しの記録』がそれ。
『戦争中の暮しの記録』
その特集は大きな反響を呼び、増補されて、翌1969(昭和44)年8月に、改めて単行本『戦争中の暮しの記録 保存版』として刊行された。
花森安治の編集者魂が炸裂する戦時証言集は、いまも版を重ねるロングセラーだ。
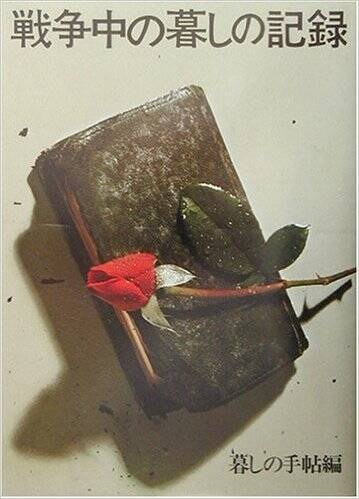
『とと姉ちゃん』のなかでは、1974(昭和49)年ごろ、心筋梗塞で2度目に倒れる直前にとりかかったことになっている。
モデルとなった現実の特集はその6年前に出ていた。花森安治は、この特集号を出して半年後に初めて心筋梗塞で倒れ、さらにその半年後に単行本化されていることになる。
戦争が終わってから生まれたベビーブーマー(のちに堺屋太一が年金制度破綻を予言した連作SF『団塊の世代』で描かれたジェネレーション)のうち、大学生の一部が学生運動に身を投じていった時代だ。

インターネットなき時代に一般人の証言を集めるということ
『戦争中の暮しの記録』は、《暮しの手帖》の呼びかけで、読者に募集した投稿記事によって、全篇が構成されている。
第二次世界大戦が終わって20年以上たち、未曾有の長期好景気に浮かれている日本の現状に、花森安治は危うさを感じていた。
戦争を記憶している一般の人々の証言を、その記憶がまだ鮮明なうちに送ってほしいと、《暮しの手帖》は募ったのだ。
インターネットがなかった当時、市井の人々の発言を集めるのは容易ではなかった。
応募総数1,736篇という数字は、どの号も80万部以上出ていた(「保存版あとがき」による数字)《暮しの手帖》だからこそできた偉業だ。
そのなかには、40歳とか50歳を過ぎてはじめて、作文らしい作文をしたと思われる記録もあったという(花森安治「あとがき」)。原稿用紙の使いかたもわからぬまま、金釘流の文字、誤字当字だらけの、文の形をなさない文のつらなりを送ってきた人たちも多いという。
多くの人がスマートフォンでSNSに文章を投稿する時代とはずいぶん違うのだ。
〈夫の出征中に強制疎開でついに廃業〉(横浜市・森井勢以)
〈タンスをお棺に〉(愛知県・宮治千枝子)
〈おやつがわりの食塩〉(武蔵野市・森川玉江)
〈聞いたこともない親戚がふえる〉(佐賀市・田中仁吾)
〈無理に疎開させた子が疎開先で爆死〉(高岡市・柿谷実子)
など、編集部がつけた見出し・小見出しを見るだけでも、日本史年表では伝わってこない戦時下の生活が伝わってくる。
できごとだけでなく
生活のディテールは、こういった「事件」「できごと」だけが伝えるのではない。
戦時下ならではのモノや風俗が書きとめられているのも、この特集の強みだ。
もともと東北の農村の仕事着だったというもんぺが、女性の国民服のような存在になっていった。
もんぺや防空頭巾、背嚢(リュックサック)、雑嚢(救急用品などを入れた大きめのショルダーバッグ)、防火演習用の鉄兜(ヘルメット)と防毒面(マスク)といったグッズ、教科書が足りないので丸写ししたノート、米つき棒(玄米を一升瓶に入れてついて精白する。ハタキの柄などを利用)……
そういうものがあった、ということは、逆に当時は、平常時にあったさまざまなものがなくなっていった、ということなのだ。
グラフィックの説得力
この本の魅力はこういった率直な証言だけではない。
『戦争中の暮しの記録 保存版』は、《暮しの手帖》の判型を単行本でもそのまま活かした大判のヴィジュアルブックでもある。
巻頭グラビアとして置かれたのは、降りかかる白い発光体によって光って、いや、燃えている町の見開き写真。
これに続いて、校舎が焼け落ちてしまったために、空の下で執り行われている卒業式の写真。
教室風景では、学徒の身で出征した生徒の机のうえに
〈出陣 深川嘉郎君 昭和十八年十一月一日〉
などと書いた三角錐の札が置かれ、同様の不在の机はひとつの教室にいくつも見られる。
エディターシップが炸裂!
火と灰と血に満ちた記録のなかにも、どこかユーモラスで生き生きした記事もある。
石井園江(静岡県)と高木ちよ(東京都)という、戦時中に産婆をしていたふたりの投稿をまとめた「産婆さんは大忙し」という記事など、産湯の燃料にも困るなか、予定日より早く産気づいた、などといった切羽詰まったケースが回想されているが、戦時下だって人は生まれるのだ、という当たり前のことが、読んでてなぜか心強い。
こういったハードな内容ながら、ページの構成は当時の《暮しの手帖》どおりの洗練されたエディターシップが炸裂し、動きのある誌面構成で読者の注意をうまく誘導する。
大判の本でありながら、組んである活字はけっこう小さい。最近の新聞より小さく感じる。「読み応えがある」程度の分量をはるかに超えている。
若い世代はどう読んだか
《暮しの手帖》編集部は、第96号の特集刊行後、1968(昭和43)年8月20日前後の新聞で、若い世代からの感想文を募集した。
これにも1,215篇の応募があった。出てくるのがすごい数ばかりなので、もういちいち驚いてられないけど、ウェブのフォームに打ちこんで送信するのではなく、紙に手書きの時代だったと思い返すとやっぱり感心する。
これらのなかから22篇、上は1938(昭和13年)生まれの30歳から、下は1959(昭和34)年生まれの小学校3年生までの感想文が、『保存版』の附録として収録されている。
もうひとつの附録は、その感想文を読んだ戦争体験世代(当時38歳から70歳)が、その若い世代へのレスポンスとして書いた文章20篇。
〈苦しかった戦時の生活が分ったという若い世代の声をよみました。
ほんとに分ったのかな、と疑りっぽい私は思います〉
と述べるのは大和市在住の55歳。
けれど小学校3年生の政本あかねは、感想文にこう書いていた。
〈父や母は、戦争を知らない人が、この本だけで戦争を知るのはむずかしいだろうと話し合っています。
(太字強調引用者)
カッコいい。
戦争にせよなんにせよ、たいへんな経験をした人が、「あなたのたいへんさがわかりました」と言われたときに、「経験していないあなたにホントにわかるのか?」と疑いの言葉をかけるのはそういう人の心の叫びだから、心中お察し申し上げるにやぶさかではない……けど、そういう「わかる」の高いハードルを他人に要求(しつつ〈やっぱりわかっちゃいない〉と慨嘆)する大人よりも、スカッと
〈わからなくても読む〉
と宣言する若い人のほうが頼りになるね!
ものごとをたくさん知ってるかどうかじゃなくて、自分が知らないことを知らないと自覚して知ろうとするかどうかで、人のカッコよさって決まる。これ、『保存版』の附録に教えてもらいました。
(千野帽子)




























