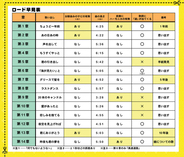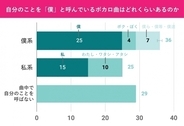Text by 山元翔一
Text by 原雅明
Text by 沼田学
Text by BAROOM
近年、YouTubeやストリーミングサービス、SNSの普及を背景に、環境音楽やシティポップ、あるいは現行のポップミュージックの領域においても、日本の音楽家たちによってつくられた音楽が海外のリスナーの耳に届くケースは珍しくなくなった。海の向こう側の彼ら彼女らは日本から生まれた音楽に、どのような眼差しを向けているのか。
「静寂の次に美しい音(The Most Beautiful Sound Next To Silence)」をコンセプトに掲げ、ヨーロッパを代表するジャズレーベル「ECM Records」。送り出された作品数は1,700を超えるが、「ECM」の55年の歴史において日本人ジャズミュージシャンによるリーダー作品は3作しか存在しない(※)。本稿ではその3人のうちの2名、福盛進也と田中鮎美に話を訊いている。
2015年に逝去した菊地雅章を含めた3人の音楽が、ヨーロッパの名門レーベルの審美眼にかなった要因は何だったのか。グローバルな音楽市場で通用する「表現」に必要なものは何か。
ーまず、お二人が海外に行こうと思った背景から教えてください。
福盛:僕はDeep Purpleが好きなロック少年で、もともとイギリスで音楽の勉強をしたいと思っていたんです。なんですが、留学をサポートしてくれた団体がイギリスとの交流があまりなくて、テキサスのブッカー・T・ワシントン芸術高校に行きました。そこにはエリカ・バドゥとかロイ・ハーグローヴ、ノラ・ジョーンズが僕らのちょっと上の世代にいました。その留学がきっかけでアメリカに行ってそのまま10年間住んで、バークリーを出てミュンヘンに移って、という感じです。

福盛進也(ふくもり しんや)
1984年1月5日、大阪市阿倍野区生まれ。15歳でドラムをはじめ、17歳のときに音楽を学ぶために単身で渡米。2018年、自身のトリオで「ECM」からリーダーアルバム『For 2 Akis』を発表。2020年、自身のレーベル「nagalu」を立ち上げ、アルバム『Another Story』をリリースする。2021年には第2のレーベル「S/N Alliance」も設立し、プロデュース業や録音のディレクションにも力を入れ、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込んでいる。
田中:私は日本の大学を卒業後、即興演奏やジャズをやりかったんですけど、私が行動した範囲では自分のやりたいジャズも居場所といえるところも見つけられなくて。
そのあと友人をきっかけにスウェーデンに1か月ぐらい滞在したんですけど、そこで見た大学生のコンサートがすごく自由だったんですね。そのとき「自分らしくいていいんだ」と思うことができて、スウェーデンで勉強したいと思ったのですが、授業料の都合で隣国のノルウェーの大学を受験したのが最初のきっかけです。当時、ノルウェーの大学は授業料がいらなかったんです。
―海外に行かれたことで、日本で自分の居場所を見つけられなかった理由はわかりましたか?
田中:当時の私も、自分が心にピンとくる音楽をしないといけない、せずにはいられなかったんだと思います。日本にいた頃、「ビバップを勉強してこい」と言われて自分なりに学ぼうとはしたんですけど、その当時は全然心に響かなくて。
スウェーデンやノルウェーの学生に会ったとき、ジャンルやスタイルにとらわれず、誰もが個性豊かでそれぞれがいろんな方向を向いていて清々しく見えました。それで私も「正直にいなきゃいけないんだ」「自分の心に響く音楽をしないと」ということに気づいたというか。

田中鮎美(たなか あゆみ)
ノルウェー在住のピアニスト、作曲家。2011年8月よりオスロにあるノルウェー国立音楽院のジャズ・即興音楽科にて学び、学士号と修士号を取得。2016年にアルバム『Memento』でデビュー。トーマス・ストレーネンのプロジェクト「Time is a Blind Guide」のメンバーとしてアルバム『Lucas』(2018年)、ストレーネンとのトリオ作品『Bayou』(2021年)に参加。
ー福盛さんはアメリカの高校に入ってから、ジャズやほかの音楽に関していろいろ学んだのですか?
福盛:日本にいるときは音楽をちゃんと学んだことがなかったですね。ドラムをはじめたのは15歳で日本の高校にいるときでしたが、音楽というものをしっかりと勉強しはじめたのがアメリカで、芸術高校に1年通い、そのあとESL(※)のコースを受け、コミュニティカレッジと4年制大学で音楽を専攻し、バークリーも行き、いわば叩き上げというかアメリカで全部経験してきた。
だから日本で大学卒業後にバークリーに行くのとはまた感覚が違うかもしれないです。特にバークリーに通ってた時期はプライドがすごく高くて、日本から来た学生に対して「こいつらと俺は違う」とずっと思ってましたし、「俺はもうアメリカ人だ」って思いながらやってました(笑)。
ーアメリカでやっていく自信はどうやってついていったのでしょうか?
福盛:何にも考えてなかったというか、自信がないことがないというか(笑)。
ー学んでいった過程で特に影響された人はいますか?
福盛:コミュニティカレッジで教えてくださった先生は僕にとって恩師ですね。もう自分の息子のように接してくれて、手取り足取り、ドラムを基礎から全部教えてくれたのですごく感謝しています。
あとは単純に、入学した芸術高校がアメリカでトップクラスのジャズの高校だったので、周りからすごい影響を受けました。当時、Souliveが流行ってたからジャムバンド的なものを真似してやったりして、そのなかで即興、アドリブの楽しさを覚えていった。そのうちもうちょっと掘り下げたいと思って、僕は特にハードバップが好きだったんで、そのあたりをずっと聴いていました。
ーアメリカでそのままずっとやってくつもりだったのでしょうか?
福盛:そうですね。ニューヨークにいつか行きたいとは思っていたんですが、大都市すぎて自分には合わないって結構早い段階で興味が薄れてしまって。自分のペースを守って生活できないというか、すごく窮屈に思えて。あと、臭かったですね(笑)。ニューヨークで生きていけるって絶対的に思えなくて、もう感覚的に違うなって思いました。

ー福盛さんはその後ドイツに渡りますが、ヨーロッパに惹かれたきっかけは?
福盛:完全に「ECM」です。バークリーの「ECMアンサンブル」という授業で、譜面上にない行間の美しさみたいなものを表現してる人たちがいることを初めて認識して、すごいハマったんですね。自分がそれまで思い描いていた音楽とはまったく別の自由度の高さがあった。
ケティル・ビヨルンスタの『The Sea』(※)でドラム叩いているヨン・クリステンセンは、「こんなドラム、聴いたことない」と衝撃を受けました。拍があるけど、拍がないというか、拍のうえで何を表現しているんだろうと考えさせられる。それが一番のきっかけですね。
ー今回お二人に話を伺うにあたって、「自分の音楽をやる」「自分の音を見つける」ということがジャズに限らず、ほかの音楽の世界でも問われている状況について顧みたかったのです。特に日本では、西洋の音楽から影響を受けて、そのなかで音楽をつくっていると、自分のオリジナリティーを発揮するのが難しい側面もあります。お二人は海外にいたことで、そういったことに対してどう考えてきたのでしょうか。
田中:ノルウェーに行ってすぐ、「ここは自由に何やってもいいけど、自分のやりたいことを深めないと何者にもなれないよ」と、少し上の先輩に言われて。オリジナリティーを持つことが当たり前で、必要とされている感じだったんですよね。
学校の雰囲気も「自分の音を見つける」「自分のやりたい音楽を深める」ってことに自然な形で、焦点が当てられていました。ジャズ科のなかでも、ジャンルにとらわれず学生それぞれが全然違うことを当たり前にやってるし、何でも器用にできることが素晴らしいという考えは全然ないんです(※)。

田中:オスロではジャズを普通に巧く弾ける人もいて、そういうアメリカのスタイルのジャズが好きでやってる人は「オスロ・ミュージシャン」って呼ばれていて、オスロを出たら演奏する機会がないっていう意味。それは技術やスタイルに目が行き過ぎていて、でも「個性」がないからなんですよね。ビールとか飲みながらラフに楽しめる感じの場所もあるので、そういう人もミュージシャンとしての需要はあるんですけど。
ー一人ひとりのなかにある「自分のやりたいこと」というのも、単に新奇なものを見つけ出すことではなく、何かに根ざしてはいるわけですよね。それは何なのでしょうか?
田中:私は「やりたいこと」よりも「やれることは何か」をすごく考えたかもしれないですね。やれることは何か考えたときに、「自分は一体誰なんだ?」というところからはじまって、自分は何が得意で、何が好きでとか……もう亡くなってしまったピアニストですけど、私の先生のミシャ・アルペリン(※)は、私が好きな音楽を持っていくと「そこにないものは何? そこにないもので音楽をつくりあげなさい」と言いました。
たぶん、自分が好きなものが一体何なのかを自覚させたかったのだと思うんですけど、「自分が好きなものは何か」「自分は何者なのか」とか、そういったことをじっくり考える時間が学生の頃にはあって、それで「自分はこれができるから、これを深めよう」って考えることができたんだなと思います。
田中:たとえば私の場合、ジャズの速いパッセージを弾いたり、フレーズを学ぶことがどうしても苦手だったので、これはできないことだから横に置いておいて。逆に自分が好きな現代音楽のハーモニーを勉強したり、好きな作品を分析したり、できることを深めていきました。そうやって自分自身に向き合っていった先で、探し求める音楽表現につながっていくというプロセスでした。
一度、アンデルス・ヨルミン(※)というミュージシャンにレッスンを受けたときに、「ジャズを弾けるようになったほうがいいんじゃないかなと思うんですけど」って相談をしたことがあって。そしたら「人生は短いし、そんな全部何でも習得するほど時間がないよね」ってニコって言ってくれて、その言葉は大きかったし、おかげですごく楽になりました。
福盛:僕も同じでやれることをやってきたし、トライアンドエラーばっかりです。そんな万能に何でもできるタイプでもないし、苦手なものは一切避けてきて、いつの間にかこうなってた気はしますね(笑)。
―田中さんの場合は周りのコミュニティで共有されている意識みたいなものからも影響があったのでしょうか?
田中:そうですね。学生のときは学校のなかのコミュニティ、徐々に先輩ミュージシャン、年上の人たちとも一緒に演奏するようになって、そこでも個性を大事にした音楽づくりを目指す意識が共有されている感じはすごくありましたね。
ノルウェーには助成金などを受け取れる機会も多く、それによって音楽制作に時間とお金を使うことが許されるということも、豊かな音楽を育てる役割を果たしているかと思います。それはミュージシャンの話だけではなく、ジャズクラブなどの会場、音楽フェスティバル、レコードレーベルなども政府から支援を受け取っているところがほとんどです。
それによって、イベントを企画する側、アルバムを制作する側も、商業的なものに走らなくていい余裕が生まれ、実験的なことも行なうことが可能になる。しかも高い質のものがつくれる。そういう全体的な機能が、個々の意識、コミュニティで共有される意識を育てているのではないかなと思います。
ーたとえば日本のミュージシャンで、そのノルウェーのコミュニティで支持されていた人はいましたか。
田中:菊地雅章さん(※)はノルウェーのほかのミュージシャンもみんな話していました。もともと向こうですごく知られていたわけじゃないと思うんですが、「ECM」から『Sunrise』が出たとき、学校内で「これはもう聴かないと」って感じになっていましたね。
田中:菊地雅章さんって誰が聴いても間違いなく素晴らしいと思うのですが、特別な唯一の音楽表現みたいなものがあって、それが自身の表現を深めようとするノルウェーのミュージシャンたちに、特に響いたのかなと思います。直接お会いしたことがないので、菊地さんがどういう考えで音楽をされていたかはわからないですけど。あと大友良英さんも尊敬されていて、「オオトモって知ってる?」みたいな感じでみんなから質問されました。
―菊地さんも大友さんも、やはり「自分の音」がある人ですよね。
田中:そうですね。あとノルウェーに行って、若者に対して年上の人もすごく興味を持っていることに感動しました。
それこそミシャ・アルペリンも「それ何?」って生徒がやっていることにとても興味があった。オスロには素晴らしいミュージシャンがたくさんいて、コンサートなどのイベントでも交流が生まれています。やっぱりコミュニティ全体が音楽を育てていると思いますね。

田中:あと、オスロにあるNasjonal Jazzsceneっていう大きなジャズクラブでは、1万円ぐらいで半年間いくらでもコンサートを観られます。オスロにはヨーロッパだけじゃなくて、アメリカとかいろんな場所からミュージシャンが来るので、最先端でいま起こっていることがオスロにいながら体験できる。それが素晴らしいなと思いますね。
福盛:ミュンヘンのUnterfahrtってジャズクラブにも、月2,000円くらい払ったらいくらでもコンサートを無料で観に行けるミュージシャン会員があります。文化を広げるためにちゃんと市やクラブがその役割を担っている感じはしますね。
ー東京にいると本当にいろんなアーティストが来日してて、気がつかずに見逃したりすることがあるほどですけど、チケット代は高いし、そういったサポートもなかなかないですよね。
福盛:行きたいなと思いますけど、全部行ったらもう破産しますよね(笑)。もっと気軽にミュージシャンが集まる場所がちゃんとできあがってほしい。
ー福盛さんはミュンヘンにいたときは、もっと動きやすかったですか?
福盛:動きやすかったですよ。それこそ鮎美ちゃんの話と同じように世代間の隔たりがないというか。もう亡くなったウォルター・ラング(※)っていう僕のトリオのピアニストとは結構年齢差もあって、最初自分のグループに誘うのに緊張したんですけど、「いいよいいよ」みたいな感じで賛同してくれた。そういうふうに若い人が何かチャレンジしようとするのを応援してくれる感じはあると思いますね。

ー日本の場合、ジャズミュージシャンが歌謡曲や劇伴をやってきた歴史がありますよね。それは「自分の音楽」を追求することが経済的な面からも容易じゃなかったことの表れでもあったわけですが、いまもなかなかサポートもない状況で、今後変わっていく可能性は感じられますか。
福盛:変わっていってほしいなと思うし、そこに希望を感じて僕は日本に戻ってきたので、何か状況を変えられる手助けができればと思っています。少なくとも僕の周りのミュージシャンも「何か違うかも」って気づきはじめている。まだ行動には移せていなくとも、「どうにかしないと」っていう心づもりに変わってきてるような気はします。
ー日本で「自分の音楽」をやるために必要なことは、何だと思われますか?
福盛:僕はまずは場所だと思うんです。リハーサルする場所も限られているし、海外みたいに学校を借りてセッションすることもなかなかできなくて、とにかくお金がかかってしまう。日本はクリエイティブに動ける場所がなかなかないから、ミュージシャンのコミュニティも生まれづらいんだと思う。それに特に東京は地理的に広すぎる気がします。
田中:ああ、たしかに。
福盛:ミュンヘンは大きいクラブは1つしかないんですよ。毎週日曜にやってるセッションに行けば誰かしらいて、そこに行くだけでもいろんな会話ができるし、いろんなジャンルの人も集まってくる。そういう場所づくりは重要なキーになるんじゃないかなと思いますね。

福盛:あと、日本と海外では、お客さんが聴いてる部分が違うのかもしれないと思いますよね。具体的にどう違うかは言葉にできないけど……でもたとえばドイツで1時間の完全即興をやっても、若い人たちもお酒飲みながら観てくれるし、終わったら歓声を上げたりする。
それが日常的な文化として成り立っているというか、文化の日常への入り込み方が海外と日本では全然違う気がします。日本では、「真剣に見なきゃいけない」「理解しなきゃいけない」って部分が大きいんじゃないですかね。
田中:気楽な感じはあまりないかもしれないですね。あまりよくわからなくても行ってみる、みたいな気軽さはヨーロッパのほうが感じるような気がします。
福盛:別によくわからなくても、「このサウンドはちょっとおもしろくて好きだな」ぐらいでもいいと思うんですよね。もっと日常の延長で聴いてもらっていいのにとは思います。
ーたしかにそうですね。必要以上にシリアスに聴いてしまっている、聴かれてしまっている状況はありそうです(※)。
福盛:あと「情報」だけで聴いちゃうというか。
田中:情報だけ?
福盛:実際の音を聴いてるというよりは「この場所でこの人がやってるからすごいんだろう」っていう本質とは違うような部分で接しているというか。だからライブを観に行くのが、「情報を確認しに行く」ことになっているケースもあるんじゃないかと思うところはありますね。

ーお二人がリリースされた「ECM」についても訊かせてください。リアルに感じたことをぜひ伺いたいのです。
福盛:僕は録音中からちょっと違和感があったんですよね。自分の音楽が「マンフレート・アイヒャー(※)のもの」になっちゃったというか、ヨーロッパの音楽になっちゃった気がして。もちろん「ECM」だから、それでいいんですけど、自分が求めていた音楽では必ずしもなかった。
ーそれは、ヨーロッパの音楽に対して、日本の音楽を意識したということでしょうか?
福盛:ずっと海外で生活してきたなかで、アメリカ時代からどうしても避けられない自分のアイデンティティーを意識させられる場面があったんです。作曲するようになってからは特に。
何をもって「日本の音楽」かはっきりは言えないですけど、『For 2 Akis』では日本の湿度に合うもの、日本の夏のジメっとした「アジアの湿度」を感じさせる質感のものをつくりたかったのに、ドイツのカラっとした美しい風景みたいになった感覚があったんですね。
福盛:もちろんマンフレートのプロデュースで「ECM」の作品っていう意味ではそれでいいと思うんです。でも逆に「ECM」での経験を経てやりたかったことがはっきりして、そのあたりから日本に帰ろうかなと思いはじめました。
―2020年に自身のレーベル「nagalu」を立ち上げたのもそういった経緯からというわけですよね。
福盛:ジャズにおいては、まだ日本やアジアの「独自の音楽」としてまだ形になってないと思うんです。たとえばノルウェーに行ったことがなくても、音楽を通じて北欧の情景が思い浮かぶことってありますよね。
日本にもアジアにまだそういうジャズがない、というのがレーベルをつくった理由のひとつです。韓国の本当に素晴らしいプレイヤーのソンジェ・ソン(※)の力を借りて、「EAST MEETS EAST」っていう日韓の共同のプロジェクトをやっているのも同じような意識からですね。
田中:私が初めて「ECM」に携わったのは、トーマス・ストレーネン(※)のTime Is A Blind Guideというアンサンブルの『Lucus』でした。そのときのリハーサルでマンフレート・アイヒャーが言った「こうしてみたら?」っていうひと言で、行き詰まっていた演奏に羽根が生えたように音楽が羽ばたいた瞬間があったんです。
アルバムの1曲目のストリングスからはじまる曲だったんですけど、「じゃあピアノはこういう感じでしたら?」って、録音のときのマンフレートは私に向かってダンスしているみたいな感じでした。それがすごく楽しくて、マンフレートは音楽家の一員としてそこにいてくれるんですよね。マンフレート自身がすごい笑顔だし、喜んでる感じがして、そのおかげでバンドの音楽も昇華された感じがしたんです。
ーアイヒャーはメディアにもあまり登場しないし、孤高の存在で、ちょっと気難しい人というイメージを持っている人も多いと思います。
田中:初めて会ったときの印象はすごく優しい目をした人でした。私が出会ったいいミュージシャンの方々はみんな人柄も素晴らしい、というふうに感じているのですが、マンフレートに会ったときも、温かいエネルギーみたいなものを感じました。日本で居場所がないと感じていたときに、「ECM」の音楽に出会って救われたところがあるので、彼の人柄に触れたとき「自分が信じてきたものは間違ってなかったんだな」と感じました。
ー以前、『Subaqueous Silence』のライナーノーツのために田中さんにお話を伺った際に、「ECM」は人のルーツに根ざした音楽づくりをしてるレーベルだっておっしゃってましたね。いろんな国の人がECMからリリースしてますが、もしかしたら意識してなかったルーツや自分の音を引き出すようなことがあるのかなとも思いました。
田中:ルーツを引き出してもらったというか、ルーツに根ざした音楽を目指して自分がやってきたことに共感してもらえた、という感じがありました。繕ったような演奏は見抜かれてしまうし、マンフレートはそれぞれのミュージシャンの深いところから出てくる真摯な音色を求めている、という印象を受けます。
ー「やりたいこと」よりも「やれることが何か」を考えてないと、見抜かれてしまうということでもありますね。
田中:やりたいことをするのはもちろん大事ですが、それに自分がちゃんとつながっていて深められていないと、音に表れるのでしょうね。それと、やはりその場の音を「聴く」ということをすごく大事にされていると感じました。
それは『Subaqueous Silence』にも通じる話で、マンフレートは「これはすごく特別なアルバムだ」って言ってくれたんです。いわゆるピアニスト、という感じで巧く演奏しているところはない作品ですけど、「ECM」はそういう音楽を大事にしてくれる。音楽のそういう部分を拾い上げてくれるレーベルがあって、しかも世界的に重要なレーベルだという事実がまた素晴らしいことだなと私は思いますね。
ーたしかにパーソナルな表現をとても大事にしているレーベルという感じがしますね。民族音楽にしても、キース・ジャレット(※)が多重録音している作品にしても、作品の完成度とは関係なく、アイヒャーが本当に気に入っているのだろうなというのは伝わってきます。
田中:そうですね。信じた作品を世に送り続ける覚悟と情熱を感じますね。
ー「ECM」からの作品でいうと、福盛さんがヨン・クリステンセンのドラムについて「拍があるけど、拍がない」というふうに話されていましたが、田中さんはどう思われますか?
田中:その人が生きているタイムというか、心臓の鼓動が速くなったり遅くなったりするように、「ここに実在している」「生きてる息」みたいなものをヨン・クリステンセンの演奏からすごく感じます。
それにすごく空間的ですよね。特に亡くなられる前は膝が悪くて足でドラムができなかったようで、シンバルだけでペインティングみたいに、色をつけていくような演奏の仕方でした。それが美しくて、ちゃんとビートがそこに存在している。ちゃんと息遣いがあって、演奏を通じて「生きてるタイム」を感じるのが不思議ですよね。
ー拍の取り方とかに、ドラマーのパーソナリティーみたいなものが感じられるということでしょうか?
福盛:タイム感って言葉で説明するのが難しいですね。ヨン・クリステンセンは全然ビートを出さないけど、拍がどこにあるかが感じられる。その時間の進行が感じられる人は「タイムがいい」って僕は思うんです。どれだけビート出してても、そこに存在するはずの拍がうまくかみ合ってない、そういう人はタイムが悪いなと思う。
ーそれはよく言われるリズム感、グルーヴ感みたいなものとは違いますか?
福盛:違うと思いますね。さっき鮎美ちゃんが言ったみたいに心臓の鼓動とか、そういう自分の持ってるペース、流れを音楽で表現できるのがヨン・クリステンセンのすごさだとは思うんです。タイムが悪い人ってテクニックにとらわれがちだったり、すごく細分化しすぎなところがあって、時間の進行というか「大きな流れ」に意識が向いていないような気はします。
僕はよく音楽のことを水で考えることが多いんですけど、川の流れってずっと一定じゃないけど、どこか美しさを感じますよね(※)。それと同じような話で、流れがずっと一定だとおもしろくないし、グルーヴもなかなか生まれない。
田中:私がレコーディングに行ったとき、マンフレートも「演奏の仕方がわからなかったら、海の波の動きを見たらわかるよ」って言ってました。
福盛:そもそもの話、ヨン・クリステンセンはやっていることがすごく抽象的なので、言葉にしづらいところはあるんですけどね。
田中:結局、「息遣い」なんだと思います。風が吹くとか、川の流れにも自然の息遣いのようなものがあるし、話すのだって息遣いですよね。そういうものが感じられる音楽が私は個人的にすごく好きです。
ー最後に福盛さん、田中さんが出演される公演について話していただけますか?
福盛:ECMからリーダーとしてリリースしている人が4人揃うのは日本ではなかなかないことだと思います。トーマスのバンドは7年ぶりで、鮎美ちゃんも「ECM」から作品をリリース後では初めての公演。両方ともドラマーがリーダーのグループで、トーマスも僕も作曲もします。
ーTime Is a Blind Guideはどういうグループなのでしょうか?
田中:室内楽とピアノトリオが共存する、そして、民俗音楽のメロディーやリズム、ジャズ、現代音楽などさまざまな要素が交わる音楽です。一人ひとりが瞬時にアイデアを出しあい一緒に音楽をつくり上げるので、メンバーの個性が輝くバンドで、リーダーのトーマスもそれを求めている、というのが私の印象です。トーマスが作曲した作品をもとに演奏するのですが、そのときどきによってどんどん変容して、ツアーに出ても毎回全然違う音楽になる。それこそ即興演奏の醍醐味を感じてもらえると思います。
福盛:僕もトーマスもドラマーっぽくないというか、思考もつくり方も指揮者っぽい気がします。
田中:そうですね。あとふたりとも空間をとても大事にされていますよね。今回、福盛さんの新しいリーダーバンドと一緒に公演させていただいて、そこの化学反応もあるはずです。それも楽しんでいただけると嬉しいです。