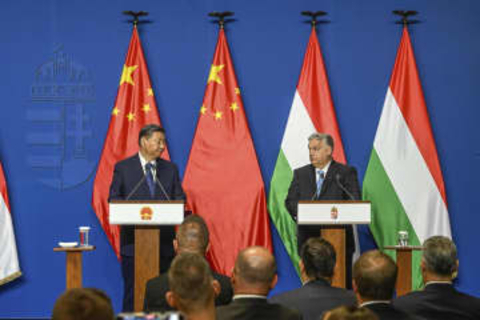何事においても、
絶望するよりは、
希望を持つほうがいい。
先のことなど誰にもわからないのだから。
これは、本書『希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話』の冒頭に引用されたゲーテの言葉だ。で、その隣のページには、カフカのこんな言葉が。
ああ、希望はたっぷりあります。
無限に多くの希望があります。
−−ただ、ぼくらのためには、ないんです。
……のっけから取りつく島もない。が、この2ページだけで本書のコンセプトが見えてこようというもの。
ゲーテとカフカ、ともに偉大な文豪だ。
ゲーテは25歳のときに上梓した恋愛小説『若きウェルテルの悩み』が大ベストセラーになり、82歳で亡くなる間際に「世界文学の最高峰」とも称される長編戯曲『ファウスト』を書き上げた超メジャー作家。
一方のカフカは、「ある朝、目をさますと、虫になっていた(要略)」という書き出しで有名な『変身』や未完の長編『城』の作者だが、作家としての名声を得たのはその40年の生涯を閉じたあとだった。
編訳者の頭木弘樹によれば、ゲーテとカフカは好対照をなしており(他方で多くの共通点もあった)、その最たるものが「ゲーテは希望の人であり、カフカは絶望の人であるということ」だという。
もっとも、ゲーテの没年は1832年、カフカの生年は1883年だから、ふたりが直接顔を合わせたことはない。本書では「架空の対話」という体で、両者の言葉を対にして紹介していく。もういくつか抜粋してみよう(以下、先攻がゲーテ、後攻がカフカ)。
太陽が輝けば、ちりも輝く。
(格言と反省)
暗闇に戻らなければなりませんでした。
太陽に耐えられなかったのです。
絶望を感じました。
(ミレナへの手紙)
***
晩に、わたしは千匹のハエをたたき殺した。
それなのに早朝、一匹のハエに起こされた。
(詩 格言風に)
かわいそうなハエを、なぜそっとしておいてやらないのですか!
(ペンションで出会った少女への言葉)
***
自らを不滅の存在とするために、
わたしたちはここにいるのだ。
(温和なクセーニエン)
目立たない生涯。
(日記)
***
朝も昼も夕も頑張れば、
いい夜になる。
(詩 人生の喜び)
ぼくの夜は二つあります。
目覚めている夜と、眠れない夜です。
(フェリーツェへの手紙)
光り輝くゲーテの言葉を、いちいち暗闇で塗りつぶすカフカ。ゲーテもゲーテで、何度黒塗りにされても輝くのをやめない。
どちらか一方の言葉だけでも強烈なのに、明と暗の鮮やかな(もしくは残酷な)コントラストが互いの言葉を引き立て合う。ゲーテの言葉を借りれば「光の強いところでは、影も濃い」。そこに編集の妙を感じずにはいられない。
本書には、合わせて56対の言葉と1対の絵画が収録されており、それらすべてに頭木による簡潔かつじつに丁寧な解説が付されている。
たとえば「ハエ」にまつわる言葉では、ゲーテのいうハエとは「うるさい世間や嫌みな言葉など」の比喩で(たしかに一晩で千匹はたかられすぎだし、殺しすぎ)、そういう悪評をたたき殺す=気にしないところに「ゲーテの力強さ」が表れており、また、それでも一匹のハエに起こされてしまうあたり、「人間らしい」と評している。
一方、本物のハエをそっとしておきたいカフカについては、「カフカの生きものに対するやさしさ、弱いものへの共感は、けた外れです」。
なんて、ふいにいい話が挿まれたりもするが、カフカはあくまで絶望名人。その称号に恥じない絶望エピソードも山盛りで、同じく例示した「目立つ失敗」がらみの逸話なんか……カフカは、自分の小説すらも失敗作とみなしていたようだ。
最初の小品集『観察』を出すときも、カフカは削りに削って、すごく薄い本になりました。
しかも、ようやく出版社に原稿を渡しても、カフカは編集者に「出版していただくよりも、原稿を送り返していただくほうが、あなたにずっと感謝することになります」と言ったりするのでした。
その『観察』が出版されて、知りあいの女性に献呈したとき、カフカは本にこんな言葉を書きました。
「いちばんいいのは、いつもパタンと閉じておくことです」
もうね、読んでいるこちらが頭を抱えてしまう。でも、そんなカフカが愛おしくもなるし、絶望的すぎて逆に笑えてもくる。
僕は、どちらかといえばネガティブな性格で、たとえば自分が落ち込んでいるときに元気な人を見ると、イラッとする。もっと正直にいうと、気分が沈んでいるときは、自分より深く沈んでいる人を見て「俺はまだマシだ」とか思いたいタイプの人間だ。絶望はしばしば絶望によって癒される。
じゃあ、だからといって「ゲーテはリア充すぎてムカつく」みたいになるかというと、そうでもない。
ゲーテという人は、超メジャー作家であるばかりか、金持ちでイケメンで天才だ。もし、そこにゲーテの言葉だけポンと置かれたなら、まぶしくて直視できなかったろう。でも、隣にいるカフカがいい感じに影になって、まぶしすぎるゲーテの言葉もちゃんと見ることができる。
加えて、本書の解説を読めば、ゲーテが必ずしも順風満帆の人生を送っていたわけではないこともわかる。
大病を患って大学を中退したり、失恋して自殺を考えたり(この体験が『若きウェルテルの悩み』のもとになった)、政治の仕事でくじけて蒸発したり、愛する妻や息子に先立たれたり……そうした苦難の数々を、ゲーテは「希望」でもって克服してきたわけで、だからおそろしくポジティブなことが素で言えちゃうのだ。
ゲーテはまた、「希望を持つほうがいい」としつつ、同時に絶望の意味も価値も知っている人だ。その証拠に、以下のような言葉も残している。
絶望することができない者は、
生きるに値しない。
(詩 格言風に)
頭木は、本書を希望と絶望の「間の本」と位置づけており、あとがきでは「希望と絶望、これはやっぱり両方ないといけないと思います」と書いている。たしかに、「酸いも甘いも噛み分ける」なんて成句もあるしね。
カフカほど生きづらさを感じていた人はなかなかいないし、ゲーテほど人生に満足していた人も極めてまれだろう。
つまり世の中のだいたいの人のメンタルは「カフカ以上、ゲーテ未満」で浮き沈みしているのであって、その日の気分でカフカとゲーテ、どちらの言葉に共振するかも変わってくるはず。落ち込んでたらカフカに慰めてもらい、テンションが上がってきたらゲーテに煽ってもらえばいい。
かくいう僕も、本書を読みはじめた当初は「希望? ねーよ。いいぞカフカさん、もっと言って」くらいに思っていたのが、カフカの闇があまりに深すぎて、いつしか「ねえ、ちょっとカフカくん聞いてる? ゲーテ先輩もああ言ってくれてるんだしさ、もう少しこう、どうにかできない?」みたいになっていたのだからおかしなもんだ。
(須藤輝)