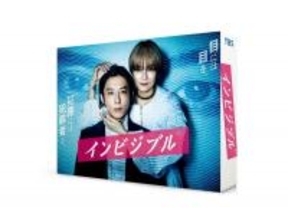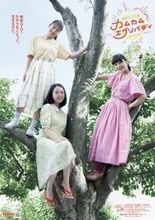ドラマ好きとしては、事前に情報を頭に入れてしまうと楽しみがなくなってしまうという人もいるだろう。私も正直そうなのだが、それでも今回のドラマは実在の人物をモデルにしている以上、その背景を知っておくとより楽しめるというところも少なくないように思う。そこで、この記事ではなるべくネタバレにならないよう、史実からドラマの見どころとなりそうなことを、いくつか紹介してみたい。なお以下の文章では、ドラマの亀山政春を「マッサン」と表記するようにした。まずは、つい最近、イギリスからの独立をめぐる住民投票が実施され注目されたばかりの、スコットランドにまつわる話題から。
■「花子とアン」「八重の桜」と「マッサン」の意外な関係
竹鶴は、ウイスキーの製法を学ぶために、その本場であるイギリス・スコットランドに留学、そこでリタと出会った。このスコットランドは、朝ドラの前作「花子とアン」でとりあげられた小説『赤毛のアン』と密接にかかわっている。
『赤毛のアン』の作者ルーシー・モンゴメリーは、スコットランド系カナダ人であり、主人公のアンは、カナダ本土のノヴァスコシア(新スコットランド)州生まれで、スコットランドの民族衣装を身につけ、スコットランド語を話す。アンを引き取ったマシューとマリラの兄妹も、母親がスコットランドからの移民という設定だった。作家の松本侑子は、植松三十里の小説『リタとマッサン』文庫版の解説を、『赤毛のアン』の新訳の取材のために訪れたスコットランドの印象を交えて書いている。
なお、ドラマでエリーを演じるシャーロット・ケイト・フォックスも、祖母がスコットランド人だという。朝ドラにはオーディションで選ばれた彼女にとって、「マッサン」が日本のテレビドラマ初出演となる。これに対し夫のマッサン役の玉山鉄二は、昨年のNHK大河ドラマ「八重の桜」で旧会津藩士・山川浩を演じたことが記憶に新しい。じつは「八重の桜」の舞台となった会津は、竹鶴政孝の設立したニッカウヰスキーの工場のある北海道余市(よいち)町とゆかりが深い。
竹鶴は、日本国内でウイスキーづくりにふさわしい場所として、北海道、それも湿度の高い日本海沿岸から余市を選んだ。しかし、すぐにはウイスキー製造に着手しなかった。彼がまず手がけたのは、余市産のリンゴを原料としたジュースの製造である。余市は日本で初めて西洋リンゴの栽培に成功した地であり、その生産を始めた人たちこそ、戊辰戦争で明治政府軍に敗れてこの地に移住した旧会津藩の開拓民だった。
なお、このとき竹鶴が設立した会社は「大日本果汁株式会社」、略して「日果」と呼ばれた。
■早見あかり演じるマッサン妹はツンデレか、デレか?
「マッサン」では、主人公夫婦の脇を固める登場人物もそれぞれ気になるところだ。マッサンの両親を演じる前田吟と泉ピン子といえば、どうしてもTBSのドラマ「渡る世間は鬼ばかり」での共演を思い出さずにはいられない。「渡鬼」ではピン子はどちらかといえば姑にいびられる役だったが、ほかのドラマではその逆の立場を演じることも多い。とすれば今回、ピン子がどんなふうに外国から来た嫁に接するのか見逃せない。
マッサンの妹・亀山すみれは、元ももいろクローバー(という前置きはもはや不要か)の早見あかりが演じる。早見といえば、ここしばらく「ウレロ未体験少女」「アゲイン!!」といったドラマでツンデレっぽいキャラを演じてきたが、「マッサン」ではどうなのか。川又一英『ヒゲのウヰスキー誕生す』によれば、竹鶴政孝は妹の沢能(さわの)をことのほかかわいがり、大阪の摂津酒造に勤務し、母とともに3人で暮らしていた頃には、よく食事をおごったり芝居見物や買い物に連れて行ったりしたという。あるとき竹鶴が高価な着物を買ってやると、沢能は《お兄様、これではお給料なくなってしまいます》と気を揉んだとか。萌える。
竹鶴は、この摂津酒造の社長・阿部吉兵衛からスコットランド留学の機会を与えられた。摂津酒造は現在の大阪市住吉区に所在したことから、ドラマでは「住吉酒造」として登場、社長の田中大作を西川きよしが演じる。
■ホームシックのマッサンの心をなぐさめた曲とは?
竹鶴政孝はスコットランドに留学当初、ホームシックとなって、下宿先では毎晩、枕を涙で濡らしたという。そんなとき出会ったのが、ジェシー・ロバータ(リタ)・カウンだった。ただし竹鶴が知り合ったのはリタではなく、同じグラスゴー大学に通う彼女の4つ下の妹エラである。いくつかの本には、竹鶴はカウン家の末の弟に柔術を教えるため、その家を訪れるようになったと書かれている。一方で、NHK出版刊のオリーヴ・チェックランド『マッサンとリタ』には、1918年のクリスマスに、カウン家に招待されたのが最初だったとある。このときデザートに出されたプディングケーキをめぐるあるエピソードが、竹鶴とリタの馴れ初めとなったらしい。これについては翌年のクリスマスの話としている本もあるものの、印象的な話なので、きっとドラマでも描かれるのではないだろうか。
竹鶴はカウン家の人たちに心をなぐさめられることになった。前出の『ヒゲのウヰスキー誕生す』には、あるとき竹鶴が鼓を持って来宅すると、リタから自分のピアノと合奏しましょうと誘ったという話が出てくる。このとき、リタがこの曲ならあなたもご存知ではと弾き始めたのは、「オールド・ラング・サイン(今は懐かしその昔)」というスコットランド民謡だった。たしかにその旋律には竹鶴も聴き覚えがあった。
「悲しい別れの曲ですね」と言う竹鶴に、リタは「いいえ、懐かしい昔を偲んで、杯を手に友と語り合おうという歌です」と歌詞の内容に加え、それがスコットランドの詩人ロバート・バーンズの詩であることを教えた。そのあとで、もう一人の妹ルーシーを交え、英語と日本語で歌ったという。スコットランドと日本のかかわりを象徴するエピソードだけに、これもぜひドラマで見たいところだ。
■リタ=エリーの出す料理も見どころとなるか
結婚して日本に来たとき、日本語を学ばないといけませんねと言うリタに、竹鶴は「日本語は不自由なく話せるようにさえなればいい。それよりも、日本の料理を習ってみてはどうか。日本料理は日本語に劣らず難しい。一人前に日本料理がつくれるようになれば、立派な日本人だ」と勧めたという。自身のスコットランド留学生活を思い起こしてのアドバイスだった(『ヒゲのウヰスキー誕生す』)。
さっきのプディングケーキのエピソードにしてもそうだが、ドラマにもおそらくたくさんの料理が出てくることだろう。余市に移ってからリタは、夫の会社の余り物のリンゴでアップルパイや焼きリンゴをつくったり、酪農の盛んな北海道だけに、新鮮な牛乳やバター、また当時は大都市でもめったに手に入らなかった生クリームを使って料理に腕をふるったという。戦後、東京に本社を移してからは、仕事で留守がちの竹鶴に代わり、息子夫婦と洋食を楽しむことが増えた。
竹鶴とリタの存命当時にニッカウヰスキーに勤務していた人たちの話によれば、社内の行事では、カレーライスやクッキーなどリタの料理がふるまわれることもよくあったという。とくに卵をかけて食べるカレーライスは彼女の得意料理だった。宴会ではドーナツを100個以上つくり、社員の楽しみとなっていたという話も伝えられる(『「マッサン」と呼ばれた男 竹鶴政孝物語』)。
食事に関する竹鶴の要求はかなり高いものだったらしい。大根を煮て食べるのでも、目の前で採って来ないと許さなかったという。採りたてのものをその場で食べることこそ、彼にとって最高のぜいたくだったのだ。夫のそんなこだわりが染みついたのだろう、リタは毎晩の食事でもできたての温かい料理を出すことを心がけ、家族が帰宅時間に少しでも遅れると機嫌を損ねたという。
リタ自身は日本食はほとんど食べなかったというが、余市では冬に備えて大量の野菜と魚を漬けこんで、漬け物をつくった。これはかなりの重労働であったようだ。それでも彼女は家事、とりわけ食事に関して妥協を許さず、息子夫婦と同居するようになってからも、ほとんど自分で用意したという。ドラマではそんな彼女の執念も描かれるのだろうか。
「マッサン」の登場人物の背景には、このほかにもたくさん興味深い話がある。たとえば、竹鶴がスポーツに貢献したという話。1972年、札幌冬季オリンピックのスキー70メートル級ジャンプで優勝した笠谷幸生は、当時ニッカの社員だったというだけでなく、もともと竹鶴が私費を投じて余市につくったジャンプ台「桜ヶ丘シャンツェ」(のちの竹鶴シャンツェ)で練習しながら育った。竹鶴はさらに笠谷の五輪優勝後、余市に新たなジャンプ台を建設、「笠谷シャンツェ」と名づけている。ここでジャンプを覚えたのが、98年の長野オリンピックで活躍する船木和喜や斎藤浩哉たちだ。
もっとも、これらは竹鶴の晩年から没後のできごとなので、ドラマでとりあげられるかどうか微妙ではある。それでも、サントリー創業者の鳥井信治郎(ドラマでは鴨居欣次郎という名前で堤真一が演じる)とマッサンの関係などは、ドラマでもくわしく描かれることが予告されている。いずれまたエキレビ!でもとりあげたいところだ。
最後に、本記事を書くにあたり参考にしたものを中心に「マッサン」に関連する書籍をあげておく。それにしても、復刊や増刷されたものも含め、放送前にこれだけ多くの関連書が書店に並んだことは、半世紀を超える朝ドラの歴史でもちょっと前例がないのではないか。そこにはおそらく「マッサン」の制作発表のあったのが、「あまちゃん」のブームが冷めやらぬ時期だったということも関係しているのだろう。「マッサン」もまた、多くの人々の記憶に残る作品となることを期待したい。
【竹鶴政孝の著書】
●『ウイスキーと私』(Kindle版。「日本経済新聞」連載「私の履歴書」の単行本化)
●『ヒゲと勲章 「ウイスキー革命は俺がやる」』(Kindle版)
【小説】
●森瑤子『望郷』
●植松三十里『リタとマッサン 国産ウイスキーを育んだ夫婦愛』
【評伝ほか】
●川又一英『ヒゲのウヰスキー誕生す』(1982年刊、85年に文庫化された同名書の増補新装版)
●早瀬利之『リタの鐘が鳴る 竹鶴政孝を支えたスコットランド女性の生涯』
●オリーヴ・チェックランド『マッサンとリタ ジャパニーズ・ウイスキーの誕生』(和気洋子訳。日英交流史の研究者である著者の『リタとウイスキー』の増補改訂版)
●野田浩史『マッサン流「大人酒の目利き」 「日本ウイスキーの父」竹鶴政孝に学ぶ11の流儀』(著者はオーセントホテル小樽のチーフバーテンダー)
●土屋守『竹鶴政孝とウイスキー』(著者はウイスキーライターで、「マッサン」ではウイスキー考証を担当)
●千石涼太郎『竹鶴とリタの夢 余市とニッカウヰスキー創業物語』(著者は北海道在住のノンフィクション作家・エッセイスト)
●NIKKO MOOK『「マッサン」と呼ばれた男 竹鶴政孝物語』(竹鶴政孝とリタの生涯、ドラマの背景などを多くの取材・図版とともに紹介する)
(近藤正高)