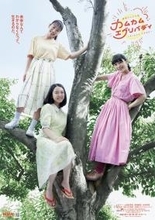ついにパリ編に突入した第7話
いよいよ主人公・秋山篤蔵(佐藤健)がパリに修業に出たTBSの日曜劇場「天皇の料理番」第7話(6月7日放送)。当然、パリで実際にロケを行なっているのだが、時代設定は1909年、100年以上も前だ。そんな昔をテレビドラマで描くのに、わざわざセットを組むことなく、実際の街並みをロケーションにして撮影できるというのは、やはりヨーロッパの都市ならではといえる。

まあ、これも一種の西洋コンプレックスなのだろう。21世紀の日本人がいまだに西洋に対してもろもろコンプレックスを抱えているのだから、西欧列強が世界中を支配していた20世紀初頭ともなればなおさらだ。1909年といえば日露戦争終結の4年後だが、ドラマのなかでも解説されていたとおり、日本がロシアに勝利したことは黄色人種に対する白人の危機感をかえって強めてしまった(いわゆる黄禍論)。
オテルマジェスティックのレストランに小僧として入った篤蔵もまた、容赦のない差別を受ける。しかし、そこは実力社会のフランスのこと、篤蔵はその包丁さばきによってすぐに料理長のパトゥル(グレッグ・デール)に認められ、たった一日でレギユム(フランス語で野菜のこと)の係に昇進する。ふたたび小僧からの出発であったとはいえ、日本で学んだことはしっかりと役に立ったのだ。
とはいえ、しばらくすると今度は、小僧として入った者はずっと小僧のまま給料は上がらないという壁に直面することになる。昇給のためにはユニオン(組合)に入らないかぎり無理だというのだが、日本人である篤蔵が加入するのはとうてい不可能だと考えられた。

パリジェンヌとの交際から気づいたフランス料理の真髄
もう一つ、篤蔵に立ちはだかった壁が、フランス人との味覚の違いである。味つけも香りも日本より強く仕上げるよう求められるのだが、これに篤蔵はなかなか慣れることができない。その壁を打ち破るきっかけを与えたのが、フランソワーズ(サフィラ・ヴァン・ドーン)という若い女だった。
篤蔵は、パリで偶然再会した元同僚・新太郎(桐谷健太)に誘われるがまま、とある酒場での「ザリガニ大食い競争」に参加させられる。
篤蔵はその後もフランソワーズと食事をともにするうち、ワインによって料理の味が変わってくることに気づく。フランス料理はいわば、ワインの味や香り込みで料理の味になっているのではないか。この発見によって、篤蔵はついにフランス人好みの味つけをマスターするにいたる。
フランソワーズもフランソワーズで、フランス語の「ウィ」が日本語では「はい」にあたることを覚え、篤蔵に話しかけてくるようになる。そういえば昔、私が出版社で働いていた頃に先輩編集者から、語学を学ぶには外国人の恋人をつくるのが一番と滔々と説かれたことがあった。
郷ひろみの身のこなしに注目
第7話の終盤では、篤蔵の愛用の牛刀(日本を発つ際に恩師の宇佐美から贈られたもの)が、彼をねたむ同じ厨房のアルベール(ロイック・ガルニエ)にへし折られる。それまでのひどい仕打ちもあって、ついに篤蔵は怒りを爆発させ、アルベールの喉元に包丁を突きつけてしまう。我に返った彼は、こんなことをしでかした以上、もうここでは働かせてもらえないだろうと、世話になっている外交官・粟野慎一郎(郷ひろみ)に相談するため日本大使館に赴いた。そこで粟野から「国際問題になるかもしれない」と告げられた矢先、料理長のパトゥルが訪ねてくる。何と、篤蔵にはうちをやめないでほしいと言うのだ。彼の高い技術、丁寧な仕事ぶりを買ってのことだった。まさに雨降って地固まる。ついでに、粟野が機転を利かせ、篤蔵の正式な料理人への昇格とユニオン入りを認めさせてしまう。それにしてもこのときのヒロミ・ゴーの軽い身のこなし、とても今年還暦とは思えなかった。
フランソワーズとの関係も、彼女にパトロンがいることを知って篤蔵はいったんは引き下がったが、ラストでは再燃する。
まったくの蛇足ながら、フランソワーズ役の女優さん、誰かに似てるなと思い、見終わったあともしばらく考えていたのだが、ようやく気づいた。NHKの久保田祐佳アナに似てませんか?
(近藤正高)