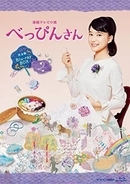脚本:渡辺千穂 演出:安達もじり

121話はこんな話
さくら(井頭愛海)は新商品の審議会に遅刻してきた挙句、課題も提出できず、すみれ(芳根京子)を苛立たせる。だがついにさくらは奮起、母子おそろいのエプロンを提案して、ようやくすみれを笑顔にさせた。
「暮しの手帖」との違い
商品提案会で、社員のひとりが、浴衣生地でつくったワンピースを提案するが、日本の着物とワンピースを融合させる根拠が弱いし、浴衣の布地では心許ないなどとすみれたちに反対される。
朝ドラをシリーズ続けて観ている人の中には、前作「とと姉ちゃん」の直線裁ちワンピースの件はどうなる? とざわつくものを感じた人も多かったのではないだろうか。
「とと姉ちゃん」のモチーフになったことでもお馴染みの伝統ある雑誌「暮しの手帖」の前身「スタイルブック」は戦後すぐの昭和21年に、着物地を利用して直線裁ちしたワンピースを提案した。「とと姉ちゃん」にもそのエピソードは描かれた。だが、それはあくまでも貧しい中でできる限り豊かな気持ちになりたいという工夫であり、あの戦後から25年経って景気もすっかりよくなった昭和45年の日本では、衣服に関する感覚も変わっていることを感じさせるエピソードだ。
まさに、すみれの〈キアリス〉や潔(高良健吾)の〈オライオン〉の発展は、戦後「暮しの手帖」が生まれた時代のように自分たちで服をつくるのではなく、既製品を買う時代になったからこそ。
アイビールックで若者に大人気となった栄輔(松下優也)の〈エイス〉がその最たる例だ。
これらの企業にはモデルがあることは、視聴者の方々はもう十分承知しているだろう。念のためまとめると、キアリスは〈ファミリア〉、オライオンは〈レナウン〉、エイスは〈VAN〉。最近、エイスと組みはじめた大手商社KADOSHOは〈丸紅〉と言われている。
22週に向けて、エイスとKADOSHOの勢いが増しているので、ここで主にエイスとそのモデルVANについて改めて解説してみよう。
VANと「カーネーション」のコシノジュンコとの関係
〈VAN〉(ヴァンジャケット)は、1955年創立、若者を対象にして、紺ブレやチノパンなどアイビーファッションを大ブームにしたブランド。創設者・石津謙介(栄輔のモデル)は、ロゴ入り紙製のパッケージ込みでおしゃれを演出する(「べっぴんさん」87話にも紙袋エピソードが出てくる)など、冴えた戦略の持ち主だった。
キャッチーな「VAN」という名前は、同名の雑誌から使用許可を得たもの。
VANは、同じく軍艦(イギリスの御召艦)から名前をとった〈レナウン〉とは浅からぬ関係にあった。
石津謙介は、かつてレナウンの前身・佐々木営業所(坂東営業所のモデル)の関連会社で働いていて、のちに東京のレナウン研究室に入り、そこで服作りの力をつけた。やがて独立すると、いまの大阪・アメリカ村にVANの前身となる石津商店を起こした。まず大阪を席巻したVANは、東京に進出し、まずは日本橋を拠点にし、銀座のみゆき族の盛り上がりに乗る。それから東京オリンピックが開催された1964年には青山に移転。66年になると、そのそばに、朝ドラ「カーネーション」のヒロイン糸子のモデルの娘であるデザイナー・コシノジュンコの店〈コレット〉が出来て、この2大勢力によって、青山は若者ファッションのメッカとなっていく。
VANとつかこうへいや野田秀樹との関係
業績がおおいにあがり向かう所敵なしだったVANは、1970年には売上高69億に到達、文化に貢献しようと、73年、別館「VAN365」ビルの一階を改装し、〈VAN99ホール〉(ヴァン・キュー・キュー・ホール)をつくる。72年、パリで石津が観たピエール・カルダン劇場に影響されたものだった。ピエール・カルダンは70年の万博で行ったファッションショーも話題の的だった。
〈VAN99ホール〉は収容人数99人と小さい小屋で、当初多目的ホールとして使用される予定だったが、スタッフのひとりが劇場にしようと思いつく。当時、早稲田大学の演劇サークルで注目を浴び、最年少で岸田戯曲賞を獲ったつかこうへいが公演を打つことになる。
「つかこうへい正伝1968−1982」(長谷川康夫著 新潮社)によると、VANはロゴ入りTシャツまで提供する気前のよさだった。
早稲田を出て、劇団「つかこうへい事務所」となったはじめての公演「飛龍伝そしてカラス」は99円の入場料で、青山通りに行列ができるほどの人気となって、つかこうへいブームの下地が完成したといっていい。
平田満や根岸季衣もこの劇場で芝居をしている。
ここで「つかこうへい全作品集」上演を行うなどして勢いをつけたつかは、76年に新宿紀伊国屋ホールに拠点を移し、その人気を完全なものにする。つかが去ったあとのVAN99ホールでは東大で野田秀樹が旗揚げした劇団夢の遊眠社が第二回公演「走れメルス 燃える下着はお好き」を上演した。演出は、現・東京芸術劇場副館長の高萩宏。朝日新聞の演劇記者・扇田昭彦がこれを観に来て「とにかく驚いた」と語っている。VANは、つかこうへい、野田秀樹と日本の演劇の重要人物ふたりのステップボードだったのだ。「つかこうへい正伝1968−1982」で面白かったのは、VANにお世話になる前に著者がVANのライバル会社JUNの三つ揃えのスーツを衣裳にしていた話を書いていることだ。
VANの終焉
だがVANの勢いもそれが最後となる。もともとVANが当たったのは、戦後のベビーブームの恩恵。若者人口が増えた時期にちょうどハマったため売上が上がった。だが、その若者は皆大人になってVANから卒業してしまうとたちまち売上は激減、VANは急速に力を失っていく。
これから〈エイス〉と栄輔の運命は今後どうなっていくのか。目下、22週ではKADOSHOと組んで万博の演出をするという流れはモデルの事実に近そうだ。ちなみに、石津には10代からのつきあいで長年連れ添った妻がいたが、ドラマの栄輔はすみれに失恋したあといまだに独身(らしい)。明美(谷村美月)との関係も気になる。
西岡徳馬とVANの関係を深読みする
ところで、KADOSHOの社長古門役の西岡徳馬(丸紅の創始者と同じ滋賀県出身)は、日本の老舗劇団文学座出身。石津は、荒木町で文学座の中村伸郎や太地喜和子などともつきあいがあったそうだから、遠い関係でもないのではないか。また、西岡は1980年代になるとつかこうへいの舞台に出演するようになる。「幕末純情伝」や「寝取られ宗介」など人気作で色気ある男の役を演じていた。
オライオンのモデル・レナウンの生き残り戦術
「べっぴんさん」で栄輔に先を越される潔のオライオンのモデル〈レナウン〉は、メリヤス販売の会社からはじまって、女性服の会社となる。「べっぴんさん」ではメリヤス工場が危機となってすみれを困らせるが、モデルの会社は関連企業がメリヤスを取り扱っていたのだ。
レナウンは、自社で広告部署をもつ稀有な会社で、広告宣伝にも力を入れていた。1951年、週刊朝日の裏表紙に広告を掲載、ニッポン放送「レナウン歌のつどい」など提供した。なんといっても61年にテレビ放送された「レナウン ワンサカ娘」のCM。この作曲は、社員の兄だった当時まだ無名の小林亜星で、これが当たって小林は人気作家になる。振り付けは先ごろ亡くなった藤村俊二である。
VANが若者向けの服に特化し失敗した一方で、レナウンは70年、大人のためのブランド〈ダーバン〉を立ち上げ、それがみごとに成功した。そのCMキャラクターはアラン・ドロンだった。
CMネタは、119話で栄輔が全面的に出ているCMが登場したので、たぶんこれっきりだろう。
(木俣冬)
参考文献
「VANストーリーズ ─石津謙介とアイビーの時代」宇田川悟著 集英社新書
「つかこうへい正伝1968−1982」長谷川康夫著 新潮社
「レナウンを創った愉快な男たち 素晴らしき奔馬たちの記録」 山下剛著 こう書房
「『楽しさの経営を貫く』レナウン」 うらべまこと著 朝日ソノラマ
「野田秀樹」内田洋一責任編集 白水社