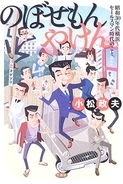試練を乗り越えた小松、独り立ちを許される
クレージーキャッツの植木等(山本耕史)に弟子入りした松崎雅臣青年(志尊淳)は、運転手兼付き人として植木を支えながら、やがて少しずつテレビや舞台に出させてもらうようになり、小松政夫の芸名も与えられた。

先週、10月14日放送の第7回では、植木が小松を独り立ちさせるため、大阪でのクレージー公演の幕間の5分間を彼ひとりでつなげるという試練を与える。
追い詰められた小松に、わざわざ大阪まで憧れの女性・鎌田みよ子(武田玲奈)が面会に来てくれた。すでにみよ子にはフラれていた小松だが、彼女から「私、ずっとまっちゃんのファンだからね。だから、きっとこの世界で一人前になるって約束よ」と励まされる。
このあと、小松は宿泊先のテレビでたまたま淀川長治が映画を解説するのを見て、これだとひらめく。翌日のステージでは、顔に太い眉とメガネを描いて登場、淀川長治の口調を真似ながら、その前のクレージーの出し物について「この作品、じつはねえ、構想5年、総予算30億円、リハーサル1日、怖いですねえ、怖いですねえ」と解説を始めた。これに会場はドッと沸く。こうして“淀長サンのモノマネ”は定番となり、小松のために太い眉毛付きの黒縁メガネと、テレビのフレームを模したセットも用意される。メガネはピアノ線を引っ張ると眉毛がピクピク動くという仕様で、彼はそれもネタにして笑いをとった。テレビのセットは「後半、ごゆっくりご覧ください」と小松が言うや倒れ、赤フンで金ダライに足を突っ込んでいる下半身が現れるという演出で、これまた爆笑をとる。
こうして小松は、試練を見事にクリアした。
このあと、植木がころあいを見はからって「うん、急いじゃいないけど、ぼちぼち行こうか」と声をかけると、二人はようやく帰宅の途に就くのだった――。この話は、いままでにも小松政夫があちこちで語っており、よく知られているが、こうして映像化されるとグッとくるものがあった。
小松ご本人と伊東四朗の共演も実現
ドラマの原案となった小松政夫の自伝的小説『のぼせもんやけん2』(竹書房)によれば、彼が幕間をまかされたのは、1967年に大阪の梅田コマ劇場で開催された「梅田コマ薫風公演」と題する時代劇バラエティの公演らしい。そのなかでクレージーキャッツの演奏会という出し物があり、途中でメンバーが着替えるあいだ、当初は15分の休憩を入れる予定が、休憩を入れたくないハナ肇は、小松に5分間つなぐよう命じたのだった。ここからあの淀川長治のネタが生まれることになる。
なお、淀川長治がテレビで映画解説をするようになったのは、1960年にNET(現テレビ朝日)でスタートしたアメリカのテレビ映画「ララミー牧場」からである。これが63年に終わると、66年には同局で「土曜洋画劇場」が始まる。これが翌67年には放送日を変えて「日曜洋画劇場」となり、淀川は亡くなるまで解説を担当することになった。小松がモノマネを始めたころには、淀川の解説終わりの「サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ」など独特のスタイルは、すでに人々にはおなじみとなっていたはずだ。
第7回の終わりがけには、淀長サンに扮して番組の案内役を務める小松政夫ご本人のところに、植木の父親役の伊東四朗がまぎれこむというサービスカットも用意されていた。
小松が自分のところに来た理由を知らなかった植木
余談ながら、最近小松政夫が著した『昭和と師弟愛 植木等と歩いた43年』(KADOKAWA。大山くまおによるレビューも参照のこと)で読んで驚いたのだが、植木等は、小松が付き人になってからも数ヵ月ほど、彼が役者志望だと知らなかったという。
ある日、植木は、小松がそれまで車のセールスマンとして十分稼いでいたにもかかわらず、なぜ自分の運転手になったのかと、あらためて本人に訊くと、《私、役者を目指してますから》との答えが返って来たので仰天する。じつは植木は本来、運転手がほしいと伝えていたのだが、事務所がそれを「付き人兼運転手」として公募したため、こんな行き違いが生じてしまったのだ。しかし、このとき小松が役者になる覚悟を決めていることを知った植木は、《そうか……俺も親父を継いで寺の坊主になるか、それともミュージシャンになるかと色々考えたときに、うん、俺は、よし、音楽で生きようっていうふうに決めたんだよ》と自らのことを話しながら、励ましてくれたそうだ。
さて、第7回のラスト、時代は一気に10年ほど飛んで1977年、50歳になった植木等が舞台『王将』に挑もうとするシーンで終わった。植木と小松、さらにほかのクレージーのメンバーのその後が描かれるであろう、今夜放送の最終回のサブタイトルは「スーダラ伝説」。植木等が60歳をすぎて、往年のクレージーのヒットソングをメドレーで歌い上げた曲(1990年リリース)のタイトルと同じだ。中学時代、紅白歌合戦でこの曲をノリノリで歌う植木の姿に感激した私には、もう号泣する準備はできている。それではまた、レビューでお会いしましょう。
(近藤正高)