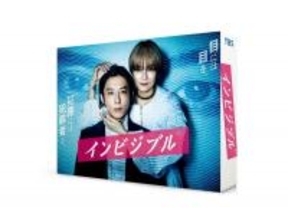ドラマの中では新聞記事の引用から在りし日の金栗四三、三島弥彦の姿が紹介される場面は多い。

天狗倶楽部と押川春浪と『運動世界』
「明治後期というのは、カラー印刷が普及したことで雑誌文化が大きく華ひらいた時代で、ちょっと心得のある文化人がどんどん新たな雑誌を生み出しました。今のYouTuberにも通じますよね。その代表格といえるのが『いだてん』でもおなじみ、天狗倶楽部主宰の押川春浪です。明治41(1908)年創刊のSF雑誌『冒険世界』の主幹を務め、さらに同年、スポーツ雑誌『運動世界』の立ち上げにも参画。数多くの記事を執筆しました」
そう語るのは、BIBLIO店主の小野祥之さん。「いだてん」でストックホルムオリンピックが描かれた明治後期に誕生し、人気を博した雑誌『運動世界』を手に、まずは押川春浪について解説してくれた。
押川春浪は日本初のSF小説家であり、さらには天狗倶楽部の創始者という痛快男児筆頭格。「いだてん」では武井壮が演じる人物だ。
ドラマのなかではあまり目立つ発言も描写もないが、この時期の運動界隈においてはかなりの重要人物だという。そもそも、天狗倶楽部の誕生は明治42(1909)年。つまり、前年にできた雑誌『運動世界』の延長線上に天狗倶楽部の活動があったわけだ。
「ドラマでは金栗四三と三島弥彦ばかりが取り上げられますが、むしろこの時代のスポーツ論評を深めるうえでは、押川春浪がキーパーソンといえます。でも、押川ではドラマとしては描きにくいのかも。選手の物語ではなく、裏方ですからね」
そんな押川春浪の周辺には、早稲田大学野球部の存在があった。
「弟の清が早稲田大学野球部の3代目キャプテンです。その関係で、『運動世界』の主幹を安部磯雄が務めたのでしょう。野球好きであれば、その名を聞いたことがあるかもしれません。“日本野球の父”と呼ばれる早稲田大学野球部創設者です。また、早大野球部5代目主将で、のちに“学生野球の父”と呼ばれる飛田穂洲も天狗倶楽部のメンバーのひとりで、『運動世界』でも寄稿者として何度も登場します。つまり、この当時のスポーツ誌は、プレーヤーが自ら情報発信するためのツールでもあったんです」
武芸百般・三島弥彦を『運動世界』はどう伝えたのか?
明治後期の雑誌を調べると、スポーツ総合誌であれば『運動界』『アスレチック』『ゲーム』、専門誌では『月刊ベースボール』などが次々に創刊されている。ただ、今挙げた雑誌たちは現在、古本界隈でも滅多に出回らないという。
「古本としての扱いが少ない、というのは、あまり流通していなかった、ということでもあります。でも、押川が深く関わった『冒険世界』や『運動世界』、さらにこの二誌を辞めて大正元年に立ち上げた『武侠世界』に関しては少なからず出回るんです。その意味で、押川印の雑誌が当時いかに読まれていたか。
三島弥彦は学習院を経て東京帝国大学(現・東京大学)へ進学。この当時の野球のスター選手であり、明治39(1906)年、秋の早慶戦で球審を務めるなど早稲田大学野球部と親交があったことから、天狗倶楽部に加わったとされる。

「実際に『運動世界』を読むと、三島弥彦の文字はよく出てきます。それは、執筆者としてだけでなく、取材対象者として。三島はとにかく武芸百般で、その活躍ぶりは『冒険世界』『運動世界』を数冊見ただけで見えてきます。『運動世界 第二十号』(明治43年1月刊行)では“ランニングに於ける予の実験”という文章を自分で書いている一方、天狗倶楽部が主催した相撲大会を報じる特集記事では、出場選手としてその様子が描かれています」
相撲ページでは、三島を評して《三島関は駈けっこ、バツテラ(※筆者注:ボート競技のこと)、球投げ、柔道の外に今度はまた角界(すもう)でも名を挙げやうという……》と書かれている。いかに三島弥彦が“何でもできる男”と認識されていたかの証左となる一節だ。
「次の『運動世界 第二十一号』(明治43年2月刊行)では、“諏訪湖の氷滑り”としてスケートをやっています。三島に関しては仲間だし、周囲の人間も面白おかしく取り上げた部分もあるんでしょうね。それと、当時の記事を読んでいてよく目につくのが“痛快”という文字です。三島たちの相撲の様子についても《痛快ぢゃ痛快ぢゃ馬鹿に痛快ぢゃ》と記しています。

金栗四三の走りと、大森兵蔵のクラウチングスタート
明治後期のスポーツ雑誌でわかりやすく描写されている三島弥彦のスター性。その一方で、ドラマ「いだてん」における真の主役、金栗四三はどのように描かれているのか?
「それがですね……なかなか金栗の文字は出てこないんですよ……あ、あった、ありました。『運動世界 第三十号』(※明治43年11月発行)の『高師名物長距離走』という記事によると、金栗君、3着になっています。記事の副題には“韋駄天達の駈競べ 大塚大宮間の十五哩をタツタ”とありますので、ちゃんと当時、彼らランナーは“韋駄天”と呼ばれていたんですね」
高師、というのは東京高師、現・筑波大学のこと。当時、学校のあった東京・大塚から大宮までの15哩(約24キロ)走ったレースの結果が記されていた。
このレースに関しては「いだてん」でも描かれたエピソード(※第4回「小便小僧」)で、ドラマではスタート直前に三島弥彦の車周辺で立ち小便をして出遅れたために3着になった、というシーンを覚えている方も多いはずだ。
記事にはレース中の写真もあり、完走タイムも全員分記載されている(※1位が1時間45分40秒。3位の金栗は1時間46分4秒)。ただ、レース内容に関しては1・2着争いについてだけ主眼を当てているため、金栗四三がどんな走りをしたのかはタイム以外にはわからない。
「オリンピック以前の号で、ほかに金栗の名前はなかなか出てきませんね。もちろん、私もすべてに目を通しているわけではありませんし、今、当店に置いている『運動世界』はほんの一部ですので、ほかの号に出てくる可能性はあります。でも、何冊がパラパラめくっただけで出てくる三島弥彦との差は歴然です。金栗三四のエピソードが『運動世界』で少ないのは、天狗倶楽部のメンバーではなかった、というのもあるかもしれないですね」
そんな金栗よりも『運動世界』に登場する名前があった。
「写真解説、ということは、それだけ当時の世の中では言葉で説明しきれない動きだったんでしょう。大森は同じ号の『運動世界』で、“オリンピツクゲームに就て”という特集記事も執筆しています。当時、オリンピックなんて誰もわからなかったわけですから、いかに大森が日本のスポーツ界において最先端の立場にいたか、ということが見えてきます」

ストックホルムオリンピック惨敗を当時の雑誌はどう論じたのか?
今も昔も、スポーツ雑誌で重要なのは、試合前の事前情報以上に、試合後の振り返り、考察記事だ。では、当時の雑誌ではストックホルムオリンピックで大敗した金栗、三島についてどう論評したのだろうか?
「ストックホルムオリンピック直後に刊行された『冒険世界』(大正元年9月号)に、“三島金栗両選手に寄す”という特集記事があります。書いたのは橋戸頑鐡です。この名前はペンネームで、本名は橋戸信。社会人の都市対抗野球MVPに贈られる“橋戸賞”の由来となった人物です。やはり当時は、一流アスリートが一流アスリートについて書く、という時代だったんですね」
では、その論評について、一部引用してみよう
《三島君と云い金栗君と云い、共に我國双絶の運動家である。現に三島君の如きは、未だに會心の敵を得た事が無いと云って居る程の剛の者である。それが瑞典の競争では予選にさえ入る事が出来なかった。
「足を痛めて居た」というのはドラマでは出てこなかった敗因だ。
《金栗氏の如きは、羽田の予選会でマラゾンレースに一躍世界記録を破つたのであるが、(中略)果然氏は殆ど問題とならぬ程の敗北を遂けた。(中略)金栗氏は他の人々の忠告に従わず、靴をはいたため敗北したと報じられたが、事実とすれば実に残念な事であつた》
これはどういうことだろうか? 金栗四三がストックホルムオリンピックで足袋を履いて走った、というのは「いだてん」で描かれた通り、こちらが史実のはず。敗因といえば、夏の暑さと長い旅路、道に迷っての途中棄権、というのは他の資料を当たっても有名なエピソードだ。この『冒険世界』は刊行時期からいって、金栗四三の帰国前に執筆されたもの。当時の通信手段では、敗北以上の情報が正しく伝わらず、憶測が憶測を呼んだとも推察できる。
いずれにせよ厳しい論調が並ぶなか、最後はこんな未来志向の文でまとめている。
《三島、金栗氏の苦い経験が、唯敗北と云ふ醜い形骸許でなく、其副産物として泰西(※筆者注:西洋のこと)の運動振りを研究して帰来るを喜ぶ》
「いだてん」第16話でも、この論説を受けたかのようなセリフを役所広司演じる嘉納治五郎が叫んでいた。最後にそのセリフを引く。それこそが、当時の識者が願ったことであり、宮藤官九郎がドラマを通して描きたいことなのではないだろうか。
《今や多くの後輩が金栗君の背中を追いかけている。陸上だけじゃない。
(オグマナオト)
※取材協力:神田のスポーツ専門古書店BIBLIO(ビブリオ)
※雑誌引用文に関しては基本的に原文ママだが、文字化けの恐れもある旧字体に関しては一部、新字体に置き換えている。