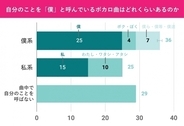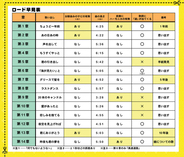J-ROCK&POPの礎を築き、今なおシーンを牽引し続けているアーティストにスポットを当てる企画『Key Person』。第29回目は自らを“期待外れの名手”と言いながらも日本を代表するバンドとして活躍し続けるmoonridersが登場。
ムーンライダーズ
ムーンライダーズ:1976年のデビューから45年以上のキャリアを誇るロックバンド。70年代前半に活躍した、はちみつぱいを母体に1975年に結成される。76年に鈴木慶一とムーンライダース名義でアルバム『火の玉ボーイ』でメジャーデビュー。翌77年にムーンライダーズとして初のアルバム『MOONRIDERS』を発表し、以降コンスタントにリリースを重ねる。86年から約5年間にわたり活動を休止したが、91年にアルバム『最後の晩餐』で活動を再開。
はちみつぱいの解散は 事務所も含めて経済面が原因
──moonridersは1975年に結成され、76年1月に“鈴木慶一とムーンライダーズ”名義のアルバム『火の玉ボーイ』でデビューされました。結成からデビューをしたあともアグネス・チャンなどのバックバンドとして活動されていましたが、なぜデビュー後もバックバンドを続けていたのでしょうか?
鈴木
「moonridersの結成前は、はちみつぱいというバンドにいたけど、当時は事務所も含めて経済面が崩壊寸前で。にっちもさっちもいかない経済面が解散の原因だったんです。それで解散して、75年にはちみつぱいの4人と私の弟の鈴木博文と椎名和夫でmoonridersを組んだんです。
──バンドを自然消滅させないために活動の一環として始められたと。
鈴木
「そうそう。アグネス・チャンのツアーでは週末になると全国に行っていました。彼女は香港の方なので、ライヴは邦楽もあるけど、だいたいが洋楽なんです。当時はいわゆる芸能界とロックミュージックとは非常に難しい関係があったんですよ。そうやってバックバンドを1年間やり通したから、経済面が少し安定しましたね。
白井
「確かにあの時代は経済面が大切だったな。僕たちも途中からアレンジやプロデュースをやり出したでしょ? バンドをメインにやりたい気持ちもあったけど、事務所の存続を考えてやるしかないというところがありましたから。」
──白井さんは77年にmoonridersに加入さたんですよね。
鈴木
「白井くんのことは加入するずっと前から知っていましたよ。斉藤哲夫さんのバックバンドをしていた時からのつき合いだし、哲夫さんのライヴの練習を私の実家でやってたよね。」
白井
「鈴木くんの家が大邸宅だったから(笑)。」
──(笑)。moonridersの作品に関してもうかがわせていただきますが、『火の玉ボーイ』はアメリカンロックの要素が多い印象がありました。続く『ムーンライダーズ』(1977年2月発表のアルバム)になると異国民謡、ラテン歌謡など、色濃く無国籍なサウンドが集まっていて。
鈴木
「楽曲が出来上がった人から録音していくという恐ろしい仕組みだったんです。コンペティションがないから、20曲作ってそのうちの10曲を録音するとかじゃないんだよね。予定曲数が集まったら終わり。だから、“早く作らなきゃ!”という競争心が生まれて、こちらとしては焦るんですよ。そんな中で作ったアルバムだったけど、私たちの原点になるくらいにメンバーの個性が出ている気がしています。」
──争奪戦が繰り広げられたからこそ、集中して楽曲を作られた結果が個性につながったのかもしれませんね。
鈴木
「どうだろうね? その当時の日本の音楽シーンに関しては、細野晴臣さんやあがた森魚さんなども無国籍な音楽を始めたんです。私も録音などに参加したあがたさんは特にだけど、影響も受けて次のアルバム『イスタンブール・マンボ』(1977年10月発表)では一気に無国籍な音楽になりました。それと言うのも、江利チエミさんがセルフカバー作品を出す時に我々が3曲ほどアレンジをしたんですよ。その中でボツになった岡田 徹くんがアレンジした「ウスクダラ」がとてもいい仕上がりだったから、もったいないと思ったことが『イスタンブール・マンボ』を作るきっかけでしたね。」
──なるほど。競争しながら曲を作るというのも驚きました。moonridersの活動歴を調べている中で、その年代に売れた曲としてみなさんの楽曲が出てこなかったから、当時の日本の音楽リスナーになかなか受け入れられなくて困ったりしたのかなとも思いました。
白井
「なかなか受け入れられないよ。」
鈴木
「ヒット曲を出したい気持ちはずっとあったけど、見事に外れていくんだよね。CMとタイアップしても外れるし。もう外れ慣れしちゃってきてね(笑)。」
白井
「外しの帝王だね(笑)。」
鈴木
「オルタナティブ感をずっと持ち続けちゃった。でも、それはそれで良かったと思っています。」
期待を持ってもらえたから ずっと挑戦し続けられた
──それ以降も発表される作品は基盤となるバンドの音楽性は残しつつも、メンバーが楽しみながらいろんなジャンルの音楽に取り組まれている印象を受けました。『ヌーベル・バーグ』(1978年12月発表のアルバム)では日本ではいち早くシンセサイザーを取り入れ、『モダーン・ミュージック』(1979年10月発表のアルバム)ではヴォコーダーを取り入れられていました。新しい機材を取り入れていると、当時の日本のレコーディングスタジオでは対応できないとか、レコード会社に制作費がかかると言われたりとかはしなかったですか?
鈴木
「新しいことに挑戦するにはすごく手間と時間がかかるから、それを許してくれた当時のレコード会社の方には感謝しています。他で得た資金でレコード会社はチャレンジを許してくれていたから、当時の音楽業界はまだ余裕があったのかもしれない。“こいつら、面白いことをやりそうだな”と思ってもらえて、先行投資してくれる感じだったよね?」
白井
「その都度、いろいろ期待してくれていましたね。」
鈴木
「次はヒット曲が出るんじゃないかという期待を持っていただけていたおかげで、ずっと新しい挑戦を続けてこられました。結果的に“ヒット曲がない!”ということになるんだけど(笑)。」
白井
「期待作りの名手!」
鈴木
「期待外れの名手かな?(笑)」
──そんなことないですよ(笑)。その時代で作られた作品や楽曲を振り返ってみて、どのように思われますか?
鈴木
「外部の方やレコード会社の方、他のバンドやいろんな方から“こんな曲をやれば売れる”と言われた音楽をやらずにアルバムを作ってきたけど、“これをやらなきゃいけない!”と思って作ってこなかったことが、結果的に良かったと思います。過去の作品を聴いて…まぁ、“これはマズいな”と思うところは多少あるけど、そんなにたくさんはないですね。」
──まさにそうだと思います。振り返って作品を聴いていても、デビュー間もない頃からバンドの軸がしっかりとありますし、moonridersサウンドが出来上がるまでがとても早い印象がありました。だからこそ今の作品を聴いても軸は変わらないですし、今だから表現できる音に挑戦しながら、クオリティーの高い音楽を作り続けてこられていると思います。
鈴木
「恥ずかしいことはやらなかったのが良かったと思いますよね。毎回、アルバムを作る時に、“違うことをしよう!”とメンバー全員が思うんです。それが推進力になっていましたね。」
──バンドの歴史の中でも起点となるのは、『DON'T TRUST OVER THIRTY』(1986年11月発表のアルバム)だと思います。発表後の結成10周年ライヴを機に5年間の活動休止をされましたので。91年発表のアルバム『最後の晩餐』で活動再開されますが、この2作は明らかに楽曲のカラーが違っていますよね? その変化を感じられた、空白の5年間はいかがでしたか?
鈴木
「メンバー全員が事務所には所属していたので、それぞれがプロデュースや個人の活動をする期間にしようと思ったんですよ。1年から2年くらいだと予想していたけど、気づいたら5年が経っていて(笑)。」
白井
「みんなが忙しくなっちゃってね(笑)。それぞれが売れっ子になっちゃった。でも、その間に若いアーティストと音楽を作ったり、ライヴをしたりしていろいろなものを吸収したんです。その経験が『最後の晩餐』に反映されていますね。」
──『DON'T TRUST OVER THIRTY』はいろんな方と楽曲を共作されていましたが、『最後の晩餐』はメンバーのみで曲を作られています。今回はメンバーの曲でアルバムを作ろうという意識があったのですか?
鈴木
「それもあったと思うね。あと、『最後の晩餐』を作る時に常に全員スタジオに入ろうということだけは決めていました。現場で弁当だけを食べて帰る人もいたけど、一緒にいるとということをこのアルバムだけは意識していました。」
──メンバーの間でもみんなでアルバムを見届けて作ろうという意識が5年間を経たことで生まれたんですね。
鈴木
「5年の間に現場で一緒になったメンバーもいたけどね。コンピューターで打ち込んで作るだけじゃなく、スタジオにいろんな楽器を置いて好きに弾いて、打ち込みしてる間に暇な人はセッションしたり。」
白井
「現場で全然違う曲を作ったりしてね(笑)。」
こう見えて我々は 意外とサービス精神が豊富
──それぞれが過ごす時間を大切にできる空間が作られていたんですね。そして、一番訊きたかったことなのですが、活動休止期間中でもバンドの周年やバンド関連のことで何かがあった時にはライヴを開催し続けています。moonridersが続いているのは、ライヴ活動も大きな要因だと思ったのですが、いかがでしょう?
鈴木
「それはあるかも。ライヴが嫌いな時期もあったけどね。ライヴをすることは楽しいし、こう見えて我々は意外とサービス精神が豊富なので(笑)。お客さんを楽しませるとか、意表を突くことを考えるのも楽しくて。それって2011年から活動休止中のことですよね?」
──はい。白井さんはいかがですか?
白井
「昨年の12月に恵比寿ザ・ガーデンホールで開催した『moonriders アンコールLIVE マニア・マニエラ+青空百景』では、新しいライヴのプロットが出来上がった手応えがありました。曲間の表現の仕方やステージの始まり方など、ものすごく新しいシーンが入ってくる気がしていて。常にライヴに対しても新人の感覚を持っているから、楽しいんでしょうね(笑)。」
鈴木
「そのライヴは『マニア・マニエラ』(1982年12月発表)と『青空百景』(1982年9月発表)というアルバムを再現するために開催したけど、完全再現にはならなかった(笑)。そうやる気も全くなかったし。でも、いろんなことをしたんです。モップで床を掃いたりしてね。終わったらとても面白いライヴになりました。」
白井
「Open Reel Ensembleも参加してくれたから、表現の幅がすごく広がったんですよ。常に面白いことを実現しようとしているから、『マニア・マニエラ』と『青空百景』を表現するためにこのような編成にしました。他にも僕が自作した楽器の“ギタギドラ”を演奏するという挑戦もしたし。81年か82年の渋谷公会堂でのライヴを再現するという意味で言えば、丸、三角、四角の札を出したりしたので、音楽以外でも忙しい部分がありましたね。」
鈴木
「それも含めてライヴをやっているということは、とてもいいことだと思います。最新作のインプロに挑戦したアルバム『Happenings Nine Months Time Ago in June 2022』(2023年3月発表)もそうですが、我々のできることは未だに広がっている気がしますね。」
──バンド活動って休止したりすると戻ってこられない場合が多い印象がありますが、moonridersのライヴはメンバーにとっても、ファンにとっても帰ってくる場所になっている気がします。
鈴木
「2020年以降にメンバーと再びライヴをやるようになってから、毎回演奏する曲が違うんですよ。個人的に私は相当練習なくちゃいけなくて(笑)。ライヴで演奏したことがない場合もあるので、耳コピしなきゃいけないのが大変。でも、それをやめちゃったら終わりだと思うな。」
──多くの方はやっていない曲や久し振りすぎる曲は避けたくなると思うので、それをされていることがすごいです。今の自分たちで演奏するから違った景色が見えたりもするのでしょうね。
白井
「そうそう。その当時とは違う感じになるし、今の自分たちの感じている雰囲気で表現したりもするから。」
──お話をうかがって、みなさんが常に音楽を楽しまれて、挑戦し続けているんだということがより深く分かりました。では、最後にバンドにとってのキーパーソンを教えてください。
鈴木
「今はやはり岡田 徹くんになりますね。知り合ってから長いし、いい曲もたくさん作っていたし、その曲に歌詞を書かせてもらったし。楽曲を並べてみるとこの曲もあの曲もいい曲だったと思いますよ。岡田くんと最後に交わした言葉について話すと、1月にファンクラブのイベントがあった時に岡田くんが私に対して“いい曲がどんどんと出来上るね”と言っていたので、“そんなことないよ。岡田くんも作ってよ。2020年以来作ってないじゃない”と答えたんです。わりと冷たい言い方をしてしまったので、それが少し悔いに残ってはいますね。」
白井
「でも、それは怒って言っているわけじゃないからね。」
鈴木
「岡田くんに“新曲を作ってよ”という気持ちが本当に強かったし、彼の曲が聴きたかったんですよ。もう新曲が聴けないのかと思うと残念で悲しいことだけど、本当にたくさんのいい曲がある。彼の曲はmoonridersのメインストリームをどこか支えていたところがあって。岡田くんがそんな曲を作ってくれるから、私は少し変な曲が作れていた気もしますね。」
──岡田さんがいるから新しいことに挑戦できたということですね。
鈴木
「そうそう。かしぶち哲郎くんもそうなんだよね。11年ぶりにレコーディングをした『it's the moooonriders』(2022年4月発表のアルバム)の制作時もふっと彼がいないことを感じたんです。私の曲がある、白井くんもある、岡田くんもあったし、武川雅寛くんも夏秋文尚くんも鈴木博文もある。でも、何か足りないと思ったら“あっ、かしぶちくんだ!”と強く思いました。」
白井
「あの人は独特な曲を作っていたからね。」
鈴木
「その要素があってバランスがいい作品が生まれるんです。だから、また次の作品を作る時に岡田くんの不在間を感じると思うんですよ。」
白井
「僕がmoonridersに加入する時、最初に電話をしてきてくれたのが岡田くんだったんです。クラブの先輩だった彼が、僕をこっちの世界へ導いてくれたんですよね。だから、今の僕があるきっかけを作ってくれたのが岡田くんなので、僕もキーパーソンは彼になりますね。」
取材:岩田知大