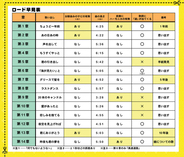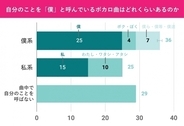「水」の歌詞に見る純粋さ
《もしも誰かを愛したら 素直なその気持ちを/その人に伝える それがこの世界へ/生まれ落ちた理由だから/Ah とまどいながら話す言葉は 何よりもきれいさ》《Ah いつの日にか みんなどこかへ消えてしまう気がする/Ah 伝えなくちゃ 素直なその気持ちを今すぐ/その人に》(M1「水」)。
人間の存在理由を突き詰めたような歌詞。ロックや音楽の意義、さらには芸術というものの意味をうかがうこともできるだろう。
これまで、SHERBETSの他、BLANKEY JET CITY(以下BJC)を始め、AJICO、JUDE、PONTIACS、浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSと、縦横無尽にさまざまなミュージシャンたちと共に音楽活動をしているベンジー。今は2、3バンドを掛け持ちしているアーティストも珍しくなくなったけれども、日本のロックシーンでは1990年代頃でもまだ、タブー視…というまでの嫌悪感があったとは思わないけれど、少なくともメジャーどころで複数バンドの掛け持ちする人はそれほど多く見受けられるものではなかった(忌野清志郎が1980年代にRCサクセションと並行して、坂本龍一とユニットを組んだり、ソロもTHE TIMERSもやっていたのは例外中の例外で、今となると何とも清志郎らしかった行為のように思う)。
だが、ベンジーはそんな慣例に合わせた様子がなかった気はする。動きも早かった。SHERBETS(当時はSHERBET)をスタートさせたのが1996年。BJCはまだ存在していた。そればかりか、前年に5thアルバム『SKUNK』、翌1997年に6thアルバム『Love Flash Fever』を発表している。
そのベンジーの新しいバンドに向かう動機を、このM1「水」の歌詞に重ねることができるように思う。今やっているバンドを一旦終わらせて…とか、ソロ活動を宣言して…とか、そんなことをやるより先に動く。そういう行動原理があるように感じられる。SHERBETSのスタート時もそうだった気がするし、AJICOやJUDEの時も同じだったような気がする。
アコースティックならではの良さ
純粋、ピュアを感じるのは歌詞だけではない。そのサウンドからも如何なく感じられるところだ。特にバンドの1stアルバムであるこの『セキララ』は、アコースティックな生音が多いだけに余計にそう思う。ザラついたアコギで極めてロック的なリフレインを聴かせるM2「760」もあれば、明るく軽快なストロークを鳴らすM7「Black Butterfly」やM8「ひまわり」もある。アコギと言えども、楽曲によってスタイルの異なる演奏を聴かせているところに、変にカテゴライズすることのないフリーダムなスタンスを見出せる。そこも特徴的ではあろう。
また、この時期はBJCと並行してSHERBETSをやっていたことを考えると、聴き手としても、どうしてもそこに両バンドの差異を見出してしまうところではある。エッジーなギターサウンドとシャープなリズムを信条としていた(と思われる)BJC。少なくとも1stの時点では、ギターサウンドにおいてそのBJCとは真逆と言ってアプローチも見せていたSHERBETS。どちらがいいとか悪いとか言うことではなく、案外ベンジー自身も当時はBJC]と異なるスタイルを求めていたのではないかと想像してしまうサウンドではある。そうだとしたら、それもまたアーティストとしての純粋さを感じるところではなかろうか。ハードさを指向したあとで柔らかなものを求める気持ちは我々も分からなくもない。
話が少しズレた。『セキララ』に戻す。本作で最もアコースティックの良さを感じられるのはM4「ソリ」ではないかと個人的には思う。エレキギターは電気的に音を増幅させるのでアンプで音の大小を調節するし、エフェクターを介せばさまざまにトーンを変化させることもできる。対して、アコースティックギターは、基本的には電気を介さないので、音の大小、トーンの強弱を決めるのは演者のみである。大きい音を鳴らす時には強く弾かなければならないし、小さく鳴らす時は優しく弾くことになる。また、一般的にアコギはしっかりと弦を押さえないといけないと言われていて、エレキギターよりは演奏が難しいとも言われる。プレイヤーの力量が問われるわけだ。M4はイントロからギターの強弱が分かるし、楽曲が進むに連れてテンションが上がっていくことがよく分かる。人が弾いているということをはっきりと認識できるのである。ギターだけではない。すべての楽器にしっかりと抑揚がある。M4に関しては個人的にはドラムもいいと思う。サビに突入する前のフィルイン。Ringo Starr的と言ってもいいだろうか。タム、フロアタムを多用したドラミングは聴いててアガるし盛り上がる。問答無用にカッコ良い。
バンドアンサンブルで言えば、M9「ゴースト」を『セキララ』のベストテイクに推したい。ピアノのループにハモニカやギターが重なっていくM6「麦」も素晴らしく、甲乙付け難いけれども、個人的には僅差でM9に軍配を上げた。まず、先に述べた通り、ド頭から強弱がはっきりと分かるアコギの音色がいい。しかも、リズムが3拍子というのが新鮮だ。アルバムの後半にあることで、作品をよりバラエティーにしているとも思う。そこに、そのアコギの音の中を縫うかのようなピアノが奏でられる。この2つのアンサンブルだけでも見事なのだが、そこに文字通りの3拍子をタンバリンが鳴らし、ベースも重なっていく。何かひとつの楽器が突出するわけではなく、それぞれが自分の持ち場を堅持しながら楽曲が展開していく様子は、このバンドの貫禄すら感じさせるところだ。1番の歌終わりのギターソロの箇所では、ピアノがスムーズに3拍子へと変化するところも実にいい。その臨機応変な感じ(?)にはメンバー間での意思疎通が良好なこともうかがえるし、こういうところがバンドならではの面白さということもできると思う。圧巻なのは後半、サビの繰り返しのあと、それぞれの楽器の音が密集していく箇所。明らかにテンポが速くなっていくが、グルーブは決して損なわれない。これもまたバンドらしさであり、バンドの醍醐味と言えるだろう。テンションの高さに思わず聴き手も煽られてしまう演奏である。そのテンポの速さを粗さと見る向きもあるかもしれない。だが、仮に粗さの表れだったにせよ、そこは好意的に受け取りたい。《とまどいながら話す言葉は 何よりもきれいさ》とは、こういうことも含まれているのではなかろうか。そんなふうに思う。
最新取材でも伺えるベンジーらしさ
先にベンジーを純粋だ、ピュアだと述べた。筆者の想像でそう考えた部分もあるけれども、決してそれだけではない。2023年4月19日に当サイトで公開されたニューアルバム『Midnight Chocolate』のSHERBETSインタビュー。そこでの発言にも彼のスタンスがはっきりと表れていて、その言葉は『セキララ』の楽曲とも見事にシンクロしているように思う。こうなると、発言のブレがないとかいうことではなく、アーティストとしての芯に強さと言ってもいいのかもしれない。例えば、新作でのギターアプローチについて、ベンジーはこんなことを語っている。
“そういうのも全部が感覚。“SHERBETSのギターはこうじゃないといけない”というようなことは一切ないんだ。時間がかかるのは大変だから、“シンプルなのが良いわ”というのはあるけど”。以下はアレンジについての質問に対する返答だ。“この4人でやると自然とそういうものになるんだよね。頭から始まってふた周りめからキーボードがフワンと入ってくるけど、それも言ったわけじゃなくて福士さんが自由にやったことだしさ。そこがSHERBETSのいいところ”。
両発言からSHERBETSには決め事がないことがよく分かる。『セキララ』のアプローチがああなったことも、この発言が証明しているように思う。最新インタビューでも“作っている時は周りがあまり見えてない。だけど、でき上がるとちゃんと良いものになるから不思議なんだよね”とも語っているが、この発言はM9「ゴースト」のアンサンブルについても同様のことが言えるのではなかろうか。
冒頭でM1「水」の歌詞を“純粋さを凝縮したかのよう”と言ったが、それもまた今回のベンジー発言をもって裏付けることができる。新作の制作にあたって事前にどんなことを構想したのかという問いに対して、“毎回だけど、何も考えずにやるのがSHERBETSの特徴”とズバリ。流石にまったく何も考えずに臨んだわけではないだろうが、妙な思考をアレコレと働かせる必要はないということだろう。その後こうも続ける。
“歌というのは作為的になっちゃダメじゃん。本物じゃないといかんでしょう? “本物になるぜ!”と歌うのも変だから(笑)。だから、フラットな感覚で歌うというかさ。歌はすごく深いものだし、ものすごく簡単なものだと思うんだ。レコーディングをする時は、何も考えずにいく”。
まさに《素直なその気持ちを/その人に伝える》ということだろう。ここでもベンジーのちゃんと筋の通った姿勢がよく分かる。そうしたスタンスが楽曲にも滲み出ているからこそ、SHERBETSを始め、ベンジーのやっていることは多くのロックファンから支持されているのだろう。
『Midnight Chocolate』のSHERBETSインタビューがとてもいい内容で、同じくインタビューを生業とする者として完全に羨望するだけだったので、そこから大分引用させてもらった。この場を借りて御礼を申し上げます。新作が聴きたくなるインタビューだと思うので、未読の方はこちらも是非!
TEXT:帆苅智之
アルバム『セキララ』
1996年発表作品
<収録曲>
1.水
2.760
3.きせき
4.ソリ
5.丘へ行こう
6.麦
7.Black Butterfly
8.ひまわり
9.ゴースト(ALBUM MIX)
10.ラズベリー/シークレットトラック