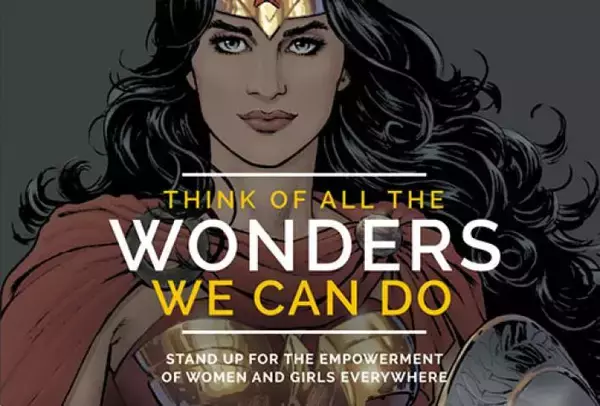
男女不平等をめぐる多くの矛盾や不条理を真正面から扱い、話題を集めたNHK連続テレビ小説『虎に翼』が昨年話題を集めた。物語の中でキーワードとなった「家父長制」。
社会学者の上野千鶴子氏と、一橋大学教授の佐藤文香氏による対話の中でそのシステムを詳しく説明する。※本記事は、2024年11月21日に丸善ジュンク堂書店池袋店で行われたイベントの内容を基に作成しています
平安時代、女は愛人を何人つくっても良かった
佐藤 『家父長制の起源』の著者であるアンジェラ・サイニーは、イギリスの科学ジャーナリストです。なので、自分自身で研究するのではなくて、いろんな専門家のところに足を運んで話を聞いていきます。
もちろん前提として、膨大な文献を読んでいます。下調べをしたうえで、最新の成果を持っている考古学者や人類学者、霊長類学者など、さまざまな人たちに話を聞きに行っている。このスタイルがすごく生きた本だなという風に思いました。
上野 科学ジャーナリストとは何か。簡単に言えば立花隆さんのような人です。立花隆さんって「知の巨人」とか言われたけど、彼自身は研究者じゃありません。膨大な情報を集めて、それをどの専門家にもできないような仕方で、網羅的にわかりやすく提示してくれた。
これって、やっぱり大切な役目ですよ。専門的な研究者と一般の人たちをつなぐための、かなめの位置にある大切な仕事なので。
佐藤 だからこそ寂しいのが、いま日本でそれに類する方はどなたになるのかな、ということです。サイニーのようなフェミスト・サイエンス・ジャーナリストが日本でも出てきてくれたら、すごく嬉しいですね。
上野 日本ではポピュラーカルチャーがある種の役目を果たしているように思いますよ。
例えば平安朝。この時代を扱ったドラマや漫画、動画は沢山ある。いろいろな形で、「えっ、平安朝って今の日本と結婚の仕方が全然違うし、夫婦同姓なんて全然なかったんだ!」と学ぶことができる。「女は愛人を何人つくっても良いんだ!」とかね。最高じゃん(笑)。
そういう知識が、漫画などのポピュラーな媒体でちゃんと広まっているから、一種の役割を果たしているんだと思います。
作者たちは、情報は専門家から得ている。例えば双系制とか、妻問婚(注:夫が妻のもとに通う婚姻形態)とか。
国連の家父長制を世に知らしめた「事件」
上野 ここで、佐藤さんが監訳されたシンシア・エンローの『〈家父長制〉は無敵じゃない――日常からさぐるフェミニストの国際政治』(岩波書店)を見てみましょう。
こんな画像を用意してきました。ちょっと解説してくださるかしら? メチャクチャ面白い話です。かつて国連でこんなことがありました。
佐藤 『ワンダーウーマン』という作品、ご存じでしょうか。アマゾネスですよね。とても強くてパワーがある、闘う女性像。これを国連が2016年に「女性と女児のエンパワーメントの名誉大使」に任命したんです。
ところが、ちょっと見ていただければわかるように、これが非常にエロティックで。女性の性的な部位を強調したようなアイコンじゃないですか。なので、女性たちをはじめとする国連職員が抗議の声をあげました。こんな実在でもない、過剰にセクシャライズ(Sexualize)されたシンボルを私たちは大使にする必要があるのか、と立ち上がった。
そういうエピソードが、『〈家父長制〉は無敵じゃない』の第8章で紹介されています。
上野 日本にも似たような炎上広告がいっぱいありますよね。いやはや、国連も同じことをやっているのかと(笑)。大きなパネルをわざわざ国連のビルに張り出したんですって。
ところが、女性の職員たちが “Don’t Sexualize Us!” と言った。だって、強い女であるためにこんな露出度の高い恰好をしている必要は何ひとつありませんから。それで、抗議があって掲出をやめたっていうんだから、国連も日本とあまり変わらない(苦笑)。
佐藤 結局、たった2ヶ月で降ろしちゃったようです。
上野 なに、2ヶ月も出していたの⁉ 3日で降ろせばよいのに!
佐藤 でもその時に、「抗議の声に応えて」ということは絶対に言わないんです。
上野 あっ、言わないんだ。
佐藤 「役目を終えた」と言うんです。
上野 ああ、そう……。
佐藤 シンシア・エンローはこういう風に書いています。「家父長制的な人びとの学習作法のひとつとは、自分たち以外の人間からなにかしら教わったという事実を否定するやり方を学ぶことのようである」と(『〈家父長制〉は無敵じゃない』182ページ)。
上野 なるほどね。“マンスプレイニング”と同じね(注:manとexplainingを合わせた造語。男性が、相手が女性だと無知であると決めつけ、上から目線で物事を説明しようとする態度)。「そういうことは元から僕ら、知ってたもん!」って。
佐藤 元から知っていたし、「フェミニズムを学んだ女性たちの圧力なんかに自分たちは屈しないんだ」ということを強硬に示そうとする。
上野 じゃあ国連も家父長制なんだ(笑)。こういう事例が出てくると、よくわかる。
エンローさんの本の中では、家父長制に亀裂が入る場面がいっぱい紹介されます。そんなに簡単に家父長制は再生産されるわけじゃないんだ、と。
そういう時に、私たちが抵抗するためのひとつの方法が、ドラマ『虎に翼』に出てくるキーワード、「はて?」だと思うんです(注:主人公の寅子が、世の中の常識や不条理などに疑問を抱いた時に発する口癖)。
この言葉には時を止める力があるから。
「はて?」を沢山の女の人たちが言い続けてきて、そのつど、家父長制を揺るがしてきた。だから家父長制は決して無敵じゃないんだよ、というのがエンローさんの本のメッセージです。
考えてみれば、まったくその通りですよね。エンローさんの言うように、「どんな制度も、それに従う人の協力や共犯関係なしでは持続しない」のですから。奴隷制度だって、奴隷頭(どれいがしら)という人たちが主人に協力していたからこそ成り立っていたわけでしょう。
佐藤 「はて?」というのは、たぶんシンシア・エンローの言葉でいうと「フェミニスト的好奇心」になると思います。
彼女は自然とか伝統とか、あるいは「些細な問題」だとか、そういう問いのひとつひとつに好奇心を寄せて、それがある種の意思決定の結果だということを暴き出していきます。そしてフェミニスト的好奇心によって、その意思決定した人に責任を取らせようとする。そんな闘い方についても、この本の中では書かれています。少し引用しましょう。
フェミニスト的注意をむけること、フェミニスト的問いを投げかけること、フェミニスト的調査を行うこと、隠されたジェンダー問題を露わにする概念をつくること、多様でひらかれた幅広い連帯をつくること、そして、慎重さと創造性をもって行動すること――そうすれば、家父長制に勝ち目はない。(『〈家父長制〉は無敵じゃない』195ページ)
これを読むと、ちょっと元気が出ませんか?
家父長制から「ご褒美をもらう」女性たち
上野 ところで、『家父長制の起源』はさまざまな時代や社会について、本当に目配りよく論じてありますが、そのうえでなかなかリアルなことも書いてある。「女同士の連帯は難しい」ということにも触れていました。
佐藤 そうですね。分断線がとてもいっぱい引かれているので、単にジェンダーが同じだからというだけで、簡単に連帯できるものでもないということですよね。
上野 家父長制からご褒美をもらえる女たち、得をする女がいる。しかし他方では、そうじゃない女たちもいるわけです。
ケイト・マンという人が『ひれふせ、女たち:ミソジニーの論理』(小川芳範訳、慶應義塾大学出版会)という本で論じています。家父長制というのは、ご褒美とペナルティのセットであると。家父長制に貢献することによってご褒美をもらう女たちがいる一方で、家父長制から逸脱することで罰される女たちもいる。
日本では、ミスコン(ミスコンテスト)に反対した人たちに向かって、「お前たちはブスでミスコンに出られないから僻(ひが)んでいるんだろう」と言った人もいる。ミスコンで優勝した人たちのその後の人生はとても有利だとデータからわかっているので、その人たちのチャンスを奪うのか、というような声もあります。
佐藤 分断統治は支配の基本ですよね。
上野 その通り。よい話が出てきましたので、せっかくだから言っておきましょう。女が「初の×××」と言われて職場に入っていくとどうなるか。大体ふたつのパターンがあります。
ひとつは、「お前は女として認めないから」「男並みに扱ってやる」と言われて、男勝りで生きていく道。もうひとつは“職場のペット”になって、“女の子”になる道。どちらに行くのかは、大体はルックスによって左右されます。これが第一の分かれ道。
2人目が来ると、今度は何が起こるか。分断統治が始まるんです。男性が「〇〇さんと違って、きみは女子力高いね~」なんて言って、女の子たちふたりの間に楔(くさび)を打ち込んでいく。片方の女の子をもてはやし、もう片方の女を腐すようになる。
3人目が入ってくると、ようやく少し変わってきます。やっぱり集団の中で一定の数を占めないと、「初の」とか「2人目の」くらいでは、組織文化というものはなかなか変わらない。3人いると「女もいろいろだね」ということになってくるでしょう。
佐藤 そうですね。だから下手をすると、「やっぱり女の敵は女じゃないか」みたいな話になりがちなんですが、いやいや、そうではないんです。男の人たちだって連帯するのは大変じゃないですか。同じように女性だって、ただ単に性別が一致していたからといって、簡単に連帯できるわけではないのだ、ということですよね。
家父長制というのは女性たちを共犯に引き込みつつ、そして分断するというシステムなので、本当に難しいです。
上野 共犯者にはちゃんとご褒美が出ますからね。それがルッキズムに左右されるというか、ルックスによって露骨に扱いが変わったりもしますけど(笑)。
私たちの目の前の状況は変えられる!
佐藤 それにしても、『家父長制の起源』の解説で上野さんが紹介してくださった「栄養人類学」のお話は面白いですね。ジェンダーの視点を持って考古学を研究する人が出てきた結果、何がわかったか。これまでの様々な発見が、私たちが生きる現代の価値観のバイアスに左右されていたと判明していく。つまり、私たちは「見たいものを見ていた」ということなんですよね。
従来の、「石器時代にはハンターは男性だった」「女性は火を焚いて子守りをして待っていた」みたいな話も、実はジェンダーの視点を持ち込むと怪しくなってくる。いやいや、ちゃんと女性のハンターもいたし、女性たちは小動物を狩るなど、重要な役割を果たしていたんだよ、と。
あるいは、壁画を描いた人は当然男性だと思われていたけれども、実は壁画アーティストに当たるような人にも女性が含まれていた、とか。そういうことが次々と明らかになっている。その最新の成果が盛り込まれているというのも『家父長制の起源』の魅力だと思いました。
上野 いま、考古学は技術的にものすごく進化しています。年代測定法も、炭素同位法という昔のやり方だけではなく、DNA鑑定もできるようになって、埋葬者の性別だけでなく親族関係もわかるようになった。その成果で古代史がすごく変わってきました。そういうことを書いた上野の解説、力が入っています。是非、『家父長制の起源』を買って読んでみてください(笑)。
『家父長制の起源』の本文では、当然ながら日本のことはあまり扱っていないので、私の解説の中では日本古代史の考古学的な発見についていくつか言及してあります。いま、古代史は日本史の中でもすごくエキサイティングな分野です。テクノロジーが発達して、新しい発見が次々と生まれているからです。
首長として埋葬されていた人が女性だったとか、そこに一緒に埋葬されている人が一族なのか、親子関係があるかどうか、というようなことが全て同定されるようになっている。今までの常識を覆すような証拠がどんどん出てきているわけです。
でも、佐藤さんがおっしゃった通り、私たちがいま生きている社会のジェンダー二元論をそのまま常識として投影した、「古代も同じだっただろう」というような乱暴な解釈が横行している。事実を突きつけられても、バイアスに凝り固まっていてなかなか認められないのが学者だ、ということも書いてありましたね。
佐藤 そうなんです。そこがすごく難しくもあり、興味深いところだとも思いました。同時に、それに抵抗する側、私たちの側が陥りやすい罠についてもきちんと言及されています。
たとえば、上野さんが紹介してくださったチャタル・ヒュユクの女性像。
こうした出土品から、下手をすると「昔は母権社会だったんだ」という主張が生まれてしまう。
かつては女神が非常に力を持っていて、女性が大切にされていた「母権社会」だったという、いわゆる“母権起源説”です。その社会が家父長制の到来によってひっくり返されてしまったんだ、という敗北の物語につながっていくわけですよね。
ところが、そうした発想の根底では、現代のことを不満に思っている私たちの目を通して、「過去を美化する」という単純化が働いてしまっている。これもまた陥りやすい罠だということが指摘されていて、とても優れた点だなと思いました。
と同時に、著者のサイニーは、だからといってチャタル・ヒュユクの母権起源説を提唱したマリヤ・ギンブタスという考古学者を、過剰に批判しすぎることも避けています。
確かに話を単純化してしまったところがあるかもしれないけれど、それはジェンダーの視点が入る前の男性の考古学者たちが「見たいものを見てきた」のと同程度の単純化です。おとぎ話をつくり上げたギンブタスだけが学者として劣っている、という一面的な評価の仕方はしていない。こうした姿勢にも好感が持てました。
上野 母権制起源説というのも、もうひとつの危うい「神話」ですからね。もし人類の起源が母権制だったとしたら、その母権制が家父長制に敗北したことになる。そうなると、今度は敗北が決定論になってしまう。女性の敗北は歴史的に運命づけられていたのだ、という話になりますから。
最後に、『家父長制の起源』から文章をひとつ読み上げてみようと思います。
家父長制は今も常につくり変えられていて、時には以前よりも大きな力をもつこともある。
(『家父長制の起源』350ページ)
近代になって、家父長制は明らかに強化されました。家父長制は時代によって姿を変え、どんどん新しい姿を取っていきます。
でも裏を返せば、「歴史のどこかに始まりのあるものは、必ず歴史のどこかに終わりがある」ということです。そう考えると、今のような真っ暗な状況も永遠に続くわけじゃないって思えるからよいですよね。
結局、家父長制を止められるかどうかは私たちにかかっている。目の前の状況は変えることができるんだ。そういう希望を与えてくれる本ではないでしょうか。
支配者になったのか
アンジェラ・サイニー (著), 道本 美穂 (翻訳)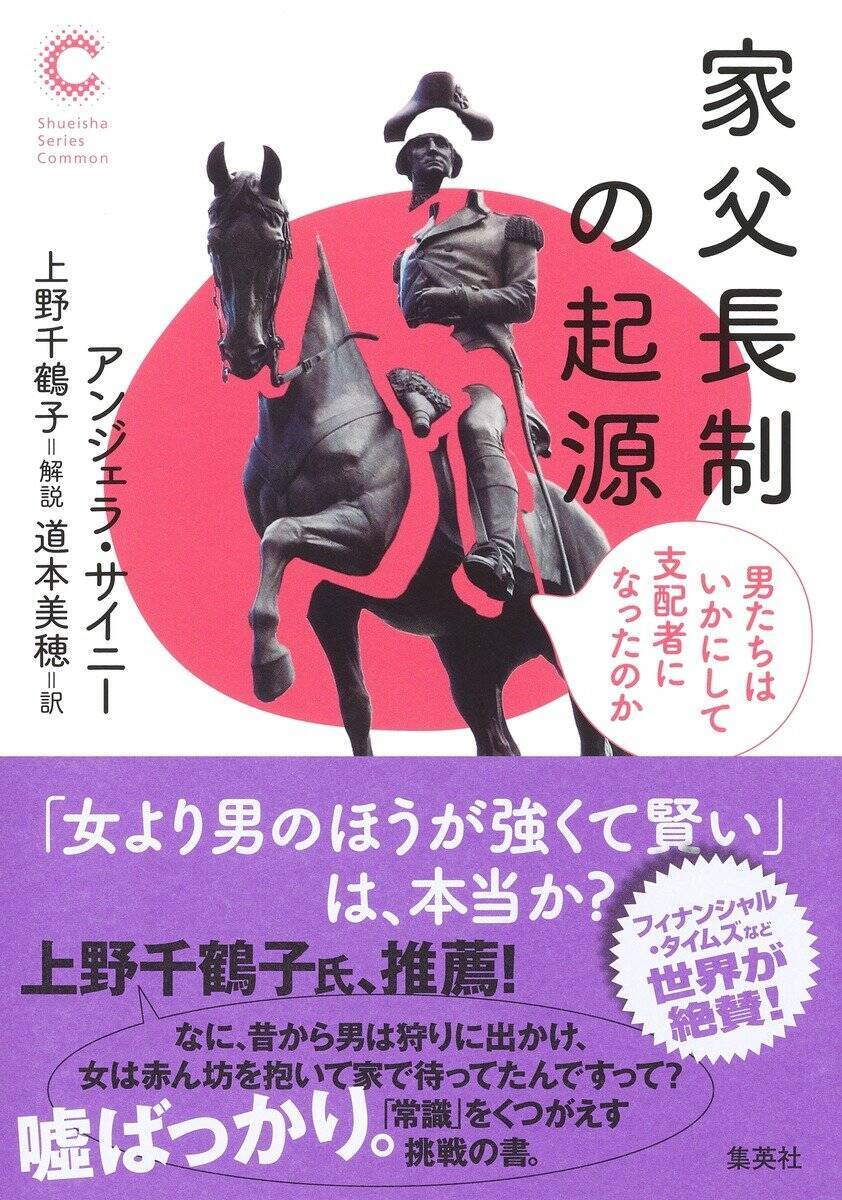
《各界から絶賛の声、多数!》
家父長制は普遍でも不変でもない。
歴史のなかに起源のあるものには、必ず終わりがある。
先史時代から現代まで、最新の知見にもとづいた挑戦の書。
――上野千鶴子氏 (社会学者)
男と女の「当たり前」を疑うことから始まった太古への旅。
あなたの思い込みは根底からくつがえる。
――斎藤美奈子氏 (文芸評論家)
家父長制といえば、 “行き詰まり”か“解放”かという大きな物語で語られがちだ。
しかし、本書は極論に流されることなく、多様な“抵抗”のありかたを
丹念に見ていく誠実な態度で貫かれている。
――小川公代氏 (英文学者)
人類史を支配ありきで語るのはもうやめよう。
歴史的想像力としての女性解放。
――栗原康氏 (政治学者)
《内容紹介》
男はどうして偉そうなのか。
なぜ男性ばかりが社会的地位を独占しているのか。
男が女性を支配する「家父長制」は、人類の始まりから続く不可避なものなのか。
これらの問いに答えるべく、著者は歴史をひもとき、世界各地を訪ねながら、さまざまな家父長制なき社会を掘り下げていく。
丹念な取材によって見えてきたものとは……。
抑圧の真の根源を探りながら、未来の変革と希望へと読者を誘う話題作。
《世界各国で話題沸騰》
WATERSTONES BOOK OF THE YEAR 2023 政治部門受賞作
2023年度オーウェル賞最終候補作
明晰な知性によって、家父長制の概念と歴史を解き明かした、
息をのむほど印象的で刺激的な本だ。
――フィナンシャル・タイムズ
希望に満ちた本である。なぜかといえば、より平等な社会が可能であることを示し、
実際に平等な社会が繁栄していることを教えてくれるからだ。
歴史的にも、現在でも、そしてあらゆる場所で。
――ガーディアン
サイニーは、この議論にきらめく知性を持ち込んでいる。
興味深い情報のかけらを掘り起こし、それらを単純化しすぎずに、
大きな全体像にまとめ上げるのが非常にうまい。
――オブザーバー
〈家父長制〉は無敵じゃない――日常からさぐるフェミニストの国際政治
シンシア・エンロー (著), 佐藤 文香 (翻訳)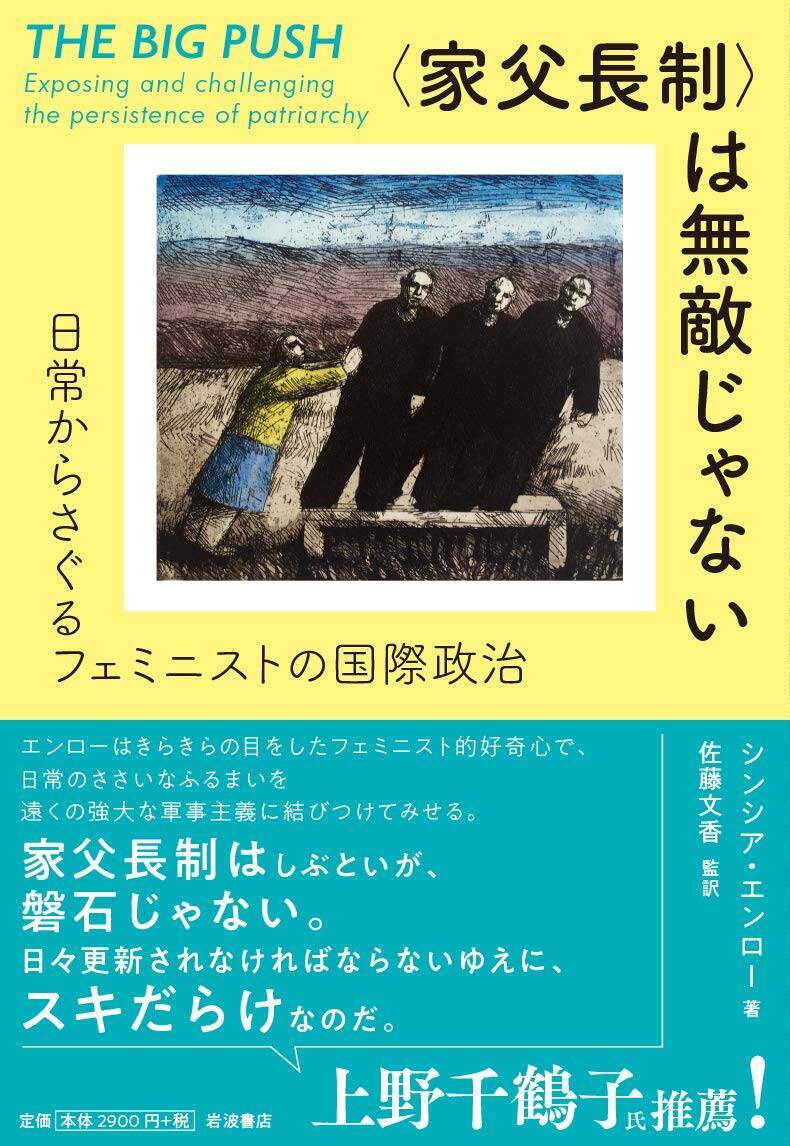























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


