
「歳を重ねるにつれて、お酒が飲めなくなってきた……」「でもついつい飲み過ぎてつらい」そう感じている人も多いのではないだろうか。できるものなら、加齢に伴う身体的変化とお酒とのうまい付き合い方を知りたいものだ。
現役医師が書いた『休養ベスト100 科学的根拠に基づく戦略的に休むスキル』から抜粋・再構成してお届けする。
飲めなくなる理由は肝臓機能低下と…
40代をすぎた人から、「昔ほどお酒が飲めなくなった」という声を聞きます。しかし、加齢に伴う体の変化は避けられませんので、昔のように飲める体に完全に戻ることは残念ながら現実的ではありません。
昔のように豪快に飲みたいと考えるのではなく、飲み方自体を見直して、友人との語らいや食事とのマッチングを楽しむことに切り替えていくのがいいと思います。
加齢とともにお酒が飲めなくなる理由は、大きく2つあります。
1つは肝臓の機能が落ちること。若いころは大量に飲酒をしても一晩寝れば元気になったのに、アルコールを分解する速度が遅くなった40代になるとそうはいきません。翌日までお酒が残っていると感じるのはそのためです。
もう1つは、筋肉量が減ってくること。人間の体内で最も水分を保持しているのは筋肉で、その重量の7割以上が水分だといわれています。しかし、加齢とともに筋肉の量が減れば、必然的に体全体の水分量も減ってきます。
その結果、昔と同じつもりでお酒を飲んでも、血液中のアルコール濃度は上がりやすくなり、すぐに酔っ払ってそれ以上飲めなくなってしまうのです。
筋トレをして筋肉量を増やせば、それに伴って体内の水分量も増えるので、多少は昔のように飲めるかもしれません。
具体的には、次のような方法を取り入れてみてください。
・食事をしっかりとってから飲む
・水も同時にたっぷり飲む
・ゆっくり時間をかけて楽しむ
・アルコール度数の低いものを選ぶ
・はしご酒を避ける
飲酒の目的は、ほとんどの人にとって大酒飲み競争ではありません。おそらく、知人とのコミュニケーションや食事を楽しむことでしょう。そう考えて、量よりも質を重視する姿勢へ転換することを提案します。
気分がよくなると、二次会、三次会と行ってしまうことがありますが、総アルコール量は単純に増えるばかりです。はしご酒には注意しましょう。
もっとも、偉そうに言っている私ですが、こうした飲み方の切り替えが十分にできているとはいえません。たまに昔のつもりで飲んで後悔することもあります。
ただ、体を壊しては元も子もありません。自分の現在の体に合った飲み方を見つけたほうが、結果的に生涯を通じてお酒を楽しめると思います。
惰性で飲み会を増やさない
ビジネスパーソンに飲み会はつきものです。しかし、飲み会が続くとどうしても太ったり体調を崩したりする原因になってしまいます。
大切なのは、「その飲み会は本当に必要なのか」と考えてみることだと思います。「毎週集まっているから」、「上司に誘われたから」などの理由があるかもしれませんが、その多くは惰性で参加しているのではないでしょうか。
もちろん出席する意味のある会もありますが、健康を考えるならば、惰性で飲み会を増やさないことが大切です。
私も、以前はよくあちこちの飲み会に顔を出していました。しかし、40歳をすぎて昔ほど飲めなくなり、加齢とともに自分自身の体が変わってきたと感じたので、無駄な飲み会を増やさないようにしました。
有益な情報交換ができればいいのですが、他人のグチや自慢話を聞いて時間をつぶしているならば、まさしく無駄な飲み会といってよいでしょう。
転機となったのが新型コロナの流行です。コロナ禍のおかげで飲み会という慣習がリセットされ、飲み会のない日々を家で過ごすことになりました。そこで実感したのは、飲み会がなければ健康的な生活が送れるということでした。体にいいものを食べ、好きな筋トレもマイペースに進めることができ、理想的な体重と体調を手に入れることができたのです。
もし、週に何度も飲み会があるという人がいたら、ある期間だけでも飲み会への参加をすべてやめてみてはどうでしょうか。
健康にリスクがあることを知ってお酒を楽しむ
2018年、医学雑誌「ランセット」において、「少量の飲酒でも疾患のリスクは上がる」という論文が掲載されて話題を呼びました。それまで「酒は百薬の長」と信じられてきたのですが、それがくつがえされたのです。
とはいえ、病気になるリスクを限りなくゼロにするために、まったくお酒を飲まないのがよいのでしょうか。もともとお酒が苦手な人はそれでもいいでしょうが、私はそうは思いません。
健康に悪いといわれるものをすべて排除して、健康によいとされるものだけを飲んだり食べたりする人生は味気ないものだと感じます。
厚生労働省によれば、日本人男性の適量飲酒は、純アルコールに換算して1日20gとされています。日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本、ワインなら2~3杯程度とされています。女性は肝臓が小さく筋肉量が少ないことから、その3分の2程度が適量だとされています。
しかし、友人や知人たちとお酒を楽しもうとしたら、これで済むわけがありません。1日20g以上飲みたいのであれば、休肝日を設けるなどして1週間単位でやりくりするのがいいでしょう。
本当に必要な飲み会だけを残して、惰性で飲み会を増やさないことが大切です。
文/加藤浩晃
休養ベスト100 科学的根拠に基づく戦略的に休むスキル
加藤 浩晃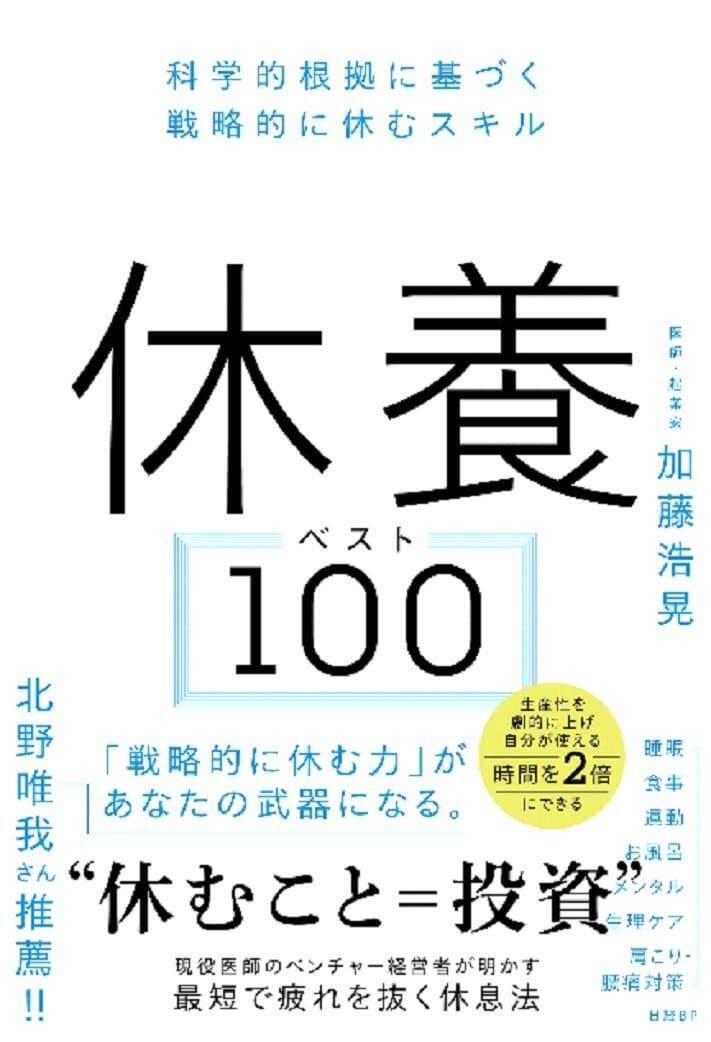





























![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


