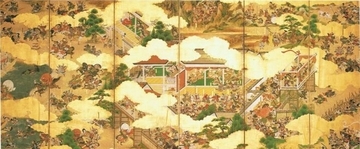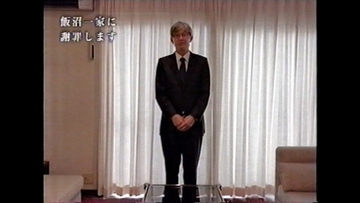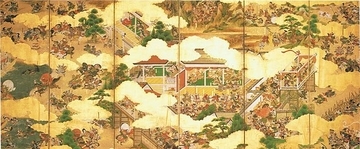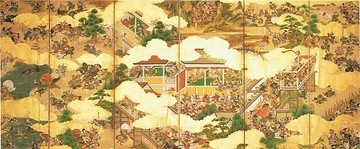「雑学」のニュース (423件)
-
やはり驚異的だった戦国武将・織田信長の「超人強度」!全盛期の石高はなんと日本の約半分!?

■織田信長という存在戦国武将といえばこの人、織田信長。その驚異的な勢力拡大と経済政策について、改めて探ってみましょう。実はお人好しだった織田信長!?最初から最後まで周囲に裏切られ続けた信長の人生今川義...
-
先陣決め、縁起かつぎ…戦国時代にどんな武将も大切にしていた「出陣の儀式」をご紹介

■「先陣」は名誉ある役割戦国時代の合戦時は、今の時代から見ると意外なほどおまじないや儀式めいた手続きが多くありました。ここでは、いわゆる「先陣を切る」武士の選び方と、「三献の儀」について説明しましょう...
-
「きつつき作戦」「釣野伏せ」など…戦国時代、名だたる武将たちはどんな戦法で勝利を目指した?

戦国時代のドラマの合戦シーンでは、両軍が対峙し、法螺貝の合図によって一斉に敵に向かって突撃する……というような場面がよく登場しますね。そうしたシーンは、参加している兵の数が多いほど迫力満点のビジュアル...
-
戦国武将たちは合戦のさなか敵味方をどう区別した?源平の時代から続く武人たちの苦労と工夫
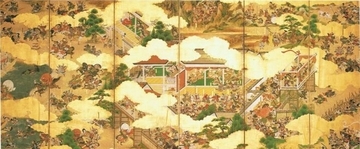
■敵味方でマーキング戦国時代を舞台にしたドラマなどを見ていて、多くの人が一度は感じる疑問として戦場で敵と味方をどう区別していたのかということが挙げられると思います。戦国時代は、合戦ともなれば混戦状態に...
-
「水鳥にビビッて退却」は作り話だった!?武将・平維盛の情けないエピソードが創作された理由とは?

■頼朝の挙兵と撤退源頼朝(みなもとのよりとも)が1180年(治承四)8月17日に伊豆で挙兵しましたが、伊豆目代の山木兼隆を討ったものの、石橋山の戦いでは完敗。命からがら、真鶴半島から安房へ落ちのびまし...
-
あの名将たちの初陣は何歳?どんな戦国武将でも経験する通過儀礼「初陣」を深堀り!

■武将たちの通過儀礼戦国時代の百戦錬磨の武将たちも、最初は必ず初陣(ういじん)から始まりました。当時の武将たちにとって、初陣はまさに人生の一大イベントだったと言えるでしょう。通常は、十二から十五歳くら...
-
すべては織田軍の罠だった!?「桶狭間の戦い」で今川義元はなぜ“休憩“していたのか…

■油断しすぎた今川義元皆さんご存じの通り戦国時代の1560年(永禄三年)、桶狭間の戦いで、織田信長は今川義元を討ち取りました。歌川豊宣画『尾州桶狭間合戦』(Wikipediaより)「桶狭間の戦い」はな...
-
これが戦国時代のリアルだ!合戦中はどう睡眠を取った?兵士のご飯を小出しにした理由とは?

■睡眠は「陣城」の中で戦国時代の武将や兵士たちは、合戦時にどのように生理的欲求を処理していたのでしょうか。ここでは、睡眠と食事について解説します。合わせて読みたい記事↓戦国時代の武士たちはのんびり「湯...
-
聖徳太子の有名な肖像画は謎だらけ…描いたのは中国人!?ではそもそも描かれた理由は?

■聖徳太子と『おじゃる丸』現代人にもっともよく顔が知られている古代人といえば、やはりかつて一万円札や五千円札に肖像が使われていた聖徳太子でしょう。彼は推古天皇の摂政として、日本の政治制度の構築や仏教の...
-
弥生時代の遺跡で出土する「銅鐸」は何に使われてたの?住居跡からは出土しない理由とは?

■朝鮮・中国との交易の痕跡今回は、弥生時代に製造されていた銅鐸(どうたく)について、その用途などを探っていきましょう。弥生時代には、青銅や鉄といった金属を用いる技術が現れました。世界的には、青銅の時代...
-
猫ってなんで『ねこ』と呼ばれるように?よく言われる3つの説 いつからこの呼び名に?

ふだん何気なく使っている言葉も、名の由来についてふと考えると、「なぜ?」という疑問が浮かんできます。我らが猫の「ねこ」もそのひとつです。今回は、「ねこ」という名前に込められた意味を、3つの説に沿って解...
-
三英傑が同地域出身なのは必然!?なぜ戦国時代の覇者はそろって「東海地方」から生まれたのか?

■信長・秀吉・家康の系譜まず、戦国時代を天下統一へと推し進めていった、おなじみの三人の武将についておさらいしてみましょう。三英傑(織田信長、豊臣秀吉、徳川家康)相対的には戦国大名の中では間違いなく実力...
-
明治新政府に最後まで抵抗した幕末のサムライ・榎本武揚は「最良の官僚」か日和見主義者か?

■もうひとつの政権幕末期に明治新政府に対して最後まで抵抗した榎本武揚(えのもと・たけあき)。今回は、彼が戦乱で敗れた後、なぜ死罪を免れることができたのか、どのような経緯で新政府の政治家となったのか、そ...
-
不穏な深夜番組『飯沼一家に謝罪します』が怖すぎると話題 SNSで考察が加速
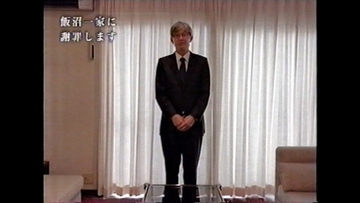
テレビ東京のフェイクドキュメンタリー特別番組『TXQFICTION』シリーズ第2弾となる『飯沼一家に謝罪します』が12月23日(月)~12月26日(木)までの四夜連続で26時00分に放送されている。本...
-
戦国時代の軍議の席順はどう決められた?実力本位で決めていた上杉謙信が基準とした「感状」とは?

■席順の基準は?どこの会社でも、会議のときの席順には気をつかうものです。大抵は、役職の順に上座から座ることが暗黙の了解になっており、社長は奥の真ん中が定位置ですね。戦国時代の軍議も似たようなもので、総...
-
実はゴールドラッシュだった戦国時代!上杉謙信や武田信玄も魅力ある金・銀の採掘に力を注いでいた

■なぜ「金・銀」なのか戦国時代は、戦乱の時代だっただけでなく、経済革命、技術革命など、多くの分野で変革が起きた時代でもありました。それを象徴するのが、金・銀の飛躍的な増産です。人類は、はるか昔から金や...
-
豊臣秀吉のようにはいかず!?戦国時代、雑兵といえど超重要な戦士だった「足軽」はどこまで出世できたのか?

■重要だった「足軽」武士の身分のひとつに「足軽」がありますが、もともと足軽は「よく走る者」という意味で、軽装歩兵の呼称です。戦国時代以降に組織化されました。※あわせてよみたい記事:略奪、強姦なんでもあ...
-
実は日本刀より圧倒的に優秀だった「槍」!戦国時代、武士の戦闘スタイルを変貌させるきっかけにも

■地味だけど優秀武士の武器といえば刀か槍が思い浮かぶと思いますが、戦場でどちらが役に立ったかといえば、圧倒的に槍のほうです。本多忠勝小牧山軍功図水野年方画(高知市民図書館より)時代劇では、武士はよく刀...
-
加賀国は「百姓の持ちたる国」!?戦国時代、百姓が自治を獲得した経緯と浄土真宗本願寺との微妙な関係

■「自治」の獲得戦国時代は日本各地が乱れに乱れましたが、なかでも特殊だったのは、富樫氏が治めていた加賀国でしょう。当地では、富樫氏は何の実権もない飾り物になり、事実上百姓が支配していました。佐久間盛政...
-
戦国武将・織田信長が舞った「人間五十年…」はそもそも何の曲?その作品名と元ネタはこれだ!

■人間五十年…「人間五十年、下天のうちにくらぶれば夢まぼろしの如くなり。一度生を享け滅せぬもののあるべきか」。これは、織田信長が桶狭間の戦いの直前に歌い舞ったことで知られる幸若舞(こうわかまい)の一部...
-
弥生時代〜古墳時代の遺物が赤く塗られていたのは何故か?〜「赤色」をめぐる古代人の精神性

■死者と赤色弥生時代から古墳時代にかけての墳墓から発見された木棺や石棺には、内部が赤く塗られているものが少なくありません。たとえば、吉野ヶ里遺跡から出土した甕棺には赤い色が残っていますし、藤ノ木古墳の...
-
現代の「食」「住」の起源は弥生時代にあり!当時の生活ぶりは意外なほど文化的だった

■弥生時代の生活は?弥生時代の人々はどのような生活をしていたのでしょうか。……こう書くと、小学生向けの歴史の本でも当たり前に取り上げられそうな、単純なテーマと思われるかも知れません。しかし、最新の考古...
-
最近は「源平合戦」という名称は使われない?理由は源氏と平氏の複雑な内情にあった
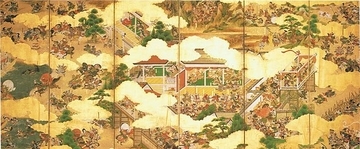
■「源平合戦」とは源平合戦といえば、平安時代末期に起こった平氏政権に対する内乱です。「源氏vs平氏」の戦いとして知られています。『源平合戦図屏風』(Wikipediaより)しかし実は、最近はこの源平合...
-
戦国武将の生首「首級」は取り扱い注意!ランク低ければ捨てられ、死に際の形相は化粧でごまかされていた

■なぜ「首を取った」のか戦国時代の武士は、倒した敵方の兵の首を切断して持ち帰るのが常でした。当時の合戦は、首の取り合いでもあったと言えるでしょう。※関連記事:戦国武将は縁起が大事!武士道バイブル『葉隠...
-
戦国時代の武士たちはのんびり「湯治」に行くヒマなどない!合戦でのケガの応急処置はどうしてた?

■湯治に行ってるヒマはない戦国時代の武士たちは、言うまでもなく、戦闘において頻繁にケガをしていたと思われます。それにしても、彼らがそうして合戦で傷を受けたとき、どうやって治療していたのでしょうか。こう...
-
蘇我馬子、小野妹子…なぜ男なのに「子」?なぜ動物の名前?古代日本の人名の不思議を解き明かす

■なぜ動物の名前?古代日本の人名は、現代から見ると「なんでこんな名前なの?」と理解に苦しむものがありますね。古代の戸籍をみると、刀良売(とらめ)、比都自(ひつじ)などのように、男女とも動物にちなんだ名...
-
隅田川があるのになぜ”墨田”区?思わず自慢したくなる東京の区名・地名に関するトリビア【後編】

いつだって話題に事欠かない街、それが東京ですよね。東京にはさまざまな地名や区名がありますが、それらの由来には歴史がつまっています。そこで、今回の記事では、そんな東京の地名に関して、知っていると誰かに思...
-
布教で来日したキリスト教系団体、実は「イエズス会」だけではなかった!知られざる四大派閥とその内情

■イエズス会以外にも修道会があった日本にキリスト教を広めた修道会といえば、フランシスコ・ザビエルが所属していたイエズス会が有名です。関連記事:フランシスコ・ザビエルとルイス・フロイス、日本でキリスト教...
-
やっぱり日本が大好きっ!「シーボルト事件」で国外追放されたシーボルト、なんと30年後に再来日していた!

■シーボルト事件とはシーボルト事件という、江戸時代に起きた事件があります。これは江戸時代後期の1828年(文政11年)に、ドイツ人医師フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが起こした事件です。シーボ...
-
お祝い事の「紅白」のルーツ!?なぜ「源平合戦」で源氏は白、平家は赤の旗を掲げたのか?
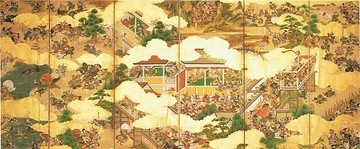
■源氏は白、平家は赤1180年(治承4年)に、源氏と平家が一族の存亡をかけて戦った源平決戦。このとき、源氏は白旗を掲げ、平家は赤旗を掲げましたが、この色分けは旗以外にも及んでいました。『源平合戦屏風図...