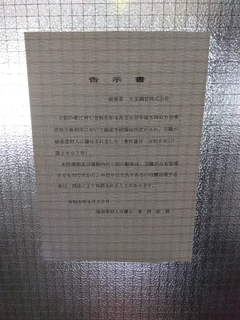本日(7.17)決定、第151回の芥川・直木賞も、エキレビ!より予想をお届けします。芥川賞もまもなくアップ。
今回も★で本命度を表しますが、作品の評価とは必ずとも一致しないことをお断りしておきます(5点が最高。☆は0.5点)。
■『ミッドナイト・バス』伊吹有喜(初。文藝春秋)
高宮利一は高速バスの運転手だ。
ある晩、彼の運転するバスに一人の女性が乗ってきた。16年前に別れた妻の美雪だ。それを機に、彼女との利一との間には不思議な縁が芽生えていく。
登場人物の誰もが自分の思いの伝え先、心の行き先がわからずに戸惑い、道に迷っている。そのため、時にぶつかり、傷つけ合ってしまうのである。伊吹は2008年に『風待ちのひと』でデビューを果たし、第2作の『四十九日のレシピ』が映画化されるなど、着実に進歩を遂げてきた作家である。彼女の描く人物は決して強くなく、むき出しの現実の中でたびたび傷ついてしまう。その傷がいかに癒えていくかを描くことが、作品の主題となるのである。
■『破門』黒川博行(6回目。角川書店)
今回ノミネートされた中ではもっとも作家としてのキャリアが長く、直木賞候補も6回と最多である。黒川は初め警察小説で注目されたが、次第に犯罪小説の方へ比重を移し始めた。1997年に発表された『疫病神』はそうした時期の作品であり、同作で2度目の直木賞候補にもなった。以降、本作『破門』まで、5つのシリーズ長編が書かれている。中心人物は他人に迷惑をかけることを屁とも思わないヤクザ・桑原だ。
本篇の「小説野性時代」連載期間は2012年から翌年にかけてである。その間に暴対法が改正され、広域暴力団の構成員は著しくその権利を制限されることになった。さしもの桑原も経営する店がつぶれるなど左前、それどころか任侠界全体に暗雲が立ち込めている。
■『男ともだち』千早茜(2回目。文藝春秋)
前回は短編集『あとかた』で初の候補となったが、今回は長編である。主人公の神名葵は29歳、新進のイラストレーターだ。ごく単純に言うと、これは彼女と距離感覚の違う三人の男たちの物語である。まず恋人で同棲相手の彰人だ。彼は必要以上に葵との間の距離を詰めようとしない。勤め人の彰人と葵とは生活サイクルがそもそも違う。うっかりすれば、何日もお互いの顔を見ないことさえありうるのだ。二人目は浮気相手の真司である。彼の職業は医師で、妻帯者だ。遊び人を気取る彼は、自分の都合を優先して葵を呼び出す。妻が不在の日には自宅に連れ込もうとさえするのである。
距離を詰めない恋人と、引き込もうとする愛人。そんな二人との関係を惰性で続けている時期に再会したのが、大学時代の友人だったハセオだった。彼は女たらしで、かついいかげんな性格だが、葵の気持ちに合わせて近くまでやって来てくれる男だった。決して自分とは寝ようとしない男ともだちと対峙している間に、葵の心境にも変化が生じていく。
葵という主人公が中心にいて、その心象風景を見ているような小説だ。男たちとの関係と並行してイラストレーターとしての彼女の成長が描かれるのも、葵が世界に向き合う態度と画業の深度とが同調しているからに他ならない。「第三の男」であるハセオはとにかくかっこよく、フェロモンたっぷりに描かれているのだが、それも葵というフィルターを通過しているからだ。この視点を許容できるか否かで『男ともだち』という小説の評価は大きく分かれる。一人で気張って生きる葵に共感できれば、本書は十二分に楽しめるだろう。こうした特徴は、人物の描き方が一面的だという評価を招く可能性もある。予想は★★☆。
■『私に似た人』貫井徳郎(4回目。朝日新聞出版)
集団的自衛権の問題から派生して日本国内でも国際テロ組織による凶行の発生が危惧されているが、本書では「小口テロ」と呼ばれる無差別殺人事件が頻発するようになった日本がオムニバス形式で描かれる。犯人たちは自らを〈レジスタント〉と称しているのだが、犯人たちの出自や経歴にはなんの結びつきも見出せない。しかし、いくつかの事件が起きた後で奇妙な共通点が発見されるのである。そうした小規模テロの発生を背景としながら、主題として選ばれるのはごく普通の市民の群像である。格差社会の不公平さに不満を募らせる者、自らは正しくありたいと願いながら理想と現実とのギャップに忸怩たる思いを抱く者、テロの実行犯に激しい憤りを感じる者、といった具合に社会の各所、いわゆる中流階級の全般にわたって登場人物たちは配置されている。
もう一つの特徴は、ここ数年の社会面を騒がせてきたトピックがどの作品にも埋め込まれている点だ。インターネットでの炎上事件、ワーキングプア、違法ハウス、過労死問題などなど。注目すべきは「川渕政昭の場合」の主人公が貧困ゆえに一家心中を遂げた友人について「日本社会が木暮を殺したのだ」と考えるように、どの登場人物も非常に類型的に描かれている点である。タイトルが「私に似た人」なので、どこの誰にでも当てはまるような特徴の無い、薄っぺらい人物として造形をしたのだと思われるが(そしてそれは諷刺小説としては普通の手法だが)、それゆえに各章の物語には既視感を覚えてしまうのが本書の最大の弱点である。現実をよく切り取ったと選考委員が評価する可能性もあるが、この「どこかで読んだ感じ」を指摘されれば厳しいと考える。評点は★★。
■『本屋さんのダイアナ』柚木麻子(2回目。文藝春秋)
タイトルを見て、さぞブッキッシュな内容なのだろう、と思ってページを開いた。主人公は同い年の二人の少女である。一人目は矢島ダイアナ。漢字では「大穴」と書く。「世界一ラッキーな女の子になれるように」と意味の名前なのだ。16歳でダイアナを産み、今なお六本木のキャバクラでママとして働く母は、源氏名であるティアラを普段の呼称に選び、小学3年生の我が子の髪を自分と同じ金色に染めさせている。しかしダイアナはそんな母親の存在を恥じ、15歳になったら絶対に改名しようと心に決めているのである。彼女自身は何よりも読書が好きな、知的趣味の強い少女なのだ。
そのダイアナが気に入り、友達になろうと自ら歩み寄ってきたのが同じクラスの神崎彩子である。「意識の高い」両親からの躾を受けて育ってきた彩子にとって、ダイアナとその母はなんとも魅力的な存在に見えた。あんな風に自由な暮らし方をしてみたい。
二人のヒロインは一種の「とりかえっこ」のようである。ダイアナという名前は『赤毛のアン』のヒロインの親友から採られている。脇役と主人公の立場を逆転させているわけだ。作品の中ではダイアナが熱心な読者となる『秘密の森のダイアナ』という少女小説が重要なモチーフとして用いられており、その仕掛けもプロットの中で見事に機能している。女性が長じるにつれて社会から押し付けられてしまう役割が、少女小説の世界観と対比、検討されていく仕掛けなのである。その技巧に私は好感を持った。この手の小説は直木賞よりも本屋大賞にむしろ愛されそうな気がするのと、男たちとの対決が描かれる終盤がやや予定調和的である点が選考時には減点対象になりそう。評点は辛めに★★★。
■『満願』米澤穂信(初。新潮社)
今回の直木賞では初めて候補になる作家がいるが、米澤もその一人。ただし、この『満願』ではすでに第27回山本周五郎賞を受賞している。〈古典部〉〈小市民〉などの青春ミステリー連作で多くの読者を獲得した米澤だが、むしろ本分は非シリーズ作品で発揮されることのほうが多い(先ごろ文春文庫から刊行された『世界堂書店』では、アンソロジストとしての見識も披露した)。本書に収められたものはいずれもシリーズ・キャラクターなどが登場しない6つの短篇である。連作短編集流行りの昨今に、こうした作品集が刊行され、しかも高く評価されたということをまずは寿ぎたいと思う。
表題作は、とある弁護士の視点から描かれる物語だ。苦学生時代に下宿していた家は、家産を食いつぶすだけで生活能力のない夫を、しっかり者で気立ての優しい妻が支えることでなんとか維持されていた。夫婦がとある殺人事件の当事者となり、主人公はその公判で初めて法廷に立った。時が過ぎ、主人公は罪を償った服役者を出迎えようとする。彼の胸には、事件に関する一つの仮説が生まれていた。それが追想の形で描かれるのである。この他巻頭の「夜警」は作者にしては珍しい警察小説、「死人宿」は犯人当てに特化した純粋度の高い謎解き小説である。米澤には『儚い羊たちの祝宴』という暗い色調の作品集があるが、それに最も近いのが「柘榴」だろう。対照的にコミカルな味がある「関守」、一件海外を舞台にした企業小説のような始まり方をする「万灯」と内容は多岐に渡っている。そもそも直木賞では純度の高いミステリー短編集は星取りがよくないので予想は★★★にとどまるが、これだけ充実した作品集は珍しく、お買い得な一冊であることは間違いない。
(杉江松恋)
芥川賞編へ