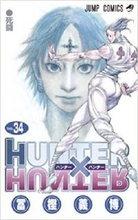私が初めて赤瀬川原平の名前を知ったのは小学生のときだったと思う。『別冊一億人の昭和史 昭和マンガ史』(1977年)という本が家にあって、それに「マンガ昭和無署名犯罪史」と題する赤瀬川の描き下ろしイラストが載っていたのだ。
8ページにわたるこのイラストは、大正末の関東大震災から刊行当時に世間をにぎわせていたロッキード事件まで、半世紀のあいだに起こった犯罪事件を各時代のマンガの主人公とともに描いたものだ。そこではたとえば、昭和30年代前半のヒーローである月光仮面が、カミナリ族(暴走族の元祖)と呼ばれる若者たちとともにオートバイで疾走している。しかしよく見ると月光仮面のバイクにはタイヤがなく、その車体はキノコ状の何やらニョキニョキ伸びた物体に乗っかっている。
その物体が一体何なのか、子供だった自分にはわからなかった。だが高校生ぐらいになってあらためて見て、それが男性のナニであり、しかも障子を突き破っていることに気づきハッとなった。そう、この絵は、石原慎太郎の小説『太陽の季節』のかの有名なシーンのパロディでもあったのだ。
『昭和マンガ史』には、この描き下ろし以外に、赤瀬川のイラストの代表作である「櫻画報」から抜粋した図版も収録されていた。もちろん子供にはその意味するところなど理解できなかったが、何か見てはいけないヤバいものを見たような気がした。そのため私のなかで赤瀬川原平は、よくわからない、何やらおどろおどろしいものを描く人だという印象がしばらくのあいだ残った。
「櫻画報」や「マンガ昭和無署名犯罪史」、あるいは私が先日べつのところでとりあげた「論壇地図」は、赤瀬川が1970年代に雑誌などに多数発表してきたパロディイラスト、パロディジャーナリズム作品の一角を占めるものだ。今回は赤瀬川が何をたくらんでパロディに手を染めたのか見ていきたい。
■朝日新聞社の雑誌を“乗っ取った”「櫻画報」
赤瀬川のイラストでも「櫻画報」は社会的にも話題を呼んだ作品だ。最初の連載誌「朝日ジャーナル」は、1960年代末の大学紛争のさなか、「週刊少年マガジン」とともに学生のあいだでよく読まれていた雑誌である。当時同誌では表紙を毎号、現代美術の作家が描き下ろし、誌面には佐々木マキの実験的なマンガが連載されたりもした。赤瀬川の起用もそんな流れからだったらしい。
大学構内だけでなく街頭でも学生と機動隊が衝突を繰り返していたこの時代、道路の敷石がはがされて投石に使われるので、それができないようアスファルト舗装が進められていた。赤瀬川はそうした状況を見て、せっかくの週刊連載なのだから、どこそこにはまだ敷石があるといった生の情報を発信しようとしていたという。タイトルも「野次馬画報」としたものの、いざ連載の始まった1970年夏には学生運動は沈静化してしまっていた。そこでいったん計画を白紙に戻したうえ、「櫻画報」と改題する。
連載をしばらく続けているうちに、見開きの絵の片面が左右反対に印刷されてしまうというアクシデントが生じる。ここから、雑誌内新聞というコンセプトが前面に押し出されることになった。
ちょうど連載開始の少し前には、赤軍派による日本初のハイジャック事件が起きており、「『櫻画報』は『朝日ジャーナル』を乗っ取った」という表現もなされた。1971年3月の「朝日ジャーナル」における最終回では、作中キャラの泰平小僧と馬オジサンが、見開きに書き出されたたくさんの雑誌名から次なる“乗っ取り先”を探している。
だが、この最終回掲載号は回収の憂き目にあう。
そもそも「櫻画報」というタイトルは、野次馬の語から馬肉=桜肉を連想してつけたものだった。また、仕込みの見物人や回し者を意味するサクラという意味も込められていた。パロディとはいわば、何らかの作品やできごとなどを別の文脈に置き換えて、その意味を変えてしまうものだから、こうした言葉の意味のずらし方はパロディの基礎ともいえる。
「櫻画報」はその後、「ガロ」や「現代の眼」など掲載誌を転々とし、単行本化もされた。単行本は『櫻画報永久保存版』(1971年)、『櫻画報・激動の千二百五十日』(1974年)、『櫻画報大全』(1977年)、さらには文庫版『櫻画報大全』(1985年)とバージョンアップが繰り返される。文庫版をのぞけばいずれも函入り、表紙・背表紙の書名と著者名は箔押しという豪華な造本だ。その内容も、単に雑誌に載ったものを再録するだけでなく、読者からの投稿、当時の日記が収録されるなど、「櫻画報」が発表された背景まで仔細にまとめられている。
■新聞というメディアを疑ってみる――「虚虚実実実話櫻画報」
「櫻画報」の連載を通じて、赤瀬川のなかで高まったメディアへの関心は、その後もあれこれと形を変えて表現されることになる。「終末から」という筑摩書房の月刊誌に1973年から翌年にかけて連載された「虚虚実実実話櫻画報」では、とくに新聞というメディアの信憑性について、手を替え品を替え考察されている(同連載は再構成のうえ、『鏡の町皮膚の町――新聞をめぐる奇妙な話』と改題して1976年に単行本化された)。
その10年ほど前に赤瀬川の「模型千円札」が警察に摘発されたとき、ある大手新聞は、当時世間をにぎわせていたニセ千円札事件に彼がさも関与しているかのように報じた。もちろんまったくの事実無根である。以来、赤瀬川のなかには新聞に対する不信が生まれた。「虚虚実実実話櫻画報」はその産物であったが、彼がユニークなのは、新聞社の報道姿勢や企業体質を追及するというよりは、新聞とは一種のフィクションだと喝破した点である。
連載では、記事本文のほか見出しの大きさや記事の並べ方、写真のキャプションなど、新聞をフィクションたらしめるトリックが次々とあばかれていくことになる。さらに実践例として、大手新聞のフォーマットを借りたウソの新聞紙面……たとえば「日本、初の水爆実験」「東京都知事に野坂昭如氏」「田中角栄氏にノーベル賞」などといった記事をでっちあげたりもした。いまのネットの「虚構新聞」のご先祖みたいなものである。しかも、記事の見出しは写植ではなく赤瀬川の手描きだ。彼はそれなりに有名になってからもしばらくは、装飾のほかレタリングで生計を立てていただけあって、さすがに上手い。
そういえば赤瀬川が亡くなる半年ほど前、ある雑誌の編集者が、イラストレーターの安西水丸の追悼記事のなかで赤瀬川らの文章を捏造するという事件があった。かつて新聞からいわれなき事実を報じられたのに対し、パロディという形で意趣返ししてみせた彼のことだから、もし病気でなければ、この事件にも何らかの形でアクションをとったのではないだろうか。
■パロディジャーナリズムの祖・宮武外骨との出会い
赤瀬川の一連のパロディジャーナリズムにはお手本があった。それは明治から昭和にかけて活躍したジャーナリスト・宮武外骨(みやたけがいこつ)である。外骨は自ら発行する「頓智協会雑誌」に、「頓智研法発布式之図」と題して大日本帝国憲法発布式での明治天皇を骸骨に置き換えて描き、不敬罪(天皇や皇族に対し不敬の行為をする罪)で禁錮刑を受けるなど、さまざまな騒動も引き起こしてきた。洒落でやったにもかかわらず、深読みされて騒ぎとなったケースも多く、そのあたりも赤瀬川とよく似ている。
1970年代の『櫻画報大全』では「宮武外骨先生に捧ぐ」との献辞を掲げ、講師を務めていた美学校でも生徒を相手に外骨について紹介もした。さらに時代を下って、外骨の没後30年にあたる1985年には『學術小説 外骨という人がいた!』を著し、にわかに起こった外骨ブームをリードした。このとき、雑誌で外骨の扮装までしている。
赤瀬川と外骨との出会いは1960年代後半にさかのぼる。このころ千円札裁判(前回参照)への対策としておもちゃのお金のような模造紙幣を集めるうち、印刷物全般に関心を抱くようになった赤瀬川は、マッチのラベルなどの収集にも手を染める。そのため古書店をしょっちゅう物色していたところ、「ハート」という明治時代に発行された変な雑誌を見つけた。さらにしばらくすると、友人の松田哲夫(のち筑摩書房の編集者となる)が、「スコブル」という大正時代の雑誌を古書店で見つけて持ってきた。似た雰囲気を持つ「ハート」と「スコブル」は、突き合わせてみるといずれも宮武外骨という人物が発行したものだとわかる。ここから外骨関連の本や雑誌の収集が始まった。
赤瀬川は何の予備知識もなく外骨の作品と出会って衝撃を受け、これをつくったのは何者なのかと調べていくうちにどんどんのめりこんでいった。その出会い方に、不遜ながら私の赤瀬川との出会いと近しいものを感じてしまう。そういうことも、あらゆる情報がネットで容易に入手できてしまう現在ではあまりなくなってきたのが、ちょっと寂しい。
(近藤正高)
3へ