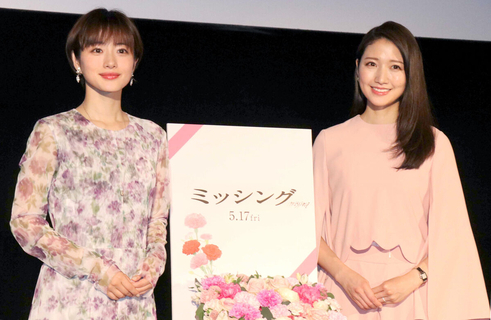でも、小説作品以外のところで、小説についてはっきりと語った小説家もたくさんいる。
小説家が小説について語っているのを読むのは、おもしろい。みんな実作者として語るし、ときには、教室で小説を教えてる作家のばあい、そこにコーチあるいはトレーナーとしての視点が加わることもある。
高橋源一郎の『デビュー作を書くための超「小説」教室』(河出書房新社)は、その点で少し違う。
高橋さんは小説の実作者だけど、この本にかぎっては、実作者としての小説論ではかならずしもないし、教師としてとしての小説論というわけでもない(高橋さんも大学で教えているけれど、小説の書きかたを教えてるわけじゃなさそう)。
この本は、新人文学賞の選考委員という立場からの小説論なのだ。
ここには、具体的な技術論はなにも書かれていない。
プロットの立てかた、視点の操作、文体の問題、世界設定の構築など、そういった「メイキング」の話は、ほとんど出てこない。
わずかに、作品の題名と、筆名(つけるならば)の話が出てくるくらいだろうか。
あ、筆名のつけかたって、技術の話じゃなかったな。ごっちゃにしてゴメン。
では、この本にはなにが書いてあるのかというと、小説の公募新人賞の選考委員は、こういうことを考えていますよ、ということが書いてある。
なお、この本の後半は2000年以降に著者が書いた新人文学賞の全選評が集められている。
選評というものは、多くは賞の発表時に雑誌に載って終わり、というものだ。
だから、ひとりの選考委員がこの15年間に、朝日新人文学賞(もう終了)、群像新人文学賞、すばる文学賞、中原中也賞(これだけは詩の賞で、詩集=単行本が対象)、文藝賞、坊っちゃん文学賞の選評でなにを言ってきたか、をまとめ読みする機会は珍しい。
この新人文学賞の全選評は、ページ数的には「後ろ半分」だけど、この「後半」は前半よりのフォントが小さい。
いっぽう「新作」である前半の小説教室は字が大きくて、おまけにまるで現代詩のように改行だらけなので、字数から言ったら3分の1くらいではないだろうか。
こういう構成だから、文学賞に応募しようと考えている小説家志望者が、『超「小説」教室』という題に惹かれて、なにか具体的なアドヴァイスが書いてあるかと思って本書を読むと、本書はひょっとしたら、
「前半は言ってることが抽象的で、結局どうしたらいいのかわからない」
「後半(分量的には3分の2)はありものの原稿で水増し」
という感想を抱くかもしれない。
そういう意味ではこの本の題名は、とにかくデビューしたいんだという小説家志望者の気持ちにつけこんだような、たいへんナメきった態度の書名だとも言える。
わざわざレヴューで取り上げといて、そこあげつらうのもどうかと思うが、本の作りがそうなっているのは厳然たる事実だ。
そのうえで、しかし、少なくとも前半部分にかんしては、どこにも間違ったことが書かれていない。僕が以下に引用・要約するのはそのほんの一部分だが、ほかにも重要な、そして正しいことを、いろいろ書いてある。
高橋さんは、候補作にかぎっては、じっさいに原稿に〈書かれたもの〉だけで判断するというよりは、その原稿をもとに、その作者がほんとうは〈書きたかったもの〉を再構築しつつ読むのだそうだ。
そこから、その作者によって〈書かれるはずだったもの〉〈これから書かれるもの〉が見えてくる、それが賞の決め手だ、という。
〈作者Aは、四回転半をねらって、二回転、跳びました。
作者Bは、三回転をねらって、二回転半、跳びました。
結果は、あきらかですね。
作者Bのほうが、より多く、回転することができました。
さて、選考委員は、AとB、どちらに高得点をつけるでしょうか?
正解は、Aです〉
これはおもしろい。
逆に言うと、いったんデビューしてしまったら、こういう「将来の伸びしろ」では判断してもらえなくなる、というわけで、これだからプロの世界は厳しいいとも感じる発言だ。
また高橋さんは、自分は選考委員に向いている、という。
どんな候補作にたいしても、歴史的な観点からのアプローチを欠かさないというのだ。そうしないと、
〈ふるいものがあたらしいとみなされたり、本当はあたらしいものが、見過ごされたりしてしまう〉
ということだ。そして、いまじっさいに多くの作品が、そういう目に遭っている、とも。
そのいっぽうで高橋さんはまた、こうも言う。
〈わたしが選考委員に「向いている」といったのは、片手に「地図」をもっているためだけではありません。
じつは、もういっぽうの手が、ぐにゃぐにゃと変形するからです〉
高橋源一郎は泉新一withミギーか? ルフィなのか? それとも『ターミネーター2』のT-1000なのか?
小説というものは、これでなかなかに自由で、融通がきく。いままでも、どんどん変形してきた。
自分が知っている小説が小説だ、などと読者が(まして選考委員が)思っていると、新しい予想外ものをつかまえそこなってしまうのだ。
それをつかまえるための、ぐにゃぐにゃと変形する片手、これが選考委員に向いている証だというわけ。
この「地図」と「ぐにゃぐにゃ」の両方が必要だ、という主張において、高橋さんは圧倒的に正しいことを言っている。
そして、文学史の「地図」を持ったほうの手と、ぐにゃぐにゃ変形するほうの手。このふたつはまったく矛盾しない──というのは、本書を読んだ僕の意見。
なぜなら、過去の小説を幅広くたくさん読めば読むほど、つまり文学史の「地図」の覆う範囲が拡大すればするほど、高橋さんが言うとおり
〈小説の「らしさ」、小説が小説たる条件なんて、特にない〉
〈小説は、守るものがないから、いくらでもかたちを変えて、生き延びることができる〉
ということが、歴史によって証明されてきたことがわかるのだ。
逆に言うと、
「小説というものは、こうでなければならない」
「これこれこういう小説こそが、いい小説である」
なんて言ってる人は、自分が読んだ少数(20冊だか、2000冊だか)の小説だけをもとに、そこから狭い結論を引き出しているので、そういう人の話は聞き流していい、ということでもあるだろう。
選考委員だけではなく、小説の読者だって──少なくとも大人の読者なら──、その両方を持つことで、どんどん小説をおもしろく読めるはずなのだ。
だから、選考委員というものは──というか、少なくとも高橋さんは──応募原稿の最終候補作を読むときに、この作者は自分といっしょに日本語の小説の未来=歴史を作ってくれる人かどうか、ということを考えているようだ。
ここからあとは、個人的な話。本書に、小説はこれくらい不定形で自由なのだ、ということを示すかのような、こんな一節があった。
〈人とコミュニケートするだけのことばや、実用的であるだけのことばは、小説とはいえないでしょう。食事の約束をかわすメールの文面や、近況を知らせる手紙、クレームの電話や、履歴書や転居届や始末書や、こういったものも、やはり小説とはいいがたい。
逆にいえば、そこに、もうすこし何かが加われば、小説になりうるのかもしれない。
そういったことばではどうしても伝わらない、何かです。〔…〕
この隙間に突っ込んでいれば、それはたぶん、小説です〉
えーと、僕レベルにもなるとですね、〈人とコミュニケートするだけ〉〈実用的であるだけ〉でもじゅうぶんたいへんなんだけど。(レベル低い!)
(千野帽子)