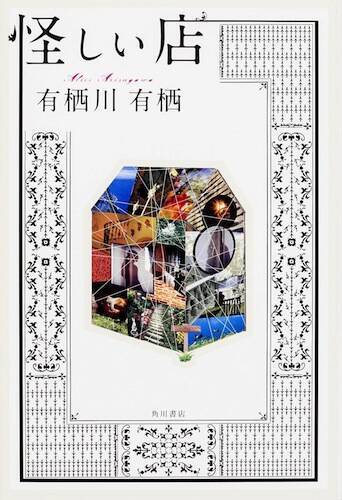
「人の死なない作品が2本入るので、折り返し地点では絶対殺そうと(笑)。また、「店が出てきて人が死ぬ」というパターンが続くと、どんなに設定をひねっても結局同じ印象を読者に与えるような気がして、倒叙にすればちょっと感じが変わるかな、思いました。ここで気分をリセットして後半に入ってもらおうということですね」(「ダ・ヴィンチ」インタビューより)
このように有栖川の短篇集では、作品の並び順にも趣向が凝らされていることが多い。巻末の作品初出一覧を見ながら、この作品はどういう意図でこの場所に置かれたのか、などと想像を巡らしてみるのも楽しみ方の1つだ。
「倒叙」という用語が出てきた『スイス時計の謎』著者あとがきには「『ブラジル蝶の謎』以降、国名シリーズの短篇集にはいつも一本だけ目先を変えて倒叙ものを入れることにしている」との記述がある。
倒れて元に戻って
最後に謎が解かれるミステリーは、逆立ちした小説といってもいい。謎解きのためには結果から原因を追究しなければならず、しばしば時間軸も遡ることになるからだ。つまり現実とは転倒した形で叙述が行われるわけである。ここにフィクションとしての妙味がある。一般小説でもしばしばミステリーの形式を借りたプロットが援用されるのもそのためだろう。
そのミステリーの中に「倒叙」と呼ばれるサブジャンルがある。
倒叙形式は近代的なミステリーが誕生した比較的早期から存在していたが、これを有効に活用した作家にイギリスのフリーマン・ウィルス・クロフツがいる。クロフツのいくつかの長篇では2部構成がとられ、第1部は犯人の側から犯行計画が綴られる倒叙形式、第2部は探偵の側からその犯行計画が暴かれていくさまが描かれる。実は第1部の犯人が予期しなかったハプニングが起きており、そのために第2部では意外な人物が犯人として指摘されたり、別の犯罪計画が露見したりするのだ。
しかし、倒叙ミステリーの知名度を上げた功労者は、小説ではなくて映像作品だった。ピーター・フォーク主演のドラマ『刑事コロンボ』である。各界のセレブリティたちが知謀の限りを尽くして殺人計画を立て、実行する。
アリス、一回休み
作家アリス・シリーズに話題を戻すと、前述の通り短篇集には倒叙作品が含まれているものが多いことがわかる。たとえば「完璧な遺書」(『英国庭園の謎』所収)では犯人が完璧と自負していた犯行計画が、火村英生が指をわずかに4回動かしただけで打ち砕かれる。以前の原稿で火村英生という探偵の特徴を「犯人の拠り所を衝く」ことだと書いた。犯人側から物語が構成されていく倒叙ではその瞬間が描きやすいのである。その代表例といってもいいのが「完璧な遺書」という作品だ。
追い詰められた犯人の目から火村を描いた1行を最後に配した「シャイロックの密室」(『スイス時計の謎』)も印象的な作品である。タイトルからわかるとおり密室ものなのだが、倒叙ミステリーには、トリックがいかにして実現されたが探偵の説明ではなく、犯人の行動によって描けるという利点もある。複雑な内容のトリックも字数を費やさず、コンパクトに書くことができるのだ。
『ペルシャ猫の謎』所収の「わらう月」は、アリスこと作家・有栖川有栖が重要な役回りで登場する短篇だ。この作品で重要なのは、火村とアリス以外の登場人物の内面が一人称で詳しく書かれている点で、他人とは共有できない内面世界を持つ人間の心を読者は覗くことができるのである。それゆえに不思議な味わいがある。
作家アリスシリーズではないが、倒叙ミステリーで重要な有栖川作品が、ノンシリーズ短篇を集めた『ジュリエットの悲鳴』所収の「落とし穴」である。ここでは「刑事コロンボ」式の探偵に追い詰められる結末ではなく、別の形で破滅を迎える犯人が描かれる。また、倒叙ミステリーではないが、叙述者としてのアリスが一回休みとなり別の人間が語り手を務める作品もシリーズには存在する。前出の『ペルシャ猫の謎』に納められた「赤い帽子」もそうなのだが、『火村英生に捧げる犯罪』所収の「鸚鵡返し」もファンならば見逃せない作品だろう。「何をにやついてるんだ、アリス」で始まるこの短篇の語り手は、なんと火村英生自身だからだ。この先ももしかしたら、火村の大家である時枝さんなど、別の人物が語り手となり、アリスがお休みをもらうことがあるかもしれない。
いよいよ朱色の空が
今回の「ショーウィンドウを砕く」は、そういうわけで原作を変則的に用いた内容だったが、犯人側の視点だけではなくアリスたちの側の物語も加えられて、厚みのある内容になっていた。どうしても倒叙形式の物語だと犯人の行動を追うのに終始し、ドラマとしては単調になってしまうことがあるので、これは幸いであった。物語の前半では、火村の教え子である貴島朱美が、過去の事件について相談を持ちかけるエピソードが挿入されていた。長篇『朱色の研究』のプロローグにある場面である。いよいよ次回は、その『朱色の研究』が原作となる。ちなみにそのプロローグは、こんな文章で締められているのである。
──え?
背後にぞくりと悪寒が走った。
その人物──火村が戦うことになる殺人犯が、夕占のお告げを受け取った瞬間だった。
(杉江松恋)



























