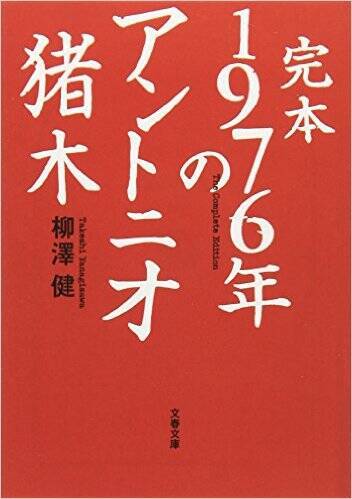
モハメド・アリといえば世界ヘビー級チャンピオンのプロボクサー、アントニオ猪木といえば日本を代表するプロレスラー。まったくジャンルの異なる二人が、なぜ戦うことになったのか? どのような経緯でどのような結末を迎えたか、については多くの書籍や映像などで語られている。たぶん、本日放送される『猪木 vs. アリ』でも触れられるはずだ。
ここでは、柳澤健による名著『1976年のアントニオ猪木』(文春文庫)を中心にして、猪木VSアリ戦の隠れたエピソードについて紹介したいと思う。試合の結末を知っている人も、知らない人も、これを読めば、より二人の戦いに対して理解が深まるはずだ(というか、『1976年のアントニオ猪木』をぜひとも読んでほしい)。
アリはプロレスが大好きだった
モハメド・アリのトレードマークの一つといえば“言葉”だ。いわゆる「名言」や「心に残る言葉」などではない。対戦相手を容赦なく罵倒し、挑発する機関銃のような“大口”“大ボラ”である。
人気番組『フリースタイルダンジョン』などで耳にする、相手を攻撃するフリースタイル・ラップを想像するとわかりやすいだろう。あれを試合前の公開練習や記者会見、テレビやラジオへの出演の際、対戦相手に向かってやりまくるのだ。
そもそも、アリの言葉遊びを交えた相手への言葉での攻撃がラップのルーツの一つとも言われている。ジョー・フレイジャーとのマニラでの試合を控えたアリは、フレイジャーに「It will be a killa...and a chilla...and a thrilla...when I get the gorilla in Manila!(オレ様がマニラでゴリラを捕らえたなら、殺し(キラー)でゾクゾク(チラー)スリラーだ)」という言葉を送っている。
それまで、アリのように対戦相手を挑発するプロボクサーは皆無だった。では、なぜアリは言葉での攻撃を行うようになったのか? それはプロレスから大きな影響を受けているからである。アリはプロレスが大好きだったのだ。
モハメド・アリ、本名カシアス・クレイは、中流家庭に生まれ、両親から愛情と教育をたっぷり与えられて育った。6歳の頃からボクシング・ジムで多くの時間を過ごし、持ち前の勤勉さでハードトレーニングに励んだ。
クレイはプロデビュー直後、試合のプロモーションで出演したラジオ番組である人物と出会う。それが人気プロレスラー、ゴージャス・ジョージだった。クレイは控えめに試合前の意気込みを語ったが、ゴージャス・ジョージは自分の試合について聞かれると、次のように語ったという。
「やつをぶっ殺してやる。やつの腕を引きちぎってやるぜ。
センセーショナルな“煽り”の効果もあってか、ゴージャス・ジョージの試合は満員になった。何千人も観客の中にはクレイの姿もあった。彼自身、ジョージの言葉に強く惹きつけられたからだった。
その頃、クレイにはもう一つの大きな出会いがあった。
彼女は、ギャランティに関する画期的な発明を行った。それは、選手へのギャランティを入場者数に比例して支払うというものである。この方法により、ボクサーたちは自分の試合のプロモーション活動に熱心になった。クレイも、その中の一人である。
ゴージャス・ジョージの常軌を逸したしゃべりと巨大な影響力を目の当たりにしたクレイは、さっそくアイリーンにジョージを紹介してくれと頼み込む。クレイはジョージから人々を挑発する力を学ぼうとしたのだ。
アイリーンはジョージの代わりに“銀髪鬼”フレッド・ブラッシーを紹介する。ヤスリで歯を磨くパフォーマンスと噛み付きの反則技を得意とする悪役レスラーで、日本で試合を行ったときは、噛み付きによって流血するグレート東郷の姿をテレビで見ていた老人が何人もショック死したという逸話を持つ。
ブラッシーはクレイに求められるまま、自分の悪役レスラーとしてのテクニックを次々と与えていった。当時のクレイの部屋には、ブラッシーのプロレスの試合が収録されたビデオテープが山積みになっていたという。クレイ――1964年にモハメッド・アリと改名――は天才ボクサーとしての道を歩みながら、プロレスから多くのものを盗み出そうとしていた。人々を挑発する言葉、パフォーマンス、ストーリーのつくり方、アイディア、すべてだ。
王者ソニー・リストンとの世界タイトルマッチ直前に放たれたアリの言葉を読めば、いかにアリがプロレスから大きな影響を受けていたかがよくわかると思う。
「もしもソニー・リストンが俺を叩きのめしたら、俺はリングの上でヤツの足にキスをして、這いずったままリングを下り、ヤツに『あなたは最高です』とい言い、ジェット機でこの国を出ていくぜ。俺は最高だ。どこへ行っても満員の観客を引き寄せることができる。俺がいなけりゃ、この試合は売れっこない」
彼が初めて聞いた、ゴージャス・ジョージの言葉そっくりである。
アリは「プロレス」をするつもりだった
プロレスから大きな影響を受け、世界のスーパースターとなったモハメド・アリだが、徴兵拒否による3年以上にわたるブランクと加齢による衰えは隠すことができなかった。1974年10月、25歳のジョージ・フォアマンを倒した“キンシャサの奇跡”のとき、すでにアリは34歳になっていた。
前述のジョー・フレイジャーとの死闘を制したのは翌年のこと。しかし、このときからアリの体力はめっきり落ち、ボクシングへの情熱も失ってしまったように見える。消化試合のようなタイトルマッチをこなした後、アリの目は日本に向けられた。背景には、当時のアメリカの“日本車ブーム”があったと言われている。すでに十分な富と名声を得ていたアリだったが、大勢の取り巻きから金をむしられ放題むしられていたため、さらなる大金が必要だったのだ。
1976年3月25日、モハメッド・アリとアントニオ猪木が同席して、正式調印が行われる。二人の試合が行われると決定したのだ。アリのファイトマネーは610万ドル(約18億3000万円)。何もかもが破格のスケールの試合だった。
当時のアメリカで――というか今でもそうなのだが、プロレスといえば「フェイク(インチキ)」だというのが常識だった。結末があらかじめ決まっている演劇の一種であり、リアルファイトであるボクシングからは一段も二段も落ちる見世物、という認識があった。世界のスーパースターが、なぜ日本のプロレスラーなどと戦わなくてはいけないのか、と多くのアメリカ人が考えていた。
記者会見でアメリカからやってきた記者たちは、アリと猪木に「この試合はフェイクなのか?」という質問を集中させた。アリの答えは「バカを言え、リアルに決まっている。俺は世界一強いんだ」。猪木の答えは「よくぞ聞いてくれました。そういう目でプロレスを戦う人たちの誤解を解くために、私はこの試合を戦うんです」。二人の言葉を聞いても無駄だった。この試合はフェイクなのか、リアルファイトなのか、記者たちにはまったく見当もつかなかったのだ。
アリの考えは決まっていた。猪木とプロレスをやる。それだけである。
アリにとってプロレスは、エキシビジョンマッチ(公式記録としない公開演技や模範試合)と同義だった。ボクシングに比べて、大きな危険がない。それでいて大金が手に入る。これ以上のことはない。何より、アリはプロレスが大好きだった。
アリはアメリカに帰ると、さっそくプロモーション活動に精を出した。この試合のアメリカ側のプロモーターはWWE(当時はWWWF)である。6月1日には、リングサイドでプロレスの試合を観戦していたアリがエキサイトして乱入、人気レスラーのゴリラ・モンスーンに挑むも、逆にボディスラムで投げ捨てられた。観客は沸き立ち、アリの失態は大きな話題を呼んだ。もちろん、すべて筋書き通りである。
その後も、アリはプロモーションを兼ねたプロレスの試合を行っている。プロレスの指南役だったフレッド・ブラッシーは、ちゃんとプロレスラー相手に受け身をとったアリのエンターテイナーぶりを絶賛し、今すぐプロレスラーになれると賛辞を送っている。
アリと猪木の試合は、どのような結末が予定されていたのだろうか?
アリの多くの試合をプロモートしてきたボブ・アラムは、猪木がアリをフォールする予定だったと語っている。アリが数ラウンドにわたって猪木を殴り続けた後、猪木は半狂乱になって剃刀の刃で自分を傷つけようとする。アリは試合を中止するようレフェリーにアピールするが、その隙を突いて猪木が後ろから襲いかかり、アリを押さえつけるという筋書きだ。真珠湾の奇襲攻撃がモチーフになったシナリオだ。
一方、現在WWEの総帥であるヴィンス・マクマホン(ジュニア)は別の結末があったと語っている。彼はブラッシーとともに試合の結末に関するアイディアを出し合った。レフェリーが何かの拍子にアリを傷つけ、さらに巧妙に剃刀で切り傷をつけることで流血によるドクターストップに持ち込もうとしていた。
アリ自身も、アメリカの一部のメディアに対して、これがエキシビジョンファイトであり、リハーサルを行うと伝えていた。アリに良心の呵責はあったものの、プロフェッショナルとして最高のプロレスを行うと決心していた。あとはシナリオを練り、入念なリハーサルを行うだけだ。
プロレスをリアルファイトに変えたのは猪木だった
日本にやってきたアリは、猪木側に「いつ試合の練習をするんだ」と伝えたという。ところが、猪木側の返事はアリの予想もしないものだった。
「とんでもない。そんなものはやらない。これはエキシビションじゃない。真剣勝負なんだ」
アリは驚いた。日本のプロレスラーが、なぜ自分とリアルファイトをするつもりなのかと。しかし、猪木側は強硬だった。ヴィンス・マクマホンは知らせを聞き、心配してアメリカから駆けつけたのだ。「ブラッシーをつけてるにも関わらずなんでこんなヒートアップして、シュートマッチをやるっていう話になってるんだ?」。
ブラッシーはアリ陣営に助っ人として加わっていたが、どの現場でも芝居がかったパフォーマンスを行って場を和ませようとしていたのだという。ところが新日本プロレスの若手選手は「プロレスラーのくせにボクシングのほうにつきやがって!」とブラッシーを目の敵にしていた。今から考えれば無理もない話だが、ブラッシーが少し気の毒でもある(『ゴング』14号より)。
「アリは、世界最高のプロレスを日本の観客に披露するつもりでやってきたにもかかわらず、猪木の罠にはまり、訳のわからない異種格闘技戦(Mixed Martial Arts)のリアルファイトを戦う羽目に陥った」
これが『1976年のアントニオ猪木』の著者である柳澤健氏が導き出した「猪木VSアリ戦」の「真実」である。
猪木の敵はアリではなく「馬場」だった
では、なぜアントニオ猪木は得意のプロレスではなく、リアルファイトを選択したのだろうか? 柳澤氏は、その理由がジャイアント馬場にあるのではないかと推理している。
馬場と直接戦って倒すわけではない。どちらが日本のプロレスの第一人者となるかの戦いである。
馬場と猪木は同期入門だったが、すぐに馬場は大きく猪木に差をつける。元巨人軍の投手で身長2メートルを超えるフィジカルエリートだった馬場は、すぐさまプロレスの本場、アメリカへ遠征し、スーパーヒールとなって大出世した。それ以来、猪木は馬場をライバル視していたが、一向にその差は縮まらなかった。
馬場はプロレス界の最高権威であるNWAとの関係を独占し、NWAは次々と世界チャンピオンらアメリカのトップレスラーを馬場の全日本プロレスへ派遣してきた。二流レスラーと対戦せざるを得なかった猪木は、馬場の論理では「二流」である。
しかし、モハメッド・アリはNWAなどとは比べ物にならない権威である。猪木がアリとの試合を熱望したのは、アリが馬場の手が届かない正真正銘の権威だからだ。
だが、「モハメッド・アリとプロレスをしたから猪木は偉い」という論理は、「NWA王者とプロレスをしたから馬場は偉い」という馬場の論理と同じ回路のものだ。あらゆる面で馬場を超えたい猪木は、その巨大な権威さえ打ち倒したくなったのだ。
そして、猪木はプロレスラーが蔑みの対象であったことに強いコンプレックスを持っていた。プロレスはたしかにショーであり、エンターテインメントだ。しかし、リアルファイトにおいて、レスラーがボクサーより弱いということでは断じてない。これは多くのプロレスラーが抱える鬱屈でもある。いつも命懸けで戦っている俺たちは、本当は強い。だが、プロレスというだけで蔑まれている――。
猪木はジャイアント馬場を倒すため、そしてプロレスラーとしてのコンプレックスを跳ね返すため、18億円もの巨額のファイトマネーを用意して世界最強の男、モハメッド・アリにリアルファイトを挑んだのである。もちろん、猪木はアリに勝つつもりだ。
プロレスを愛した天才ボクサー・アリと、打倒アリに狂気じみた執念を燃やす猪木。二人の闘志が交わった先にどんな結末が用意されているのか? それは今夜の『猪木vs.アリ』を見て、あなたの目で見届けてもらいたい。
(大山くまお)
































