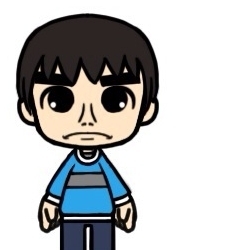その横でタモリと談笑するウッチャンナンチャン。
「とんねるずが来たらネットが荒れるから!」と叫ぶ松本人志。
その声に応えて乱入する、とんねるずと爆笑問題。
2014年3月31日。『笑っていいとも!』のグランドフィナーレ。戸部田誠(てれびのスキマ)『1989年のテレビっ子』の回想は、あの伝説の一夜から始まる。現在のテレビの基礎を築いた”テレビバラエティの青春時代”を「1989年」とし、BIG3やお笑い第3世代、テレビマン達の生き様を描いた歴史絵巻だ。

「土曜8時」という戦場
『1989年のテレビっ子』で軸となっているのは、TBSとフジが交互に天下を取った「土8戦争」だ。本書巻末にある年表を元に、1970〜90年代における土曜8時の移り変わりを図にしてみた。

『全員集合』の練りこまれたコントの逆を目指し、『ひょうきん族』は会議をせず、とにかくカメラを回して現場で偶発的に起こる笑いを拾った。『カトケン』はさらにその逆を行き、カーチェイスや水中撮影などあらゆる手を尽くして長尺のコントを作りこんだ。
芸人やテレビマンが死力を尽くす姿に、まさに当時テレビにかぶりついて観ていた世代としてテンションが上がる。だがそれだけではなく、本書では番組が終焉する空気まで丁寧に描かれている。
休養を機に全てのレギュラー番組を失った萩本欽一。
テレビを観ている側は、常に面白い番組のほうを観る。かつて観ていた番組に「終」のマークが付いているのに気がついて「やっぱり」と言ってしまう。「終」の裏にある想いには気づかない。かつて中居正広は『笑っていいとも!』グランドフィナーレのスピーチで、タモリに「バラエティは残酷」と語った。
「非常にやっぱり……バラエティの終わりは……寂しいですね。他のジャンルは、評判が良かろうが悪かろうが、終わりがあるんですけど、バラエティって……ゴール無いところで終わらなければならないので、こんなに……残酷なことがあるのかなと、思います」
番組開始前のスタッフの意気込みや、初めて満足いく数字が取れた時の手応え、チャンスをものにしてのし上がる芸人たちの姿を読みながら、「終わるつもりで作っているバラエティなど無い」という当たり前のことに気がつく。
「テレビ」から始まったとんねるず
テレビ史に残る土8戦争に直接携わっていないにもかかわらず、「第4章 時代を先取るとんねるず」で丸々1章割かれているのがとんねるずだ(ちなみに章題はとんねるず往年のギャグ「時代を先取るニューパワー」からきてる、はず)。
とんねるずは高校時代に「日本一おもしろいシロート」として素人参加番組に出まくっていた。プロになる気はなく、高校卒業と共に二人とも就職した。
師匠がいるわけでも、寄席に通っていたわけでも、芸人を目指していたわけでもない。二人を育てたのはテレビだった。デビュー後は『オールナイトフジ』でカメラを倒したり、『夕やけニャンニャン』で観客と乱闘したり、『みなさんのおかけです』で木梨憲武追悼特番ドッキリを放送したりした。やりたい放題のとんねるずを支持したのもまた、テレビの前の若者だった。そして1989年、『みなさんのおかげです』は同時間帯の『ザ・ベストテン』を終了に追い込む。
本書では「内輪受け」という切り口でとんねるずを捉え、大衆の時代から個人の時代を先取りしたのがとんねるずである、と語る。確かに、土8戦争のように視聴率を争うと相手は「大衆」だ。近ごろテレビが「つまらない」と言われるのも、個人の好みが細分化した今の時代に視聴率=大衆を相手にした戦いをしているからかもしれない。
「ただものではない」所さん
ところで、最後まで本書を読んでもある人物が登場しないことに気がついた。『笑っていいとも!』のレギュラーを過去7年努め、1980年代に冠番組を多く持ち、「理想の上司」ランキングには必ず顔を出し、今現在もほぼ全曜日にテレビに出ている。素人時代のとんねるずが初めて二人揃って出演した『ドバドバ大爆弾』の司会もしていた。
調べてみると1989年付近、所ジョージも多くの番組を始めていたことがわかる。『所さんの目がテン!』(1989〜)、『世界まる見え!テレビ特捜部』(1990〜)、『所さんのただものではない!』(1985〜1991)、『どちら様も!!笑ってヨロシク』(1989〜1996)などなど。1990年には『マジカル頭脳パワー!』が日テレ土曜8時に始まっており、先述の土8戦争にもちょっとだけ関わっている。現在まで続いている番組もあり、まさに「ただものではない」活躍ぶり。
所ジョージはミュージシャン出身であり、芸人たちの覇権争いとは無縁の立場。そのため本書には登場しないのだが、激闘を横目に「すごいですねぇ〜」と冠番組を成功させているのも“バラエティ青春時代”の一幕と言えるだろう。
戸部田誠(てれびのスキマ)『1989年のテレビっ子』は8つの章で構成されている。
第1章 『THE MANZAI』とマンザイブーム
第2章 ひょうきん族の時代
第3章 土8戦争
第4章 時代を先取るとんねるず
第5章 お笑い第3世代の胎動
第6章 日本テレビの逆襲
第7章 BIG3の1989年
最終章 テレビの嘘と希望
いつも本を読むときはぐっと来たところに付箋を貼っているのだけど、当時からテレビっ子の自分には付箋を貼りたい箇所が多すぎて、結局全部貼らないことにした。どこを開いてもぐっと来てしまうから。でも一つだけ、どうしてもパッと開きたくて貼ってある箇所がある。
「マッチ、セットを壊しながら歌い続け、最後に死ぬ」(P.106)
「ひょうきんベストテン」で、片岡鶴太郎が初めてマッチのモノマネをする時に台本に書いてあった言葉。
(井上マサキ)