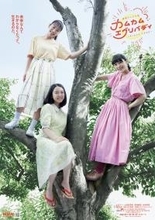この足音をはじめ、アニメ版「鉄腕アトム」の音響を手がけたのは大野松雄という人物である。まもなく公開される映画「アトムの足音が聞こえる」(5月21日より東京・渋谷のユーロスペースにてレイトショー開始。以後、全国の劇場で順次公開予定)は、大野の足跡をたどったドキュメンタリーだ。監督が「パビリオン山椒魚」「パンドラの匣」などの劇映画で知られる冨永昌敬というのも、何だか異色である。
「アトムの足音が聞こえる」の前半では、大野松雄とともに仕事をした人たちの証言によって彼の業績が振り返られる。大野は劇団・文学座の演出部からすぐにNHKの効果団に移り、効果音の仕事を手がけたもののいずれも長続きせず、1953年にはフリーになる。このころ彼が夢中になっていたのが、まだ誕生まもなかった電子音楽だ。その影響から以来、彼はさまざまな映像の効果音を手がけながら、新しい音づくりをめざすことになる。
映画のなかでは「アトム」の前後に彼が手がけた作品も何本か紹介されていて、たとえば1962年に公開された科学映画「血液 止血のしくみ」では、血小板(血液の成分のひとつでかさぶたをつくる)の映像に祭ばやしのような音が当てられていたりと意表を突かれた。
大野がやりたかったのは、単に映像に効果音をつけるのではなく、音全体をプロデュースする音響デザインというべきものだった。
そのなかにあって大野をはじめ多くのエンジニアたちは試行錯誤を続け、“本物よりも本物らしい音、本物を超えた音”をつくり出していく。シンセサイザーなどといったものはまだなく、オープンリールのテープレコーダーしかなかったこの時代、音づくりはテープをはさみと糊で切り貼りするというまったくの手作業でやるしかなかった。ちなみに長寿アニメ「サザエさん」は、いまだにこの手法で効果音がつくられていたりする。
「アトム」での大野の仕事は多くの仲間や後進に影響を与えた。「宇宙戦艦ヤマト」や「機動戦士ガンダム」といったアニメ作品もその延長線上にある。だが当の大野は、その後依頼された「ルパン三世」(ファンのあいだでは「緑ルパン」と呼ばれるシリーズ第1作)の仕事も「ぼくの趣味じゃない」と助手にまかせて、さっさとテレビアニメの世界から離れてしまう。その後は仲間たちと映像制作の会社をつくったり、“この世ならざる音”を求めて宇宙の果ての音をイメージしたレコードをつくってみたりと、自分の世界へとのめりこんでいく。
と、前半でここまで紹介されても、この映画にまだ大野松雄は登場しない。証言するかつての仲間たちも、じつは長いこと大野に会っていないのだという。それというのも、彼は「アトム」で稼いだ金をごっそり持っていかれてしまい、ついには借金取りに追われ夜逃げしてしまったというのだ。
むかーし、私が手伝っていた雑誌(何を隠そう先述の「Quick Japan」でやんす)で、ノンフィクションライターの大泉実成氏が「消えたマンガ家」という連載をしていた。そこに登場する元マンガ家たちはかつて才能を発揮しながら、さまざまな理由から筆を折り、その後は隠遁したり宗教を開いたり、場合によって自ら死を選んでしまうケースが目立った。大野も金をだまし取られたというのなら、他人を信用できなくなって隠遁生活を送っているのではないだろうか。そこまでいかなくても、偏屈でひとつの物事に執着しなかったとされる彼の性格のこと、音響の仕事から引退しているかもしれない……。不吉な予感が私の頭をよぎった。
(ここからネタバレ注意)
取材陣がようやく見つけ出した大野松雄は、人間不信に陥ってもいなかったし、引退もしていなかった。とはいえ、大野がいたのは、知的障碍を持つ人たちが集団生活を送る福祉施設というちょっと意外な場所であったが。彼はこの施設で年に一回催される演劇会で、もう30年間も音響を担当しているのだという。
大野が知的障碍の人たちとかかわるようになったきっかけは、この施設に取材した記録映画で音響を担当したことだった。だがこのとき彼は監督と大ゲンカをしている。その理由は監督が施設の人たちを「上から見ていた」からだという。たしかに、そのときの記録映画は一部だけを見ても、いかにも暗いトーンで、障碍者たちは社会から隔離された“かわいそうな人たち”という印象しか残らない。やがて彼は自主的にこの施設に住む人たちを撮りはじめる。そこでは先の記録映画とは打って変わって、障碍者たちが明るく、生き生きと描かれている。
福祉施設にかかわるいっぽうで大野は、80年代には日本各地での博覧会の仕事を数多く手がけたのち、90年代に入ると京都に“亡命”、京大教育学部の研究室に居候して、子供の発達に関する記録映像にたずさわったり、音響効果についてのワークショップを開いて若者たちに指導したりという活動を行なっていた(ちなみに、ミュージシャンのレイ・ハラカミはその頃の大野の教え子の一人)。大野は引退するどころか、むしろそれを発展させ、後継していくことに力を注いできたわけである。そこには人間に対する強い関心というか、深い愛情を感じる。
さて、大野の口から直接語られる「鉄腕アトム」のころの話がまた痛快だ。音へのこだわりから大野にあれこれ注文を出す手塚治虫に対していっさい耳を貸さず、ついには「おたく(手塚)は印刷媒体ではプロだと思ってるし尊敬もするけど、映像ではド素人なんだから黙っててくれ」と突っぱねたというからすさまじい。
それにしても大野のべらんめえ調の語り口は、どこか江戸前の噺家っぽくもある。
大野の江戸っ子気質というか職人気質は、彼がことあるごとに口にする“プロフェッショナル観”にも表れている。大野がプロフェッショナルの条件としてあげる2点のうち、「常にアマチュアになれること」というのは何となくわかる。プロになっても一つ方法にとらわれず、いつでも新しいものを柔軟に取り入れていくという意味にもとれるし、あるいは、ときには金をもらわなくてもきっちりと仕事をこなすこと、というふうにも解釈できる。大野がほとんどボランティアで福祉施設での仕事を続けているのは、まさにそれだろう。
大野のあげるプロの条件のもうひとつ、「どんなに手を抜いても、他人にはそれをわからせないこと」というのは、私みたいなペーペーが言ったらブン殴られそうだ。これはやはり天才だから言える言葉ではないか。例のアトムの足音はテープに録音したマリンバの音を加工したもの(じつは電子音ではなかった!)だが、これも大野に言わせれば「適当につくったらできちゃった」ものだという。
かつて大野は「鉄腕アトム」の音はシンセサイザーでもつくれたかと問われたとき、「絶対にできない!」と答えたという。たしかにどんなに機械が発達しようとも、手を抜いたり、適当にやるなんてことは永遠にできないだろう。大野松雄は天才は天才でも、じつに人間くさい天才だった。この映画はそんな彼の魅力を十分に伝えてあまりあるドキュメンタリーである。