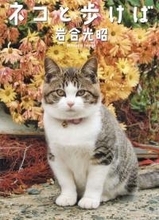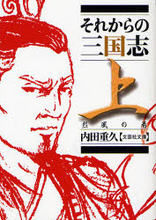シングル盤は17センチ、アルバムだと30センチのアナログ盤。そのジャケットのサイズは、比べるまでもなくCDのものよりかなり大判だ。そのサイズと、その時代の空気でしか生み出せないだろう、デザインセンスにそこは彩られていた(逆にCDのジャケットでしか生まれないデザインも数多くあるとは思うけれど)。
そんなイカした昭和中期のレコードジャケットデザインの数々を一冊に集めたのが、そのままズバリ、『昭和のレコードデザイン集』(山口‘Gucci’佳宏 鈴木啓之/Pヴァイン・ブックス)。
「デザイン集」なので、ここで取り上げられているのはジャケットのみ。いわゆる「名盤紹介」の類の本ではないので、盤に収録された内容についてはここでは触れられない。さらに、「アンディ・ウォーホルがデザインを手がけた」とか、「篠山紀信が撮影した」的な意味での有名デザインを扱うわけでもない。有名無名、売り上げ、内容などは問わず、ジャケットのデザインセンスのみを基準にピックアップされているレコードたち。だから、美空ひばりや橋幸夫、フランク永井に弘田三枝子、和田弘とマヒナ・スターズなどメジャーどころのレコードと、民謡や童謡にラテン、リズム歌謡、さらにはミラクル・ヴォイス(仮名)なんて謎の歌手のレコードまでが、等列に並ぶ。なかには「システム視聴用レコード」なんていう、業務用的なものまであったりする。
これらの作品は、「ダンス」「女性」「日本」「クリスマス」などのテーマごとに分類されて紹介されている。
あれこれ眺めていると、配色や構図、文字のデザインに至るまで、正方形の中に気持ちよく収まる美学みたいなものを感じる。
なかでも、ああ昭和だなぁみたいな、「ならでは」感が強いのが、「少色刷り」というくくりのジャケット群。フルカラーではなく、2〜3色で印刷されたもので、当時の限られた予算などの中で、このようなものが多く作られたという事情があるが、この限られた条件で工夫をこらしたからこそ、デザイナーのセンスと腕が問われるのだとか。
本書はジャケットだけでなく、アルバムにはつきものの「帯」や、レコードの内袋にも目を向け、イカしたデザインを紹介している。
盤に収録された楽曲の世界への‘旅’をより楽しむための小道具でもあった、ジャケットや帯(手に持って眺めて、いろんな想像しながら聴くこともあったかと)のデザイン。配信で気軽に音楽を楽しむことができる今だからこそ、あらためてその魅力に注目したい。
(太田サトル)