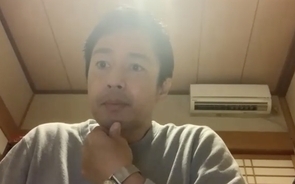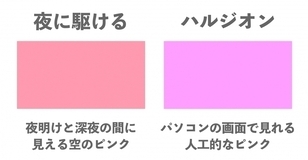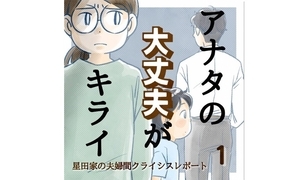「長い付き合いの彼氏に、結婚の意思が一向に見えない」、「夫がバスタオルやTシャツの置き場所を覚えない」、「ただ愚痴を聞いてもらいたかったのに、解決策を提示してきた」……。女性にとっては、“あるある”な男性の困った行動。
恋バナ収集ユニット“桃山商事”の代表を務めるライターの清田隆之は、著書『よかれと思ってやったのに 男たちの「失敗学」入門』(晶文社)の中で、ありふれたすれ違いの裏にある男性側の思考を分析している。1200人以上の女性たちの失恋話や恋愛相談に耳を傾ける中で、清田は、男性にとっても“おしゃべり”が重要な行為であることを感じているらしい。
一部の男性読者は激怒!?

――女性がこの本を手に取るのは、男性側の心理が知りたいからだと思うんですが、男性はどんなことを求めて、『よかおも』を読むのでしょうか? 耳の痛い話ばかりな気がしますが……。
男性向けに書いてはいるものの、実際に読んでくれるのは女性が多いかもなと思っていたのですが、ありがたいことに読者のうち半分くらいは男性だそうです。その多くは「女性とどうコミュニケーションを取ればいいのか」「無意識にセクハラをしてしまっていないか」といったことを気にして本書を手に取ってくれたようですが、「話題になっている本みたいだから」といった理由で読んでくれた人もいて、そういう男性の中にはブチギレ気味の感想を書かれている人も一定数いました。ただでさえ男性に耳の痛い話が続くので、叱責するような語り口にはならないよう意識し、可能な限り論理的な記述を心がけたんですが、なかなか難しいところですね……。
――ジェンダーを勉強したことで、自分の性別が持つ加害者性に悩むことになる男性もいます。それでもジェンダーについて知る意味をどのように捉えていますか?
「フェア」や「平等」ということに敏感でいられると思うんですよね。たとえば自分がソファでダラダラしている横で、妻や恋人が家事をしている。あるいは、入試や就活の試験で、男性であるというだけで知らぬ間に得をさせられていた。そんな男性優位の構図が世の中のいろんなところで生まれているとしたら、「ラッキー♪」なんて絶対に思えませんよね。
――いろいろな著書の中で出てくる、清田さんの過去のエピソードはなかなか衝撃的ですよね。男友達の笑いを取るために、彼女と乗ったスワンボートの中で立ちションするとか……。
お恥ずかしい限りです……。自分はなぜあんなことをやっちまったんだって、思い出すだけで「うああああ!」となります。でも当時の自分としては、それで男友達のウケが取れると思っていたし、そんな“おバカな俺”を恋人も許してくれるだろうと思いこんでいたんですよね……。でも、女性から恋愛の話を浴びるように聞いたり、ジェンダーを学んだりする中で、あのとき自分が取った行動が“ホモソーシャル(男性同士の結びつきのこと。いわゆる男の絆に近いものだが、その危険性も指摘されている)”の典型例だったことを痛感し、何度も「うああああ!」ってなりました。
――言い方は悪くなりますが、女性側の心理に詳しくなって、自分を見つめ直す“メリット”とはどんなものだと思いますか?
女性心理に詳しくなるというより、共感能力(=エンパシー)を養うというイメージだと自分では考えています。メリット/デメリットで語れる次元の問題ではないと思いますが、構図としては、「楽をしていることを自覚しよう」「既得権益を手放そう」って話だから、男性にとってはメリットがないと思われそうですよね。
素直な感情を共有する“おしゃべり”の効力

――おしゃべり?
話は少し回り道になりますが、精神科医でミュージシャンの星野概念さんと「話を聞くこと」について考える対談連載で、「コミュニケーションには4つのステージが存在する」という話を教わりました。臨床心理士の堀越勝さんが書いた『精神療法の基本:支持から認知行動療法』(医学書院)によれば、まず第1ステージは「挨拶レベル」、第2ステージは主観の入らない情報のやり取りをする「事実・数字レベル」、第3ステージは自分の見解を述べたり、相手と議論を交わす「考え・信条レベル」、第4ステージは感情を共有する「感情レベル」となるそうです。
TPOや関係性によって適切なコミュニケーションは異なってくると思いますが、個人的な印象では、第4ステージのコミュニケーションができる男性って、女性に比べてめちゃくちゃ少ないと感じています。おそらく、なるべく感情を排し、理性的に話すことを良しとするジェンダー規範が影響しているのだと思われます。
――たしかに、多くの男性は第3ステージにあたる議論は重視しても、シンプルな自分の感想や気持ちを話す第4ステージの会話には照れがあるように感じます。
もちろん一概に性別で括ることはできないし、あくまで「全体で見たとき、こういう傾向があるんじゃないか?」という意見ではあるんですが、会話に“テーマ”や“ゴール”がないと不安を感じる男性って多いように感じるんですよね。会議や議論のようなものはできるかもしれないけど、話をすることそのものが目的となる“おしゃべり”が苦手な傾向になるというか。
一方で、いわゆるガールズトークと呼ばれるものは、シナプス結合のようなスタイルで会話が進んでいく印象がある。仕事の話から「そういえばさ~」と食べ物の話やファッションの話になり、そこから今度は恋愛や健康の話になっていく。脈絡のない話をしているようで、実はすべてつながっているのが面白いなと感じます。もしも男性がその会話に放り込まれたら、「これって何の話?」「どこに向かってんの?」と不安になってしまう人が多いような気がします。
――いわゆるガールズトークを「取り留めがない」「オチがない」と嫌う男性は多いですよね。
そうですよね……。個人的にはこういう会話スタイルのほうが楽しいし、ある種のスキルを要する高度なものだと感じるんですよね。話題を数珠つなぎのようにして展開していくためには、相手の話に耳を傾け、内容を的確に理解する必要があるし、当意即妙な相づちや、自分の気持ちをわかりやすい言葉で言語化していくことも求められる。そうやってそれぞれ話したいことを気ままに語り合いながら、お互いのいろんな側面がシェアされていくというのがおしゃべりの醍醐味だとガールズトークから学びました。
僕は演劇が好きなんですが、ハイバイという劇団が以前、『おとこたち』という作品を上演しました。これは4人の男性の生涯を描いた作品なんですが、学生時代からの同級生である彼らはことあるごとにつるんでいて、就職、転職、出世、失業、不倫、子育て、事故、病気、老い……など人生の様々なイベントを経験していくんですね。物語の終盤、仲間の中で最も順調な人生を歩んでいた鈴木という男が死んじゃって、そのお葬式のシーンで、他の男たちが「俺、鈴木の顔、じっくり見たことなんてなかった」「そう考えるとそうだな」って話す場面があって、ぞっとしたんですよね。
というのも、男性って「こいつは、こういうキャラクター。自分は、こういうキャラクター」というふうにキャラや役割を固定化しちゃう傾向がある気がしていて、下手すると相手をちゃんと見なくなっていくんじゃないか。1人の人間の中には、いろんな顔があって変化している部分もたくさんあるはずなのに、それに目を向けない。あのセリフにも、もしかしたらそんな背景があったのかもなって。
相手の“キャラ”を設定し、コマンドを選んでいく会話
――たとえば私はプロレス観戦が趣味なんですけど、大人しそうな雰囲気をしているから意外に思うのか、そこを“イジれるポイント”のように捉える人がいて、その場は盛り上がるかもしれないけれど、正直話していて疲れはします……。
それはかなりキツいね……。いわゆるバラエティ番組のようなコミュニケーションですよね。まず相手のキャラクターを勝手に設定した上で、「こいつは、こういう系だから、こんなふうに接しよう」とコマンドを選んでいくというか。自分なりに相手の人となりをじっくり観察していくのではなく、パパッと枠組みを決め、以後はそれに則って戯れを延々くり返していく……。たしかにそれは楽だし盛り上がりもするけど、取りこぼされるもの、切り捨てられるものも多くて、特にイジられる側はつらくなってきますよね。
――逆に「プロレスのどんなところが好きなの?」のように質問されると、なんだか安心します。
めっちゃわかる。質問してもらえると自分への興味や関心を感じられるし、それはまさに、人間の感情に焦点を当てた“おしゃべり”ですよね。普段から仲良くしている人たちには男女問わずおしゃべり好きが多く、「向こうの話を聞かされるばかりで話し足りなさが残った」というフラストレーションを感じることは正直ないんですが、出版業界の先輩みたいな人が相手だと、「清田くん本を出したんだって? もう大先生だ! ワッハッハ!」みたいな感じで、一方的にイジられて終わっちゃうことが多く……。
――雑~!
あと、これは自分の中でかなり衝撃的な出来事だったんですけど、仕事でシニア世代の男性たちに取材する機会があって、そのとき渡された名刺に「元○○新聞記者」って書いてあって。「元」をつけるほど肩書きが大事なんだ!って、びっくりした(笑)。役割や肩書きありきの関係性しか取り結べないと、定年後が心配ですよね。
もっと素直に“バブバブ”言おう
――ここまでのお話をまとめると、お互いの感情や人となりを共有するタイプのコミュニケーションが苦手だと、会話をしていても自分そのものを受け入れてもらった感覚が得られず、孤独感を募らせていく危険性があるということなのかなと。“おしゃべり”ができるようになるためには、どんなことが有効だと思いますか?
簡単に「おしゃべり大事!」と言ってきましたが、やろうと思えばすぐにできるものでもないですよね。そのためには傾聴力や読解力、想像力に感情の言語化能力……といろんな力が必要な気がするので。う~ん、どうしたらいいんだろ。ちょっと抽象的な話になってしまいますが、まずは「相手は自分が想像している“キャラ”とは限らない」みたいな前提を持つことが大事だと思っています。「この人は、こういうキャラだから、こうだろう」みたいな枠組みありきのコミュニケーションをいったん崩さないと、おしゃべりは難しい。
まずはサシ飲みとかしてみると、いいかもしれない。いくら男性的なコミュニケーション──ツッコミだったりイジりだったりに慣れている人でも、さすがに1対1ではそれ一辺倒だと限界がある(笑)。相手の人格や自分の内面に向き合わないと、1対1の会話は成立しないと思うので。
――なるほど。
もしかしたら、自分のありのままの感情や体験を話すことができない理由には、俗に言う「自己肯定感」の低さも関係しているのかもしれません。この言葉はあらゆる不安や不調の源泉になり得る“マジックワード”っぽい部分があるため、個人的にはあまり簡単に使わないほうがいいと感じていますが、いずれにせよ、「自分がそんな話をしたところで誰が聞くのか」「自分の内面なんかに誰が興味あるのか」といった感覚があると感情レベルのコミュニケーションは難しく感じられるはずです。
たとえば僕には姪っ子と甥っ子がいるんですが、あの人たちを見ていると、思いついたことをそのまま話すし、やりたいことは何でもやるし、嫌なことは嫌って言うんですよね。そんな姿を見ていると、「自分の感情に従い、それを誰かに受け止めてもらいたい」というのは、人間が持つ基本的欲求のひとつなんじゃないかと感じます。そこに理由とか合理性とか必然性とか価値とかは関係ない。男女問わず、「なんでもいいから、あなたが今感じていることを好きにしゃべってごらん」と言ってもらえたら、人間は楽な気持ちになれると思うんですよね。
――子供の“そのまま話しっぷり”みたいなものを我々大人も見習って……。
『よかおも』は、ある意味、大人の男性による形を変えた甘え──つまり“バブバブ”をまとめた本と言えるかもしれません。でも、急に不機嫌になるとか、自慢話をするとか……そういう甘えって1ミリもかわいくないですよね(笑)。相手からのケアを期待するとか、プライドを保つために変な屁理屈をこねるとか、気弱そうな相手を選んでやるとかではなく、「これが好き!」「これ食べたい!」「そんなの嫌だ!」とか、思ったことや感じたことを素直に言っていけばいい。もちろんTPOや関係性ありきですが、我々大人ももっと素直にバブバブ言ってみたほうがいいと思うんです。慎重な自己開示は人間関係を開く鍵になると思うので。最初はハードルが高く感じられるかもしれませんが、真っ直ぐバブってみれば、周りも意外と受け止めてくれるかもしれません!

1980年生まれ、東京出身。恋バナ収集ユニット“桃山商事”の代表として、これまで1200人以上の体験談やお悩み相談に耳を傾け、“恋愛とジェンダー”をテーマに執筆活動をしている。桃山商事名義では、『二軍男子が恋バナはじめました。』(原書房)、『生き抜くための恋愛相談』(イースト・プレス)、『モテとか愛され以外の恋愛のすべて』(イースト・プレス)を出版。個人名義では、『大学1年生の歩き方』(左右社/トミヤマユキコとの共著)がある。2019年7月10日、男女の日常生活でのすれ違いを分析した新刊『よかれと思ってやったのに 男たちの「失敗学」入門』を晶文社より出版。