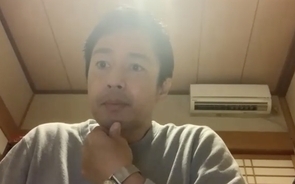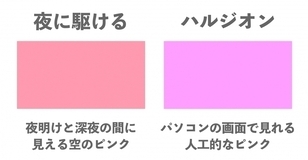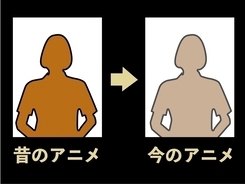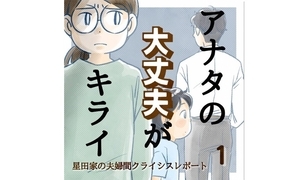2030年という今から10年後の近未来を舞台にしたサスペンス映画『AI崩壊』。劇中では、働ける人間は国民の50パーセント、未来を担う子供は10パーセント未満、残りは老人と生活保護者という設定のもと、AI(人工知能)が、全国民の個人情報、健康を完全に管理し、人々の生活に欠かせないライフラインとなっている。
そんな“人に寄り添う”はずのAIが突如暴走をはじめ、年齢や年収、家族構成、病歴などから“生きる価値”を選別し、殺戮を開始する――。これまで近未来サスペンスというと、リアリティよりはファンタジックな要素が強い作品が多かったが、この映画には、10年後という時代設定や日本の置かれている状況を考えると、あながち非現実的とも思えないリアリティが感じられる。
そこで、完全オリジナル作品として本作を世に送り出した入江悠監督と“10年後の日本”を監修したAI研究のトップランナーである東京大学大学院の松尾豊教授に話を聞いた。果たして、映画で描かれているような未来は本当にやってくるのか――?
10年後の日本はどんな未来に……

――近未来サスペンスということですが、10年後という時代設定にした理由を教えてください。
入江:小さいころから近未来パニックやSFが好きだったのですが、日本映画で『ターミネーター』や『ガタカ』のような映画にチャレンジすると痛いことになるんじゃないかという計算もあって、今と地続きの10年後ならば、日本映画でも描けるのかなと思ったんです。
以前からAIに興味があって、松尾先生のトークショーなども聞きにいったりしていたんです。AIはいま飛躍的に進歩している。10年後、風景はいまと変わらないとしても、裏側では劇的な変化が起きる可能性がある。そういう部分でも10年後というのは適当な時間設定かなと考えました。
――劇中では、人に寄り添うはずの医療AIが、人間を脅かす存在になっています。
入江:テクノロジーと人がどう関わっていくのかというのは昔から変わらないテーマ。そのなかで、今はAIが一番ホットなテクノロジーだと思うんです。しかも2045年には、人工知能が人間の脳を超えるシンギュラリティ(技術的特異点)がやってくると予測する専門家もいます。
――松尾教授は作品を監修されて、『AI崩壊』で描かれている世界はどのように感じられましたか?
松尾:AIの持つリスクについては常に議論されています。例えばAIで管理された自動運転の車が乗っ取られるシーンなどは、実際にイスラエルのベンチャー企業が、自動運転の車がサイバーアタックによってコントロールされることを未然に防ぐソリューションを提供しているので、リアリティはありますね。
AIが命の選別をしていくという描写も、実際中国では「芝麻信用」という個人信用評価システムが導入されていますし、まったくファンタジーなものとは思えません。専門家の目から見て、細かい部分がしっかりとしたリアリティのもとで描かれていると思います。よく映画である描写のようにAIが自身で考え始めて行動するというわけではなく、あくまでも人間が何らかの判断を下してAIが動くという部分も正確だと思います。
関心を持たないことの怖さ

――松尾教授はシンギュラリティについてはどうお考えですか?そのことで人間社会がAIに凌駕される危険性はあると思いますか?
松尾:AIが人間の知能を超えてしまうという部分で言えば、単純な四則演算の能力ではとうに人間を上回っていますし、人間を超える領域はどんどん増えていくと思います。ただ、AIがAIを生み出すといったシナリオに関しては否定的です。どちらかと言えば、悪い意図を持った人間が、AIを悪用して社会が混乱する、あるいは軍事的な利用などの方が大きなリスクだと思います。
――AIが国民を管理するという考え方は?
松尾:非常に難しいところです。抽象的には、イデオロギーによる対立の決着というのは、結局はどちらの考え方が優れていたかということではなく、どちらが繁栄したか、力を持ったかで決まります。AIで国民を管理するのは今の価値観では非常に良くないことに思えます。しかし、将来にわたってそうなのか、そういう考え方で繁栄する国がこの先現れないのか、それに対して、民主的に個人の情報やプライバシーを守る国が勝ち続けられるのかというのは、予断を許さないと思います。
入江:技術の進化って人間の進化と一緒で戻れないと思うんです。便利だから進化していくわけで、AIも今後、飛躍的に日常に入り込んでくるはずです。そこで「あまり自分には関係ない」と思って関心を持たないでいると、気づいたら大変なことになってしまっているかもしれない。実はそれが一番恐怖でもあると思うんです。AIをテーマにしたことには、そういう注意喚起的な視点もあります。
――マイナンバーなども一例なのでしょうか?
入江:極論でいえば、マイナンバーがいろいろなものに紐づき、監視社会になれば、本作で描かれていたような世界になる可能性もあります。それがいいのか悪いのかは、それぞれの人が判断するしかないと思うのですが、「全然知らなかった……」で意図しない世界になることは怖いですよね。エンターテインメントが現実を扱う意義というのは、そういう問題提起をしやすいし、伝わりやすいという側面もあると思います。AIが人を選別する世の中が“正”とされたなら、もしかしたらコンビニに入ることも、できる人とできない人が出てくるなんてことだってあるかもしれません。
人間の行動はまだほとんど解明されていない

――松尾教授はなぜAI研究をはじめたのでしょうか?
松尾:一番は人を知りたいということです。昔から人間の認識を作っている仕組みってなんだろうと思っていました。例えば目の前にコップがある。でも本当にコップはあるのかという疑問です。
実は人間って人間のことを全然分かっていない。自分の脳のアルゴリズムを知らないんです。よく混同するのが、知能の力と生命性に起因する現象です。例えば、目の前にコップがあるとして、倒すとこぼれてしまうとか、熱いだろうと予測するのは知能の力です。一方で、コーヒーっておいしいねと感じる力は生命性に由来します。人の持つ倫理観や善悪は、進化の過程によって形成されてきたものだと思います。
――進化ですか?
松尾:進化心理学という分野が僕は好きなのでそれに基づいて話すと、困っている人がいたとき、それを助けた方が個体の生存率や集団の生存率が上がるような種は、助けるように進化していく。そのような行動を取るような報酬系が脳のなかに作られます。一方で、自分一人で生きていった方が生存確率が上がる動物や生物は、基本的に他者が困っていても無関心です。生存戦略としてそうなっているんです。
――AI技術が人間の生活を変えると言われていますが、松尾教授にとって、この10~20年の間に、もっともAI技術を活用して爆発的に世の中に影響を与える産業分野はどんなものだとお考えですか?
松尾:ロボットと自然言語処理(対話や翻訳)だと思います。そういった技術を取り入れやすい農業や建設業、食の分野などは大きく変わっていくと思います。自然言語処理で大きなブレークスルーに到達すれば、ホワイトカラーの仕事の仕方も大きく変わっていくと思います。
――今後AIの分野はさらなる発展を遂げていくと言われていますが、現時点で人間の行動というのはどのぐらい解明されているのでしょうか?
松尾:脳の仕組みについて言えば、ミクロな挙動については多くの研究があり、かなりの部分が分かっていますが、マクロ的な挙動については、ほとんど分かっていません。
――エンターテインメントでありつつ、今後の社会に対して非常にメッセージ性の強い作品でもあると感じました。
入江:10年後を描いていますが、正直どうなっているかは想像できない。人間自体にAIが組み込まれていくかもしれない。いま「歩きスマホはやめましょう」と言われていますが、コンタクトに情報が組み込まれることで、人間の動き自体が変わっていき、人体の拡張みたいなことが普通になっているかもしれない。先ほども言いましたが、作品を観た人が、それぞれどこか引っかかるものを感じてもらえればいいなと思っています。

――人間が記号化されていく怖さを感じました。
入江:人もデータの一部と考えると怖さもありますね。
松尾:人類の幸せのためにAIは研究されていくものだとは思います。
作品情報

映画『AI崩壊』
1月31日(金)全国ロードショー
監督・脚本:入江悠
出演:大沢たかお、賀来賢人、岩田剛典、広瀬アリス、高嶋政宏(※高ははしごだか)、芦名星、玉城ティナ、余貴美子、 松嶋菜々子、三浦友和
配給:ワーナー・ブラザース映画
(C)2019 映画「AI 崩壊」製作委員会
<ストーリー>
今から10年後の日本。AI が、全国民の個人情報、健康を完全に管理し、人々の生活に欠かせないインフラとなっていた。そんな“人に寄り添う”はずのAIが突如暴走、人間の生きる価値を選別し、殺戮をはじめる!日本中がパニックに陥るなか、AI を暴走させたテロリストに断定されたのは、開発者の桐生だった。警察は日本中に張り巡らされたAI監視網で、逃亡者となった桐生を追い詰める。AI はなぜ暴走したのか。決死の逃亡劇は衝撃の結末へと進んでいく!
日本大学芸術学部映画学科在籍中から注目を集め、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭・オフシアターコンペティション部門で、短編作品が2年連続入選。2009年に手掛けた、埼玉でくすぶるヒップホップグループの青春を描いた『SR サイタマノラッパー』が、ミニシアター系劇場における数々の動員記録を更新し、日本映画監督協会新人賞を受賞するなど旋風を巻き起こした。その後も、2014年には松竹配給の『日々ロック』、2015年には東宝配給の映画『ジョーカー・ゲーム』、2017年には『22年目の告白―私が殺人犯です―』を手掛けている。
東京大学教授。人工知能が専門で、特に、ディープラーニング(深層学習) 、ビッグデータ、ウェブ等が専門である。多くの学生やスタッフが新しい技術の研究と応用を行っており、研究室から数多くのスタートアップも生み出している。人工知能学会では2012年から 2 年間、編集委員長を務め、2014年から2018年まで倫理委員長を務めた。さらに2017年には、日本ディープラーニング協会を設立し、理事長に就任。また、Webに関する学術会議のなかでもっとも権威の高い、Web国際会議(World Wide Web Conference)では、Webマイニング部門のトラックチェアを2回務めた。日本のAI研究の第一人者の一人。