
技術の発展により、台風情報など気象に関する予測の精度は上がっているが、まだまだ予測が難しいとされている線状降水帯。近年聞くようになった線状降水帯とはそもそもどのようなものなのか、2021年の6月から始まった新たな取り組みとは?
書籍『天気予報はなぜ当たるようになったのか』より線状降水帯から人命を守るための気象庁の闘いの記録を紹介する。
予報官泣かせの線状降水帯
この線状降水帯は予報官泣かせです。前もって発生を予測することが難しいのです。気象の予測は、気象衛星などの最新の観測システムやスーパーコンピューターを駆使して行われていて、年々精度が上がってきています。ところが、この線状降水帯の予測はまだまだ難しいと言わざるを得ません。
理由はいろいろありますが、そもそも、なぜ積乱雲があのように線状に連なって次々に発生するのかがよくわかっていません。
たとえば、よく天気図に現れる低気圧や台風などは、ある程度、発生や発達のメカニズムがわかっています。なぜ台風が発達するのか、低気圧が発達するときとしないときで何が違うのか、気象学の教科書にしっかり説明が書かれています。
ところが、線状降水帯については、なぜ線状になるのか、できるときとできないときとで何が違うのか、そうしたメカニズムが十分わかっているとはいえません。最近、どのような状況のときに線状降水帯が発生しやすいかということについては、研究が進んできました。
大気が不安定であることに加えて、水蒸気が大量に流れこんでくることや上空の風に一定の特徴が見られることなど、発生しやすい条件がわかってきたのです。
ところが、そのような条件のもとでも、実際に線状降水帯が発生するかどうかを予測するのは難しく、2020年に球磨川を氾濫させた豪雨のときも、大雨になることは予測できましたが、線状降水帯が発生し、あのような記録的な豪雨になることは予測できませんでした。
有名になった「線状降水帯」
線状降水帯という言葉は、ここ10年くらいで急に使われるようになりました。このため、線状降水帯が最近になって発生するようになったものだと思っている人も多いのではないでしょうか。地球温暖化の影響で発生するようになったと考えている人もいるかもしれません。
実は、線状降水帯は昔からあったのです。筆者が気象庁に入った年、1983年にも山陰地方で集中豪雨があり、大災害になりました。
島根県の浜田市で、1時間の降水量が91ミリという猛烈な雨が降り、1日の降水量が300ミリを超える大雨となったのです。この豪雨も、今から見れば線状降水帯によるものだとされています。
なぜ、最近になるまで線状降水帯という言葉を聞かなかったのかというと、その名前がなかったからです。この名前をつけたのは気象庁の気象研究所で長く集中豪雨などの研究をしていた研究者で、2000年頃のことです。それ以来、研究者の間ではこの言葉が使われていました。
気象庁が記者会見などでこの言葉を使い始めたのは、2014年8月に発生した広島の大雨の頃からです。広島市の住宅地で大規模な土砂災害が発生し、多くの人命が失われました。
この地域の住宅地の地形とともに、水を含むともろくて崩れやすくなる真砂土とよばれる土が土砂災害の要因として話題になりました。この災害の後、土砂災害をもたらした大雨の原因として、気象庁は線状降水帯という言葉を使いました。
その後も、福岡県朝倉市などで河川の氾濫や土砂災害が相次いだ「平成29年7月九州北部豪雨」、先ほどの球磨川の氾濫が起きた「令和2年7月豪雨」など、毎年のように線状降水帯による犠牲者が出ています。
そのたびに、「線状降水帯」という言葉がマスコミにも取り上げられました。2017年には、流行語大賞に線状降水帯がノミネートされました。
このときは「インスタ映え」、「忖度」などにおされて大賞、ベストテンにはなりませんでしたが、線状降水帯が多くの人が知る言葉になったことは間違いありません。災害をもたらす危険な気象現象だという認識が広まったのです。
この言葉で命を守れ
気象庁はこのことを防災に活かそうと考えました。いつも災害の後になって、この災害の原因は線状降水帯でした、などと解説するのです。
それならば、前もって、そういう危険な線状降水帯がこれから発生しますよと伝えられれば、多くの命を助けられるのではないかと考えたわけです。
しかし、線状降水帯の予測は容易ではありません。ほんの少しでも可能性があるのなら教えてほしいという声もありましたが、そうすると、梅雨時には毎日のように線状降水帯が発生しそうだということになってしまいます。それでは「オオカミ少年」になってしまって、情報は用をなさなくなります。
その後も線状降水帯による災害は続きます。気象庁は、最重要課題として線状降水帯対策に取り組んでいきました。
発生したら瞬時に伝える
線状降水帯の発生を事前に予測するのが難しい中、気象庁はまず、線状降水帯が発生したときに、瞬時にそのことを伝えることにしました。
予報官たちは、線状降水帯が発生したとわかると、「このあとも大雨が続き、さっき出した『土砂災害警戒情報』の範囲を急速に広げることになるのではないか」「場合によっては特別警報を出すことになるのではないか」などと先を読んで対応していきます。
そして、「あっという間に避難すら危険な状況になるのではないか」「みんな避難してくれているだろうか」と危機感を募らせます。
この危機感を伝えたいのです。「線状降水帯」というキーワードを使うことで危機感を伝え、「避難指示」の発出を迷っている自治体の防災担当者に決断をうながすことができるのではないか、避難をためらっている人たちの背中を押すことができるのではないか。そう考えたのです。
早速、有識者のみなさんからもアドバイスをもらい、情報のあり方について検討を始めました。また、線状降水帯の発生をすばやく検知し、迅速に情報を発表するための技術的な検討も行われました。
「顕著な大雨に関する気象情報」
この検討が行われているさなか、2021年の1月に、筆者は気象庁長官に就任しました。気象庁が抱えている課題はたくさんありましたが、先ほども書いたように、線状降水帯対策は最も重要な課題のひとつです。特に、前年の球磨川を氾濫させた「令和2年7月豪雨」を受け、線状降水帯が発生したときの情報発信は喫緊の課題でした。
では、その情報をどのような形で出すべきなのか?
気象、災害情報、報道、地方自治体、河川、土砂災害などの分野の専門家からは、「重要かつ緊急な情報なので受け手がすぐにそれとわかるような情報にすべきだ」、「危ないのは線状降水帯の雨だけではないので、これだけを特別扱いすべきでない」、「ただでさえ情報の種類が多すぎるのにこれ以上新しい情報を作るべきではない」など、さまざまな意見が出されました。それぞれにごもっともな意見です。
こうした声を踏まえて、情報の形を決めるのは容易なことではありませんでしたが、庁内の担当チームがさまざまな考えを丁寧に聞き取り、最適な形は何か、懸命に考えてくれました。
また、線状降水帯の情報を迅速に発表するため、技術的な準備も進められました。
そして、その定義に当てはまる現象を雨のデータから自動的に検出し、情報発表する技術も開発しました。
予報の現場の作業で時間をロスすることなく、迅速に情報発表ができるようにするためです。これには、気象庁以外の研究成果も、ありがたく使わせていただきました。
こうして2021年の6月に始まったのが、線状降水帯が発生したときに発表される「顕著な大雨に関する気象情報」です。この情報の中で、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いていることを伝えることにしたのです。
線状降水帯というキーワードを情報の中で使うことによって、迷っている人、ためらっている人の背中を押すことができるようにしました。
一方で、線状かどうかが問題なのではなく、すでにひどい大雨になっているということを伝えることが大事なので、情報のタイトルは「顕著な大雨に関する気象情報」としたのです。
この情報のタイトルは少し中途半端だと思われるかもしれませんが、実は、将来の防災気象情報全体の見直しを先取りする意図がありました。
大雨などへの警戒が続く中、実際に大変なことが起こったときにそれを伝えて防災行動を後押しするほかの情報、たとえば「記録的短時間大雨情報」などと一緒に整理して、よりわかりやすく伝えるようにしていこうと考えていたのです。今後の防災気象情報の体系の整理の中で、よりよい形に整理されることと思います。
線状降水帯が発生したら
「顕著な大雨に関する気象情報」が発表されると、テレビなどでは速報が流れますし、ニュースや天気番組で豪雨の状況を解説する際にもこの言葉がキーワードとして使われます。
また、気象庁のホームページの「雨雲の動き」や「今後の雨」で、線状降水帯がどこで発生しているのかを確認することができます。
この情報が出されるのは、場所によっては、すでに警戒レベルが4になっている状況です。すでに市町村から「避難指示」などが出されているのであれば、一刻も早く避難が必要です。
「避難指示」などが出ていなくても、線状降水帯の雨域にいる場合には、事態が急激に悪化していきます。「キキクル」や水位の情報などを確認し、少しでも危ないと思ったら、早めに避難を始めてください。
ただし、気を付けなければならないことがあります。それは、線状降水帯が発生しなければ安全だというわけでは決してないということです。従来からある「大雨警報」や「キキクル」などを使って、早め早めの避難行動で自分の命をしっかり守ることが大切です。
写真はすべてイメージです 写真/Shutterstock
天気予報はなぜ当たるようになったのか
長谷川 直之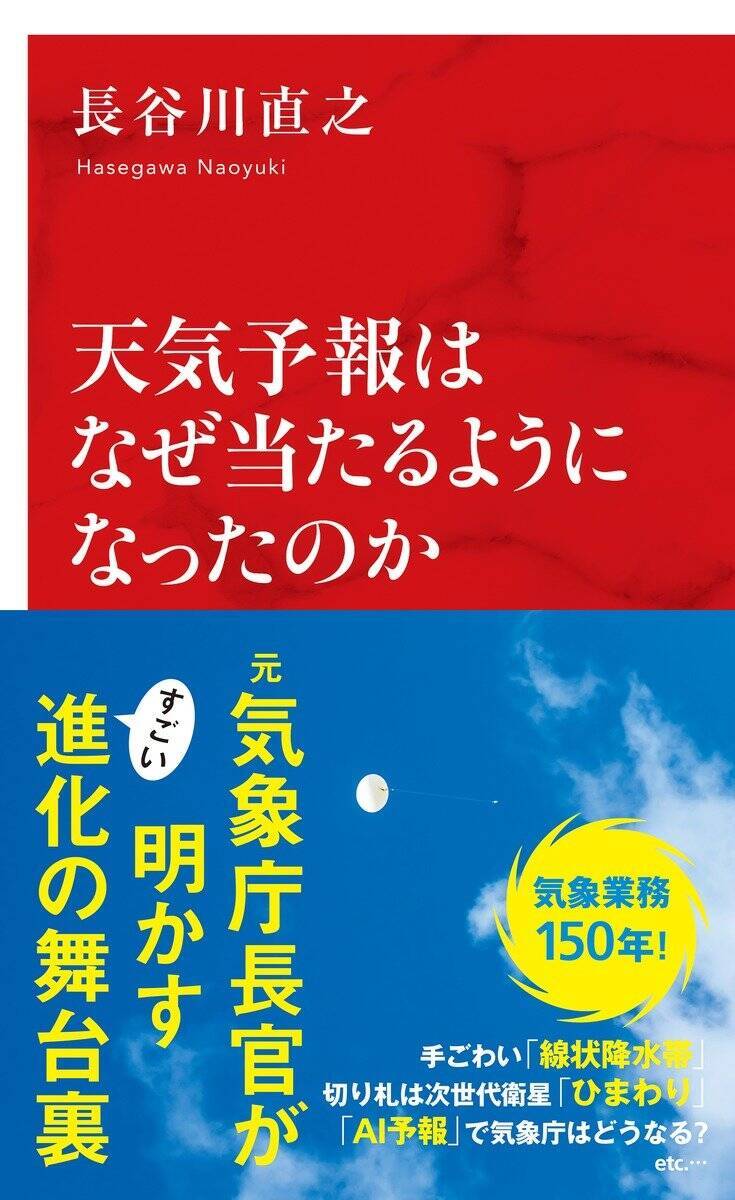
私たちの生活に欠かせない「天気予報」はどのように作られているのか?
気象の予測技術開発、国際協力業務、「線状降水帯」の情報発表などに取り組んできた
元気象庁長官の著者が、その舞台裏をわかりやすく解説する!
身近だけれど、実は知らないことだらけの「天気予報」のしくみがわかる!
2025年は、日本の気象業務のはじまりから150年の節目の年!
【内容紹介】
○「天気予報」の精度は上がり続けている! そのワケは?
○「降水短時間予報」は、ふたつのいいとこ取りの技術を使っている
○正しく知る「警戒レベル」と「防災気象情報」の意味
○手ごわい「線状降水帯」。予測の切り札は次世代衛星「ひまわり」
○「天気に国境はない」。気象データは無料・無制約で国際交換
○地球温暖化は本当かフェイクかと論じている場合ではない
○「AI予報」で気象庁はどうなる?
など































![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)
![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)




![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)


