たしかに! と鴻巣友季子が材料を揃えて、実際に料理をつくってみたのが前編。

お酒のチョイス問題
つぎに、村上春樹『騎士団長殺し』に関して、現在ちょっとした物議を醸しだしているのが、お酒のチョイスだ。


料理はほとんど友人の雨田政彦が作る。
雨田が伊東の魚屋で買った新鮮な生牡蠣四つずつ
同じく雨田が買ってきた鯛のおろしたての刺身
ぱりぱりに炙った鯛の皮
わさび漬け
豆腐
鯛のあらで出汁をとった吸い物
雨田持参のシーヴァス・リーガルをオン・ザ・ロックで。
(『騎士団長殺し』第2部P171より)
小田原名物わさび漬けは買い忘れたが、おおむね忠実に作った。伊東の魚屋の生牡蠣は、相模湾産の殻付き牡蠣だろう。
「ぱりぱりに炙った魚の皮」は作り方が不明だが、手近にあった鰤の皮を引いて、塩をふり、網焼きグリルで裏表を返しながら焼いた。
豆腐は食べ方がこれまた不明だが、腹がくちくなってきたところで、雨田が持参した木綿豆腐かなにかを手早くくずして、薬味を添えたりしたのではないか。ちょっと粋な居酒屋で「くしゃくしゃ豆腐」などと称されるメニューのイメージ。木杓で食べたりする。
うーん、全体になかなか美味しそうな酒のつまみではないか。日本酒、おかわり!
……と言いたいところだが、酒はなぜだかシーバス・リーガル。
ここでなにがしかの違和感を覚えるかどうかで、どうも世代的に分かれるようなのだ。
聞けば、今の30代以下の多くは「えっ、シーバス・リーガルのどこがいけないの?」と言うらしい。しかし、たぶん40代以上のお酒好きなら、「どうしてここで、よりによってシーバスなんだよう!」と、のけぞる人もいようかと思う。
30代以下の人たちには、シーバスは数あるウィスキーのなかのひとつで、おそらく意識して飲むような銘柄ではないだろう。現在このウィスキーの普及版は2千円台だし、スーパーで買える。

なぜにシーバス
素人の推測だが、洋酒の酒税法改正で元値自体が下がったこと、本格的なシングル・モルトが続々と輸入されるようになって価格競争のために売値を下げる必要があったこと、これらの理由で安くなったと思われる。
しかし、1980年代あたりには、シーバス・リーガルというのはちょっと高いウィスキーの代名詞だったのだ。通好みというより華やかな風味。当時、会社の経費をじゃぶじゃぶ使えたおじさんたちは水割りにして大いに飲んでいただろう。さらさらーっと心地よい喉越しでピート香もきつくないので、どんどん飲める。
とはいえ、春樹作品においては、シーバス・リーガルがだいぶ特別な扱いをされているのが、前々からいささか不思議ではあった。たとえば、『1Q84』にも「こだわりの酒」として登場する。
で、『騎士団長殺し』では、ウィスキーを買ってきてくれと主人公に頼まれた食通の雨田政彦が、上記の鯛や牡蠣などと一緒に携えてくるのが、シーバス・リーガルなのだ。
この小説はおそらく2008年あたりの設定で、ふたりは36歳。ゼロ年代に30代の「酒や食べ物にうるさい」という男性が、このブレンデッド・ウィスキーの代表みたいな銘柄をわざわざ選ぶとは、ちょっと考えにくいのだが、密かなブームでもあるんだろうか。
いいや、しかし実際に組み合わせてみなければわからない! というので、おそらく人生で初めてシーバス・リーガルを買った。そして、タンブラーなるものを何年かぶりに取り出した。
主人公によれば、「瓶からグラスにウィスキーを注ぐときに、とても気持ちの良い音がした。親しい人が心を開くときのような音だ」という。この描写からも作者がこのお酒をとても大切にしているのがわかる。
………トクトクトク………トクトクトク………???
まっ、まあ、考えてみたら、親しい人が心を開くときの音を知らないので、トクトクトクとしか聞こえなくてもしょうがない。音はあきらめて、食べ物との相性だ。
もしや、食通の雨田くんは……
まず、生牡蠣!

牡蠣は村上春樹の紀行エッセイ集『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』にも出てくる。スコットランドのアイラ島で、殻付きの生牡蠣にアイラのシングル・モルトを注いで、そのまま口に運び、殻に残った汁とモルトをぐいと飲む、という豪快な食べ方。
生臭さのないアイラ島の牡蠣とアイラのモルトでしょう? これは、いかにも旨そうですよ。アイラ・モルトはまさに潮の香りがしてスモーキー。ぷりっとこぶりの牡蠣と「とろり」と調和するそうだ。おー、美味しそう。アードベッグでもブナハーブンでも、持ってきて!
と思い馳せながら、牡蠣を食べたのちに、シーバスを口に含んでみた。
……………………………。
ま、まあ、きっと牡蠣が生臭い安物だからいけないんだろう。
でも、でも、でも、シーバス・リーガル、甘すぎです! いや、スコッチには、こういうバニラ、フルーツ、カラメルのニュアンスのものはあります。良いと思います。がっ、日本の生牡蠣との相性は良くない気がします(*個人の感想です)。
でも、もっとつらかったのは、鯛の刺身だった。ぷりぷりした淡泊な鯛、そしてぱりぱりに炙った魚の皮! うう、早く、早く、日本酒ください! 助けてー。
それにしても、シーバス・リーガルが記憶にある味とだいぶ違う。ここで初めて調べてみると、このウィスキーは1980年代のどこかを境に、造りがずいぶん変わったらしい。1970年代以前のボトルは非常に旨いと書かれていた。
ハッ、もしや、食通の雨田くんは70年代のオールドボトルをさくっと持ってきたのではないか。なのに主人公それに気づかず、後で「近所の酒屋でも同じの買えたよん♪」と雨田にシーバスを用意する場面があるが、雨田は「ったく、しろうとはよお」と、内心毒づくことになったかもしれない。
ともあれ、食中にウィスキーを飲む習慣がない身としては、どのみち違和感があるのだが、思いだしてみると、自分の親の世代は家でも、鮨屋でも、中華料理店でも、洋食屋でも、ウィスキーの水割りで食事をしていた。今みたいなハイボールじゃないですよ、水割りね。この飲み方は戦後、ある酒造会社が仕掛けたもので、その戦略が大成功して、全国廿浦浦のバー、スナック、料亭、割烹、鮨屋などの飲食店に丸っこい形の黒いウィスキーがずらっと並ぶことになった。
そんなわけで、ウィスキーでごはんを食べるというのは、わたしにとってはある意味、すごく昭和の象徴的光景なのだ。
虚構と現実をつなぐリンク
最後に。村上春樹の小説には多くのブランド、銘柄、メーカー名、アーティスト名などが出てくる。もちろん、小説は虚構だから、それらも「架空のミニクーパー」だし「架空のカティーサーク」なのだ。しかし、それらの固有名詞から読者がある漠然としたイメージを共有するのを想定して書かれている。たとえば、今回も似て非なるものの表現に、「ジャズベースでもレイ・ブラウンの音とチャーリー・ミンガスのそれが全然違うのと同じぐらいかけ離れている」といった比喩が出てきた。先行作では、「プルーストの小説のような長い長い廊下」というのもあった。
これらは、現実のレイ・ブラウンやミンガスやプルーストのなんたるかを知っていて初めて効果を発揮する喩えだろう。比喩とはそういうものだ。読み手のいる現実レベルで共有できるイメージを軸に機能する。
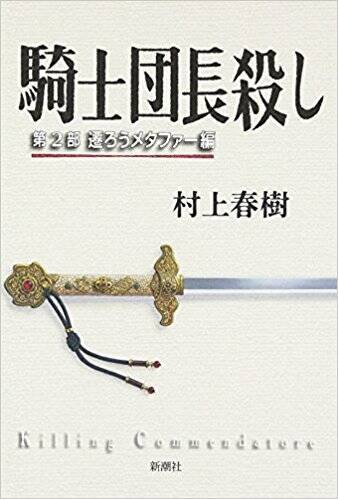
その他、登場人物の読む本、着る服、聴く音楽など、現実世界に存在する相当物を多様に引くことで、春樹の虚構世界は現実感がいい具合に補強されていた。だからこそ、その日常がずれ始めたり、裏返ったり、どこか異界とつながったりしたときに、より大きな衝撃があるのだ。それらの固有名詞が尖端的なテイストを持っていた頃と、昭和のレトロな味わいを醸し出してきている今では、虚構と現実をつなぐリンクとしての機能も効用も変わってきているのではないか。
長年の一読者としては、自分の青春時代の思い出だってセピア色に変わってきているんだから、それも致し方ないと思う。でも、これからの若い読者はどんなふうに村上春樹を読むのか、それにとても興味がある。
(鴻巣友季子)
こうのす・ゆきこ:1963年東京生まれ。翻訳家。訳書にマーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ』、エミリー・ブロンテ『嵐が丘』、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』、J.M.クッツェー『イエスの幼子時代』、『恥辱』、T.H.クック『緋色の記憶』、マーガレット・アトウッド『昏き目の暗殺者』ほか多数。文芸評論家、エッセイストとしても活躍し、『カーヴの隅の本棚』『熟成する物語たち』『全身翻訳家』『孕むことば』『明治大正 翻訳ワンダーランド』『翻訳問答シリーズ』など、多数の著書がある。































